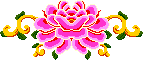|

 |
『孟嘗君』 |
全五巻 講談社文庫 |
1995 |
初めて読んだ作品がこれです。単行本ではなく、たまたま家でとっていた新聞に連載されていたんですが、これが面白くて面白くて。なんたって第二回にして最後の行が
「でも、今夜、わたしは、自分の子を殺さなければならないのです」
さあ「その赤ちゃんはどうなっちゃうの?」と引き込まれてしまうこと否応なしで、場面転換の巧さにじらされつつ、新聞屋さんが夕刊を配りにくるのが待ち遠しい二年半を過ごさせていただきました。
ほぼ全回分をスクラップしてとってある、というあたりでどれほど気に入ったかお分かりかと(笑;佐多芳郎氏の挿し絵も好きでしたので)。
(余談ながら、高校時代にファンになれたおかげで、漢文で点が稼げるようになる、という余得もありました。いや、「学問の基礎は読み書き算盤だ。漢文を読め!」という父親をもったおかげで十八史略とか読まされてはいたんですが;笑)
題名は「孟嘗君」なのですが、前半部分は彼の養父である風洪(後に白圭と改名)の物語のようなもので、田文(=孟嘗君)の襁褓の中の赤ん坊時代の長さに、この調子で進んでたら、終わるまでに4・5年かかっちゃわないかしらと心配になったほど(笑)。歴史の表舞台に登場するのは作品後半になってからで、全体からすると比較的少ない割合です。清少納言の歌で有名な鶏鳴狗盗の逸話など、最後の章になってやっとでてくるくらいですから。
斉の公子田嬰の子として生まれながら、五月五日生まれであることを不祥とした父に殺されそうになる、というのが波瀾万丈の生涯の始まりだったりするのですが、いろいろないきさつから、それとは知らぬ処士風洪の元で育てられることになり、その後孫子の手から実父田嬰のもとにひきとられ、様々な紆余曲折を経て魏の宰相となり、天下に盛名を轟かすまでが描かれています。この間、公孫鞅(=商鞅)による秦の変法、孫子が龐涓に復讐した馬陵の戦い、蘇秦・張儀による合従連横、などのよく知られた出来事も登場します。
田嬰を威王の子ではなく弟だとしているなど、作者なりの読みとりが随所に見られます。ただ、一つだけ、宰相を罷免されると去っていった食客が復職すると戻ってきたことに、田文が不快を示して諫められた、という比較的よく知られた逸話に全く触れられていないのが、ささやかながら不満だったりするのですが。

 |
『王家の風日』 |
文春文庫 |
1991 |
商周革命と、商王朝末期を支えた名臣箕子を主に描いています。
暴君の典型という既成のイメージのある受王(=紂王)ですが、そうしたステレオタイプで描かれていないのがなんといっても面白いです。
いわば“敵役”で登場する太公望がなかなか凄みがあって魅力的です。

 |
『天空の舟 小説伊尹伝』 |
上下二巻 文春文庫 |
1990 |
副題にあるとおり、商王朝を開いた湯王に仕えた摯(=伊尹)の生涯を描いています。
紂王と並んで暴君の代名詞になっている桀王ですが、こちらは実際に性格悪いという設定。一方、さほどはっきり性格設定されていない妲己に対して、妺喜の方は同情的な描き方になっています。

 |
『夏姫春秋』 |
上下二巻 講談社文庫 |
1991 |
傾国の美女として悪名高い夏姫。
「うしろを向けて」(作者の弁)描いた作品です。

 |
『華栄の丘』 |
文藝春秋 |
2000 |
主人公は宋の大夫・華元。父の華御事は無道な君である昭公には仕えぬ方がよく、王姫と呼ばれる襄公夫人に一つの貸しがある、と言い残して亡くなる。悪評高い昭公に対して、年々人気を高めている異腹の弟・美公子鮑は、王姫と協力して宋に正道を取り戻そうとしていた・・・。
なかなかにスリリングな出だしです。
戦いを好まない宰相・華元もそうですが、とりわけ襄公夫人・王姫の存在が印象的。慧眼にして政治力もあり、隠然たる力を行使するこの女性、主人公と協力する立場の人間としては、今までに登場しなかったタイプの女性のような。内助の功型の女性はいたと思いますが、このひとの場合、文公(公子鮑)も華元も、何か、彼女の手の内にいるような印象すらあります(笑)。
「食い物の恨みは怖い」の話は『夏姫春秋』の書き方の方がすっきりしているように思いますが。

 |
『管仲』 |
上下二巻 角川書店 |
2003 |
管鮑の交わり、で知られる管仲と鮑叔。小説は二人の出会いの場面から始まりますが、どうしたらこういう場面が思いつけるかなあ、と思わせる冒頭部でした。あとがきで「天祐」と書かれているのも納得。なぜ二人が別の公子に仕えることになったか、のくだりも納得のゆく展開です。
公孫無知の横死後、管仲仕える公子糾と鮑叔仕える公子小白の後継争いとなるわけですが、どちらが先に斉に着けるか、の単なる競走として描いていないところが興味深い。無難に斉の君主になるようにと召忽に育てられた公子糾と、天下に関心を持つよう鮑叔に育てられた公子小白の差。持つ望みの大きさで人の器量が決まってくるのだなあ、としみじみ思わせられたりして。
物語の流れから襄公と魯公夫人文姜の不倫関係(二人は異母兄妹)が出てくるのは当然なのですが、
先の夏姫ほど丁寧に書き込まれているのではないにせよ、文姜の非難に終始していないというか、理解を投げていないところがやはりこの作者だなあと思わせます。

 |
『重耳』 |
全三巻 講談社文庫 |
1993 |
重耳、つまり「春秋五覇」の一人・晋の文公の生涯を描いた長編。彼の父は晋の献公、母は白狄の一族狐氏の娘。物語は曲沃の主と、翼を根拠地とする晋の本家の対立のいきさつから始まり、重耳の祖父称のとき、翼を滅ぼして晋の主となります。父の献公は晩年驪戎を攻めて驪姫を手に入れるのですが、我が子奚斉を次の君主にしたいと願う驪姫と、優施という俳優(実は・・・という設定)の謀略により太子申生は死に、重耳は狐氏へ、弟夷吾は梁に亡命。実に十九年間にわたる放浪の後、重耳は弟夷吾、その子圉との争いに勝ち、秦の穆公の援助で晋の君主となります。当然のことながら、重耳の放浪時代がこの作品の大半を占めています。
申生の師になることを称に頼まれ、重耳が天下に号令するという予言を信じながらも、称を喜ばせるために承諾した狐突と、重耳の師に任命されて不運を嘆く郭偃との対比が、二人のその後の運命の違いと思いあわされて、印象に残る場面でした。

 |
『介子推』 |
講談社文庫 |
1995 |
『重耳』にも登場する、重耳に仕えた棒術の達人・介推を主人公に据えた作品です。

 |
『孟夏の太陽』 |
文春文庫 |
1991 |
春秋時代の晋の名家趙氏の盛衰を描いた連作短編。
重耳に仕えた趙衰の子で、自らが強引に君主に立てた夷皐と対立せざるをえなくなった趙盾
(「孟夏の太陽」)、
父が夷皐暗殺の首謀者とされたことにより誅殺された趙朔
(「月下の彦士」)、
趙朔の曾孫で、王子朝の乱において周王を助け、晋の大臣士氏と中行氏を滅ぼした趙鞅
(「老桃残記」)、
下女の子ながら嫡子に立てられ、知瑤の悪辣さに耐えてついに知氏を滅ぼした趙無恤
(「隼の城」)の四人がそれぞれ独立した一篇を構成しています。
とりわけ「月下の彦士」における、趙家誅滅の際に趙朔の遺児趙武を守りぬいた公孫杵臼と程嬰の活躍がドラマチックです。
趙無恤といえば思い浮かぶのが知瑤の仇を討とうとした豫讓の話ですが(漢文の授業で読まされた記憶が)、作中には登場しません。確かに入れたら話がまとまらなくなってしまいますけれども。

 |
『沙中の回廊』 |
上下二巻 朝日新聞社 |
2001 |
主人公は晋の宰相・士会。晋の混乱期に君命尊重の立場をとったため、時流を外れている貴族の末子である彼が武勇の人から兵略の天才となり、ついには宰相になるまでの物語。
前半部分は『重耳』、『介子推』で、後半部分は『孟夏の太陽』、でなじみのあるところなので、強烈な目新しさはないですが、安定した面白さは健在。『孟夏の太陽』との趙盾の描き方の違いも興味深かったです。
ただ、叔姫の一件はちょっと設定をひねりすぎのような気がしますが・・・。

 |
『子産』
 |
上下二巻 講談社 |
2000 |
鄭の名宰相子産を描いた作品。晋と楚という二大大国に挟まれて向背を繰り返す小国の公孫に生まれた彼が、父の横死に遭いながらも、若年にして卿となり、子皮の庇護のもとに国制改革を行うまでの物語。前半部分はどちらかといえば、優れた武人であった父の子国の視点で描かれています。
『詩』などを引いて諷意を尊ぶ貴族が政治の実権を握る当時にあって、大衆を重視し、大衆にわかりやすい言辞を用い、批判されても言論の弾圧を行わず、法を明文化して訴訟の道を拓いた子産。「民が法を知れば法のぬけ穴をさがすようになる」という叔向の批判、「政治をおこなうには、真意に反して人民に媚びることをせねばならぬときがある」という子産の述懐を読むと、いつの時代も人間は変わらないんだなあ、と苦笑したいような気分にもなりましたが。「為政者が凡庸であるときも、民が苦しまず、生業に専心することができるような行政の形というものはないのだろうか」という子羽の台詞も印象的でした。
同時代に活躍した晏子も含めて、名君の時代から名宰相の時代になった、と指摘されているのが面白かったです。
著者はあとがきで架空の人名を全く使わなかったと書いてられましたが、なるほど、みごとに女っ気がない話ですね(笑)。

 |
『楽毅』 |
全四巻 新潮文庫 |
1999 |
中山国の宰相の子・楽毅が、中山を攻め取ろうとした趙の武霊王と戦い、中山が滅びたのちは趙から魏へゆき、その後燕の昭王に仕えて斉の七十余城を陥落させ、しかし次の恵王に疑われて将軍を罷免され、趙の恵文王に仕えるまでの物語。さきに『孟嘗君』を読んでいたので、薛公の偵人として僕羊や李滑がでてくるのにおもわずにやりとしてしまいました。男勝りの侍女なんかもでてきましたが、これも女装のうまいあの食客のことですよね?
読みどころは四面楚歌の中山国の延命のためや、斉への復讐の野望を秘めた燕の昭王のために楽毅が粉骨砕身するところ、であるべきなのでしょうが、実は個人的には沙丘の乱のくだりが好きなんですね。父と兄に追いつめられて絶体絶命の恵文王、人相見の名人・唐挙の予言とそれに翻弄される李兌。これが何度読んでものめり込む、手に汗握るスリリングさ。感情移入して読んだ分だけ、その後の展開で奉陽君がいたって冴えない存在なのがなんだかさみしいワタクシでありました。

 |
『青雲はるかに』 |
上下二巻 集英社文庫 |
1997 |
重耳や晏嬰、楽毅といった、なんというか、納得できる人選が続いていたので、この作品の主人公が范雎と知った時には「一飯の徳も必ず償い、睚眦の怨みも必ず報ゆ」のあの人だよね、とやや意外な気がしたものでした。考えてみれば『王家の風日』の紂王みたいなケースもあったわけですが。
主であった魏の中大夫・須賀に斉と通じたと疑われ、宰相の魏斉から笞打たれた上に廁室におかれたという屈辱を忘れず、微賤の身から昭襄王の信頼を得て秦の宰相となり、みごとに二人への復讐をやりとげた范雎。蔡沢という人物に「大功を立てた者が高位にとどまっていると、かならず禍がその身に至る」と言われて潔く引退した逸話も有名ですが(代わりに自分を宰相にしろ、という人物を本当に代わりに推薦しちゃうんだからすごい話だ、と思った;笑)、どうも順風満帆の状態で引いたというわけでもないようですね。
無名時代を丹念に描き、むしろ功成り名遂げてからはあっさりと切り上げて終わる、というのがこの作者の作風のようで、たまにちょっと物足りなさを感じることもあるのですが、この作品についてはさらりと切り上げて正解かな、と思いました。

 |
『香乱記』
 |
上中下三巻 毎日新聞社 |
2000 |
陳勝・呉広の乱以後王として自立した斉の田儋・田栄・田横の三兄弟、とりわけ田横をメインに描いた作品。終章に以下のような文章があるのを読むと、項羽でも劉邦でもない彼らを主人公にして楚漢戦争の時代を描いた意図はよく分かるのだけれど、「三人の王」という許負の予言が決して嘉言ではないことを知りながら読み始めるのは切なかったです。彼らがいい男であればあるほど、そして終盤に至って股肱の臣下を次々と失っていくあたりはよけいに・・・。
劉邦はみえと猜疑のかたまりのような人物であり、人を信じて用いるという点においても、じつは項羽よりも狭量であったとおもわれる。劉邦は項羽のように物を破壊せず、民を殺さなかっただけで、人の尊厳を量る能力に欠け、とても人の範になれない淫狡さをもち、そういう悪性を恐れた人々が次々に離叛し、劉邦は悪鬼のごとくかれらを討ち、殺して生涯を終えることになる。劉邦は項羽を嗤えない殺戮者であった。項羽と戦っていたころの劉邦は英雄の風景にふさわしい人物であったが、皇帝となってからは醜悪となった、というのは歴史の印象にすぎず、劉邦の実相は挙兵まえからさしたるちがいはない。
「韓信の股くぐり」といえば隠忍自重の代名詞のようになっているので、司馬遼太郎氏の『項羽と劉邦』でくぐれと言われればくぐる人間であったような書き方をされているのに驚いた記憶がありますが、この作品ではさらに辛い評価です。彭越も、登場当初は颯爽としていたんですが・・・
前作『奇貨居くべし』を読んでいる時にも思ったことですが、なんだか男女の仲が分かりにくくなったな、という感じがします。なんというか、一途な想い、というのが明らかにハッピーエンドという形に結実しない、という分かりにくさなんですが、これは分かりにくい時代にあるとそういう形になってしまうのか? とちょっと考えてしまいました。

 |
『長城のかげ』 |
文春文庫 |
1996 |
項羽に仕えて劉邦を苦しめたため追われる身となったが、後に許されて漢に仕えた季布を描いた
「逃げる」。
劉邦の幼なじみで彼の近くにいたが、功臣たちが滅ぼされていくのを見て謀反を起こした盧綰を描いた「長城のかげ」。
外交によって劉邦を助け、その死後呂氏を滅ぼす計画を立てた陸賈を描いた
「石径の果て」。
劉邦と曹氏との間に生まれた斉王肥を描いた「風の消長」。
漢王室の儒家の宗家となった叔孫通を描いた「満天の星」。
楚漢戦争の時代に題材を採った、以上五つの短編が収められています。

 |
『花の歳月』 |
講談社文庫 |
1992 |
漢の文帝の皇后竇猗房を描いた作品。
今は貧しい家の娘・猗房が県の代表の名家の娘に選ばれて呂太后のもとにあがり、代王に下賜されて妃となり、ついには皇后になるまでの物語。「天子を産む」という郷父老の予言あり、知り合いの宦官のひそかな計らいあり、
そして最後の再会劇、となかなかドラマチックな展開です。
彼女が道家の思想を好み、それを非難する者を激しく攻撃した、とあるのを読んではたと思い出したのが、誰だったかも話の詳細も忘れ果ててますが、とある儒教の学者さんのエピソード。彼を迫害する意地悪ばあさんみたいな役どころででてくる皇太后様がいましたが、あれが多分彼女ですね。晩年をあまり詳しく書き込まなかったのは賢明な措置というべきか(笑)。
あと、猗房の長男は生まれたときは嫡男ではなかったはずなのに、代王が皇帝になるときには太子になっていて、いつの間に? とちょっと面食らいましたです。

 |
『侠骨記』 |
講談社文庫 |
1991 |
・侠骨記
主人公は魯の荘公に仕えた曹劌。講和会議の席上、斉の桓公に短刀をつきつけて奪われた土地を取り戻したというエピソードで有名ですが、なかなか魅力ある人間に描かれています。
・布衣の人
古代の聖帝として名高い俊(=舜)が主人公。親孝行の権化というイメージのある人物ですが、なかなかユーモラスな味わいのある作品になってます。
・甘棠の人
商周革命を、召公の立場から描いた作品。この作品では太公望に釣り竿持たせてますね(笑)。
・買われた宰相
主人公は秦の穆公に仕えた名宰相百里奚。斉で知り合った貴門の子・蹇叔との友情が感動的な作品です。しみじみ「長生きはしてみるものである」ですねえ。七十代になってからでも名は残せるんだから・・・

 |
『沈黙の王』 |
文春文庫 |
|
・沈黙の王
中国で初めて文字を創造した高宗武丁の生涯を描く。
・地中の火
・妖異記
・豊饒の門
・鳳凰の冠
晋の羊舌氏の子・叔向を描いた作品。夏姫の娘を妻とした人です。

 |
『玉人』 |
新潮文庫 |
1996 |
・ 雨
・歳月
・指
・風と白猿
・桃中図
・玉人

 |
『晏子』 |
全四巻 新潮文庫 |
1994 |
斉の名臣晏弱、晏嬰の父子の生涯を描いた作品。

 |
『太公望』 |
全三巻 文藝春秋 |
|
 |
『奇貨居くべし』 |
全五巻 中央公論社 |
|
|