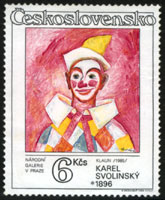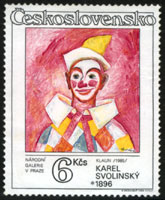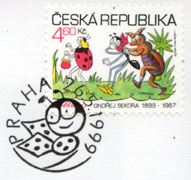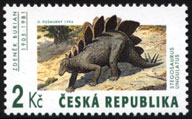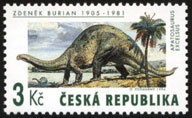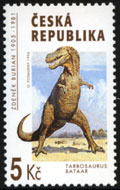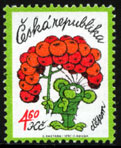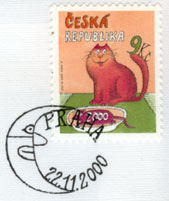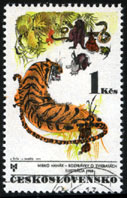チェコ絵本とアニメーションの世界
刈谷市美術館で2007年4月21日から5月27日まで「チェコ絵本とアニメーションの世界」が開催されたのにちなんで立てたチェコ特集企画。(実は、刈谷まで来るの知らなくて、最初の京都会場にも見に行っちゃった私。)以後もこの手の展覧会やってるとついつい行っちゃってます。チェコの切手のデザインを好んでいる人間なので、何か通じるものを感じるようで。

「こいぬとこねこは愉快な仲間」
ヨゼフ・チャペック Josef Čapek 1887-1945
ボヘミア東部フロノフに生まれる。1904年からプラハ美術工芸学校に学び、20世紀前半のチェコ前衛芸術の様々な潮流を学びとる。キュビズムの画家として活躍し、戯曲、舞台芸術、装丁、挿絵など多彩な分野で才能を発揮した。弟のカレル・チャペックとは仕事上のパートナーでもあり、カレルの著作『R.U.R』に登場する「ロボット」の名付け親とされる。『お話のバスケット』(1918年)で初めて子ども向けの挿絵を描き、子ども向けには数冊程度しか作品を発表しなかったものの、自著『こいぬとこねこは愉快な仲間』(1929年)は、今日に至るまで幼い子どもたちに親しまれており、没後、原画のイメージを元にしたアニメーション映画も作られた。1939年、第二次大戦の勃発と共にナチスに逮捕され、ドイツのベルゲン−ベルゼンの強制収容所で死去した。
2008.5.28 チェコ発行
【子どもたちのために】

「秋」(1955年)
ヨゼフ・ラダ Josef Lada 1887-1957
プラハ近郊フルシッツェに生まれる。プラハの製本所で働き、1906年の短期間、プラハ美術工芸学校で学んだ。
1906年に最初の挿絵本『ホンジーチェクと金髪のイゾラ』を手がけた後、『私のアルファベット』(1911年)、『カラマイカ』(1913年)など多くの子ども向けの絵本を創作した。文章も書くように友人にすすめられてかいたのが『黒ねこミケシュの冒険』(1933年)で、『きつねものがたり』(1937年)でも文と絵をかいている。色調と形態を単純化した線描スタイルと牧歌的で民族色の強い独特の作風により、チェコの田舎、自然、クリスマスを象徴する国民的絵本作家となり、絵本のほか、ポストカード、ポスターなどの印刷物を通して人々に広く親しまれた。J.ハシェクの長編小説『善良な兵士シュヴェイク』(1921年)の挿絵でも名高い。そのほか、演劇や映画のための舞台美術や、衣装デザインも手がけるなど多様な分野で活躍した。
小学生の時に図書館で借りて読んだ『黒ねこミケシュのぼうけん』、大好きでした。欲しかったんですが、その当時からすでに絶版・・・。
1970.4.21 チェコスロヴァキア発行
| 【第7回ブラチスラヴァ世界絵本原画展】 |
【国立美術館所蔵名画】 |
 |
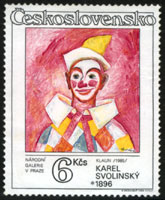 |
|
ピエロ |
| 1979.7.30 チェコスロヴァキア発行 |
1986.10.13 チェコスロヴァキア発行 |
カレル・スヴォリンスキー Karel Svolinský 1896-1986
オロモウツ近郊スヴァティー・コペチェクに生まれる。1919年から1926年にかけてプラハ美術工芸学校で学んだ。
1925年、K.H.マーハの詩集『五月』の挿絵でパリ国際装飾芸術展覧会のグランプリを受賞。ガラス工芸、モザイク、タペストリー、油彩、グラフィック、切手などの応用グラフィック、舞台芸術、イラストレーション、タイポグラフィーなど広範囲な仕事に取り組み、チェコの伝統を強く意識させる作品で知られている。J.ネルダ、J.サイフェルトといったチェコの詩人たちの書籍の挿絵や、『魔法の世界』(1949年)、『チェコの四季』(1944-60年)などの絵本など、手がけた書籍は1500冊以上にのぼる。チェコスロヴァキア、ミラノ、ブリュッセルなど国内外の国際展で何度も受賞し、1972年にはそれまでの全仕事に対してライプチヒ国際ブックアート展でグランプリを受賞した。
水彩画風の『真夏の夜の夢』が印象的でした。人形アニメの映像はトゥルンカが絶品だと思うけど、挿絵だったらこういう絵もいいなあと思います(未掲載だそうですが)。
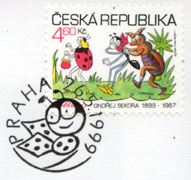
『アリのフェルダ』
オンジェイ・セコラ Ondřej Sekora 1899-1967
ブルノ近郊クラーロヴォ・ポレに生まれる。ブルノ・マサリク大学では法学を学ぶが、2年で中止し、1921年からチャペック兄弟と同じ「人民新聞」紙のスポーツ欄編集者、挿絵画家として働き始める。スポーツの分野では、自身ラグビーのトレーナー、のちに審判として活躍し、乗馬やスキーもした。同紙のクリスマス特集に際し、子ども向けの仕事を依頼されて生まれたのが、代表作となる『アリのフェルダの本』である。アリのフェルダの話はシリーズになり、さらにこの本のもう一人の主人公、カブトムシのピトゥリークも数冊の本になった。アリの生態を正確に分かりやすく描くと同時に、昆虫たちの世界を人間社会になぞらえ、ユーモアに富んだ教訓作品として、国境を越えて愛されている。
自著のみならず、数多くの作家の作品に挿絵を提供しており、V.ヴァンチュラ『クブラとクバ・クビクラ』、V.チトヴルテク『ライオンが逃げた』などがある。「アリのフェルダ」シリーズは、ズリーンで活躍していたH.ティロールロヴァーがアニメーション化したほか、後年、何人かの作家によって映画化されている。
会場ではティロールロヴァーのクレイアニメも上映されてました。人形になると、ちょっと雰囲気変わりますね。
1999.5.26 チェコ発行
【子どもたちのために】
ズデニェク・ブリアン Zdeněk Burian 1905-1981
北モラヴィア地方のコプシヴニツェに生まれる。マンモスなど古代生物の化石が発見されたシプカ洞窟の近くで育ったことが、彼の幼少期よりの古代世界への関心を育んだ。14歳の時にプラハ造形美術アカデミーに入学し、専門的に絵の勉強を開始する。その後カレル大学の古生物学の教授であるアウグスタ博士やスパイネル博士たちと出会い、学術的知識に基づいた古生物画を数多く制作し、その第一人者となった。
その他『ロビンソン・クルーソー』やジュール・ベルヌの作品など、冒険文学の挿絵も手がけており、日本でも、ベルヌらの作品は、ブリアンの挿絵とともに紹介された。
1994.6.1 チェコ発行

『アンデルセン童話』
イジー・トゥルンカ Jiři Trnka 1912-1969
プルゼニュに生まれる。幼少期にチェコスロヴァキア現代人形劇の創始者であるヨゼフ・スクパに学ぶ。プラハ美術工芸学校を卒業後、人形劇の分野から活動を始め、第二次世界大戦後に創設されたばかりの国営スタジオで映画制作に携わる。1945年初の映画作品『おじいさんと砂糖大根』を制作。1946年には『動物たちと山賊』でカンヌ国際映画祭でトリック映画最優秀賞を受賞。人形アニメーション映画『チェコの四季』(1947年)など、26作品で監督、美術を務めた。1953年にはヴェネツィア映画祭で銀獅子賞を受賞し、チェコのアニメーション映画を世界的に知らしめた。
その一方で、1937年に最初の挿絵を描いた後、『ほたるっこたち』(1941年)や『ふしぎな庭』(1962年)など、子ども向けの本を晩年に至るまで発表。1968年には国際アンデルセン賞画家賞を受賞した。絵画、彫刻などを制作する芸術家としても活躍した。
アニメのDVDは廉価版が出たのを知って、5枚揃えてしまいました。彼の『真夏の夜の夢』はやっぱり絶品です!
1977.9.9 チェコスロヴァキア発行
【第6回ブラチスラヴァ世界絵本原画展】

『中国のおとぎ話』
エヴァ・ベトナーショヴァー Eva Bednářová 1937-1986
プラハに生まれる。プラハ美術工芸大学で、A.ストゥルナデルに師事。
挿絵画家。児童文学から、ロシア文学の古典にいたるまで幅広い作品の挿絵を手がける。象徴主義を想起させる内省的な要素が強い作品や、独自な形で文学を扱った絵画などでも知られる。挿絵の代表作品はO.シャインプフルコヴァー『おとぎ話』(1974年)、プーシキン『オネーギン』(1975年)、C.ペロー『童話』(1978年)、F.フルビーン『生よ、立ち上がれ』(1987年)、ドストエフスキー『罪と罰』(1988年)など。『レニと呼ばれた私』は日本でも翻訳出版されている。
『大岡裁き』(1984年)なんて本の挿絵も描いているとか・・・
1971.9.10 チェコスロヴァキア発行
【ブラチスラヴァ世界絵本原画展】

クルテク(もぐらくん)
ズデネック・ミレルによって1957年に誕生したキャラクター・クルテク。クルテクとはチェコ語で"もぐら"という意味(“もぐらちゃん”という意味でクルテチェックとも呼ぶらしいです)。クルテクは仲良しのねずみくん、うさぎくん、森の仲間たちと楽しく暮らしており、好奇心いっぱいのクルテクは、冒険をしたり、街におでかけしたり、映画に出演したり。ただ、ちょっとした事ですぐ泣いちゃう、泣き虫さんでもあるとか。
ズデニェク・ミレル Zdeněk Miler 1921-
プラハ近郊クラノドーに生まれる。プラハ美術工芸大学で学ぶが、第二次世界大戦で学校は閉校になり、1942年にズリーンにあるアニメーションスタジオでアニメーターとして働き出す。終戦後プラハに戻り、1945年にトゥルンカのアニメーションスタジオ「トリックブラザーズ」に入る。アニメーション初監督作品『おひさまを盗んだ百万長者』で1948年にヴェネツィア映画祭特別賞を受賞。彼が生み出した国民的キャラクター『もぐらのクルテク』を主人公とする映画作品を次々と制作したが、『もぐらくんとかえる』(2002年)を最後に引退。一方、アニメーション制作と並行して、最初の挿絵を描いた『三銃士』(1946年)以後、『もぐらとズボン』『しりたがりやのこいぬとみつばち』『ひよことむぎばたけ』など多数の絵本を手がけている。
会場では「もぐらくんとズボン」のアニメが上映されてました。“Děkuj vám”“Není zač”が聞き取れたのが嬉しくて、ついDVDまで買ってしまったという・・・(笑;たかだか「どうもありがとう」と「どういたしまして」って会話なんですけど)。個人的な好みですが、もぐらくんは初期バージョンの絵の方が好きですね。
2002.5.29 チェコ発行
【子どもたちのために】
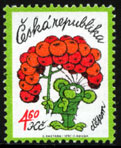
ズデニェク・スメタナ Zdeněk Smetana 1925-
プラハに生まれる。カレル大学教育学部でC.ボウダの授業を受ける。
1946年以降、あらゆる技術を駆使したアニメーションの制作に携わるようになる。映画のほか、テレビのアニメーション番組『ヴェチェルニーチェク』に数多くの作品を提供したことでも知られる。TVアニメーションの代表作は『苔とシダのおとぎ話』(1965-1972年)、『裁縫鳥』、『小さな魔法使い』(1983年)など。アニメーション映画には、『正午に』(1964年)、『4枚の切符』(1965年)、『ロミオとジュリエット』(1971年)、『チャールカ氏とテッチカ氏はどうやって輪っかを追いかけたか』(1974年)などがある。『立方体の終わり』は、カンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞した。
1997.5.28 チェコ発行
【子どもたちのために】

クヴィエタ・パツォフスカー Květa Pacovská 1928-
プラハに生まれる。プラハ美術工芸大学でE.フィラに師事し、応用美術を学ぶ。
絵画、挿絵、デザイン、商業美術などの分野で活躍。ブリキや紙を素材にした立体作品も数多く制作する。児童書の絵は1950年代より手がけていたが、1980年以降、文章やブックデザインも自身で手がけた絵本作りに取り組む。『ふしぎなかず』(1990年)、『あかあおきいろ、色いろいろ』(1992年)などの絵本には、型押し加工や小さな扉、鏡、折りたたまれた紙など、様々なしかけが盛り込まれているほか、また文字や数字も絵の一部としてデザインし、赤と緑の補色を効果的に使うなど、視覚的にも高度に洗練されている。彼女の絵本は国外での評価が高く、多くが英語、フランス語、イタリア語、日本語などに翻訳され、出版されている。代表作品は、『アルファベット』など。80年代には、「世界で最も美しい本」で連続して受賞している。1983年ブラチスラヴァ世界絵本原画展で金のりんご賞、1992年には国際アンデルセン賞画家賞を受賞した。
1985.9.5 チェコスロヴァキア発行
【第10回ブラチスラヴァ世界絵本原画展】
| 【第8回ブラチスラヴァ世界絵本原画展】 |
【子どもたちのために】 |
 |
 |
| 1981.9.5 チェコスロヴァキア発行 |
1996.5.29 チェコ発行 |
アドルフ・ボルン Adolf Born 1930-
チェスケー・ヴェレニツェに生まれる。プラハ美術工芸大学卒業後、造形美術アカデミーでA.ベルツに師事。
挿絵画家、アニメーション作家。幻想的な雰囲気が漂う作品がある一方で、社会風刺の要素が込められている挿絵もあり、非常に幅のある作風の画家としてチェコのイラストレーションにおける代表的な存在となっている。1964年以降、アニメーション制作にも携わり、M.マツォウレクらとともに短編アニメーションを制作したことでも知られる。
挿絵作品の代表作は、J.アルベス『現代の吸血鬼』(1969年)、A.フランス『ペンギンの島』(1978年)、M.マツォウレク『おとぎ話』(1985年)など、多数。1974年にブラチスラヴァ世界絵本原画展で金のりんご賞を受賞したほか、数多くの賞を受賞している。
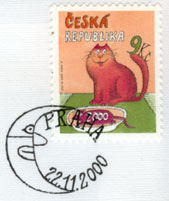
2000.11.22 チェコ発行
【千年紀最後の切手】
ネコちゃんの絵が独特。「あの切手、この人の絵だ!」ってすぐ分かりました(笑)。

『おおいぬフィーク』
イジー・シャラモウン Jiři Šalamoun 1935-
プラハに生まれる。プラハ美術工芸大学で、V.プクル、V.ショフスキーに師事。後にライプツィヒでブック・デザインとタイポグラフィーを学ぶ。1991年から2003年までは、プラハ美術工芸大学のグラフィック学科で指導にあたった。
挿絵画家、アニメーション作家。ラダやトゥルンカの精神を継承する作家として高く評価されている。挿絵の代表作品は、I.ブーニン『サンフランシスコから来た紳士』(プラハ、1970年)、J.R.トールキン『ホビットの旅』(1979年)、P.シュルット『かたつむり』(1983年)、サルティコフ=シェチェドリン『ある都市の歴史』(1989年)など。アニメーション作品には『3×ダウフィン』(1970年)、『おおいぬフィーク』(1975-1984年)、『愛』(1977年)などがある。「チェコの最も美しい本」を繰り返し受賞したほか、『燻製所の物語』は「世界の最も美しい本2000年」にも選ばれた。
会場で『おおいぬフィーク』のアニメが上映されてました。ただし字幕無し。なくても小犬がえらい勢いで大きくなっていく面白さは味わえますけど(女の子が池に落っこちて“Pomoc!”(助けて)と言っているとこだけ分かりました)。アニメの後で絵本化もされてますが、フィークはアニメのがかわいい気がするのは私だけでしょうか(笑)。
2001.5.30 チェコ発行
【子どもたちのために】
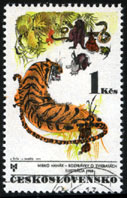
トラと動物たち
ミルコ・ハナーク Mirko Hanák 1921-1971
スロヴァキアのマルティンに生まれる。プラハ美術工芸大学で水彩画を専攻。趣味の釣りや狩猟を通して得た豊かな知識に裏付けられた、いきいきとした動物の姿を描いた。1951年に初めて狩人をテーマにした絵本を描いて以後、生涯に170冊以上の本の挿絵を手がけ、その多くがチェコ国外で出版された。世界各国で自然や動物を描く画家として親しまれているが、詩やおとぎ話の挿絵も手がけている。
1971.9.10 チェコスロヴァキア発行
【ブラチスラヴァ世界絵本原画展】

アルビーン・ブルノフスキー Albín Brunovský 1935-1997
スロヴァキアのゾホルに生まれる。ブラスチラヴァの美術アカデミーに学ぶ。
クラコフ国際版画ビエンナーレ(1980年)にてグランプリ、ブラスチラヴァ世界絵本原画展(1967、1976、1981年)にて金賞、ウッジミニアチュールビンナーレ(1979、1983年)にて受賞など、国際的な版画展において30回以上の受賞歴がある。また、個展はブラチスラヴァ、ベオグラード、パリ、シカゴ、ローマ、ボストン、ニューヨーク、サンフランシスコなどで100回以上開催し、その版画の功績に対し、1980年にスロヴァキア芸術化連合賞、1981年には国民芸術家の称号を与えられた。
1981.9.5 チェコスロヴァキア発行
【第8回ブラチスラヴァ世界絵本原画展】

インドラ・チャペック Jindra Čapek 1953-
チェスケー・ブジェヨヴィツェに生まれる。1969年にスイスに移住。チューリヒの美術工芸学校で1年間学んだ後、ドイツのフライブルク美術アカデミーでグラフィックデザインやイラストレーションを学ぶ。ゴシック期のイタリア絵画など古い時代の絵画様式からインスピレーションを受け、水彩絵の具やエッチングによる細密な描写を得意とする。スイス、イタリア、ドイツ、日本で個展を開催するほか、多くの国際展に参加。主な受賞歴に1983年ボローニャ国際絵本原画展入賞、1985年ブラチスラヴァ世界絵本原画展金のりんご賞、1987年魔法のペン賞(ドイツ)、1999年と2000年にチェコ・イラストレーター賞(チェコ)など。
2004.5.26 チェコ発行
【子どもたちのために】
参考文献:
『チェコアニメの巨匠 イジー・トゥルンカ展 子どもの本に向けたまなざし』(2004年)
『チェコ絵本とアニメーションの世界』(2006年)
『ブラティスラヴァ世界絵本原画展 世界の絵本がやってきた』(2006年)
『チェコへの扉 子どもの本の世界』(2008年)
(いずれも展覧会図録)
|
《戻る》
>>Stamp Album