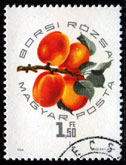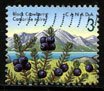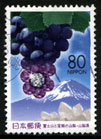Fruit
| 【りんご100年】 |
【ふるさと切手・青森県】 |
|
 |
 |
 |
| 1975.9.17発行 |
1998.11.13発行 |
中華民国発行 |
リンゴ
バラ科リンゴ属の中・高木性落葉果樹。アジア西部からヨーロッパ南東部の原産といわれる。世界各地の温帯域に広く栽培されている。ヨーロッパのリンゴは4000年以上の栽培歴をもち、中国でも古くから栽培されていた。一般に冷涼な気候を好む。日本では中国から渡来したものがワリンゴと呼ばれ、江戸時代になって栽培が普及していたが、明治時代になって欧米諸国からセイヨウリンゴが導入され、東北地方、北海道、長野県などの適地で栽培が進展した。日本では生産量の約95%が生食用だが、欧米では40%以上がリンゴ酒、ビネガー、ジャムなどの加工原料に利用される。古くから知恵・不死・豊饒・美・愛などのシンボルとして知られ、神話や伝説の多くに反映している。
| 【ふるさと切手・山形県】 |
|
 |
 |
| 1989.4.1発行 |
1956年 ブルガリア発行 |
サクランボ
バラ科の落葉果樹。アジア西部からヨーロッパ南東部にわたる地域に原生、分布し、ヨーロッパの栽培歴は古い。日本でおもに栽培されるのは,明治初年に渡来した生食用のセイヨウミザクラ(甘果オウトウ)で、かん詰、ジャムにもする。成熟期に雨にあうと実が割れるので、梅雨の少ない地方で作られる。主産地は山形。
このほかスミノミザクラ(酸果オウトウ)は菓子、ジャムなどの加工原料に利用されるが、生食としての利用は行われない。中国ではシナミザクラが果樹として栽培されている。

スモモ
バラ科スモモ亜属スモモ区の落葉果樹。英語のプラムはスモモ亜属スモモ区に属するものの総称。中国の華中地方、長江流域が原産で、中国、朝鮮半島および日本での栽培歴は古い。
スモモ亜属は北半球温帯に約30種が分布。ヨーロッパで栽培されてきたものにセイヨウスモモがあり、ニホンスモモと一括してスモモと扱われることも多い。アジア西部の原産で、欧米の夏季に雨の少ない地域で多く栽培される。果実を乾燥した乾果および乾果用品種をプルーンとよぶ。自家不結実性が強いので受粉樹の混植または人工受粉が必要である。開花期が早いので晩霜のない地域が適する。主として生食とするが、果実酒、ジャム、ゼリーなどの原料にも用いる。セイヨウスモモは乾果や砂糖漬として料理や菓子にも用いられている。
1956年 ブルガリア発行
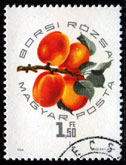
アンズ
バラ科の落葉小高木。東アジア原産。ヨーロッパへは1世紀ころ中央アジアを経て伝わり、改良されて欧州系品種群がつくられた。アメリカのカリフォルニア州へは18世紀に伝わり、ここが現在では世界一の産地となっている。日本には,古く中国より渡来し栽培された。現在の主産地は甲信越と東北地方
。3〜4月にスモモよりやや大きな紅紫色の花を枝いっぱいにつける。果実は6〜7月に収穫。果実は生食のほか、乾果・シロップ漬・ジャム・果実酒の原料などに利用される。種子は杏仁といい、咳止めや喘息の漢方薬とされる。
1964.7.24 ハンガリー発行

桃
バラ科モモ亜属の落葉果樹。中国の黄河上流、陝西・甘粛の両省にまたがる高原地帯の原産。中国から各地に伝わって変種を生じた。高さ3〜8mほどの小高木で、葉は広披針形から長楕円形。4月にふつう淡紅色の花をつけ、6月中・下旬〜8月下旬に成熟する。果実は球形で細毛を有する。
中国での栽培歴は古く、黄肉のモモやネクタリンは7世紀ごろから栽培が始められた。ヨーロッパへはシルクロードを通り、ペルシア・小アジアを経てギリシア、ローマにもたらされ、ついで地中海諸国に普及した。日本では《古事記》や《日本書紀》に記載が見られるが、果樹としての栽培は江戸時代からで、現在の栽培種は明治になって中国から輸入された水蜜桃をもとに改良したものが多い。
1993.9.10 中華民国発行

梨
バラ科ナシ属の落葉高木の総称。果樹として栽培されるものはニホンナシ、チュウゴクナシ、セイヨウナシの3種。ニホンナシは中国の中・北部に原生するヤマナシから改良された栽培品種の総称で、韓国や中国でも栽培される。栽培歴は古くて7世紀末にはナシ栽培が奨励され、また10世紀には信濃や甲斐の国からナシが朝廷に献上された記載がある。果実は球形で成熟果の色は緑、赤褐、黄褐色など。果肉には石細胞が多く独自の舌ざわりがある。セイヨウナシは複雑な雑種起源で、ギリシア時代にはすでに栽培法が述べられている。果実は倒円錐形。ニホンナシに比べ石細胞は小さく、追熟させて食べる。チュウゴクナシは中国の東北・華北地方から朝鮮半島北部原産のミチノクナシをもとに改良された栽培品種で果実は紡錘形に近い球形。中国での栽培歴は古く、《史記》に記載がある。日本にも導入されたが、一般に普及するまでに至らなかった。
中華民国発行
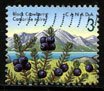 |
 |
| ブラック・クロウベリー |
サスカトゥーンベリー |
カナダ発行
| 【ふるさと切手・山梨県】 |
|
|
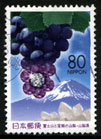 |
 |
 |
| 2001.3.30発行 |
1990年 ハンガリー発行 |
ブドウ
ブドウ科ブドウ属に属する落葉つる植物。前3000年頃には、カフカス地方から地中海東部沿岸地方にわたる地域でヨーロッパブドウの栽培が行われるようになり、同じ頃ブドウ酒造りも始められたとされる。アメリカでは17世紀の初め頃ヨーロッパブドウが持ち込まれて栽培が始まり、気象条件の好適なカリフォルニア州で盛んになった。東部諸州では気象条件が適さず、病虫害がひどいので、耐病虫性の強いアメリカブドウが栽培化されるようになり、ヨーロッパブドウとアメリカブドウの交雑による改良品種も作られるようになった。
日本でのブドウ栽培は、1186年に甲州ブドウが見いだされ、栽培に移されたのが最初とされている。明治に入ってからフランスとアメリカから多くの品種が導入された。種なしブドウには無核品種のほか、ジベレリン処理により単為結果させたものがあり、日本ではほとんどが後者。主要生産国はイタリア、フランス、スペイン、米国など。日本では山梨、長野、山形などが多い。

キーウィ
中国原産のマタタビ科のつる性小木(なので、キーウィの木でも猫は酔っぱらうそうです;笑)。中国の長江南部に自生するシナサルナシの種子が1906年にニュージーランドに導入され、その実生苗から改良されたもの。楕円形で褐色毛に覆われた様子が同国特産の鳥キウィに似ているのでこの名が付いた。
貯蔵性が良好のため各国へ輸出される。雌雄異株なので両者が揃わないと結実しない。
1983.12 ニュージーランド発行
 |
 |
| 1999.9.17発行 |
中華民国発行 |
メロン
果実を食用とするウリ科のつる性植物の一群の総称。日本では主に網メロン、カンタループ、冬メロンなど欧米系の3変種およびそれら相互あるいはマクワウリとの交雑品種をさす。古代エジプトで栽培されていたことが寺院の壁画に見られ、古代ローマのモザイクの中にもこの果実が描かれている。
日本へは明治以降多くの露地メロンが導入されたが,戦前はハネデューなどのアメリカからの導入品種がわずかに栽培されたにすぎなかった。戦後はマクワウリとカンタループや網メロンとの変種間の交雑育種が行われ、とくに1962年プリンスメロンの作出されたことが一大転機となって、現在までに数多くの一代雑種品種が発表されている。

シトラス
かんきつ類。ミカン科ミカン亜科に所属する多数の種。
1983.12 ニュージーランド発行

マンダリン
マンダリンオレンジの略で、狭義のミカンとほぼ同義語。名称は中国清朝の官吏(マンダリン)の服と果実の色が同じであることに由来する。基本的にはインド北東部で生じ、アジア温暖域で古くから栽培分化したミカンの一群。19世紀以降世界の各地に伝播し、オレンジと並ぶ重要な品種群に分化発達した。
ちなみに英語で“Mandarine”とあると、これは「北京官話」(北京語ですね)の意味。
ドイツ語ではオレンジのことをApfelsine(中国から来たリンゴの意味。オランダ語だとsinaasappel)
といいます。柑橘類の多くが中国原産だそうですが、名前にもその影響があるようです。
ガボン発行
| 【ふるさと切手・沖縄県】 |
|
 |
 |
| 1997.6.2発行 |
マレーシア発行 |
パイナップル
熱帯アメリカ原産のパイナップル科の多年草。世界の熱帯,亜熱帯で広く栽培されている。日本では沖縄県に明治から大正時代にかけて、多数の品種が導入試作された。サトウキビ以上に台風に抵抗性があり、主要農産物の一つとなっている。果実は楕円形状の集合果で食用部分は花柄と子房の肥大したもの。芳香の豊かさと風味のよさに加えて、ビタミンA・B・C・G に富み、タンパク質分解酵素ブロメラインを含んでいる。
ブラジルでナナと呼ばれていたのがポルトガル人によってアナナスという名になり、スペイン人は
松毬に似ているからとピナスと名付けたそうです。これを献上されたカール5世はしかし、用心して手を出さなかったとか。
【ふるさと切手・沖縄県】

マンゴー
ウルシ科の常緑の高木。果皮の色は成熟すると黄から桃紅色と変異に富むが、果肉は黄色が多い。果肉は特有のかおりがあり、多汁で美味。北インドからマレー半島にわたる地域が原産地と推定され、古くから果樹として栽培されていた。現在は全世界の熱帯域で広く栽培されている。花は無数に咲くが、結実の少ないことから、宗教上の悟りの困難さを示唆する木ともいう。
1997.6.2発行

番石榴(グアバ)
フトモモ科の常緑小高木。熱帯アメリカが原産で、紀元前からインディオが利用していた。新大陸発見後、急速に世界の熱帯〜亜熱帯域に広がった。台湾には17世紀に伝播し、沖縄にもそのころ渡来した。果実はセイヨウナシ形が多く、果皮は熟すと黄色、果肉は白色になるものが多い。特有の麝香臭があり、甘味と淡い酸味がある。果実には100g当り150mgものビタミンCが含まれているほか、ビタミンAやカルシウム、リンなどを含み栄養価が高い。生食のほか、ジュースやジャム、ゼリーなどに加工される。
。台湾には葉を茶に利用する風習がある。
中華民国発行

龍眼
ムクロジ科の常緑高木。古来から栽培範囲が広く原産地は特定できず、中国南部からインドにわたる地
域のいずれかである。樹高は10mに達し、葉は偶数羽状複葉。果実は直径2〜3cm、5gほどで、10〜20個が集まり房となる。果面は淡褐色でジャガイモの表皮に似ているが、やや硬く殻のようである。暗褐
色の種子を包んだ仮種皮が可食部であり、乳白色でブドウ果粒より硬く、コリッとした感覚と特有の風味がある。乾燥した果肉は竜眼肉といい、漢方薬としても重用される。
中華民国発行

ライチ
ムクロジ科常緑高木。中国南部、ベトナム、ミャンマーに自生する。葉は革質の偶数羽状複葉で披針形。果実は球形で径3cmぐらい、六角形の鱗片でおおわれ、熟すと鮮紅色となる。1個の黒い種子の周囲をとりまいた仮種皮が可食部である。ゼリー状で多汁、甘酸適和し、香気もある。
楊貴妃の好んだ果物として知られ、人馬が8昼夜かけて華南より直送されたという。
2002.2.8 中華民国発行

ランブータン
ムクロジ科の常緑高木。マレー半島原産と推定されるが、古くから栽培されてきたためにはっきりしない。種子の寿命が短く、また成木に育てることが難しいため、東南アジア以外ではあまり栽培されない。
果実は径5〜6cmの楕円球形〜球形で、1枝に10〜20個が房状について垂れ下がる。外果皮は薄く鮮紅色で、柔らかく曲がった肉刺に覆われており、中に種子を1個含む。果肉は半透明の乳白色をしており、多汁で甘味と酸味がある。ビタミンC、糖含量が高い。主に生食用だが、ジャムやゼリーなどに加工されることもある。日本へはタイから一年中冷凍品が輸入されている。
マレーシア発行
解説は平凡社マイペディア、世界大百科事典より

>>Stamp Album