Fishery
1966〜67年発行の魚介シリーズ。 成りゆきまかせコレクションの中では珍しい完集です。 |
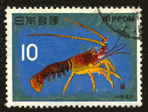 |
 | |
| イセエビ | コイ | |
甲殻類イセエビ科のエビ。祝い事の際によく食べられる。体長は30cmほど。宮城県北部から九州、
韓国、台湾に分布し、浅海の岩礁にすみ、貝、ゴカイ、エビ・カニ類などを食べる。
|
コイ科の魚。ユーラシア大陸温帯部に広く分布する。体長はふつう40cmほど。
フナに似るが4本の口ひげがある。池や沼、流れのゆるやかな川の中・下流などにすむ。雑食性。
| |
| 加藤栄三筆 | 堅田南風筆 | |
| 1966.1.30発行 | 1966.2.28発行 | |
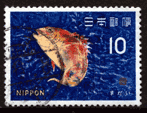 |
 | |
| マダイ | カツオ | |
タイ科の魚。体長は40cmくらい。日本〜南シナ海などに分布。定着性の近海魚で肉食性。
4〜6月に産卵のため沿岸に来遊する。古来、「魚の王」といわれ、刺身、塩焼、うしお、浜焼、
鯛みそなどとして賞味される。
|
サバ科の魚。体長は60cmくらい。生前は不明瞭だが、死ぬと4〜10条の青黒色の縦帯が現れる。
日本では太平洋側に多い。北半球では春になると北方へ回遊する。
遊泳力が強く、時速100kmにもなる。
| |
| 前田青邨筆 | 橋本明治筆 | |
| 1966.3.25発行 | 1966.5.16発行 | |
 |
 | |
| アユ | ウナギ | |
アユ科の魚。香気があって味がよいので香魚ともいう。日本各地に分布。河川の上・中流の瀬や淵に
すみ、各縄張り内の付着藻類を食べる。秋に川底に産卵。孵化した稚魚は海に下り、プランクトンを食べて越冬し、翌春ふたたび川を上る。 |
ウナギ科の魚。日本〜中国に分布。産卵場は太平洋の沖合といわれるが、はっきり分かってはいない。
11〜4月に群をなして川を上り、ふつう8年ほど淡水生活をして成熟し、産卵のためふたたび海に
下る。 | |
| 杉山 寧筆 | 吉岡堅二筆 | |
| 1966.6.1発行 | 1966.8.1発行 | |
 |
 | |
| マサバ | サケ | |
サバ科の魚。体長40cm以上になり、体は太く紡錘形。千島列島以南、日本各地〜中国、フィリピンに
分布する。表層回遊魚で、主として小魚、大型プランクトンを食べる。
|
サケ科の魚。全長1m、産卵期には紅色の斑紋を生じる。9月頃から川を遡って産卵する。孵化した稚魚は、春、川を下って海に入り、2〜5年で成魚となってふたたび川を遡る。
| |
| 上村松篁筆 | 森田沙伊筆 | |
| 1966.9.1発行 | 1966.12.1発行 | |
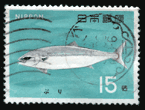 |
 | |
| ブリ | トラフグ | |
アジ科の魚。地方名が多く、また大きさによっても名が異なる。全長1m以上になる。カムチャツカ半島
、サハリン、沿海州、日本各地、朝鮮半島、台湾近海に分布。春に産卵する。
|
マフグ科の魚。全長は70cmほど。室蘭以南の日本、中国に分布。フグ料理の材料として最上。
卵巣や肝臓に強い毒を持つ。春産卵し、旬は冬。
| |
| 奥村土牛筆 | 山田申吾筆 | |
| 1967.2.10発行 | 1967.3.10発行 | |
 |
 | |
| スルメイカ | サザエ | |
軟体動物アカイカ科。死ぬと褐色になり、さらに白色になる。水深30〜100mにすむ。おもに夏〜冬に東シナ海で産卵、12〜5月頃孵化した幼イカは成体となり、黒潮に運ばれ北上し三陸沖〜北海道の太平洋側で漁獲される。
|
リュウテンサザエ科の巻貝。高さ10cm。殻表の2列の突起が特徴だが、瀬戸内海など内海にすむ
ものには無いことが多い。潮間帯から水深20cmくらいまでの岩磯にすみ、夜活動して藻類を
食べる。北海道南部〜九州、朝鮮半島南部に分布。
| |
| 高山辰雄筆 | 山口蓬春筆 | |
| 1967.6.30発行 | 1967.7.25発行 | |