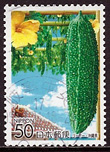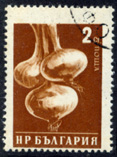Vegetable
| 【ふるさと切手・北海道】 |
|
|
 |
 |
 |
| 1999.9.17発行 |
チェコスロヴァキア発行 |
1964.7.10 ソ連発行 |
とうもろこし
イネ科の一年草。一般に温暖適雨の地を好む。粒の形は品種によって異なり、色も白・黄・橙・赤・紫色などがある。原産地はメソアメリカもしくはアンデス地域のいずれかとされ、新大陸の諸文化の成立や発達に大きな役割を果たしてきた。メソアメリカではトウモロコシを材料とするトルティリャを主食とし、アンデスではチチャの名で知られる酒の材料として主に利用されている。15世紀末にコロンブス一行がスペインに持ち帰り、16世紀前半以降、イベリア半島・地中海地方をへて東ヨーロッパや北アフリカにも普及した。ポルトガル人によってインド・東南アジア・中国へも16世紀の間に伝えられた。日本にも1579年にもたらされたといわれるが、本格的な栽培が始まったのは明治初年、北海道にアメリカの品種を導入してからである。アメリカではコーンと呼ばれるが、元来この英語は穀物を意味する(イギリスでは“Indian Corn”)。17世紀の北アメリカで、当初厳しい自然環境と食糧不足に直面した植民者たちは、ネイティブ・アメリカンからトウモロコシの栽培法を学び、食糧とした。栽培地域は南部から中西部に広がり、いわゆるコーン・ベルトが形成されて今日に至っている。
風によって受粉する風媒花なので、粒の揃ったものを育てるには密植させるのが必須。
「まずお湯を大鍋にたっぷり沸かすために火にかけるのだそうです。それから出かけて行って畑の玉蜀黍を食べる人数分だけもぎとり、帰りは全速力で走るなり、信号無視で車をとばすなりして、全員で皮をむくのももどかしく、たぎった湯の中に放り込むのだそうです。・・・」というのが「玉蜀黍の正しい料理法」だそうですが(『アメリカの食卓』本間千枝子/文春文庫より)、そこまで気合い入れなくても(笑)、もいですぐのゆでたては本当に甘くておいしいんです!


ジャガイモ
アンデス温帯地方原産のナス科の多年生作物。地下茎の先端に肥大したいもを形成する。花は白・黄・淡紫色等で、果実はトマトに似る。冷涼な気候に適し、生育期間も短いので、栽培適地はひじょうに広く、また年間を通じて作られる。
最初に栽培化されたのは500年頃の中央アンデス中南部高地とされ、ペルーやチリの遺跡からはジャガイモをかたどった土器が発掘されている。16世紀中ごろにはスペイン人によって本国に持ち帰られ、ヨーロッパ各国へ伝えられていった。ヨーロッパに入ったジャガイモは、当初はその枝葉や花が好まれ、もっぱら観賞用であった。17世紀にアイルランドにおいて食用作物として本格的に栽培されるようになり、18世紀には大陸諸国にも広く普及した。フリードリヒ2世(大王)がその栽培を奨励したことはよく知られている。日本へは16世紀末にジャワのジャカルタから渡来したのでジャガタライモとも呼ばれたとされる。江戸時代にも栽培の記録があるが、明治初期に北海道開拓使などがアメリカから優良品種を北海道へ改めて導入してからようやく本格的に栽培されるようになった。
1999.9.17発行


アスパラガス
ユリ科の多年草の一属で、茎はときには木本化する。葉は通常退化的で鱗片状となり、光合成は緑色の短縮した小枝(仮葉)が行う。花は小さく6弁、実も小型で球形。日本にもクサスギカズラなど数種を産する。多くは観葉植物として温室栽培され,切葉にもする。
食用のアスパラガスは原産地のヨーロッパでは紀元前から栽培され、日本へは1781年以前にオランダ人によって観賞用として長崎に伝えられ、1871年開拓使によって食用として再導入された。
一度定植すると10〜15年は収穫ができる経済的な永年性の野菜である。グリーンアスパラガスは幼茎が25cm ぐらいに伸びたころ収穫し、ホワイトアスパラガスは盛土の上に頭部をだす直前の幼茎を収穫する。ビタミン類、アミノ酸を豊富に含む。
1999.9.17発行

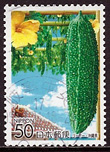
ゴーヤー
ウリ科の一年草。果皮が苦いためニガウリ(苦瓜)とも、ツルレイシとも呼ばれる。インド原産で熱帯アジア、中国、日本で栽培される。中国には明のころ南方から入り、日本へは江戸時代に中国から導入された。主に南西諸島や九州で食用として栽培される。つるは細いが分枝は多く、よく繁茂する。葉は掌状で淡緑色、雌雄異花で夏に黄色花をつける。果実は長楕円形か紡錘形で表面に多数のこぶ状突起を有する。乾燥に強く、栽培は容易。未熟果は油いため、三杯酢、漬物などで食べる。
2005.5.6発行

 |
 |
| 1963.4.25 ルーマニア発行 |
1989年 スペイン発行 |
トマト
ナス科の一年草。アンデス西斜面のペルー、エクアドル地方の原産。熱帯から温帯地方にかけて広く栽培されている。アンデス高原からしだいに中央アメリカやメキシコに伝播し、ヨーロッパへは16世紀に導入されたが、始めは観賞用で、食用にされたのは18世紀以後といわれる。日本には18世紀初めには渡来していたとみられるが、観賞用として栽培されるのみで、食用としての栽培は、明治初年、開拓使による新品種の再導入を機に始まる。しかし食味が一般の嗜好にあわず、大正末ごろまではわずかに栽培されるのみであった。昭和に入ってから食生活の洋風化に伴って需要が増加し、また加工利用の道も開けて、急速に栽培が増えた。ビタミン類に富み、とくにAとCが多い。果実の赤色はリコピン、橙黄色はカロチンによる。
フランス語ではPomme d'amourともいい、これは「愛のリンゴ」の意味。イタリア語のポモドーロは
「黄金のリンゴ」の意味になります。

 |
 |
| 1958.9.20 ブルガリア発行 |
1963.4.25 ルーマニア発行 |
トウガラシ
熱帯アメリカ原産のナス科植物。高温乾燥の環境を好む。重要な香辛料として世界各地で栽培されている。果実は球形・長卵形・細長いくちばし形など種々で、辛味成分カプサイシンの多少によって辛味種と甘味種とに分ける。辛味種は成熟すると赤色になり、一般にトウガラシとはこれをさすが、黄色または紫色になるものもある。果実のほか、葉にも辛みがあり、葉トウガラシとして利用される。15世紀にコロンブスによって伝えられ、ヨーロッパ各地に広まった。その後インド・東南アジアに伝わり、中国には16〜17世紀ころ渡来したといわれる。日本には朝鮮出兵の際に伝来したとみられ、急速に普及し定着した。


ラディッシュ
アブラナ科の一年草。ヨーロッパから導入されたダイコンの一種。季節、品種により早いものは播種後20日ほどで収穫できるため、ハツカダイコンの別名がある。根茎は小型の球形で表面は鮮紅色が多いが、白・黄・紫などもある。古くから西洋に分布し、ピラミッドの碑文にもピラミッド建設のときにタマネギやニンニクとともにハツカダイコンを労働者に食べさせたことが記されている。原産地は不明で、古いヨーロッパの野生種の交雑によりできたものと考えられている。手軽に栽培できるので、家庭菜園用にも適している。色彩が鮮やかなため、生でサラダやオードブルの添物にしたり、酢漬などにして利用する。
1963.4.25 ルーマニア発行


キュウリ
ウリ科のつる性一年草。キュウリは〈黄瓜〉の意で成熟したときの色にちなみ、〈胡瓜〉はその来歴を示す。インドのヒマラヤ山系地帯の原産。温暖な気候を好む。茎は細長く、巻ひげで他物にからみ、雌雄異花で、ともに花冠は黄色で5裂。果実は円柱状で、果皮には多数のいぼがある。品種や栽培法の違いで苦味を感ずるものがあるが、これはククルビタシンCによる。若干のビタミンAとCを含むが、栄養・保健上はあまり重要視されない。しかし未熟の間は遊離アミノ酸が多く、独特のうまみがあり、古くから各種の漬物、酢の物に利用された。日本へ伝えられた時期は不明だが、奈良時代に食用にされていたことが立証されている。ウリ類は古来水神と縁の深いものとされてきたが、キュウリも水神やその妖怪化した河童の好むものとされている。
1958.9.20 ブルガリア発行

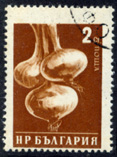
タマネギ
ユリ科の二年草。葉は濃緑色の円筒形で、基部は肥厚した鱗片となり、これが重なり合って鱗茎を形成する。鱗茎の形成は温度と日長とに影響され、温度は15.5〜21℃、日長は11.5〜16時間でよく結球する。原産は中央アジアとされる。古代エジプトには早く伝わり、ピラミッド建設の際には奴隷に食べさせ労働に従事させたという記録がある。その後、地中海地方で発達し、ヨーロッパ全域に広まった。アメリカには16世紀以後、スペイン人によって導入された。東洋ではインドで古くから重要野菜として栽培が盛んで、輸出も行われている。日本では1627-31年に長崎での栽培記録があるが、当時のものは土着せず、その後1871年に欧米から種子が導入され、北海道で土着した。第2次大戦後、食生活の洋風化とともに栽培、利用ともに著しく伸びている。用途は生食用、炒め物、煮込料理などきわめて広く、洋風料理の副材料として欠かせない。
1958.9.20 ブルガリア発行


ニンニク
ユリ科の多年草。原産は中央アジアまたはインドなどとする説もあるが、野生植物が発見されず明らかではない。花茎は円く高さ30〜60cm に直立し、下部が鞘状になった扁平な葉を2〜3枚出す。夏、白紫色の散形花を開く。鱗茎は5〜6個の小鱗茎からなり、すりつぶすと強烈な刺激臭を発する。5〜6月に収穫。古くから香辛料・強壮剤として知られ、エジプトではすでに王朝期以前から栽培され、ギリシア・ローマ時代にもよく利用されていた。日本では《本草和名》以後に記載がみられるところから、導入、栽培されたのは10世紀以前からのことといわれる。ニンニクのにおいはアリルトリサルファイド(三硫化アリル)で、またビタミン B1を多く含んでいる。油脂によくなじみ肉類のうまみを引き立てるので、肉料理などに多用される。強烈な異臭にまつわる俗信が多い。
1958.9.20 ブルガリア発行

解説は平凡社マイペディア、世界大百科事典より

>>Stamp Album