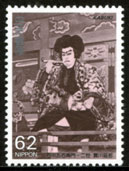歌舞伎
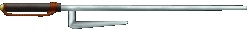
【国立劇場開場】

歌舞伎
『菅原伝授手習鑑』の吉田社頭車引の場面を描いた初代歌川豊国の浮世絵。
何しろカタログにはそっけなく「歌舞伎」としか書いてなかったので、この演目だということは
内藤陽介氏のブログで知りました。図案の解説についてもこちらをお読みください。
生まれて初めて見た歌舞伎がこの演目の「寺子屋」でした。小学5年生の時、父が御園座に連れて行ってくれたんです。終わると同時に父に尋ねましたが。「ねえ、お父さん、菅原道真って、太宰府に流罪だったよね。何で関係ない子どもが首斬られるの?」・・・父の返事は覚えてませんが、これはそういう話なんだ! と言うより仕方がなかったでしょうなあ(笑)。他の演目の早変わりとかが面白かったのも覚えてるんですが、未だに歌舞伎好きにはならない娘でありました。
1966.11.1発行
《古典芸能シリーズ》

娘道成寺
宝暦3年(1753)3月、江戸中村座初演。熊野詣の僧安珍を追った清姫が、蛇体になって道成寺の鐘に巻きつき焼きとかしたという、道成寺縁起の物語。その後日譚としてできた能『道成寺』を、初代中村富十郎が女形の長編舞踊として演じ、大好評を博した。
焼失した鐘が再興の日、女人禁制の寺へ白拍子が訪れ、さまざまな舞を披露するうち、僧の隙を見て鐘にとりつく。蛇体となるが祈り伏せられる。

助六
天保3年(1832)3月、江戸市村座での上演時に現行演出が完成。歌舞伎十八番の一つ。上方では揚巻助六は心中物の主人公であった。それを江戸に移して世話風の色男につくりかえたのが2代目市川團十郎で、正徳3年(1713)上演時の新機軸であった。
市川家の台本では全体を曽我物狂言に連結させ、助六は紛失した名刀友切丸の探索のために廓に通い、喧嘩を売って刀を抜かせて探しているという設定。助六の馴染みの傾城揚巻に執心する意休は、助六の悪態にも刀を抜かない。白酒売の兄十郎が弟に意見するが、刀詮議のためと聞くや、喧嘩指南、喧嘩相手に股くぐりをさせる滑稽な場面となる。侍姿の母の満江が来て喧嘩をやめさせ、十郎を連れて帰る。意休が三本足の香炉台を切ると、その刀こそ尋ねる友切丸。揚巻は勇み立つ助六を制して、意休の帰りを待ち伏せすることをすすめる。この後に助六が地回りに追われて用水桶に隠れる「水入り」の演出がつく場合もある。

勧進帳
天保11年(1840)3月、江戸河原崎座初演。能『安宅』を題材に、7代目市川團十郎によって初演。のち、9代目が洗練した。歌舞伎十八番のうちのひとつ。
源頼朝と不和になった義経は、弁慶らとともに山伏、強力姿に変装して逃避行。安宅の関へさしかかる。関守富樫左衛門の前で、何も書かれていない巻物を勧進帳として読み上げたり、見咎められた義経を杖で折檻するなどの苦労の末、許され陸奥へ落ちのびる。
1970.7.10発行
《歌舞伎シリーズ》
六世 中村歌右衛門の八重垣姫(本朝廿四孝)、十三世 片岡仁左衛門の翁(寿式三番叟)が抜けているので完集ではないです。額面100円の方はなかなか揃わなくて・・・

鏡獅子(六世 尾上菊五郎)
明治26年(1893)3月、歌舞伎座初演。9代目市川團十郎が娘の『枕獅子』を稽古している姿を見て、設定を遊郭から千代田城大奥に移しかえて、時代の高尚趣味にあわせてつくり直したもの。
千代田城の大奥。正月七日の行事である鏡曳きの余興に殿様が小姓の弥生に舞を所望。獅子頭を手にすると魂が乗り移り、獅子に変じる。
1991.6.28発行

武蔵坊弁慶(七世 松本幸四郎)
演目は「勧進帳」。内容は上記で紹介したとおり。

粂寺弾正(十一世 市川團十郎)
演目は「毛抜」。歌舞伎十八番の一つ。寛保2年(1742)1月大坂の佐渡島座で2代目市川
團十郎が演じた『鳴神上人北山桜』の3幕目「小野春道館」が独立したもの。
小野春道の息女錦の前は文屋豊秀の許嫁だが、病気を理由に祝言が延びているので、豊秀の家来の粂寺弾正が使いに出された。姫の病気は髪の毛が逆立つという奇病。ところが弾正が毛抜を出して髭を抜きはじめると、毛抜が立って踊りはじめる。弾正が天井を槍で突くと大きな磁石をかかえた忍者が飛び降りた。姫の鉄製の櫛や髪飾りを磁石で吸い上げていたのである。すべてはお家乗っ取りをたくらむ家老の八剣玄蕃の策略と判明、弾正は意気揚々と引き上げる。
1991.9.27発行

扇屋夕霧(三世 中村梅玉)
演目は「吉田屋」(「夕霧」、「廓文章」とも)。
正徳2年(1712)大阪竹本座初演。近松門左衛門作。
正月支度の師走餅つきの日、廓に通いつめたため、勘当の身となった藤屋伊左衛門は、紙衣姿で大阪新町の吉田屋を訪れる。相方の傾城夕霧が来るのが遅いのにじれて、さんざんに悪態をつくうちに、勘当が許され、身請けの金も届きハッピーエンドとなる。夕霧の紫の鉢巻は病の象徴。

紙屋治兵衛(二世 中村鴈治郎)
演目は「心中天網島」。近松門左衛門作。享保6年(1721)夏、江戸森田座にて歌舞伎化初演。
大坂天満の紙屋治兵衛と曾根崎新地の遊女小春は深い仲になっていた。治兵衛の妻おさんは、小春に手紙を書いて夫と別れてほしいと頼む。小春はおさんの気持ちをくんで、偽りの愛想づかしで治兵衛と別れる。しかし、小春が夫の恋敵に身請けされると聞いたおさんは、小春が死ぬつもりだと直感、小春を身請けさせようとする。ところが、怒った父親におさんは実家に連れ戻されてしまう。小春と治兵衛はその晩、網島の大長寺で心中するのだった。
1991.11.21発行

熊谷次郎直實(初世 中村吉右衛門)
演目は「一谷嫩軍記」。宝暦2年(1752)5月、江戸の中村座と森田座の両座で歌舞伎化初演。源平合戦を背景に、一ノ谷の合戦における熊谷次郎直実と平敦盛、薩摩守忠度と岡部六弥太の物語を中心に脚色した作品で、今日では三段目の「熊谷陣屋」が多く上演される。
平家の公達の若い命を散らすなという義経の心を察した熊谷直実は、一ノ谷で組み伏せた平敦盛の命を助け、わが子小次郎の首を首実検にそなえた。また、弥陀六を幼いころの自分を助けた平宗清と見破った義経は、旧恩を謝して鎧櫃を与える。宗清は、その中に敦盛が忍んでいることをさとり、義経と直実の志に感謝する。我が子を犠牲にしても武士道を立てる無常をさとった直実は、剃髪出家して、諸国行脚に出るのだった。
1992.2.20発行
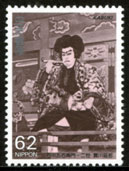
石川五右衛門(二世 實川延若)
演目は「楼門五三桐」。安永7年(1778)4月、大坂角の芝居初演。初世並木五瓶作。原作は、大泥棒石川五右衛門を主人公とした五幕の通し狂言だが、そのなかの南禅寺山門の場が代表的な場面となっている。
豪華絢爛たる南禅寺山門で、石川五右衛門が煙草をくゆらしながら桜の景色を楽しんでいる。そこへ鷹が運んできた着物の片袖から自分が宋蘇卿の子であることを知り、敵である真柴久吉への復讐を誓う。山門の回廊の下に一人の巡礼が現れ、五右衛門が手裏剣をうつと、男は平然と柄杓で受け止める。この巡礼、実は真柴久吉であった。

大石内蔵助(初世 松本白鸚)
演目は「元禄忠臣蔵」。真山青果作。全10編。
昭和の忠臣蔵と呼ばれる連作で、昭和10年(1935)1月、東京劇場「江戸城の刃傷」からはじまり、「御浜御殿綱豊卿」「大石最後の一日」をふくめ、元禄14年3月、浅野内匠頭の吉良上野介への刃傷から、赤穂浅野家家臣の苦労、同16年2月の46人の切腹まで、歴史の事実を綿密に調査したうえで、雄渾な大作として6年がかりで上演された。
1992.4.10発行

藤娘(七世 尾上梅幸)
文政9年(1826)9月、江戸中村座初演。吃の又平が描いた大津絵の精がつぎつぎと抜け出して、悪者たちをこらしめる五変化所作事の一曲。現在は藤の精が松の大木にからみつく、という6代目尾上菊五郎の演出が一般的。

曽我五郎(二世 尾上松緑) 曽我十郎(十七世 中村勘三郎)
演目は「寿曽我対面」。享保以後の江戸歌舞伎ででは、曾我兄弟が敵である工藤祐経に対面する形式が、正月狂言一番目大詰に必ず設けられていた。
小林朝比奈が兄弟の目通りを祐経に頼み、許されると祝儀の島台を掲げて兄弟が登場する。与えられた盃を叩き割る五郎だが、祐経は狩場の通行切手を兄弟に与え、再会を約束する。
1992.6.30発行
【歌舞伎発祥400年】

「暫」と「土蜘」
発行されたばかりの時に、きってコレクションの
きって★れびゅーを爆笑しながら読んだものです。というわけで、私の中では“ネタ”確定の切手。うん、こうして並べてみると、いよいよしょぼさが際立ちますね〜。
リンク先からとべる公社のページに一応解説がありますが、演目の紹介は無いに等しいので、簡単に載せておきます。
「暫」:初代市川團十郎作。元禄10年(1697)1月、江戸中村座初演。
清原武衡が家来たちを従えて善人たちの首をはねようとすると、花道から「しばらく」と声をかけて鎌倉権五郎景政が登場。善人側は命が助かり、権五郎は大太刀をひと振りすると仕丁(雑役夫)の首をずらりと切り、悠々と花道を引っ込んでいく。
「土蜘」:明治14年(1881)6月東京新富座初演。能『土蜘』が題材。
病中の源頼光を僧が見舞うが、土蜘の精とわかる。名刀の威力で逃げ帰った土蜘を四天王らが立回りの末、退治する。くもの糸を投げつけるスペクタクル。
2003.1.15発行
参考文献:『歌舞伎ハンドプック 第3版』(藤田洋【編】/三省堂)
Images by トリスの市場
>>Stamp Album