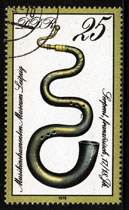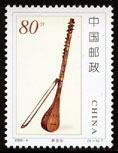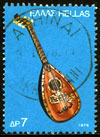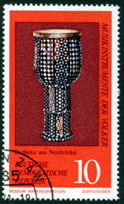Instrument
木管楽器
金管楽器を除く管楽器。管の材質が木製のものが多いので木管楽器と呼ばれるが、サクソフォンのように金属製の楽器もある。

オーボエ(1785) クラリネット(1830) クヴェルフレーテ(1817)
マークノイキルヒェン博物館所蔵
【オーボエ】 楽器の先にアシのくきを乾燥させて薄く削ったリードという小片を取り付け、上下のくちびるを巻き込みながらくわえて息を吹いて演奏する。バロック時代以降表現力の高い木管楽器として独奏・合奏に用いられ、管弦楽に常席を占める楽器となった。現在多く使われている型はコンセルバトワール式と呼ばれ、19世紀にフランスのオーボエ制作者のトリエベールが完成させた。
【クラリネット】 18世紀初期に生まれた木製の縦笛が祖先。高音トランペットの「クラリーノ」に音色が似ていたので、「小さなクラリーノ」という意味のこの名があるといわれる。18世紀後半にマンハイムの楽団で常用されて脚光を浴び、1790年ころにはヨーロッパ各地の楽団に定着。以後オーケストラに欠かせない重要な楽器となった。音域は4オクターブ近くあり、幅広い表現力を持つ。
1977.6.14 ドイツ民主共和国発行
金管楽器
奏者の唇を振動させて音を出している管楽器。唇の振動だけでは大きな音にならないので、管の末端に大きなベルを付けて大きな音になるようにしている。
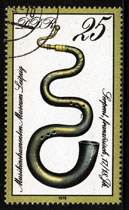
セルパン
17/18世紀 フランス ライプツィヒ楽器博物館所蔵
蛇のような曲がりくねった形をしていることから「蛇」という名前を持つ。16世紀にフランスで登場、教会で使われた。低音楽器の元祖といえる楽器。下向きに抱えて演奏する。
1979.8.21 ドイツ民主共和国発行

スーザフォン
アメリカのマーチ王スーザが作らせた楽器。スーザはベルを上に向けたが、彼の死後、前に向けられるようになった。マーチングバンドに欠かせない楽器。
1974.5.12 チェコスロヴァキア発行
【プラハとブラチスラヴァの音楽祭】
鍵盤楽器

アコルデオン
1900頃 マークノイキルヒェン博物館所蔵
【アコーディオン】 楽器に付いている「蛇腹」を伸ばしたり縮めたりして、空気を楽器内部に送り込んでリードを鳴らす楽器。種類は様々だが、基本的には両手で抱えて構え、右手側の鍵盤やボタンでメロディーを、左手側のボタンで和音などを鳴らして演奏する。
この楽器の一種であるバンドネオンは、ドイツで1840年頃に発明されたのち、アルゼンチンに導入されてタンゴの主要楽器として使われるようになった。
1977.6.14 ドイツ民主共和国発行
その他の気鳴楽器

トルステンケ
【パンパイプ】 アシの茎で作った長さの違う管を並べ、息を吹き込んで音を出す単純な構造の笛。ギリシア神話の半獣神パンの笛ということからこの名が生じ、古代ギリシアではシュリンクスと呼ばれた。ルーマニアではナイと呼ばれ、アジア,オセアニア,ラテン・アメリカにもみられる。
1993年 スロヴェニア発行
 |
 |
 |
 |
| ドゥーデルザック(ボヘミア) |
カイディ |
ドゥデイ |
ガイダ |
1971.10.26
ドイツ民主共和国発行 |
1974.5.12
チェコスロヴァキア発行 |
1984.2
ポーランド発行 |
1975.12.15
ギリシャ発行 |
【パグパイプ】 牧羊地域に広く分布する民族楽器。起源については定かではないが、西アジア、おそらくはメソポタミアあたりの発祥で、東西に広められていったものと推定される。ヨーロッパでは13世紀に普及した。地域によって形態や名称にきわめて多様なものがみられる。
演奏法は、まず羊や山羊の皮で作った袋を左脇に抱え、吹き口から息を吹き込む。そして左手でバッグを押さえて、空気をそれぞれの管へ送る。ドローンで伴奏の音を出しつつ、チャンターについている穴を押さえてメロディーを奏でる。

ブッケホルン
ノルウェー発行
打弦楽器

ピラミドヴィ・クラヴィル(19世紀のピラミッド型クラヴィール)
1974.5.12 チェコスロヴァキア発行
【プラハとブラチスラヴァの音楽祭】
擦弦楽器
弦を弓で擦って音を出す弦楽器。管楽器のように出した音を持続することが可能。

ポントスのリラ
リュート属擦弦楽器。トルコの古典音楽のケメンチェ(トルコで踊りの伴奏などに使われる擦弦楽器)と同系で、西洋中世のルベックとも関係が深い。木製の洋梨形共鳴胴と短い棹をもつ。3弦の弓奏楽器。
1975.12.15 ギリシャ発行

リラ・ダ・ガンバ
1592年 イタリア ライプツィヒ楽器博物館所蔵
【リラ】 西洋ルネサンスのリュート属擦弦楽器。バイオリンに近い共鳴胴に多数の弦を張り、幅広の棹と板状の糸倉に垂直に差し込んだ糸巻が特徴。
1979.8.21 ドイツ民主共和国発行

ヴィエル・ア・ル
1750年頃 フランス ライプツィヒ楽器博物館所蔵
ヨーロッパに広く分布する機械的な擦弦楽器。10世紀頃に伝わり、16〜18世紀にかけて現在みられるような形になった。リュート型の共鳴胴をもち、右端にハンドルがつく。右手でハンドルを回すと松脂を塗った木輪が回転して弦をこすり、音が出る。鍵盤がついており、左手の指で鍵を押して旋律を奏する。ふつう旋律弦2本、ドローン(持続音)弦2〜4本。ドイツ語ではライアー、英語ではハーディ・ガーディなど、各地で様々な名称がある。大道芸人がよく使う民俗楽器。
1979.8.21 ドイツ民主共和国発行

ディスカント・ガンベ(5弦ガンバ)
1747年 マークノイキルヒェン博物館所蔵
1977.6.14 ドイツ民主共和国発行

フスレ(ヴァイオリン)
1974.5.12 チェコスロヴァキア発行
【プラハとブラチスラヴァの音楽祭】
 |
 |
| 軋琴(アッキン) |
二胡 |
【軋琴】 箏琴ともいわれる河北北方の戯曲伴奏用楽器。10弦弓奏の琴。
【二胡】 2本の弦を張り、その間にはさんだ弓を弾く。胴は木や竹の筒の片面にヘビの皮を張ったものが普通。もともとは合奏用の楽器だが、やがて独奏もさかんになった。
【板胡】 表面に薄い桐板を張った木製二胡。
【薩它尓】 ウイグル族はじめイスラム圏での糸弦2、金属弦7の長頚楽器。
【馬頭琴】 「スーホの白い馬」でも知られる民族楽器。モンゴル語ではモリンホール。民謡の伴奏、独奏、合奏に用いられる。2弦で木製の台形の胴に皮を張り、1メートルほどの長さの棹の先に馬頭の彫刻をつける。弦と弓には馬の尻尾の毛が使われる。
2001.10.12 中華人民共和国発行
撥弦楽器
弦を指ではじいて音を出す弦楽器。和音など同時にたくさんの音を奏でるのに適している。
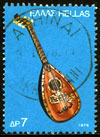
ラウート
リュート。古代パンドゥーラなどと呼ばれていたものがアラブの影響で改作された。
1975.12.15 ギリシャ発行

マンドリン
イタリア マークノイキルヒェン博物館所蔵
18世紀にマンドーラ(小型のリュート)から発展。現在のものはナポリ式と呼ばれ、バイオリンと同様に5度間隔で調弦される。金属弦を同音に2弦使用し計8弦。胴は半球状で指板にはフレットがつく。右手に持ったプレクトラム(義甲、ピック)で演奏され、トレモロ奏法が特徴的。独奏、合奏に用いられ、米国のカントリー・ミュージックでも愛用された。音量が小さく、19世紀以降の管弦楽に使われるのはまれだが、マーラーの《交響曲第7番》や《大地の歌》はこの楽器の音色を巧みに生かした好例。
1971.10.26 ドイツ民主共和国発行
 |
 |
| コンツェルトツィター(1891) |
チトレ(小型のチター) |
| 1977.6.14 ドイツ民主共和国発行 |
1993 スロヴェニア発行 |
【チター】 オーストリアやスイス、ドイツなどで演奏される伝統楽器。18世紀末には現在使われているような形のものが作製されている。一般的にはメロディー専用のフレットに弦が5本、伴奏用の弦が40本前後。2キロほどの重さの楽器で、ピアノよりやや少ない6オクターブの音を奏でることができる。椅子に座り、テーブルや膝に楽器を乗せて左手で上からフレットを押さえ、右手の親指に金属製のつめを付けて、メロディー用の弦と伴奏用の弦をいっしょにはじいて演奏する。

箏
東アジアに分布するロング・ツィター属の撥弦楽器。秦代には存在していたとされる。はじめは5弦であったとされるが、次第に増えて、唐・宋代には13弦、清代には16弦、今日普及しているのは21弦の金属弦のもの。可動柱を用いる。古代には合奏用であったが、その後独奏にも用いられるようになった。日本へは奈良時代に伝来し,雅楽に用いられるようになった。
1969.3.16 中華民国発行

サウン・ガウ
ハープ属撥弦楽器。11〜16本の絹糸またはナイロン弦が舟形の共鳴胴と、先にのびている弓形の棹にかけて張られている。右手の親指と人差し指で弦をはじき、左手は弓形の棹に当てて機敏に上下させながら親指の先で弦を押して、音高をあげたり頻繁に装飾をつけたりする。インドから伝わったともいわれるが,現在はビルマの竪琴として知られる。
ミャンマー発行

ビーナー
南インドのリュート属撥弦楽器。カルナータカ音楽(ヒンドゥー的要素の強い古典音楽)の独奏楽器。最高級品は1本の木をくりぬいて作り、棹の片端には紙のはりぼてか瓢箪製の共鳴体を取り付ける。4本の演奏弦と3本のリズムを刻むサイド弦。あぐらをかいて座り、楽器を横に抱きかかえるように構え、棹の上にワックスで固定されたフレットに沿って弦を押したり引いたりして、うねるような独特の旋律を奏する。シタールによく似ているが、ビーナーの方が地味な音色。
1974.10.1 インド発行
体鳴楽器
楽器そのものを叩いて音を出す打楽器。

ラナート・トゥム
【木琴】 赤道をはさんで、雨量が多く、したがって樹林の多い熱帯圏を、東南アジアからアフリカを経てラテンアメリカへ伝播。インドシナ半島のラナート系は、舟形の共鳴箱の上に、多少の反りをもって並べられる。
1982.11.30 タイ発行
膜鳴楽器
張ってある膜を叩いて音を出す打楽器。

ミルダンガム
インド、タミール系の両面太鼓。ムリダンガム
1969.11.10 シンガポール発行
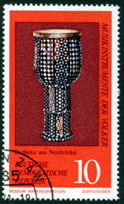
ダルブッカ
南アフリカ マークノイキルヒェン博物館所蔵
アラブ世界で広く演奏されている太鼓。素焼きの胴体に薄いヤギの皮やエイなど魚の皮を張った片面の太鼓。皮を下に床に立てると花瓶のように見えることから、学術的には「花杯型片面太鼓」と分類される。形を生かして、通常は左足のももの上に床に平行になるように於いて、手で叩いて演奏する。紀元前後の古代ペルシャから、中世にアラブ人やイスラム教徒によって東南アジアから西アフリカまで広がっていった。
1971.10.26 ドイツ民主共和国発行
その他

ムンハルペ
【口琴】 細長い弁を振動させ、口腔に共鳴させる楽器の総称。奏者は舌と喉頭を動かして口腔の
形を変化させ、いろいろな倍音を増幅して多様な音高と音色を出す。金属製、竹製や木製など
(ムンハルペは金属製)。世界各地にさまざまな名称で広く分布。英語での通称はジューズ・ハープ。
1983.5.3 ノルウェー発行
参考文献:
『平凡社マイペディア』
『切手に見る世界の楽器』(江波戸昭・著/音楽之友社)
『世界楽器切手総図鑑』(江波戸昭・著/日本郵趣協会)
『世界の民俗音楽 〜切手でみる楽器のすべて〜』(江波戸昭・著/生活情報センター)
『切手に見る世界の民俗楽器』(江波戸昭・著/音楽之友社)
『カラー図解 楽器の歴史』(佐伯茂樹・著/河出書房新社)
『世界なるほど楽器百科』(ヤマハミュージックメディア)
|
《戻る》