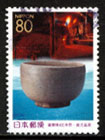【陸羽】 ?〜804 中国・唐の茶の創始者。復州竟陵(湖北省天門県)の人。生まれは不明で捨て子ともいわれる。竟陵龍蓋寺の智積禅師のもとで育てられたが、僧になることを嫌って出奔。芝居一座の一員となったが、太守の李斉物の目にとまり、学問を授けられた。安禄山の乱ののち、呉興(浙江省)に移り住んで隠棲。この地で皎然という友に出会い、湖州刺史であった顔真卿の保護を受けた。著書に「茶は南方の嘉木なり」ではじまる『茶経』(3巻)があり、茶道の元祖として名高く、茶神として祀られている。
図案といい切手のでかさ(これでも実はきもち縮小)といい、いかにも中国発行の小型シートのおもむきなのですが、これがなぜかタンザニア発行。なんでまたこんな外貨稼ぎにもならなさそうな図案をわざわざ? というのが面白くてつい買ってしまったのでした(笑)。
陸羽については陳舜臣氏の『茶事遍路』(集英社)に詳しいです。
下は正真正銘中国発行の〈茶〉シリーズより。