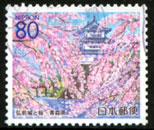さ く ら
 |
ハナニアラシノタトエモアルゾ サヨナラダケガジンセイダ
どーせこの時期は花見に行くような余裕なんか時間的にも精神的にもないんだー、といささかヤケ気味になって考えた企画です。
数年前から考えてはいたんですが、「河津桜」の切手がきっかけで、実現意欲がわきまして。
ネットで調べにまわったところ、ふるさと切手博物館の第22回展示ですでに先を越されているのを発見して、多少悩みましたが、ま、せっかく作ったということで・・・。(苦笑)。 |

河津桜
2月上旬から3月上旬の1か月間、静岡県伊豆地方南部で淡紅色の花を咲かせ、「本州一の早咲き桜」として知られる。原木が静岡県賀茂郡河津町にあることから1974年に「河津桜」と命名された。
1955年頃、河津町の河津川沿いで発見されて移植・栽培されていたものが、1966年から開花がみられるようになり、1968年頃から増殖された。緋寒桜と早咲きの大島桜の自然交配と推定されている。
参考サイト : 郵政公社東海支社報道発表 河津桜まつり情報局
【ふるさと切手・静岡県】
2006.2.1発行
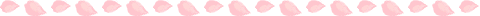

淡墨桜
岐阜県本巣市にある樹齢1500余年、樹高16.3m、幹囲9.9mを誇る大木の名桜。枝張りは東西方向に約27m、南北方向に約20mもある。彼岸桜の一種で、蕾のときは薄いピンク、満開に至っては白色、散り際には淡墨色になることから淡墨桜と名付けられた。継体天皇お手植えとの伝承もある。
大正初期から何度も枯死寸前になり、昭和23年頃の文部省の調査では、「あと三年以内には枯れるだろう」といわれるまでになっていた。昭和24年3月10日より、根に巣くっていたシロアリを駆除、土壌の入れ替え、僅かに活力のある残根に近くの若い山桜の根を238本継ぎ足すなどの大手術が行われ、往年の盛観を取り戻した。しかし昭和34年の伊勢湾台風により、太い枝が折れ葉や小枝はほとんどもぎ取られるという大きな被害をうけてしまう。この時、作家の宇野千代がその保護を訴えて活動した。
大正11年10月12日には、三春の滝桜、実相寺の神代桜(山梨県北杜市)と共に国の天然記念物に指定された。
参考サイト : 本巣市ホームページ
これだけ有名な桜なんだから一度くらいは見ておこう、とはるばる樽見鉄道に乗って見に行ったことがあります。見物客の多さには閉口しましたが、やっぱり実際にあの大きさを眼にすると、迫力ありましたね〜。散り際になるという淡墨色ってどんな色なんだろうな、と思いながら、まだ確かめる機会を得ていません・・・
【ふるさと切手・岐阜県】
1999.3.16発行
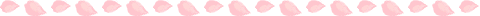
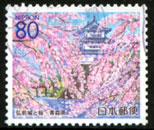
青森県「弘前城と桜」
日本一の規模を誇る弘前公園の桜は、正徳5(1715)年津軽藩士が25本のカスミザクラなどを京都から取り寄せ、弘前城内に植えたのが始まりといわれる。明治に入って、荒れ果てた城内を見かねた旧藩士・菊地楯衛が、ソメイヨシノ1000本を植栽。平民の花見は許さんと、一部士族の迫害を受けたが、明治30年代に再び1000本を植栽。その後も市民からの寄付は続き、大正に入るとお城の周りは見事な桜で埋まった。現在、公園内には、現存する日本最古のソメイヨシノをはじめ、シダレザクラ、八重桜など、約50種類2600本の桜がある。
参考サイト : 弘前さくらまつり
【ふるさと切手・東北のさくら】
2000.4.3発行
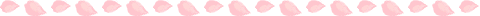

岩手県「石割桜」
盛岡地方裁判所の敷地にあり、巨大な花崗岩の狭い割れ目から生えていることから「石割桜」と呼ばれる。種類はエドヒガンザクラで、直径約1.35メートル、樹齢は360年を越えるといわれる。昭和7年に盛岡地方裁判所が火災に遭い、石割桜も北側の一部が焼けたが、幸い全焼を免れ翌春には再び花を咲かせた。現在は保護管理も良く、毎年見事に開花を続け、たくさんの人の目を楽しませている。ここは南部藩主の分家にあたる北監物の庭園であったといわれ、明治初期には桜雲石と呼ばれていたらしい。大正12年に国の天然記念物に指定されている。
参考サイト : 盛岡さくらまつり
【ふるさと切手・東北のさくら】
2000.4.3発行
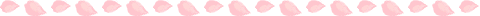

宮城県「一目千本桜」
阿武隈川の支流・白石川の両岸7kmに立ち並ぶ、まさに「一目で千本見える」感じのソメイヨシノ群。大河原町出身の事業家・高山開治郎が、大正12年と昭和2年に合計約1200本の桜の苗木を寄付、職人とともに自らもたずさわって植樹したのがこの桜名所のはじまり。晴れた日には、残雪の蔵王連峰と桜並木が水面に映り、絶妙な調和をみせる。
参考サイト : 大河原町ホームページ
【ふるさと切手・東北のさくら】
2000.4.3発行
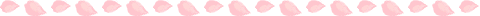

秋田県「桧木内川と桜」
仙北市の桧木内川沿いにある約2kmのソメイヨシノの並木。昭和9年、現天皇陛下のご誕生を記念してソメイヨシノが植えられたのが始まり。昭和50年、国の名勝に指定された。
参考サイト : 仙北市ホームページ
【ふるさと切手・東北のさくら】
2000.4.3発行
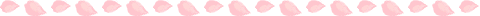

山形県「久保桜」
山形県長井市にある、樹齢約1200年といわれるエドヒガンザクラの古木。根周10.8m、目通りの幹囲8.1m、高さ約16m。幹の部分 は3つに分裂し、根元は空洞になっている。 枝張りは約10m。坂上田村麻呂と地元の豪族久保家の娘・お玉との悲愛伝説にちなんで、地元では「お玉桜」とも呼ばれている。1924年に国の天然記念物に指定された。
参考サイト : 長井市ホームページ
【ふるさと切手・東北のさくら】
2000.4.3発行
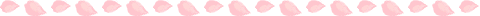

福島県「三春滝桜」
福島県田村郡三春町にある、樹齢1000年以上のエドヒガン系のベニシダレザクラの古木。樹高は12m、根回りは11m、枝張りは幹から北へ4.6m、東へ10.7m、南へ13.9m、西へ14.5mの巨木。毎年4月中・下旬に、四方に伸びた太い枝から、薄紅の滝がほとばしるかのように小さな花を無数に咲かせ、その様はまさに滝が流れ落ちるかのように見えることから、古来滝桜とよばれるようになったといわれている。大正11年10月12日、国の天然記念物に指定された。
参考サイト : 三春町ホームページ
【ふるさと切手・東北のさくら】
2000.4.3発行
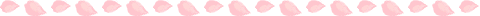

チシマザクラ
ミネザクラの変種。日本の桜の中で最も標高の高い場所に生え、北海道や日本の高山地帯で見られる。寒さに強く高さ1mくらい(4年生苗木)でも花を咲かせる。若葉と同時に直径2〜3cm位の淡紅色または白色の花を開く。開花時期は5月中旬から6月にかけて。
【ふるさと切手・北海道】
2005.8.22発行
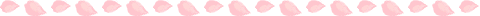

円山公園のしだれ桜と東山
春の円山公園は、京都の桜の名所の1つ。ソメイヨシノをはじめヤマザクラ、シダレザクラ、ヤエザクラなど約850本の桜が満開になる。中でも有名なのが公園の中央にあるしだれ桜で、明治の開園当初からあった古木の2代目。夜になると、この木の前でかがり火が焚かれ、幻想的な夜桜が楽しめる。環境悪化で弱ってきたこの木を鳥や虫などからの害から守るため、この桜の幹や枝は白く塗られている。
【ふるさと切手・京都府】
2000.10.20発行
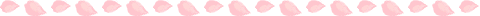

高遠の桜
長野県伊那市高遠町にある高遠城址公園では、3月下旬から4月上旬にかけて「タカトオコヒガンザクラ」約1500本が咲く。地元では「天下第一の桜」と言われており、長野県の天然記念物の指定を受けている。タカトオコヒガンザクラは、エドヒガンザクラとマメザクラの中間種で、花はヒガンザクラに、葉はマメザクラに似ており、花はやや小ぶりで赤みを帯びている。中には樹齢100年を超える老木もある。
かつて馬の姿が桜の花に埋もれて隠れたという高遠藩の桜の馬場。明治8年、荒れたままになっていた高遠城址を何とかしようと、旧藩士達が馬場の桜を城址に移植したのが公園の桜のはじまり。
参考サイト : 伊那市ホームページ
【ふるさと切手・長野県】
2000.3.3発行
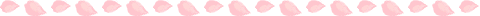

玉川上水 羽村の堰付近
玉川上水の羽村堰周辺には桜並木が続いていて、花見の名所となっている。桜の本数は約500本。桜の木の根に殺菌作用があることから、上水を浄化する目的で2000本のソメイヨシノが上水沿いに植えられたのがはじまり。戦時中に切られたこともあったが、昭和29年〜35年にかけて、緑の募金補助で村の水源愛護会や青年団により補植が続けられ現在にいたっている。
祖父母の家がこの辺りにあったので、東京出身でもないのに、子どもの頃一番よく遊んだ川はといえば「多摩川」です(笑)。夏休みに行ったのがほとんどで、桜の季節の記憶は一度しかありませんが、きれいだったのを思い出しますね〜。
【ふるさと切手・東京都】
2000.1.12発行
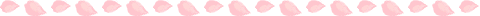
>>Stamp Album