表題は司馬遼太郎氏の同名の短編より拝借。大砲の話を書くのにちょうどいい題名を思いつけなかったので・・・(汗)。
ライン河とモーゼル河が合流する地、ドイツ・コブレンツ(ラテン語のコンフルエンテス(=合流)が名前の由来)。このすぐ近くにエーレンブライトシュタイン要塞というお城があります。敷地内にはユースホステルもあり、お城に泊まれるというのでなかなかに人気なんだと聞きました。
(ちなみに何ゆえ初めてドイツに行く人間が真っ先にコブレンツを行き先に選んだかといえば、ここがコブレンツの帝国議会(英国王エドワード3世が皇帝ルートヴィヒ4世から“帝国総代理”の称号を与えられた、百年戦争ゆかりの地だから、でした;笑)。
現在のたたずまいはプロイセン時代のものだそうなのですが、要塞の名にふさわしいいかにもごっつい建物。バロックロココの絢爛豪華も悪くないけど、やっぱりこういうシンプルに実用品なお城って好きだなあ、とかなり気に入ったお城だったのでした。
10世紀に建てられたこの城(エーレンブライトシュタインの名は最初の城主エーレンベルト(又はエーレンブレヒト)にちなむ)、11世紀にはトリアー大司教の所有するところとなります。大司教区の重要拠点として、城は絶えず防衛設備の充実が図られ、大砲技術の発達とともに大砲を装備するに到ります。
現在、敷地内の博物館の入り口で出迎えてくれるのがその大砲「フォーゲル・グライフ」。選帝侯リヒャルト・フォン・グライフェンガウ(1511〜1530)にちなんで名付けられたという重さ9トンのこの大砲、75kgの砲弾を発射できる威力があるにもかかわらず、実際には一度も使われることがなかったのだそうです。持ってるぞ、というだけでにらみをきかせるのには十分だったとか・・・(笑)。
しかし、評判になるような大砲であるということは、戦利品として目を付けられやすいということなわけで、以後数回にわたってフランスとドイツの間で持ち主を変えることになりました。ナポレオン戦争の時のように要塞がフランスに占領されればフランスに持ち去られ、次にドイツが勝つと取り戻されるというわけ。
この要塞は第二次大戦の時にも軍事施設として使われており、そんなわけで1945年には大砲は最終的に
フランスの所有するところとなりました。しかし1980年代の終わり、エーレンブライトシュタインに展示するという条件で、永続貸出品としてドイツに里帰り。なるほど、それでパリの“musee”なんて刻印があるんですね。
一度も実戦の役に立ったことがない大砲をめぐってドイツとフランスが争奪戦、というのは、部外者からするとそこはかとなく愉しい構図だったりします。というわけで、一度も本来の仕事をしていないのになぜか人生波瀾万丈、の大砲さんのお話でした(笑)。
ひとつ面白いのがあちら流の作者銘の入れ方。日本だと“○○之ヲ作ル”と人が主体になりますが、あちらでは「○○が私を作った」とモノを主体にして書くのですね。というわけでこの「フォーゲル・グライフ」の銘を直訳すると「1524年にジーモン親方が私を鋳造しました」となります。
参考文献:Rüdiger Wischemann Zur Geschichte der Festung Ehrenbreitstein
(博物館で購入した本。ちなみに、えっらく読みにくいドイツ語でした・・・)
いつもに比べてちょっと短めなので、旅行絡みの小ネタを二つほど。
![]()
おお、大砲
〜 “Vogel Grief”の話 〜
![]()
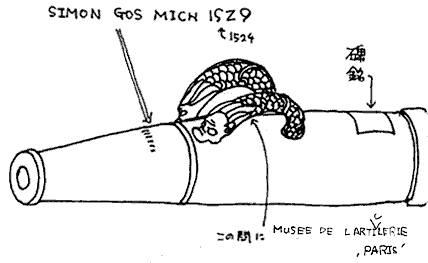
Vogel Grief
コブレンツ:Landesmuseumにて(同行者のスケッチより)

De Burcht
オランダ・ライデンにて
某ガイドブックに「1573〜74年の独立戦争の際、ライデン市民が1年間籠城しスペイン軍に対して抵抗を続けた歴史的舞台」とあるこの砦。しかし実際に行ってみたら、掲示してある説明書きに「ここでは一度も戦闘が行われたことはありません」との文章が。ガイドには「市民が籠城したとは思えないほど小さな城壁内部」ともあるのですが、それももっとも、と言うか、はっきり言ってこんなところで籠城するなんて無理でしょー、ってな建物なんですよね。現地の解説が大嘘ってこともないだろうと思いますし。
じゃ、ガイドブックの文章は何がネタ元だったんだろうな〜と思ってたら、ひょんなところで答えらしきものに出くわしました。司馬遼太郎『街道をゆく』のオランダ編。ライデンのくだりにこの砦は独立戦争の舞台でとしっかり書かれているんです。はてさて、司馬氏はどこでその知識を仕入れたんでしょう?
じゃ、ガイドブックの文章は何がネタ元だったんだろうな〜と思ってたら、ひょんなところで答えらしきものに出くわしました。司馬遼太郎『街道をゆく』のオランダ編。ライデンのくだりにこの砦は独立戦争の舞台でとしっかり書かれているんです。はてさて、司馬氏はどこでその知識を仕入れたんでしょう?
 |
 |
| フロワッサールの像 | プレヴォの家 |
フランス・ヴァランシエンヌにて
イザベル王妃が夫に対するクーデター作戦を練り、未来のエドワード3世とフィリッパ王妃が出会った地・ヴァランシエンヌ。この時代を専門にする人間としては、かねてから是非とも行きたい場所だったので、旅行計画を立てるに際して、地図を頼りにここも旅程に組み込みました。しかし日本のガイドブックでは地図に地名が載ってるだけでも良い方。となると頼りになるのは観光案内所のホームページです。ところがせっかく見つけたそれはえらく使いにくい設計で、おまけにフランス語のページしかなかったのでした。当方フランス語はほとんど解しません。辞書を引きまくってなんとか見当をつけましたよ・・・。
も一つ問題だったのが行き方です。街の地図すら手に入らないような所に宿をとる度胸は無かったので、ベルギーに泊まって日帰り、の計画でした。ところが路線図では最短距離を直通で行けるように見えるのに、実際にはV字に遠回りして乗り継ぎしなきゃ行けないことが判明。それ以上のことは日本では調べられず、ベルギーの目的地に着くやいなやバス事務所に飛び込みました。拙い英語で粘った結果、電車に乗って国境駅まで出て、そこから5分歩くとバス停があってバスが出ている、ということを聞き出し、めでたく時間短縮に成功! ついでに歩いて国境を越える、という珍しい体験までしてしまったのでした。
とまあ悪戦苦闘したわりには、アヴェーヌ家ゆかりの建物はほとんど残っておらず、フロワッサールのモニュメントがあったくらいでした。でも15世紀の建物であるプレヴォの家や、市壁の残存などから中世の雰囲気が感じられたので、まあ良しとします(笑)。
も一つ問題だったのが行き方です。街の地図すら手に入らないような所に宿をとる度胸は無かったので、ベルギーに泊まって日帰り、の計画でした。ところが路線図では最短距離を直通で行けるように見えるのに、実際にはV字に遠回りして乗り継ぎしなきゃ行けないことが判明。それ以上のことは日本では調べられず、ベルギーの目的地に着くやいなやバス事務所に飛び込みました。拙い英語で粘った結果、電車に乗って国境駅まで出て、そこから5分歩くとバス停があってバスが出ている、ということを聞き出し、めでたく時間短縮に成功! ついでに歩いて国境を越える、という珍しい体験までしてしまったのでした。
とまあ悪戦苦闘したわりには、アヴェーヌ家ゆかりの建物はほとんど残っておらず、フロワッサールのモニュメントがあったくらいでした。でも15世紀の建物であるプレヴォの家や、市壁の残存などから中世の雰囲気が感じられたので、まあ良しとします(笑)。
2003.11.20 up