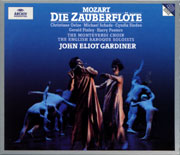多分最初にその存在を知ったのがこのオペラだと思います。小学校の音楽の時間にソプラノリコーダーを吹きましたが、その時吹いた曲の一つが“何てきれいな鈴の音”で、その時に一応出典も教えてもらったのでした。・・・タミーノ王子とパパゲーノが、パミーナ王女を助けに行く話、というレベルでしたけどね(笑)。以来、なんとなく頭の隅にずーっと引っかかっているオペラではあり、かつて「オペラ講座」に通ってた頃は、初めて見るなら「魔笛」かな、と思ってました。“死にオチ”と「史劇」が嫌い、な私でも楽しめるオペラっつったらこのくらいだろう、と。おあつらえ向きに最初にご贔屓になったソプラノが夜の女王を得意にしていて、DVDに収録された映像を、それこそアリアの前の長台詞なんかほとんど暗記できそうなくらいのいきおいでさんざん見た割には、いざ全曲鑑賞となると、少々時間を要しました。ご厚意でいただいたこのガルニエの映像と、BS2を録画したロイヤルオペラの録画を手元に持ってはいたのですが、途中までは見たものの、残りがついつい後回し。舞台を見に行く計画した時には、さあ予習だ! って思ったんですけど、結局気が変わって「フィガロ」に行ってしまいましたし。ストーリーが一応まともで楽しめるオペラって他にもあるんだ、って知ってしまうと、この破綻具合がネックなのかなあ、などとも思ってみたり・・・。
・・・白状すると、どちらも実は「おれは鳥刺し」でつまづいたのでした。見たことはないとはいえ、曲は知ってるし、ストーリーは切手をアップする時に調べて、なんとなくのイメージは持ってるわけです。でも、どちらも、え、これがパパゲーノ? という感じだったんですよね。オペラ座のデトレフ・ロートは、格好はそれっぽいけど、なんか違う、という印象。ロイヤルオペラのキーンリーサイドはどう見てもくたびれたおっさんなのに面喰らったし・・・。初っ端から出てくるタミーノがこれまたどちらも王子っぽくないものですから、夜の女王の最初のアリアが終わったあたりで集中力が切れてしまったという次第。
中断したまんまというのも落ち着かないものですが、さりとて、続きを見ようにも気合いが入らず。もうまるっきり別の映像で全曲鑑賞を目標に頑張ってみるか、と他をあたってみましたら。おお、「ドンジョ」と「フィガロ」でダントツご贔屓のガーディナー指揮の映像(1995年)がライブラリーで見れるじゃないですか。じゃあこれを、とLD鑑賞に行って参りました。
「ドンジョ」と同じコンセルトヘボウでのセミステージ形式。舞台装置は無いのですが、ダンサーが魔笛を聴く獣たち、門、首吊りの木、火の世界、水の世界などを表現。ピロボルス・ダンス・シアターというところだそうですが、この趣向がなかなか楽しめました。そういえば冒頭に出てくるのはヘビじゃなくてライオンでした。自筆スコアにはライオンて書いてあるそうです。時の皇帝レオポルトを憚って変更したらしいとか。小道具も最小限で、ほとんど演技で表現していたのですが、その数少ない小道具の一つが額縁。おいおい、絵が入ってないよ? と思ってたら、そうきたか〜って感じのオチでした(笑)。タミーノとパパゲーノが夜の女王の話をする場面、やけに観客がウケてるなあと思ったら、ベアトリックス女王が客席にいたんですね。
タミーノはミヒャエル・シャーデ。王子様らしい気品には欠けますが、若くて精悍な感じが良かったです。悪魔の城に殴り込みをかけようっていうんだから、やっぱりこれでないと。声も張りがあって、しかも私にしては珍しく“うわあいい声”って思うテノール。“絵姿”のアリアなどうっとり聞き惚れました(このアリア、ボストリッジの録音も持ってますけど、可もなく不可もなくという印象・・・)。パミーナのエルツェも可愛いらしくてお姫様にぴったり。もちろん歌も良かったです。やっぱり主役級が若いと見た目に違和感なくて良いですね(YouTube参照)。
パパゲーノはジェラルド・フィンリー。正直言うと、出てきた瞬間、うっ、と思いました。だって、何だか真面目そうなパパゲーノだったんですもの(YouTube参照)。どう見ても野生児パパゲーノにぴったりの風貌ではなかったのですが、実に身軽で演技の上手だったこと! そのちょっと不器用な一生懸命さが巧まずして笑いをさそう感じで、ブッフォの芸達者さとは違いますが、この方が本人の柄にも合っていて、すっかり気に入ってしまいました。タミーノの方がちょっぴり(横にも)ガタイがいいので、おい行くぞ、みたいな感じで引きずられてくとこがかわいかったです。(当該箇所ではないですが、フム、フム、フムの場面)
そしてまた何と! グロッケンシュピールをフィンリー本人が弾いているのですよ! 最初に見たときにはてっきり弾く真似と思い込んでいたのですが、あまりの熱演ぶりが気になって再視聴。・・・これ、弾いてるわ! そう、「恋人か女房か」のアリア、指揮者がフィンリーの方を随分気にしながら振ってました。そりゃあアリアの後は大喝采ですよね〜(下りてきたガーディナーと握手するシーン、大好き)。「何てきれいな鈴の音」も(終了後拍手喝采)、パパパの二重唱の前の部分も本人の演奏です。
演技も上手いですが、歌も上手。聴くのは初めてだったんですが、私本来の(笑)好みの、輪郭のはっきりしたバリトンで聞き惚れました。
弁者、どっかで見た顔だなと思ったら、ガルニエでパパゲーノやってたロートでした。5年後でも十分若いパパゲーノだったのですから、えらい若い弁者。・・・まあ、この役の方が出番が少ないだけあまり存在感云々が気にならないかな(苦笑)。CDで音だけ聴く分には悪くないです。続いて出てくるザラストロまで若かったのにはちょっと閉口しましたが、まずまずみごとな低音。「この聖なる殿堂には」が印象に残ったのはこの人くらいでしたし。シンディア・シーデンの夜の女王も悪くないです。デセイの聴きすぎで、最初かなりの違和感がありましたが、聴いてるうちに慣れました(苦笑)。Youtubeには2つめのアリアがアップされてますが、個人的には1つめのアリアのが好きです。演出が人力だけでここまでできるかってくらいにゴージャスです。
というわけで、初めて「魔笛」を堪能することに成功。このオペラ、女性蔑視的なセリフが多いのがひっかかる、てな話も聞きましたが、あんまり気になりませんでした。だって、試練なんてめんどくさいもの嫌だ、っていうパパゲーノに“可愛い女の子”をエサにわざわざ試練受けさせる教団ですよ〜。いちいち真に受けてられないわ(笑)。
演奏は期待した通りのきびきびとエネルギッシュなもの。最後まで退屈することなく見ていられたのはこのテンポの良い演奏に引っ張られたせいもあると思います。これがまた、例によってDVDになっていない映像なのですが、アマゾンで視聴音源を聴いていたら、CDでもいいから欲しくなってしまって、つい買ってしまったり・・・(苦笑)。追記:ご厚意でLDからDVDに焼いたものをいただきました。これでいつでもこの映像を楽しめて嬉しいです〜。
とまあ、「魔笛」というオペラそのものを嫌いではないことが分かったので、放置していた録画に再挑戦。まずは2003年のロイヤルオペラの方。オーソドックスなメルヘン調の演出は悪くないと思います。ただ、途中で飽きてしまったのも納得、でして・・・。男声陣が軒並み見た目に美味しくないんですわ。なんだか老けたタミーノのハルトマンに、これまたくたびれた感じのパパゲーノ。ザラストロは賢者というにはなんだかひょうきんなお顔だし。はまってたのは弁者のアレンくらい? 貫禄あって良い感じでした。
女声陣の違和感は、どっちかというと演出のせいでしょうか。ダムラウの夜の女王、怖い母親がはまってて良かったといえば良かったのですが、最初のアリアでもおっかないのが個人的には・・・。“zittre nicht”って、アナタが怖いんですけどって女王様、これが未来の姑かと思ったら、王子、引きません? このお姫様もウン十年経てばああなるのか・・・とか思うんじゃないかしら、などと思ってしまうので。そう考えると、パミーナの絵姿と女王をオーバーラップさせて王子を誘惑、というエクサンプロヴァンスのカーセン演出って、よくできてたんだなあ、などと思ってしまいました。アリアの前の長台詞をカットしてないのは好感度大ですが(あるのとないのでは女王のイメージが変わってくると思う)。パパゲーナの登場シーンがいかにも現代風なケバいおばはんだったのも違和感あり。レシュマンのパミーナも、ガルニエの公演の方がちゃんと王女様に見えましたし。
でまた、ガーディナーの軽快できびきびした演奏を堪能した後では、デイヴィスの指揮はいかにも遅かったです。というわけで、なんとか頑張って最後までたどりついたものの、よっぽどのことがないかぎり、再々チャレンジはしないでしょうなあ・・・。
も一つ再挑戦だったのが2000年のガルニエの映像。こちらはまた極彩色のメルヘン調。タミーノが笛を吹くとぞろぞろと寄ってくる動物さんが妙に擬人化された着ぐるみなのが笑えました。二人の武士は中途半端に古代エジプト風で、そこにも着ぐるみのふくろうさん。タミーノとパミーナはなんだか“月の砂漠を〜”って感じのアラビアン・ナイト風。デセイの夜の女王は、最初と最後の登場シーン、なんだか紅白歌合戦みたい、と思っちゃいました(笑)。ザラストロは賢者というより七福神の福禄寿風で、シェーネの弁者の方がよほど賢者に見えたりして。聖職者の服はえりに照明入り。民衆が黒の礼服姿で、ザラストロが女性批判的なセリフを言うたびに、女の人たちが下向いてました(笑)。モノスタストスのペパーはコンセルトヘボウでもこの役でしたが、これだけメイクが違うと同一人物には見えませんね〜。
まあ元のストーリーがめちゃくちゃの「魔笛」ですから、少々ぶっ飛んでるくらいの舞台の方が合ってるんだろうとは思うので、こちらも不満は主に演奏面ということになります。
文句なしだったのはデセイの夜の女王とレシュマンのパミーナ。レシュマンのパミーナ、なかなか意志の強いしっかり者のお姫様でした。結婚したら絶対タミーノが尻に敷かれること間違いなし(笑)。近頃、ロンドンの「魔笛」とかザルツの「フィガロ」あたりのイメージしかなかったので、綺麗なパミーナなのに最初びっくりしてしまいました。そういえば、デセイのDVD見てる時には、わー、若くて綺麗なパミーナ、ちゃんと親子に見える! って思ったな、と・・・。どうしてこうも印象変わりますかしら。
それに引き替え、存在感の薄かったのが男性陣。ベチャーラのタミーノもロートのパパゲーノも、若くて視覚的に違和感が無いだけましとは言えますが・・・。演奏のテンポも、聴いてるこちらが少々だれ気味になりました・・・デイヴィスほど遅くはなかったですが。最後の合唱に夜の女王も侍女たちもモノスタトスも加わってて、ちゃんと大団円になってたのは面白かったんですけど。
最近、この演出のDVDを見かけ、あら、とうとうDVDになったのね! とよくよく見たら・・・。他のキャストは全く同じですが、夜の女王だけランカトーレ。・・・デセイってば、これだけ美人で演技力抜群で、これほど映像向きの人はいないだろうと思うのに、映像ソフトには恵まれないんですね・・・。
なかなか納得のいくパパゲーノっていないのね、とYouTubeを見に行ってみたところ、意外に大して数もない中、一つだけ、お、これは、と思ったのがありました(現在削除)。DVDになっているチューリヒ公演のアントン・シャリンガー。おっさんパパゲーノなんですけど、これは面白かった。飲み助の泣き上戸、「恋人か女房か」のアリアで、だんだん呂律が回らなくなってくるあたりとか、実に芸達者で巧い! ジャケ写までパパゲーノなのがとっても納得です。
しかし、ハルテリウスのパミーナはなかなかいいな、と思ったのですが、モシュクの夜の女王は今ひとつの印象。サルミネンのザラストロとベチャーラのタミーノはもうええわ、だし・・・。ミラーの演出も、も少しメルヘン調のが「魔笛」って感じがすると思います。うーん、パパゲーノだけ目当てに買うには結構いいお値段なのよね・・・
余談ですが、“魔笛”の材料になった木、字幕によって欅だったり柏だったり、意外にバラバラだったのでちょっとびっくりしました。パミーナが“Eiche”って言ってるこの木、英語でいうところの“Oak”で、“樫”と訳すのが一般的だったと思いますが・・・。もっともこれは誤訳で、正しくは“ミズナラ”なんだそうであります。という受け売りを個人的にさんざ聞かされたので、つい気になっちゃいまして・・・(苦笑)。