ところが、チケットをとってしばらくしたら、昨年には無かったキャスト変更発生。ボニーが来日できなくなったというのです。とはいえ、もともと彼女にそれほど思い入れがあるわけではない私(何しろ手元にあるのは「メリー・ウィドウ」の録音が唯一ですから・・・)、代役の名前を聞いて、おっ、と思いました。カミラ・ティリングって・・・あの天使!!
昨年の「こうもり」追っかけのお目当てロッド・ギルフリー、その前にアムステルダムで、メシアンの「アッシジのフランチェスコ」を歌っていて、DVD化もされています。現代音楽で宗教モノ、舞台はサイケ調でやたらに長い!(DVDは3枚組、計6時間超)と四重苦揃っちまっては、当然(苦笑)手は出していないのですが、YouTubeに上がっていた公式ビデオクリップだけはチェックしておりまして。いい声だなあ、と思った天使役がこの人だったのです。というわけで、こんなにすぐに生舞台で見られるなんて、と私にとってはむしろ楽しみが増えた格好になりました。共演者つながりといえば、キルヒシュラーガーもこんな写真がありましたっけ・・・
曲の一つさえ知らないオペラですから、当然要予習。ところが少々のんびり構えすぎ、いくらなんでもまずいぞと、仕事帰りに地元の図書館に駆け込んだのは、すでに公演まで1ヶ月を切っていた頃(汗)。ここ、オペラ映像鑑賞にはほとんど役に立たないのですけど、なぜか所蔵オペラDVDの約1/4がこの演目の1998年チューリヒ公演の映像なんです。館内視聴のみOKなのですが、昼間行くと数少ないブースは大抵占領されてますし。
いくら100分少々と短い作品とはいえ、開館時間内に全部見るのは不可能で、ひとまずこの日は魔女登場の直前まで。途中で閉館放送と二重音声で聴くはめになったりもして集中力が削がれたというのもあるのですが、・・・これはちょっと気合いを入れ直さないといけないわ、というのが正直な感想でした。
当方、目下のところいわゆるオペラはモーツァルト、ロッシーニ、ドニゼッティでおしまいです(そこからオペレッタ、ミュージカルに逸れます)。そういう人間には、ワーグナーの影響を受けたというこの音楽、大分勝手が違って聞こえます。こりゃあもっと聞き込んでおかないと、本番楽しめないんじゃないか、と。
というわけで、例によってYouTubeを物色していて見つけたのがこの映像。 いつも使っているライブラリーにこのショルティ指揮の映画版があるのは知っていて、この映像でも予習をするつもりではいたのですが、チューリヒの映像より好みに合いそう、と好感触。早速その週末に出向いて試聴してみたところ、予想通り気に入って(こちらの方が地元図書館より設備が格段に良いので、集中度も違いましたが)DVDも購入してしまいました。
ほぼ理想的にオーソドックスなメルヘンを楽しませてくれるエファーディングの演出。レープクーヘンのお菓子の家には、そうそう、これよ! と思いました。色味が抑えられているのも、霧深い山の中を感じさせて物語の雰囲気にぴったり。序曲などではショルティの指揮姿や楽器を演奏しているところが映ったかと思えば、アニメーションに切り替わったりして、ちょっと今までにない作りの映像です。
キャストは、プライの父親もデルネシュの母親もユリナッチの魔女もはまっていて良いですが、なんたってファスベンダーのヘンゼルが最高! バイエルンの「こうもり」の変人オルロフスキーもインパクトがありましたけど、わんぱく坊主役がこれ以上ないほどはまってます。グレーテル役のGruberová、実はオペラ一曲通してまともに聴いたのは初めてだったりしたのですが、納得の巧さでした。ヘンゼルと並ぶとお姉さんに見えるグレーテルですが、そういうもんだと思って見れば役にもぴったり(チューリヒのハルテリウスもニキテアヌのヘンゼルよりお姉さんに見えましたし)。たまたまYouTubeにはポップ&ファスベンダーの音声(ショルティ指揮のCDバージョン)も少々アップされていて、聞き比べをしたところでは、彼女の声は少し硬質に聞こえるというか、ポップの声の方がこの役には合っている気もしましたけど。
大のお気に入りになったところで、チューリヒの映像に再チャレンジ。うーん、ムフの父親は、プライに負けず劣らずいいと思ったけど、主役2人はやっぱり映画版に比べると分が悪いし、冒頭の場面に遊び友達がわんさといるのにも馴染めない。魔女に指を出せ、と言われるシーンで、ヘンゼルがまんま自分の指を出していたのにもびっくりしたし・・・。一応メルヘン調なので(参考:夕べのお祈りの二重唱)最後までついていけたものの(変に現代化した上、しかもグロテスク路線に走ることもあるこの演目ですから)、やっぱり映画版の方が全体に好みだったのですが、ただ、一カ所だけ、断然こっちの方がいいな、と思ったのが魔女。チューリヒの映像ではテノールのフォーゲルがこの役なのです。
テノールの方がこの世ならぬ感じがあってすごいインパクト。そもそもヘンゼルがズボン役でメゾなので、魔女もメゾだと女声が3人。テノールの方が聴いていてコントラストがつくのもいいです。
音楽塾のキャストでは、テノールが魔女役ということで、俄然楽しみに。
ちなみに、YouTubeにテノール版の魔女の映像がないか探してみたのですが見つからず、予習には音声だけ上がっていたペーター・シュライヤーのを愛聴していました。余談ながらこのスイトナー盤、全曲アップされているようで、序曲とか「魔女の騎行」とか、これで予習させてもらったのでした。慣れてくると、こういうオケだけの曲も割と好んで聴けるようになったので、案外“ワーグナー風味”、抵抗無く聴けるのかもしれません。まあ、べらぼうに長い本物ワーグナーに手を出すきっかけにはならないと思いますけど・・・(笑)。
さて、直前に胃腸を悪くして、実質2日間何も食べてない状態で「カルメン」を見に行ったわけですが、その後も身体的不調はいっこうおさまらず、これで浜松なんか行けるんかしらん、という状態だったのですが、幸いなんとか持ち直し。これなら大丈夫そう、と思ったら当日の朝はものすごい土砂降りで、どうなることやらと思いましたが、昼過ぎの浜松はよいお天気で一安心。当初は、楽器の切手のページなど作ったことだし、と開演前に楽器博物館に寄ろうと計画していたのですが、体力温存のためにこれはまたの機会ということにしました。
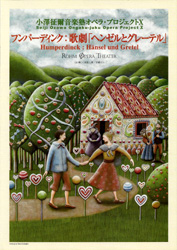 グレーテル:カミラ・ティリング
グレーテル:カミラ・ティリング
ヘンゼル:アンゲリカ・キルヒシュラーガー
ゲルトルート(母親):ロザリンド・プロウライト
ペーター(父親):ウォルフガング・ホルツマイアー
魔女:グラハム・クラーク
眠りの精/露の精:モーリーン・マッケイ
指揮:小澤征爾 演出:デイヴィッド・ニース
序曲が終わって幕が上がると、向かって右半分にえらくリアルな民家のセット。ロープ張って洗濯物が干してあって、残りに森。・・・しかしそれにしては子どもたち2人、けっこうきれいなおべべ着てますが(笑)。お庭にはブランコなんかもあるし。でも主役2人とも役にはぴったり! グレーテルは耳の上で2つ分けに結んだ髪型がいかにも女の子って感じで、お人形遊びしていても違和感がないし、ヘンゼルもちゃんとやんちゃな男の子に見えます。
ただ、これチューリヒの映像見てる時にも思ったことなのですが、子どもが遊んでる生き生きとした感じを舞台で演出するのって難しいんですかね? 映画版だと何度見ても引き込まれるのに、なんとなく手持ちぶさたに見えるというか、動きがきちんと計算されてない感じがしてしまいました。
親のいいつけをさぼって遊んでいた子どもたちを叱ったはずみに、ミルク壺を割ってしまった母さん。2人をイチゴ摘みに行かせると、テーブルに突っ伏して寝てしまいます。そこへ山から父さん帰宅。子どものブランコに座って歌ったりしております。声量はあっていいバリトンだと思うのですが・・・、オペラグラスで見ているとどうも表情に乏しいのが気になる、というかどうにもご機嫌な酔っぱらいに見えないんですけど。予習で見たムフもプライも芝居気たっぷりで面白かったので、ちょっと物足りなく感じてしまいました。
で、父さんの買ってきた食料を棚に並べる母さんですが、その棚がけっこう高いので、そんなとこに卵なんか置いて大丈夫? なんて思ってしまったり。その棚の近くにジンジャーマンみたいなものが置いてあるなあ、と始めから気になっていたのですが、はたして、魔女は子どもたちを焼いてレープクーヘンにしてしまう、というところで父さんそれを持ち出してきました。あれは抜き型なんですかね? それにしてはレープクーヘンというよりジンジャーマンに見えましたが。
両親2人が子どもたちをさがしに出かけたところでセット転換。家が引っ込んで全面森に。でも転換したらそのまんまなんです。え、これ「魔女の騎行」だよね、なのにこれだけ? と思ったところで、舞台中央でキラキラとライティングが動いていましたが。
第2幕。言いつけられたのはイチゴ摘みだというのに、なぜ実際に働いているのはヘンゼルだけで、グレーテルは花輪なんぞ作ってるのか、常々不思議に思うこの場面(笑)。まあせっかく摘んだイチゴも2人で残らず食べてしまうわけですけど。
暗くなる中、帰り道がわからなくなってしまった2人を眠らせる眠りの精は、ネズミ男みたいなフード付きの上着で登場。金の砂をキラキラと撒きます。夕べのお祈りをする2人。そしてこの二重唱の美しかったこと! もとの曲が良いので、どの版で聴いても美しい曲ですが、生で聴くのはまた格別。声の相性ぴったりで、心地よい融け合いを堪能しました。グレーテルに自分の上着を着せかけてやり、それから自分も眠るヘンゼル。
おや、と思ったのがここ。ヘンゼルとグレーテル、グリムの原作では兄と妹ですし、作曲家と台本作家も兄と妹。なんですが、予習で見た映像2つとも、どう見ても頼れる兄さんとおしゃまな妹、ではなくて、しっかり者のお姉さんと少々甘ったれの弟、だったんですね。出演者の年齢とはあんまり関係なく、台本の性格がそうなっているんだと思います。
それが、怖がるグレーテルを大丈夫だよと励ます場面といい、この寝る前の行動といい、初めて普通にヘンゼルが兄に見えたのでした。キルヒシュラーガーの方がキャリアも年齢も上だし、背も高いということもあったかもしれませんが、なんとなく、これは兄と妹なんだ! という演出のコンセプトがあるように見えたのが興味深かったです。
2人が眠ると、森のセットが両袖に引っ込んで、その後ろには階段状のセットと、天使様が14体。さっきの「魔女の騎行」の肩すかし感が残ってましたので、しばらく動かなかったし、この天使様もセット? なんて思ってしまったのですけど、次々と地面に下りてきて、眠る2人のまわりに勢揃い。なかなか豪華な衣装に金色に輝く舞台。みごとに荘厳なシーンになっていて、そうそう、これじゃなくちゃ! という王道の演出に拍手喝采でした。
休憩終わって第3幕。
舞台の上で2人が寝ています。あれ、ヘンゼル、さっきと寝てる位置が違いますが。上着もいつの間にか取り返してるし(笑)。
2人を起こしに来る露の精は、眠りの精と一人二役なのですが、さっきの地味な衣装とはうってかわって、花の形のゴンドラに乗って空中からゴージャスに登場! 合わせて衣装もゴージャスになってました。
起き出した2人の前に、舞台後方からせりだしてきたのは、なんともイメージにぴったりのお菓子の家。屋根がピンク色にキラキラ輝いて、きれいだったのなんのって! なんだかんだと言いながら、一かけとって食べようとする2人ですが、「私の家をかじるのはだれだね」の声に硬直。持っていたお菓子を取り落とすヘンゼルに会場から起きる笑い。戸口のドアの上半分が開いて、そこに2人を偵察する魔女。
しばらくして2人の前に登場した魔女、あまり大柄な人ではないのですね。ちょっと意外でした。魔女の甘言に、怪しいわ、とか言いつつ呑気に家の砂糖飾りをなめてたりするグレーテルを引っ張って、逃げようとするヘンゼルですが、そこへ魔女の魔法。カクカクと妙な動きしかできなくなる2人。
家のセットが二つに割れて180°回転。また2つに合わさって魔女の家の中。ヘンゼルを檻に閉じこめて、グレーテルには食事の支度を命令。その間にオーブンの温度を確かめて、「アツイ」などと日本語で言う魔女(笑)。
“魔女の踊り”ではほうきにまたがって踊る魔女が2階に上がると・・・おお! 窓から魔女の影絵が! こんなことできるんなら、それこそさっきの「魔女の騎行」にも一工夫できように、としつこく思う私。
子どもたちのレープクーヘンは、家の左右の板(?)に描かれていました。それが左右に引っ込むと合唱団の子どもたち。映画版ではお菓子の家が爆発した後にでっかいケーキが残るラストなので、確認しに家の中に戻っていくのを見てちょっとドキドキしましたけど(笑)、めでたくレープクーヘンになった魔女が運び出されてきました。最後は探しにきた父さん母さんと再会して大団円。
主役2人の印象ですが・・・そもそも、なんだかオケの音が大きかったような気がします。ものすごく声量のある人たちではなく、また大声張り上げて歌う歌でもないのでしょうが、なんとなく声がオーケストラピットでブロックされてたような印象でした。特に冒頭の二重唱。
それでも小人さんの歌に至ってティリングには聞き惚れましたが、そもそもまともな歌のないヘンゼルとあって、キルヒシュラーガー、残念ながら歌の印象は薄いです。役にはどっちもぴったりで大満足だったのですけど。
父親役のホルツマイアー、最後まで見てもやっぱり、歌はいいんだけど、表情が陽気な酔っぱらいに見えないのがちょっと・・・、でした。ちなみにステージドアで見てたら、一番なんというか、ドイツに行ったらどこにでもいそうな普通のおじさんという印象でした。
母親役のプロウライト、声量はあるのですが、どうも歌詞が聴き取りにくいところがあって。一番ろくに歌うところのない役とあって、なぜかしらと考えているうちに、大方の出番がすんでしまいました。生活に疲れた母親の雰囲気は良く出ていたと思いますが。
役としては小さいものの、歌的にはけっこう美味しい役ではないかと思う眠りの精/露の精(録音だとけっこう有名歌手が歌ってたりしますし)。モーリーン・マッケイ、無難に歌ってたとは思いますが、特別という感じはしませんでした。
楽しみにしていた魔女役のグレアム・クラーク。この役を歌うのってこういう声なのね、となんとなくイメージしていた通りの声でした。とにかく歌も演技も素晴らしい! この人の魔女なら絶対外れなし、と思わせる怪演ぶりで、拍手喝采でした。DVD欲しい! (このロサンゼルス公演の映像のラスト10秒ほどで辛うじて見られます。)カーテンコールで、魔女レープクーヘンの陰に隠れながら出てきたのにまた笑わせてもらいました。ステージドアでも、サービス精神旺盛な面白いおじさんだったです。
予習の時点で期待が高すぎたかしら、と思わないでもないのですけど、やや物足りない点も散見された演出だったように思います。でもまあ、王道のメルヘンであったのが何より。オペラ化された時点でグリムの原作の毒気はすっかり抜かれてるんですから、オペラにその毒気を戻されても困るってもんです。セットに関してはほぼ完璧にイメージ通りのオーソドックスな舞台で大満足でした。名古屋公演のチケットもとっとけば良かったかな、と思ってしまったくらい(どのみち体調不良で難しかったわけですけど)。
去年の最終日のびわ湖ではみごとに振られたので、今年はどうかしら、とちょっとドキドキしましたが、ステージドアにも行きました。待つことしばし、めでたく出てきてくれたのですが、昨年と違ってみなさまいっぺんに出てきた上、待ってる人間の数は去年と変わらず数えるほど。一同パニック!
というわけで、サインはマッケイを除く全員にもらったのですが、写真はまともにとれず。実はクラークとプロウライトにカメラを向けたら肩組んでポーズ取ってくれたのですが、慣れないデジカメでちょっとぶれてしまったのが残念です。この2人、仲良しみたいで、ずっと一緒に喋ってました。プロウライトのが随分背が高いのですけどね。あと、セットをトレーラーで運び出しているところをキルヒシュラーガーが写真に撮っていたのが面白くて、それを後ろからパチリ。息子さんに、ママ早く、てなことを言われてました(多分)。
みなさま新幹線でお帰りとあって、浜松駅までついて行きまして、改札までお見送り。昨年のような“猛暑の日本”ではなかったけど、代わりに今年は“豪雨の日本”をあちらこちらの2週間。お疲れ様でした!
去年の写真がお目当てでもあったプログラムですが、リハ風景の写真が色々あって大満足。特におじさん2人のじゃれ合う写真には、これ載せてくれてありがとう! でした(笑)。
余談ですが、オペラ鑑賞の1週間後、北ドイツに旅行に行きました。ゴスラーなどハルツ山地の方にも行ったのですが、ここの名物(?)といえば魔女。これも何かの縁だったのかしら? そういえば魔女の歌に「チョコレート、トルテ、マルツィパン」なんて歌詞がありましたが、その後行ったリューベックの名物がマルツィパン(マジパン)だったのでした。
これまた余談ですけど、“ヘンゼル”“グレーテル”ってのはそれぞれ“ハンスちゃん”“グレーテちゃん”という意味なんだそうです。それで冒頭の二重唱で、ヘンゼルが「僕はハンス様だぞ」とかなんとか言うのですね。
