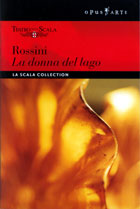珍しい買い物です。ストーリーなんざどうでもいい、トータルとしての評価は完全無視、ただ1つのアリアのためだけに買ってしまったというDVD(CDでアリア集買うより安いしな〜、というお値段だったのでやってしまった暴挙ですが・・・)。
メト公演の「セビリアの理髪師」で伯爵を歌ったロックウェル・ブレイク。こ、これでリリック・テノール?! どこが叙情よ? と解説を読んで目を回したほどで、結構暗めの力強い声(あとでビリャソンもリリック・テノールの扱いだと知って、オペラの世界におけるリリックと叙情はイコールじゃないのね、と理解した次第)。ベルカント・オペラのテノールって、こういう声が歌うんだ、と理解してきた明るい声とはまるっきり違ってたのですが、どういうわけか、このタイプの声がどうにも好きになれない私にとってはもっけの幸い。あんまり気に入ったので、この人が見れるなら、とおよそ話の筋が好みから外れるであろう「ミトリダーテ」や「湖上の美人」のLDまで見に行ってしまったのでした。
あと検索で引っかかってきたのに「ドン・ジョヴァンニ」があって、この人だとどんなオッターヴィオになるんだろ、と逆に興味を引かれたのですが、当該LD、メイキングでした。主役のライモンディを堪能する分にはいいけど、脇役のオッターヴィオなんざ、当然出てきませんやね。まあ、どう考えてもこの人はオッターヴィオのキャラではないと思いますが。ドンナ・アンナを引きずって、ドン・ジョヴァンニにタイマン勝負を挑んじゃうようなオッターヴィオになっちゃいそう。さすがの私もブレイクの声でオッターヴィオのアリアを聴きたいとは思わないし。ただ、ドン・ジョヴァンニにピストル突きつけるシーンだけちょっと見たいような気がしないでもないこの頃。
一応最初のうちは、真面目に聴こうと頑張ってみたのですが、「ミトリダーテ」は女声の競演に早々にギブアップ。ちょっと前にデセイのモーツァルトのコンサートアリア集を借りてみたことがあるのですが、いくら好きなデセイといえど、頭のてっぺんから出してるような声のオンパレードがだんだん耐え難くなりまして。それでも頑張って聴いてたら、今度は家族から頭が変になりそうだと苦情が出たのでそこでストップ(笑)。モーツアルトのソプラノ、たまの夜の女王のアリアくらいならともかく、あんまりえんえんと聴くもんではないらしいです。というわけで、タイトルロール登場シーンだけ、端折って聴いてしまいました。この頃はまだリアル銀髪じゃなかっただろうけど、まだまだ現役の王様の役とあって、怒りのアリアとかはまってて良かったです(こんなのとか)。もっとも、声は堪能しましたが、メロディーの方はさほど印象には残ってなかったりして。
次に見たのがこの1992年スカラ座の「湖上の美人」でした。スコットの小説が原作ですから、ちゃんと起伏のあるストーリーではあるのですが、やはり私向きではなく、ウベルト登場シーン以外は結構飛ばして見てしまったのでした。ただ1カ所、うわあ、なんてロマンチックな曲! とすっかり魅了されたのが第2幕の冒頭、ウベルトの歌う「ああ、甘き炎よ」。そう、あれをもう一度聴きたい一心で、日本語字幕無しのDVDを買ってしまったという次第なんであります。このウベルトという役、惚れた女に拒まれてもストーカーになるでもなく、反乱軍に加わった彼女の父親と恋人をそっくり助命、結婚まで許しちゃうという、王様の態度としてはいかがなものかと思ってしまうくらいに格好良すぎる役です。なにせタイトル・ロールのエレナの、本命恋人のマルコムは男装アルトの役ですし。このオペラ、反乱軍の首領でエレナの婚約者というのがもう一つ超高音テノールの役なのですが、一方のこちらは舞台裏で殺されてしまう上、その後一同大円団という損な役。このロドリーゴを歌ったクリス・メリットもロッシーニ・テノールとしては知られた人のようなので、どうしてこのキャスティングなのかな? などと思ったりしたのですが、2幕途中の3重唱を見て納得。王様と反乱軍の親玉に当てはめるとすれば、ルックスからいってこれが適当でしょうねえ。ちなみにエレナ役のジューン・アンダーソン、身長178cmだとかで結構長身です。メリットもブレイクもそのくらいはあるので、この3重唱でも身長が揃ってて様になるのですが、高音テノールって長身は珍しいみたいですから、チビの男二人に挟まれたエレナってのもありえるわけだ、と想像したらちょっと笑っちゃいました。この3人で「オテロ」をやったこともあるそうで、この時はタイトルロールはメリット。それはそれでとても納得。
さらにYouTube見てたら、2002年のリエージュ公演の映像を見つけてしまいまして、ついに非正規映像にまで手を出してしまいました。ところがこれ、YouTubeのがましに思えるほどのぼけっぷり。おまけにロドリーゴはまずまずですが、タイトルロールの出来が相当落ちます。じゃおとなしくスカラ座の見とけって話なのですが、困ったことに鷹の頭かぶって登場するスカラ座版より、狼の頭かぶって登場するこっちの方が、ブレイクが数段格好いいのですわ。この2、3年後には引退してるんだから、もうだいぶ下り坂なんでしょう、音を転がすところでたまにぎょっとするような音が入ってたりしますが、私の好きな高音の響きはこちらの方が堪能できるような気が(何か、スカラ座の方は高音が突き抜けてない印象なんですよね)。というわけで別のところで買い直し(ようやるわ、私)。その甲斐あって、画質音質ともにかなり良くなったものを手に入れることができました。とはいえ、もっぱら楽しんでるのは「ああ、甘き炎よ」のアリアばかり。二重唱、三重唱はついスカラ座版で耳直ししちゃうんですが。
ブレイク、素直に美声を響かせるという歌い方ではなく、張り上げるようなというか、ちょっとクセのある歌い方なので、好き嫌いがはっきり分かれるらしいですが、私は断然ご贔屓です。エネルギーのある役柄なら、このパワフルな歌い方がとってもはまってるし、きれいに高音がのびた時の力強さが大のお気に入り。これだけパワフルな高音を出せる人って、今いないんじゃないかしら。ちなみにYouTubeにこの人の歌探しに行くと、結構な確率でコメント欄でフローレスのファンとブレイクのファンがバトル繰り広げてるのを見るはめになります(苦笑)。フローレスなんて、飛んでる飛行機でも落としそうな勢い(©斎藤美奈子『文壇アイドル論』)、と言いたくなるような歌手のファンやってる人間が、すでに現役引退した歌手のとこいってケンカ売らなくても、と思うんですけど・・・。(ま、フランス語ものでクセが耳に付くのは認めます。さすがに。)
余談ですが、YouTubeの動画についての詳細のところに"The always smiling American tenor"とか書いてあるところがあって、思いっきり爆笑してしまいました。怒りの歌なんか歌わせるとやたらとはまる人ですが、コンサートの映像とか写真では、いっつも笑顔ですね〜、確かに。ふと思いついて画像検索なんかしたら、こんな写真なんか見つけちゃいました(笑)。
まあ、そういうわけで、いささか持てあまし気味のこの演目。たまたま子ども向けに翻案されたものを見かける機会があって、理解の一助になるかと手に取ってみたところが、俄然興味がわき、大人向けに翻訳されたものも読んでしまいました。
・・・オペラと全然話が違う、というかオペラより数段ドラマチックで面白いんですけど!
まず、父ダグラスのキャラクターが全然違います。王の不興をかって追放されながらも、かつて手ずから武芸や馬術を教えた王に対しての忠誠心を失わない、気骨ある武人でめちゃくちゃ格好いいです。原作ではロデリック(=ロドリーゴ)のエレンへの求婚を断るのはダグラスその人。もちろんエレンとマルカムの仲を認めているからでもありますが、ロデリックと手を結んで王に逆らうことを望まないため。戦いが避けられないとみるや、我が身と引き替えに縁者の助命を願って単身王の元に出頭する潔さ。そして、王に武芸を教えたというのはだてでなく、武芸大会では連戦連勝でめっちゃ強い! どうしてオペラだと娘に意に染まぬ結婚を強制するだけの父親になってしまうのかしら。
で、ロデリックがこれまた格好いいのです。王権に従わず、略奪と闘争に明け暮れるハイランドの領主ですが、彼なりに騎士道精神を身につけていて、領内に入り込んできたジェイムズを、敵と知りつつも丁重に扱い、国境まで送り届けます。このあたりの、二人がお互いをよき好敵手と認め合うあたりがたまらなく良いです(笑)。最後は剣と剣の一騎打ちとなり、技で勝るジェイムズが辛くも勝利するのですけど。
エレンも、ダグラス家の娘だという自覚を持つ毅然とした女性で、自分の意志も行動力もあり、これまた嘆きっぱなしのオペラとはえらい性格が違います。仮に意に染まぬ結婚を押しつけられそうになっても、ルチアみたいに発狂するようなことはまずあるまいという感じです。これですから、マルカムの影がとんと薄くなるのは致し方ないでしょう(ロデリックとは対立していて、反乱軍には加わっていないので念のため)。解説(佐藤猛郎訳/あるば書房)によると、当のスコットが「最初からマルカムはお荷物でした。恋する男などというものは、彼の恋人にとっては興味ある存在でしょうが、それ以外の人には、まったく馬鹿みたいなものですから」「ロデリックにしても、ずいぶん注意はしているのですが、彼が主役の座を奪いそうになっています」と書いているのだそうで。
ところで、ロデリックには「あの天使のような声を、ロデリックが聞くのはこれが最後だ!」という切ない独白がありますが、この時エレンが歌っている歌にシューベルトが曲をつけたのが有名な「アヴェ・マリア」(私はバーバラ・ボニーを愛聴)です。このシューベルトの歌曲については解説でもふれられているのですけど、ロッシーニのオペラについては全く言及がないのですね。
ともあれ、オペラへの苦手意識をさらに助長してしまった感なきにしもあらず。こういう改変をしないと、イタオペにはならないんですかね。まあ、確かにジェイムズとロデリックの一騎打ちとか、武芸大会のシーンなんか、オペラには向かないと思いますが。比較的原作に忠実に映画化されるなら、是非是非見てみたいと思うのですけれど。