うそお、まだ1月じゃないんだけど、と思いながらお名前の出てくる公演を探すと、ありました、「メルビッシュ湖上音楽祭ガラコンサート 瀬戸市文化センター ソプラノのダグマー・シェレンベルガーら」。
えー!!! 熱愛するチューリヒの「メリー・ウィドウ」、そのハンナですよ! 慌ててネットで詳細を検索。いつの間にやら彼女、メルビッシュの総監督になってたんですねえ。歌手は4人なんだそうで、他に知った名前はテノールのモンタゼーリ。・・・またキミか、という感じでしたが。
是非とも行きたい! しかし1週間後の話であります。ドキドキしながら「ぴあ」のサイトにアクセスしたら、在庫状況は「○」。なんでこのぎりぎりにそんなに余裕があるんだ? と訝りつつ、月曜日の仕事帰りにコンビニへ寄り、ありがたく無事チケットを発券していただいたのでした。
というわけで遠路はるばる瀬戸市文化センターまで行ってきました。栄で名鉄瀬戸線に乗り換えて終点まで。そこからさらに800m(但し上り坂)。
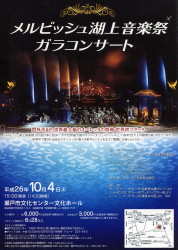 ヨハン・シュトラウスII: オペレッタ『ヴェネツィアの一夜』より
ヨハン・シュトラウスII: オペレッタ『ヴェネツィアの一夜』より
序曲 「麗しのヴェネツィア」
ヨハン・シュトラウスII: ポルカ・シュネル「トリッチ・トラッチ・ポルカ」
ヨハン・シュトラウスII: オペレッタ『ウィーン気質』より「こんにちは、懐かしい愛の巣よ」
ヨハン・シュトラウスII: 「シャンパン・ポルカ」
ヨハン・シュトラウスII: 「ほろ酔いの歌」(アンネン・ポルカ)
クライスラー: 愛の喜び
ヨハン・シュトラウスII: オペレッタ『ヴェネツィアの一夜』より
「さすらいのつばめ」 「みんな仮面をつけて」
ヨハン・シュトラウスII: ワルツ「春の声」
ヨハン・シュトラウスII: オペレッタ『こうもり』より「ぶどうが火と燃える情熱となって」
ヨハン・シュトラウスII: オペレッタ『こうもり』より序曲
レハール: オペレッタ『メリー・ウィドウ』より「ヴィリアの歌」
レハール: オペレッタ『微笑みの国』より「君こそ我が心」
カールマン: オペレッタ『伯爵家令嬢マリッツァ』より
「ヴァラシュディンへ行こう」 「来てくれ、ジプシー」
レハール: オペレッタ『メリー・ウィドウ』より
舞踏会のワルツ「メリー・ウィドウ・ワルツ」 「メリー・ウィドウ・ワルツ 唇は閉じても」
オスカー・シュトラウス: オペレッタ『ワルツの夢』より「そよ風の吹く庭で」
ヨハン・シュトラウスII: オペレッタ『ウィーン気質』より「ヒッツィングはお祭り騒ぎ」
ヨハン・シュトラウスII: ワルツ『美しく青きドナウ』
ヨハン・シュトラウスI: ラデツキー行進曲
会場の扉を開けた瞬間、謎は解けましたが・・・。思わず口あんぐり。1階席の前半分しか人いません。こんなガラガラの会場見たの初めて(・・・シャレになってないんですけど)。いつもの愛知県芸術劇場のコンサートホールがいかに豪華であったか痛感させられる会場自体の殺風景さも相まって、これで出演者のモチベーションはどうなっちゃうんだと不安でいっぱいに・・・。
いささか足元がおぼつかなげにマエストロ・ビーブル登場。そのせいでしょうか、指揮台もなし(楽譜も無し!)。始まった「ヴェネツィアの一夜」の序曲は、・・・軽やかで楽しい! 続く「トリッチ・トラッチ・ポルカ」でダンス登場だったのですが、女性ダンサーに張り合うように男性が踊るシーンがありまして、そのどや顔に、曲の途中にもかかわらず会場から起きる拍手。うん、これなら今日のコンサート、いける! それにしても、こんなに少ない観客相手でも手を抜かない出演者の皆様のプロ根性にただただ感謝。
心配の種さえ消えれば、なんたって前から10列目です。いつものニューイヤーコンサートと同じ値段しか払ってないというのに、声はまっすぐ飛んでくるし、歌手の表情は良く見えるし。ここしばらく、笑いをとりにいく場面があんまりなくて、さみしい思いをしていたのですが(ゆえに、感想もさぼってしまったのですが)、「ほろ酔いの歌」のペピちゃんのはじけっぷりに、そう、そう、オペレッタはこれでなくちゃ! とこちらのテンションも上がり調子。
後半最初の「こうもり」序曲で、鐘の音ってあの楽器から出てくるのか、初めてまともに見たな〜、なんて思ってたら、次の「ヴィリアの歌」の前に通訳とともにマエストロ・ビーブル登場。
「この曲にはコーラスの部分があるのですが、我々はコーラスを連れてきていません。会場の皆さまにお手伝いいただきたいのです。」
何と! というわけで観客一同、マエストロの指揮でコーラスの練習をしたのでありました(もちろんハミングでしたけど)。こんなオモシロいことやってくれると知ってたら、歌詞しっかりさらってきたのに〜(笑)。説明があっさりだったので、本番、ハンナのソロのはずのとこから歌ってる人が多数発生したのがご愛敬、でしたが。
アンコールは「トリッチ・トラッチ・ポルカ」を再度演奏してくれました。
初めて生で聴いたシェレンベルガーですが、高音が辛そうなのは録音で聴いてたとおりですね。でもこの人は舞台の上での身のこなしがすっごい巧い! 中でも受けたのは「ヴァラシュディンへ行こう」で、舞台でもやってるだけあって、抜群のノリだったのはもちろんなんですが、デュエットの途中でダンスのペアが舞台に出てきて、男女ペアが入れ替わって踊りながらフィニッシュする趣向だったんです。で、女性ダンサーと並んで拍手を受けていたジュパン役のバデアに向かって、行くわよ! ってあごをしゃくってみせた仕草が、めちゃ面白かったのでした。
もう一人のソプラノ、シェルは2007年のメルビッシュの『ウィーン気質』でペピ役だったそうで(映像で見たのはダブルキャストの別の人でしたが)、こういう役にはぴったりですね。歌も良かったですが、演技も楽しかったです。
真正面で聴いたせいか、毎度印象に残らないモンタゼーリも、悪くなかったです。ただ、「君こそ我が心」みたいなド直球の歌ならまあ見てられるんですが、メリー・ウィドウのデュエットのダニロ役は・・・うーん、キミ、その佇まいじゃカミーユだ・・・。
というわけで断然印象に残ったのがもう一人のテノール、アレクサンドル・バデア。なかなか張りのある声で声量も十分だったのですが、何より芝居気があって、見てて楽しい! 「ヴァラシュディンへ行こう」でコミカルなジュパンを歌ってくれたと思ったら、次の「来てくれ、ジプシー」のタシロもこの人で、今度は脱いだ上着を肩に引っかけて、やさぐれ感たっぷりに登場。後半になったら、ヴァイオリン奏者からヴァイオリン借りて弾き始めるじゃないですか! これが結構な腕前で、会場はやんやの大喝采だったのでした。
『ワルツの夢』の「そよ風の吹く庭で」はテノール2人の二重唱だったので(こんな曲です)、多分モンタゼーリがニキでバデアがモンチだったのであろうと推理しますが、それというのもこの人の方に“ちょっと企んでます”的雰囲気が良く出てたからなんですね。
何でもモネ劇場の「天国と地獄」のDVDではオルフェ役で、バイオリンの腕前も披露しているとか。5年前にカラフで来日してるそうなんですが、芸達者さが要求される役で是非また見てみたいです。
終演後、CD購入者へのサイン会。サインは欲しかったのですが、DVDは日本語字幕なしの輸入盤だけしか置いてないし、音だけCDで聴くならメルビッシュじゃなくてもいいんですが・・・。第一、本日の出演者の出てるディスク、無いときてるし(商品化されてるのはシェレンベルガーの『マリッツァ』のDVDだけでしょうが、それすら見ませんでしたよ?)。うーんと悩んだ挙げ句、「ジプシー男爵」のCDを購入し、出演者の皆様のサインはチラシの裏にいただいてきました。シェレンベルガーには『メリー・ウィドウ』のDVDにも。(主役カップルのサインコンプリート^^。)
・・・そう、会場で初めてお目にかかったチラシ、今どき珍しい片面印刷で、出演者の写真も載ってなかったんです。輪転機で刷ったとおぼしきプログラムには、出演者の概略は載ってましたが、曲目が載っているだけで、演目の解説も曲の解説もなし。私は、『ヴェネツィアの一夜』と『ワルツの夢』は、見たことはなくても話の筋くらいは知ってましたが、初めての人には何が何やら、だったのではないかと想像します。歌ものは、どんな内容なのか、ざっくりでも知りたいのですけど・・・。そういえばアンケート用紙が配られない公演ってのも初めてでしたねえ。
 モーツァルト:
モーツァルト: ヨハン・シュトラウスII: オペレッタ『こうもり』序曲
ヨハン・シュトラウスII: オペレッタ『こうもり』序曲 スメタナ: オペラ『売られた花嫁』序曲
スメタナ: オペラ『売られた花嫁』序曲 ヨハン・シュトラウスII: オペレッタ『ジプシー男爵』序曲
ヨハン・シュトラウスII: オペレッタ『ジプシー男爵』序曲 ツェレの街中を散策中、見かけたポスター。“Die Zauberflöte” ならぬ “Das Zauberflötchen”。「小魔笛」ってなとこでしょうか。ハンブルクのオペラハウスの引越公演みたいです。
ツェレの街中を散策中、見かけたポスター。“Die Zauberflöte” ならぬ “Das Zauberflötchen”。「小魔笛」ってなとこでしょうか。ハンブルクのオペラハウスの引越公演みたいです。 ホイベルガー: オペレッタ『オペラ舞踏会』序曲
ホイベルガー: オペレッタ『オペラ舞踏会』序曲 ドニゼッティ:《ドン・パスクァーレ》
ドニゼッティ:《ドン・パスクァーレ》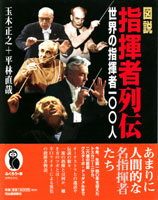 たまには普通に読んで愉しかった本を(笑)。というわけで『図説指揮者列伝 世界の指揮者100人』(玉木正之+平林直哉/河出書房新社)です。
たまには普通に読んで愉しかった本を(笑)。というわけで『図説指揮者列伝 世界の指揮者100人』(玉木正之+平林直哉/河出書房新社)です。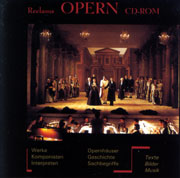 やれ実演だDVDだとオペラに大騒ぎするようになったら、こんなCD-ROMをもらいました。1997年のソフトとあって、OSにWindows3.1とか書いてあるんですが・・・XPでもちゃんと動いてくれました。
やれ実演だDVDだとオペラに大騒ぎするようになったら、こんなCD-ROMをもらいました。1997年のソフトとあって、OSにWindows3.1とか書いてあるんですが・・・XPでもちゃんと動いてくれました。