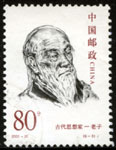Chinese
Ancient History

帝舜
中国の伝説的帝王。五帝のひとり。氏は有虞。堯と並び称される中国太古の聖天子。孝・悌の聞こえが高かったため、堯から禅譲を受けて天子となったと伝えられる。
中華民国発行

商湯王
前18世紀頃の商王朝初代の王。甲骨文では唐または大乙、戦国時代の金文では成湯と称される。亳におり、周囲の諸族を合わせ、夏の桀王を滅ぼして商王朝を開いたとされる。古文献は、多く明哲王としてその徳をたたえている。
中華民国発行
 |
 |
| 父丙角 |
父癸鼎 |
1975.11.12 中華民国発行
【故宮古物 <古代銅器>】 |
1995.10.9 中華民国発行
【国立故宮博物院建院70周年記念】 |

周武王
前11世紀頃の周の建国者。名は発。父の文王を継ぎ、商の紂王を滅ぼして鎬京に都し、一族功臣を各地に封じて周の基礎を築いた。商の漢字文化を継承し、武王という王号を定め、父に文王という追号をおくった。父とともに王者の範とされる。
中華民国発行

周公
文王の第4子で武王の弟。名は旦。武王が商を滅ぼしてのち、封ぜられて魯公となったが封地におもむかず鎬京にとどまって武王を助け、その死後は幼少の成王の摂政として国事にあたった。三監の乱を鎮定してより、特に東方経営に力を注ぎ、洛邑に副都を建設するなど、西周王朝草創期にその基礎を確立。後世、周の礼楽・制度を定めた理想の聖人として孔子をはじめ儒学者から尊ばれた。
中華民国発行

毛公鼎
清の道光年間(1821-1850)、岐山の麓の鳳翔(現在の宝鶏県)で出土したといわれる。高さ53cm、径48cmの円鼎で、32行、497字の銘文をもっている。現在発見されている青銅器の中で、最も長い銘文を持つもの。咸豊2年(1852年)、陝西の商人の蘇億年が北京に持ち出し、山東の陳介祺という人物の手に渡った。
銘文の内容は、周王が毛公という人物に政治の一切を託すというもの。器形からみても西周後期に属するものなので、厲王が出奔して、共伯和が摂政となった混乱期(前841年ごろ)のものではないかとみられる。銘文にある周王が誰であるか、毛公が何者であるかは不明。台湾の故宮博物院所蔵。
1961.5.1 中華民国発行
【古物(故宮と中央博物館蔵)】
 |
 |
| 2000.11.11 中華人民共和国発行 |
中華民国発行 |
孔子 前551/2-前479
春秋時代の思想家。儒教の始祖。名は丘、字は仲尼。魯に生まれ、魯に仕えるかたわら、広い学識により信望を集め、多くの門弟を教えた。51歳で大司寇となり魯の国政に参加したが、政争に巻き込まれて官を辞した。のち弟子を率いて諸国を遊説し、明君を求めて自己の政治理念を生かそうとしたが用いられず、晩年は再び魯に戻って門弟の教育と古典の整理にあたった。『論語』は彼の言行を弟子たちが記録したもの。堯、舜、文王、武王、周公旦らを尊崇し、古来の思想を大成し、為政者の徳によって民衆を化育する徳治主義を根幹とし、周の遺制たる礼楽制度による周の復古を説いた。その教えは、儒教として中国思想の根幹となり、後世に大きな影響を及ぼした。
 |
 |
| 孫子像 |
呉宮教戦 |
孫子
春秋時代の名将。名は武。呉王闔閭に仕えた。彼の著述といわれる兵法書『孫子』は国策の決定、将軍の選任、行軍、輸送、その他作戦、戦闘の全般にわたって、格調高い文章で、簡潔に要点を説いており、戦わずに勝つことを主とする。
1995.12.4 中華人民共和国発行
【孫子の兵法】
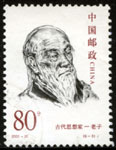
老子
中国古代の思想家。姓は李、名は耳、字は聃。楚の苦県の生まれで、周王室の守蔵室使をしていたとき、孔子に礼の道を教えたこともあるが、やがて周の衰えを嘆き隠棲しようと志し、その途中で『道徳教』(通称『老子』)を著したという。しかし、この『史記』の伝える伝記には疑問が多く、彼の生存を孔子より100年後に下げる説や、その実在そのものを否定する説もある。儒家の教説に反論して無為自然の道を説いた。荘子がこれを継承したので老荘思想ともいう。後世の道教は老子を祖とするが、道教の教理と老子の思想とは直接関係はない。
2000.11.11 中華人民共和国発行

孟子 前372?-前289?
戦国時代の思想家。鄒の人で名は軻、字は子輿。孔子の孫の子思の門人に学び、梁・斉・宋などを遊説したが志を得ず、晩年故郷で門人の教育にあたった。彼の言論を記した『孟子』は『論語』『中庸』『大学』とともに四書といわれる。孔子の道を継承し発展させることを自任。自給自足の衣食住の確保、井田法の施行、自由関税などにより人民の恒産を安定させたうえで、教育を普及して道徳国家を実現するという王道の理想を掲げ、あまねく人間は、道徳の価値を主体的に判断し、実行する善なる性を先天的に固有しているという性善説を根拠として、道徳的自覚的実行、道徳人の自由独立を主張した。
2000.11.11 中華人民共和国発行

秦公簋
1923年の出土といわれる。
銘文は「秦公曰く」ではじまっており、おそらく哀公(在位前537-501年)の時期かとおもわれる。
銘文の大意は、秦の皇祖が天命を受けて禹跡(中国)を統治してから、十二公が帝(天帝)のところに在る、厳として天命をつつしみ、その秦を保ち、蛮夏を治め、明徳をもって万民を勅し、胤士(歴代に仕えた士)を養い、不廷(服従しない邦)を鎮静した。朕は祀を虔敬するためにこの器を作り、皇祖にささげる、永いあいだ在位して、高弘にして慶有り、四方をたもたせていただきたい、といった内容。二度用いられている文字は一分の狂いもないほど同形であり、この銘文は字母をつくって押捺したというのが羅振玉の説。
春秋戦国時代では諸侯以外でも有力者が銅器をつくるが、秦では王室以外の作器はほとんどない。
北京の中国歴史博物館所蔵。
2003.12.13 中華人民共和国発行

秦半両
秦で発行された円形の銅貨。始皇帝26(前22)年の天下統一時に発行されたといわれている。このときのものは中央に方形の穴があり、無郭で、直径約3.6㎝、重さ半両(約8グラム)あり、実質貨幣であった。漢半両は、秦半両より小型で、重さも半両より軽く、名目貨幣であった。
1975.5.20 中華民国発行
【陳勝・呉広の農民蜂起】

農民蜂起の像
秦末の農民、陳勝と呉広の起こした叛乱。陳勝は陽城、呉広は陽夏の人。秦の2世皇帝の元年(前209年)1月、漁陽の守備に徴発されたが期限に遅れた。この場合、秦の法では斬罪であったため、二人は「王侯将相いずくんぞ種あらんや」と一行を扇動して挙兵。貧民を糾合して河南で一時勢力をふるったが、秦軍に敗れ、また内紛を起こして6ヶ月で壊滅した。しかし二人の挙兵を機に項羽、劉邦らによる群雄割拠となり、秦は滅亡した。
1991.7.7 中華人民共和国発行
《目次》
◆ 中国考古学編 へ
参考文献:
『ブリタニカ国際大百科事典』
『NHKスペシャル四大文明 中国』(鶴間和幸・編著/NHK出版)
|