Year of Snake
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
��肩���g�߂ȑ��݂̊��ɂ́A�V�}�w�r�Ƃ��}���V�Ƃ��A�I�_�C�V���E�̐؎���āA���{�ɂȂ��ł��ˁB
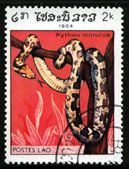
�C���h�j�V�L�w�r �@Python molurus
1984.8.20�@���I�X���s
�j�V�L�w�r�ȃj�V�L�w�r���ɕ��ނ����w�r�B����A�W�A�A�����암�ɕ��z�B�S��3�`6m�ŁA�ő�S��823cm�̋L�^������B�̐F�͒����F�ŁA���䂪���������������B�M�щJ�тɑ����������A���ӂő��������邪�����n�тɂ��������Ă���B�c�̎��ɂ͎��㐱�X�����������A�����ɔ����قڊ��S�ɒn�㐱�ƂȂ�B�H���͓����H�ŁA�傫���ɉ������J�G���A��ށA���ށA�M���ނ�H�ׂ�B��^�̌̂ł̓q���E��l�̕ߐH�������B���͗�������悤�ɂƂ���������A�ؓ������k�����̉����グ�ė���g�߂�B

�h���[�t�{�A�ȁ@Tropidophis paradaels
1982.6.15�@�L���[�o���s
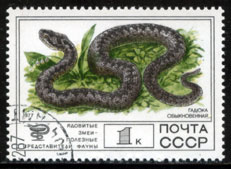
���[���b�p�N�T���w�r �@Vipera berus
1977.12.16�@�\�A���s
�N�T���w�r�ȃN�T���w�r���ɕ��ނ����w�r�B�L�ŁB���[���V�A�嗤�̖k���n��ɍL�����z���A���̓T�n�����A�X�J���W�i�r�A�����ł͖k�Ɍ��t�߂ɂ�������B�S��50�`60cm�A�ő�90cm�قǂŁA���͗Y�����傫���Ȃ�B�����͒��O�p�`�ł���قǑ傫���Ȃ��A���E�͏c���Ŋ�O�ɂ̓s�b�g�튯�������B������X�тɐ������A���^�M���ނ⏬�^��ޓ���H�ׂ�B���ِ��ŁA2-20���̗c�ւ��Y�ށB
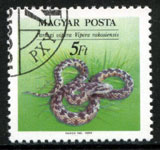
�m�n���N�T���w�r�@Vipera ursinii
1989.7.26�@�n���K���[���s
�N�T���w�r�ȃN�T���w�r���ɕ��ނ����w�r�B�L�ŁB�t�����X�암���璆���k�����ɂ����čL�����z���邪�A�J���ɂ�鐶���n�̔j��Ȃǂɂ��̌Q�͏��������f����Ă��Đ������͌������Ă���B�S��50cm�B�����̗͑�^�B�w�ʂ̗ɂ͋؏�̗��N�i�L�[���j������B�w�ʂ̑̐F�͊��F�≩���F�A�D�F�B�ÐF�̑ȉ~�`�̔��䂪2��Ō��݂ɓ��邪�A���䂪�q����̂�����B�W��3000m�܂ł̑����ɐ������A�����ށA���^��ށA���^�M���ނȂǂ�H�ׂ�B
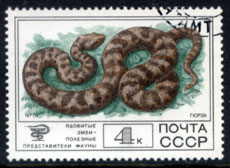 |
 |
| �}���n�i�N�T���w�r �@Vipera lebetina |
�T���n�_�N�T���w�r�@Echis carinatus |
1977.12.16�@�\�A���s
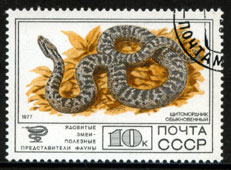 |
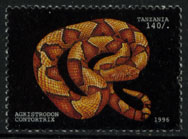 |
| �A�����J�}���V�� �@Agkistrodon halys |
�J�p�[�w�b�h �@Agkistrodon contortrix |
| 1977.12.16�@�\�A���s |
1996.3.29�@�^���U�j�A���s |
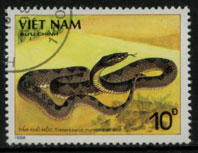
�^�C�����n�u�@Trimeresurus mucrosquamatus
1989.5.1�@�x�g�i�����s
�N�T���w�r�ȃn�u���ɕ��ނ����w�r�B��p����ђ����암�A�C���h�V�i�����k���ɐ�������B�܂��A�l�ɂ���Ď������܂ꂽ�̂��A����{���ɂ����z���L���Ă���B�S����60-120cm�B�z���n�u�ɔ�ׂ�Ə��^�ŁA��┒���ۂ��D���F�ɁA�����͗l���K������������ł���B�ł͋����A�܂����̃n�u�ނ���������������߁A�g�̂̂��[���ɓł�ł����ނ��Ƃ��ł���B��p�ł͎R�[�i����낭�j����C��1000���[�g���Ɏ���X�т₻�̕t�߂ɑ����������A���̃n�u�ɔ�ׂĎ���ł̊����������B��s���Ńl�Y�~���̏��^�M���ށE�����Ȃǂ̒��ށE�g�J�Q�E�J�G����H�ׂ�B
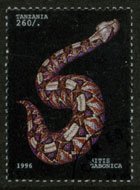
�K�{���A�_�[�@ Bitis gabonica
1996.3.29�@�^���U�j�A���s
�N�T���w�r�ȃA�t���J�A�_�[���ɕ��ނ����w�r�B�A�t���J�嗤��������암�ɂ����Đ����B�S���͒ʏ�120�]160�p���ł��邪�A�ő�ł�205�p�̋L�^������A�̏d��183cm�̌̂�11kg�̋L�^������B�̌`�͑����A���G�Ȕ��䂪���邪�A�����t�̏�Ȃǂł͕ی�F�ɂȂ�ƍl�����Ă���B�ʼn�̒����͑傫�����̂�5cm�ɒB���A�֗ޒ��ő�̓ʼn�����B�M�щJ�тɐ�������B�댯��������ƕ��C���������ĈЊd����B ���^�M���ށA���^���ނƂ������P����������ɐH�ׂ邪�A�q�L�K�G������H�ׂ邱�Ƃ�����B��U���ݕt���ƁA�l�������ʂ܂ŗ����Ȃ��B
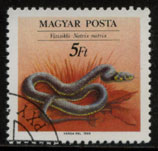 |
 |
| 1989.7.26�@�n���K���[���s |
1963.6.1�@�|�[�����h���s |
���[���b�p���}�J�K�V �@Natrix natrix
�i�~�w�r�ȃ��E�_���ɕ��ނ����w�r�B�A�t���J�嗤�k���A���[���V�A�嗤�����ɕ��z�B�ő�S��200cm�B�̐F�͌̂ɂ��ψق��傫���A���F�A�Ί��F�A�×ΐF�A�D�F�A�����̌̂�����B�̑��ʂɂ͍������Ȃ�����B�͐�A�A�r�����̐��ӂ⎼�n���̎��������ɐ�������B���s���ŁA���ށA�����ށA���ށA���^�M���ޓ���H�ׂ�B�j���͏�肭�A�����ł��l����߂炦��B�댯��������Ɩ݂␅���֓�������A�̂�c��܂��ĈЊd����B����ł����肪���܂Ȃ��ꍇ�́A�����ɂȂ��Č����J������o�����r���o����L���������o���[���s�����s���B���O�Ɂu���}�J�K�V�v�Ƃ��邪�A���{�̃��}�J�K�V�ƈقȂ�ł͎����Ȃ��B

�N�X�V�w�r �@Elaphe longissima
1989.10.20�@�u���K���A���s
�i�~�w�r�ȃN�X�V�w�r���ɕ��ނ����w�r�B�p���ȓ�̃t�����X�A�C�^���A�k���A�o���J�������S�y�Ə��A�W�A�ɂ����čL���������A�ł͎����Ȃ��B���������110-150cm�A��^�̂ł�200-225cm�ɂȂ�A���[���b�p�ő�̃w�r�̈�ł���B����u������A�K�x�ȉ��x�E���x�̂���ω��ɕx�����D�ށB���s���ŁA�ؓo������܂��B���b�g�ȉ��̑傫����ꖎ��ށE�H���ނ⏬���A���E���Ȃǂ�ߐH����B�Ñ�M���V���E���[�}�ɂ����āA�A�X�N���s�I�X���J�����_�a�Ŏ��炳��Ă���A"Aesculapian snake"�Ƃ��������t����ꂽ�B���̐_�̎���Ɋ����t���Ă���w�r�́A���̎�ł���Ɛ��������B
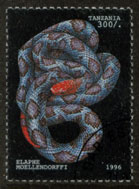
�c�}�x�j�i���� �@Elaphe moellendorffi
1996.3.29�@�^���U�j�A���s
�����쓌���A�x�g�i���k���ɕ��z�B�S����160�|180cm�A�ő�ł�250cm�ɂȂ�B �̐F�͗Ί��F�ŁA���F�ɉ����ꂽ�Ê��F�̔��䂪���сA�ג��������Ɣ��͐Ԋ��F�B��̑������ɐ������Aꖎ��ނⒹ�ށA�����ނ�ߐH���Ă���ƍl�����Ă���B
 |
 |
| 1977.12.16�@�\�A���s |
1992.7.10�@���I�X���s |
�C���h�R�u���@ Naja naja
�R�u���ȃt�[�h�R�u������ ���ނ����w�r�B�C���h�A�X�������J�A�l�p�[���A�p�L�X�^���ɕ��z�B�S��135-150cm�B�̔畆�i�t�[�h�j�w�ʂ�2�̖ڋʖ͗l���q���������䂪����̂���ʓI�����n��ɂ��ψق�����B�ł͋��͂Ȑ_�o�łŁA�ŗʂ������B�܂��A�_�k�n�ɐ������邽�߁A�l�����܂���Q�������A�댯�ȓŎւƂ��ċ�����Ă����B�����A�X�сA�_�k�n���̗l�X�Ȋ��ɐ�������B�댯��������ƃt�[�h���L���ė���������A���C���������ĈЊd����B���^�M���ށA��ށA�J�G������H�ׂ�B
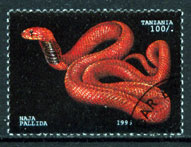
Naja pallida
1996.3.29�@�^���U�j�A���s
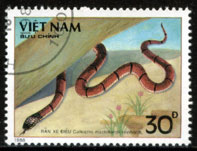
�������x�j�w�r�@ Calliophis macclellandi
1989.5.1�@�x�g�i�����s
�R�u���ȃ������x�j�w�r���ɕ��ނ����w�r�B��A�W�A�A����A�W�A�A��p�A���d�R�����̕W��1000���[�g���ȉ��̒n��ɕ��z����B�S���͕��ς���ƃI�X��635mm�A���X��780mm�Ń��X�̂ق����傫���B���������{�Y����̃C���T�L�������x�j�w�r��300-500mm �Ə��^�̂��̂������B�̐F�ɂ��ẮA�w���̒n�F�͐Ԃ������͒����F�ł���A�ׂ����F�̊�䂪��芪���B�n�F����̐���`��͎Y�n�ɂ���ĕω�����B�L�t���т̗я����Z���Ƃ��A���삪�ɖ��Ő��i�͉��a�ł���B�g�J�Q�⓯�ނ̏��^�̃w�r��ߐH����B
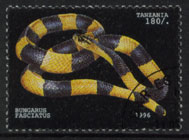
�}���I�A�}�K�T �@Bungarus fasciatus
1996.3.29�@�^���U�j�A���s
�R�u���ȃA�}�K�T�w�r���ɕ��ނ����w�r�B�C���h���瓌��A�W�A���o�āA�����암�ɂ܂Ő�������B�L�ŁB�S��150-230cm�B�̐F�͍��ŁA���F�����т�����B�w��������オ���Ă���A�w���͎O�p�`�Ɍ�����B�포��fasciatus�́u�т̂���A���Ȃ̂���v�̈ӁB�����ۂ݂�тт邱�Ƃ��a���̗R���B���n���R�n�̐X�сA�����A���ӁA�_�n�ɐ�������B��s���Œ��Ԃ̓l�Y�~�̌@��������A�V���A���̌Ñ����ŋx�ށB���^�M���ށA���^���ށA��ށA�J�G������H�ׂ邪�A���ɑ��̃w�r�ނ��D��ŕߐH����B������ł́u���ցv�܂��́u���r�сv�Ə̂���A���������ł��邽�߁A�L�������ł͎O�ւ̂ЂƂƂ��ĎփX�[�v�Ȃǂ̐H�ނƂ��ė��p����Ă���B
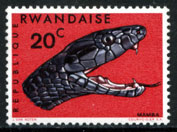
�}���o�@ mamba
1967.1.30�@�������_���s
�R�u���ȃ}���o���Ɋ܂܂��w�r�̑��́B���̑�Dendroaspis�̒��Ԃ͊댯�ȓŃw�r�ŁA�k���������A�t���J�S���4�킪���z����B�ő��̓u���b�N�}���oD. polylepis�őS��3�`4.5���[�g���ɒB���A���n�ł͂����Ƃ��������Ńw�r�ł���B�����������ג����Č`�ԓI�ɂ͈�ʂ̖��Ńw�r�Ƒ卷�Ȃ��A�̐F�͊D���F���獕���F�܂ŕψق�����B������X�сA���Ȃǂ��܂����I�����܂��܂Ȋ��Ō�����B�ؓo�����肭�A��Q���̑����݂̒��ł͂����Ƃ��������铮���Ƃ����B�v���I�ȋ����_�o�ł������A�ɐB���ɂ͂Ƃ��ɋC���r���Ȃ�B

�^���r�T���S�w�r�@Micrurus frontalis
1996.3.29�@�^���U�j�A���s
�R�u���ȃT���S�w�r��

Yellow-faced Whip Snake�@Demansia psammophis
1982.4.19�@�I�[�X�g�����A���s
�R�u���ȃ��`�R�u�����ɕ��ނ����w�r�B�L�ŁB�I�[�X�g�����A�ɍL����������B�S��80cm�A�ő�ł�1.2m�ɂȂ�B�̐F�͊D�F���������B�����͉��F�ŁA�ڂ̎��肩����p�ɂ����ăR���}��̍����͗l������B��Ƀg�J�Q��ߐH����B

�E�~�w�r���@Hydrophis brookii
1975.11.25�@�k���F�g�i�����s
����̓E�B�L�y�f�B�A�A���E��S�Ȏ��T���
 �@Back
�@�@Top
�@�@Next�@
�@Back
�@�@Top
�@�@Next�@
![]() �@
�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
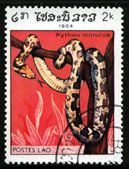

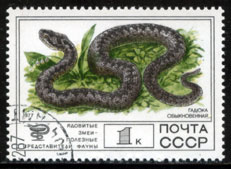
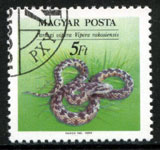
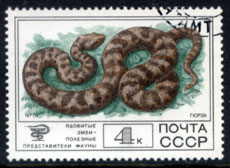

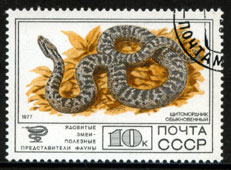
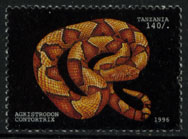
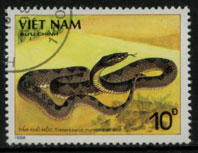
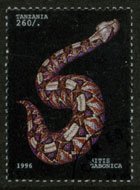
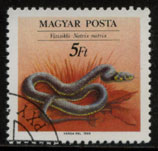


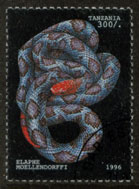


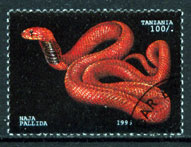
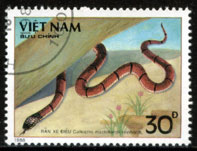
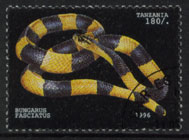
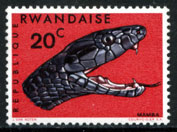



![]() �@Back
�@�@Top
�@�@Next�@
�@Back
�@�@Top
�@�@Next�@![]()