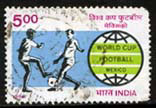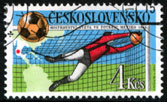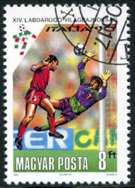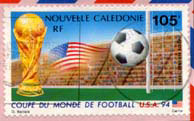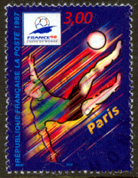World Cup Football
野球ほどの切実さが無かったせいか(苦笑)、未だにほとんどルールを憶えられないサッカー。
というわけで、説明は「W杯70年の物語 16大会を振り返る」(上・2002年1月19日、下・2月16日:中日新聞)をそのまんま引用です。
【第6回 スウェーデン大会 1958年】

スウェーデン国旗とジュール・リメ杯を掲げるペリーニ主将
1970.8.4 ブラジル発行
ブラジルの大会優勝3回達成記念
50年大会で優勝を逃したブラジルが屈辱を晴らした大会だった。そして、天才プレーヤー・ペレが
17歳の若さで初めて世界にその名を響かせた大会でもあった。
当時新戦術の4−2−4システムで臨んだブラジルは、1次リーグでオーストリアを下したが、続くイングランド戦で引き分け、ソ連戦に準々決勝進出をかけていた。
その勝負どころで白羽の矢が立ったのがブラジル国内では無名に近い少年、ペレだった。
ペレはW杯という初舞台で、俊敏に動き、得点能力の高さを見せつけ、常に冷静さを保って奇跡のようなプレーを連発した。同じく新人で起用された右サイドのガリンシャとともに好連携を見せ、中盤を支配した。
準決勝のフランス戦ではハットトリック。決勝でも同僚のババと2ゴールずつを決めて地元のスウェーデンに5−2で圧勝、ブラジルを初の優勝に導いた。
神秘のベールを脱いだペレは、史上最も偉大な選手として名を刻む第一歩を踏んだ。それは、ブラジルの黄金時代の幕開けでもあった。
【第8回 イングランド大会 1966年】

ボールを争う選手
1966.6.1 イギリス発行
サッカー発祥の地でありながら第二次大戦前まで不参加、戦後から参加したが最高成績はベスト8だったイングランドが、初めてW杯の開催国となった。意地と名誉をかけた大会だったが、ムーア、B.チャールトン、ハーストらの活躍で初優勝を飾った。
無失点の2勝1分けで決勝トーナメントに進んだイングランドは、準々決勝でアルゼンチンに1−0で勝ち、準決勝では9ゴールを挙げて得点王に輝いたエウゼビオを擁するポルトガルにB.チャールトンの2得点で2−1で勝った。
西ドイツとの決勝は2−2で延長にもつれ込んだが、クロスバーに当たって真下に落ちた後、ゴール外にはねたハーストの“疑惑のシュート”などで4−2で下した。ハーストは今でも、W杯決勝でハットトリックを達成した唯一の選手だ。
この大会では朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が、アジア勢で初めてベスト8に進出。史上初の3連覇を狙ったブラジルがペレの負傷もあって1次リーグで敗退するなど、番狂わせが相次いだ大会でもあった。
【第9回 メキシコ大会 1970年】

ドイツ対ウルグアイ 準決勝
1970.10.29 チェコスロヴァキア発行
高地に特有の強い日差しと悪条件がそろった大会は、神様・ペレをはじめ多くのタレントを擁したブラジルが「フテボル・アルテ」(サッカーの芸術)といわれた攻撃的なサッカーで制した。
1958年のスウェーデン大会、62年のチリ大会に続く3度目の優勝で、大会規約通りジュール・リメ杯の永久保有権も獲得(のちに紛失。盗まれたという説も)した。
得点王は「爆撃機」の異名をとったミュラー(西ドイツ)。2度のハットトリックを含め、10ゴールを挙げた。
大会屈指の好カードは決勝戦ではなく、前回王者・イングランドと本命・ブラジルが激突したグループリーグ。ペレの決定的なシュートをイングランドのGKバンクスが超美技ではじき出すなど、最後まで予断を許さなかった試合はブラジルが1−0で辛勝した。
日本にとっても歴史的な出来事が―。丸山義行が日本人として初めてレフェリー(線審)を務めた大会でもあった。
【第10回 西ドイツ大会 1974年】

1974.5.15 ドイツ連邦共和国発行
神出鬼没のプレーから「空飛ぶオランダ人」と呼ばれた天才・クライフ率いるオランダが、画期的な「トータルフットボール」で大会を席捲。2次リーグでは前回王者・ブラジルも圧倒し、新時代の到来を世界に強烈に印象づけた。
豊富な運動量を後ろ盾にした全員守備、全員攻撃のサッカーは、30年近くたった今の戦術にも息づく。
決勝で「皇帝」ベッケンバウアー率いる西ドイツの“魂のサッカー”の前に屈するが、W杯史上屈指の好チームの1つとして必ず名前が挙がる。
統合前の東西ドイツがそろって出場。偶然(?)にも1次リーグで同組に入り話題となった。
試合は劣勢と思われた東ドイツが1−0で競り勝った。優勝した西ドイツが唯一喫した黒星は、のちに「2次リーグの組み合わせを視野に入れた意図的な敗戦」などと勘ぐられた。
西ドイツのストライカー、ミュラーは今大会4ゴールでW杯通算14ゴール(最多記録)とした。
【第12回 スペイン大会 1982年】
 |
 |
 |
| 1980.5.23 スペイン発行 |
1982.1.29 チェコスロヴァキア発行 |
1982.4.28 フランス発行 |
イタリアがベテランGKゾフを中心とした鉄壁の守り、ロッシの活躍で3度目の優勝を飾った。しかし、大会はむしろ、ジーコ、ソクラテスら「黄金のカルテット(4人)」を擁し優勝候補の筆頭だったブラジルが勝てなかった大会として、人々に記億されている。
テレ・サンターナ監督が「夢のチーム」と胸を張ったセレソンは、1次リーグは危なげない試合運びで3連勝。2次リーグでもアルゼンチンを撃破、次戦・イタリアとは引き分けでも得失点差で準決勝進出と優位に立っていた。
だが、ロッシのハットトリックの前に沈んだ。八百長事件による2年間の出場停止が響き、それまで全く振るわなかった「黄金の坊や」(ロッシの愛称、童顔・細身の体つきからそう呼ばれた)の突然の“目覚め”に、ソクラテス、ファルカンによる2度の同点ゴールも徒労に終わった。ロッシは準決勝で2得点、決勝でも1得点と、ブラジル戦を契機に大ブレークし、大会得点王に輝いた。
【第13回 メキシコ大会 1986年】
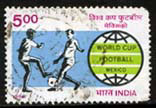 |
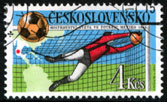 |
| 1986.5.31 インド発行 |
1986.5.15 チェコスロヴァキア発行 |
コロンビアが経済情勢の悪化を理由に開催権を返上、代わってメキシコが2度目のホストを務めたW杯は、アルゼンチンのマラドーナのための大会だった。
彼の名を世界に知らしめたのは、決勝トーナメントの準々決勝・対イングランド戦だった。
まずは後半6分の“神の手”ゴール。相手DFが不用意に浮き球で返したバックパスに、マラドーナが絡む。GKシルトンと競り合った結果、マラドーナが手で押し込んで、アルゼンチンの先制点となった。「ハンド? いや神の手だ」(マラドーナ)は、今も語り継がれる名言だ。
ただ、そのままで終わらないのがファンタジスタたるゆえん。その3分後には自陣からボールをキープして60メートルをドリブル突破、シュートも決めた。
5人の選手を次々にかわしての得点は、W杯ベストゴールの座を今も譲っていない。
優勝はもちろん、アルゼンチン。ただ、不思議と得点王はイングランドのリネカー(元名古屋)の
6点だった。
高田静夫審判が、日本人として初めて主審を務めた大会でもあった。
【第14回 イタリア大会 1990年】
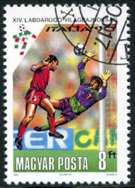 |
 |
| 1990.4.27 ハンガリー発行 |
1990.5.8 チェコスロヴァキア発行 |
マテウス、クリンスマン、ブレーメらを擁した西ドイツが、ブラジル、イタリアと並ぶ史上最多3度目の優勝を飾った。
監督は1974年大会で優勝したときの主将、「皇帝」ベッケンバウアー。選手と監督で優勝を経験したのは、ブラジルのザカロに続き、史上2人目の快挙だった。
ヌコノ、ミラらの活躍で前回優勝のアルゼンチンを開幕戦で下したカメルーンがその後も快進撃を続け、アフリカ勢初のベスト8入り。「不屈のライオン」の躍進で、国際サッカー連盟(FIFA)はアフリカの出場枠を次大会から増やさざるを得なくなった。
得点王は「未熟なストライカー」をいわれたイタリアのスキラッチ(6点、元磐田)。1次リーグの第2戦までは控えだったが、第3戦で先発に抜擢されると勝利に貢献する貴重なゴールを積み重ね、大会MVPにも選ばれた。
連覇を狙ったアルゼンチンは決勝で敗れ、マラドーナは悔しさからピッチで号泣した。2人の退場者を出しては仕方のない結果だった。
【第15回 アメリカ大会 1994年】
 |
 |
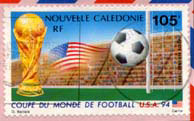 |
|
M.ダリンとK.インイェソン |
|
| 1994.5.26 アメリカ発行 |
1994.5.11 スウェーデン発行 |
1994.7.14 ニュー・カレドニア発行 |
守備的な戦いが主流を占め退屈になりかけていたW杯は、米国大会で勝ち点を従来の「2」から「3」に引き上げるなど、若干のルール改正で少し息を吹き返した。
前回大会よりやや攻撃的にシフトされた大会の中心にいたのが、ブラジルのロマーリオだった。
“ゆりかごダンス”でおなじみのベベットとの2トップは破壊力満点。得点王こそサレンコ(ロシア)、ストイチコフ(ブルガリア)に譲ったが、ブラジルの史上最多4度目の優勝に貢献、米国大会は「ロマーリオの大会」と呼ばれた。
80年代から90年代にかけてのスーパースター、マラドーナはこの大会途中に禁止薬物の使用が
発覚。栄光の舞台から姿を消すことになった。
さらに悲しい事件も。1次リーグの米国戦で敗戦につながるオウンゴールを記録したコロンビアの
DFは帰国後、無残にも射殺された。
昼間に猛暑の中で行われて消耗戦となった決勝は、イタリアの至宝、R・バッジオがPKを外して
幕が下りた。
サッカー不毛の地での開催は、意外にも史上最高の観客動員、興行収入を記録した。
【第16回 フランス大会 1998年】
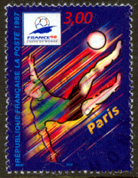 |
 |
 |
| 1998.1.24 フランス発行 |
1998.7.12 フランス発行 |
1998.6.26 ネパール発行 |
史上最多32カ国が参加した20世紀最後を締めくくる大会は、「W杯生みの親」である第3代FIFA会長、ジュール・リメの功績をたたえるようにその母国・フランスで開催された。
天才ロナウドをはじめリバウド、ロベルトカルロスなど、まばゆいばかりのタレントを擁し、多くの評論家がブラジルの5度目の優勝を疑わなかった大会はしかし、ジダン率いる“多国籍軍”フランスが、地の利も生かして初優勝を飾った。
ストライカー不在といわれたフランスだが、屈強な守備陣に創造性あふれる中盤、エメ・ジャツケ監督のさい配もさえて悲願を達成した。
ブラジルは決勝直前にロナウドが体調不良を訴えるなどチームが浮足立ち、本来の力の半分も出せずに敗れ去った。得点王は3位になった新鋭・クロアチアのシュケル(6点)だった。
イランとのプレーオフを制しW杯初出場を果たした岡田ジャパンだが、1次リーグで3戦全敗と世界の洗礼を受けた。
 |
 |
 |
| チームワーク |
トロフィー |
国旗、サッカーボール、フィールド |
| 2001.5.31発行 |
2002.5.24発行 |
2002.5.2 ドイツ発行 |
左の切手の図案は大会公式マスコット「スフェリックス」。
開催資金を集めるために寄付金付きで発行された切手なのですが、図案が不気味とかでえらい不人気
だったという話を聞きました(ま、それも納得ですが;笑)。
しかし、そんなんで本来の目的は達成されたんでしょうか・・・?
トップにも書いたとおり、季節ネタでこのコーナーはつくったものの、ろくにルールも知らない身とあってはさほどの興味もなく、6月の梅雨の日本でワールドカップって、考えてみればすごい選択だなー、と土砂降りの中で行われる試合を横目で眺めていたくらいだったのですが。
ところがたまたま眼にしたドイツ・パラグアイ戦で、ドイツのGKオリバー・カーンの“ゲルマン魂”が似合いすぎるお顔がいたくツボにはまり、続くドイツ・アメリカ戦でGKゲルマン対決(アメリカのGKフリーデルも名字を裏切らぬゲルマン顔だった)を面白がってるうちに、結局準決勝の韓国戦、決勝のブラジル戦の途中までお付き合いしてしまったのでした(笑)。
世間では「ベッカム様」「イルハン王子」あたりが話題の中心だったみたいですが、なぜか私の周囲では全員揃って「カーン様」だったのがおかしかったですね〜(笑)。大分後になってからですが、プリンツェンの歌う応援歌「オリ・カーン」、なかなかかっこいい曲なのを知ってびっくり、
CD購入してしまいました。ビルトの「走れぐず共」のポスターも傑作だったな〜。
個人的には韓国・トルコの3位決定戦、「オレは替えてくれって言ってるんだ!」と思いながら必死に守っていたにちがいないトルコのGK・リュシュトゥさんもひそかにツボでした。両手クルクルやって「交代!」って合図してるのに、ベンチは無視した上にあっという間に選手交代枠を使い切るという・・・(笑)。
>>Stamp Album