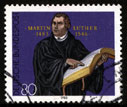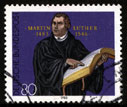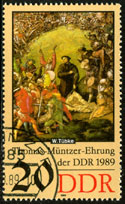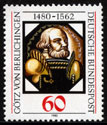Modern History
《宗教改革》
 |
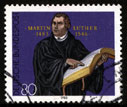 |
| 1983.11.11 アメリカ発行 |
1983.10.13 西ドイツ発行 |
マルティン・ルター Martin Luther 1483-1546
ドイツの宗教改革者でプロテスタンティズムの始祖。北ドイツ・アイスレーベンに鉱夫の子として生まれる。エルフルト大学で文学を学び、法学科に進んだが、劇的な出来事に遭遇し(道で落雷にあったという)、アウグスティヌス会修道院に入り、ウィッテンベルク大学神学教授となる。魂の救済を求めての苦闘の末、人間は善行によらず信仰のみによって救われるとの確信に到達する。1517年、贖宥状販売に抗議して『95か条の意見書』の論題を発表し、宗教改革の発端となった。1519年にはライプチヒ討論でローマ教皇・宗教会議の権威を否定。1520年精力的に著作活動を始め、『キリスト者の自由』『教会のバビロン捕囚』などの主要作品を世に送る。これにより1521年破門が宣告され、4月には
カール5世にヴォルムス国会へ召喚されたが、自説をまげず、帝国追放刑を宣告される。その帰途、ザクセン選帝侯フリードリヒにヴァルトブルク城に匿われて『新約聖書』のドイツ語訳を完成した。1524年にドイツ農民戦争が勃発すると、諸侯を支持して農民の農奴制廃止運動に反対し、領邦教会制確立に貢献することとなる。晩年は大学の講義、著作活動、教会の仕事に専念した。
【ヴォルムス国会450年】

カール5世の前のルター
1971.3.18 ドイツ連邦共和国発行
【アウグスブルクの信仰告白450年】

アウグスブルク帝国議会で皇帝カール5世に告白書を奉呈する新教徒
1530年、ルター問題に決着をつけるために
カール5世はアウグスブルクで帝国議会を開催。ルターは帝国保護外に置かれているため出席できないので、友人メランヒトンが新教徒の代表となり、意見書として「アウグスブルクの信仰告白」を提出した。
1980.5.8 ドイツ連邦共和国発行

メランヒトン Philipp Melanchthon 1497-1560
ドイツの神学者、宗教改革者、教育者。本名Schwarzerd(黒い土の意)からギリシア語化してメランヒトンと呼ばれた。母のおじで人文学者のロイヒリンの薫陶を受け、ギリシア古典に通じた。1518年ウィッテンベルクでギリシャ語教授となり、ルターとともに宗教改革に乗り出し、1521年には新教初の体系的神学書を出版してルターに次ぐ指導者となった。ローマ教会との論争を通じて『アウグスブルクの信仰告白』『弁証』などを執筆、ルター派の正統を代表するものと見なされた。その後、特に聖餐に関してルターとの考えの相違が明らかとなったが、両者は最後まで友情を保った。ルターの死後、アウグスブルクの暫定取り決め(1948)に対して、信仰による義認を否定しない限り非本質的なことは実践してよい、とローマ教会に妥協的であったので鋭く批判され、孤立した。またカルヴァンの立場とも妥協的であり、ルター派内の論争のもととなった。メランヒトンに従う人々はフィリップ派と称された。
1997.2.4 ドイツ連邦共和国発行

カルヴァン Jean Calvin 1509-1564
ジュネーヴの宗教改革者。フランスピカルディー地方ノワイヨンに司教書記の子として生まれる。最初聖職を志し、パリ大学で人文学とスコラ神学を学ぶが、父の勧めで進路を変更、オルレアンとブールジュで法学を学ぶ。宗教改革への支持を公にしたためにパリを逃れて国内を転々とし、ついでスイスのバーゼルに亡命。1536年バーゼルで『キリスト教綱要』を出版する。この年、ファレルの説得によりジュネーヴの改革運動に協力することになる。しかし教会のあり方をめぐって市当局と衝突し、1538年に同市を追われてシュトラスブールに移る。1541年に再び迎えられ、改革派教会の建設に献身した。神の救済の恩恵に浴することができるのは一部の人間のみで、しかもすでに神によって決定されているという「予定説」を唱えた。神を信じてキリストと一体となった信徒は自らが選ばれていることをもはや疑わないとして、すべての人が真の信仰と善き道徳を厳しく実践する義務を負う教会制度を整え、「神政政治」の実現を目指した。
1964.8.3 ドイツ連邦共和国発行
【カルヴァン派世界連合会議】

フッテン Ulrich von Hutten 1488-1523
ドイツの人文主義者、風刺詩人。帝国騎士の子としてシュテッケルベルクに生まれる。幼時虚弱な体質だったため、父親の配慮でフルダの修道院に入れられたが、17歳の時に脱走、以後各地を遍歴。1515年従兄弟がヴュルテンベルク公ウルリヒに殺されたのを機に、聖俗権威に抗する文筆と闘争の生涯に入った。エラスムスを通じ、ロイヒリン、ルターの支持者となる。1522年、ジッキンゲンとともに、領邦国家形成や軍事技術進展のなかで経済的に行き詰まっていた騎士たちを率いて騎士戦争を起こした。カトリック教会体制の動揺につけ込み聖界諸侯領を世俗化したうえで帝国改革を果たし、地位の回復を図ろうとしたものであったが、1年後に鎮圧された。彼はスイスに逃れ、ツヴィングリの保護を得たが、同年秋、チューリヒ湖上のウーフェナウ島で病没した。
1988.4.14 ドイツ連邦共和国発行
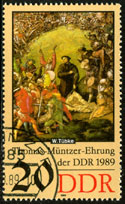
戦闘風景
トマス・ミュンツァー Thomas Müntzer 1490?-1525
ドイツの急進的宗教改革者。1519年のライプツィヒ討論会でルターと出会い、ルターの推挙でツヴィカウの説教師となり、改革者として活躍を始めた。しかし下層市民の立場に立った過激な発言がもとで同市を退去、プラハをへてザクセン領内の小都市アルシュテットの司祭となる。ルターの「信仰のみ」「聖書のみ」を否定し、直接神の声を聞き取ってのみ救われるとし、社会的に抑圧されたものが神に選ばれたものであると主張。同地を追われるとミュールハウゼンで宗教改革を指導、市参事会の反撃で追放されると西南ドイツ・スイスを旅行、1525年2月末ミュールハウゼンにもどり、下層市民を組織化した「神の永久同盟」により改革を推進。動きを恐れた諸侯に弾圧されたが、同盟の輪を拡大して戦いにそなえた。5月にはテューリンゲン農民軍が結集していたフランケンハウゼンにおもむき、諸侯軍と戦ったが、敗れて捕らえられて拷問され、カトリックに改宗させられたうえ、斬首された。その急進的態度は人々に入れられなかったが、神学説は大きな影響を及ぼした。
1989年 ドイツ民主共和国発行
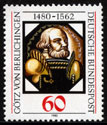
ベルリヒンゲン Götz von Berlichingen 1480-1562
宗教改革時代の没落騎士でドイツ農民戦争指導者の一人。ドイツ帝国騎士の身分に生まれ、戦闘で片腕を失い、鉄の義手をはめていたので「鉄腕ゲッツ」と呼ばれ、激動の時代を生きながら長寿を保った。略奪的な戦闘を各地で挑むとともにドイツ皇帝のためにフランスとも戦った。1525年ドイツ農民戦争にも加わり、オーデンワルトに農民勢を結集させた。1528年シュヴァーベン同盟に捕らえられ、1530年までアウグスブルクで獄中生活を送った。自叙伝を残しており、伝説的人物として、ドイツのロビン・フッドといわれ、
ゲーテも彼を題材とした戯曲を書いている。
1980.1.10 ドイツ連邦共和国発行
《目次》
■ その1「絶対王政から市民革命へ」 へ
■ その3「大航海時代」 へ