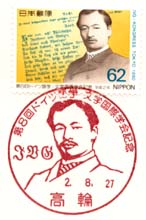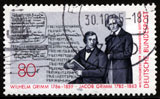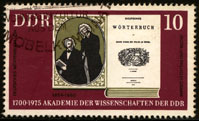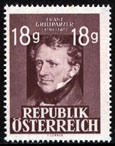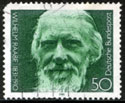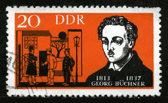|
Literatur |
 |

ザックス Hans Sachs 1494-1576
ドイツの職匠歌人、劇作家。ラテン語学校に学び、のち靴屋の親方となる。その間職匠歌の修行をつむ。宗教改革に関心を示し、詩『ヴィッテンベルクの鶯』(1523)で ルターを支持した。素材を聖書や物語集にとり、4000余の職匠歌をはじめ謝肉祭劇、笑劇などを残す。作品は『天国の遍歴学生』、『熱鉄』など。
1994.10.13 ドイツ連邦共和国発行

グリンメルスハウゼン Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen 1621?-1676
ドイツの作家。三十年戦争のさなか、12歳で戦乱のため両親を失い、1648年まで兵士となって各地を転々とする。1667年からレンヘンの村長を務めた。波乱に富んだ人生経験をもとに自伝的小説『ジンプリチスムスの冒険(阿呆物語)』を1669年に発表。これは悪者小説の形式を模した民衆小説であり、一人の貧しい百姓の子の成長を追求した点で教養小説の系譜の中にも数えられる。三十年戦争当時の世相が興味深くかつ批判的に描かれている。
1976.8.17 ドイツ連邦共和国発行

ゲーテ Johan Wolfgang von Goethe 1749-1832
ドイツの詩人。フランクフルト・アム・マインの名家に生まれる。シュトラスブルク大学で「シュトルム・ウント・ドランク」の理論的指導者であったヘルダーと出会い、文学に目ざめる。小説『若きウェルテルの悩み』で一挙に文名を高めた。
1775年以後はワイマール公国政府の要職を歴任しつつ、イタリア旅行やシラーとの交友をかてとしてドイツ古典文学を確立した。作品には『ヴィルヘルム・マイスター』『ファウスト』などがある。
1973.6.26 ドイツ民主共和国発行
【第8回ドイツ語学・文学国際学会】
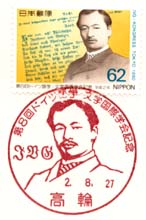
森鴎外とゲーテ作『ファウスト』の一節
1990. 8.27発行
【ファウスト】 ゲーテの戯曲。26歳の時ファウスト伝説(15.6世紀頃実在した錬金術師に由来するといわれる、ドイツに広く伝えられた魔術師伝説)に触発されて『初稿ファウスト』(1775)が書かれ、以後第1部(1808)、第2部(32)と前後60年間にわたって書き進められた。
主人公ファウストは絶対を追究する学者で、第1部では悪魔メフィストフェレスとの契約、グレートヒェンとの恋とその死など、善と悪をめぐる彼の人間的な葛藤が描かれ、第2部ではより象徴的な、世界観の獲得がテーマとなっている。従来のファウスト作品とは異なり、主人公の救済に結末に終わる。
珍しく初日印つきなのは、おみやげでもらった品のため(笑)。
以下が切手にデザインされた部分の、鴎外の訳です。(切手についていた説明書きより)
「夜」
狭き、ゴチック式の、高き圓天井の下に、ファウストは不安なる態度にて、
卓を前にし、椅子に座してゐる。
ファウスト
はてさて、己は哲學も
法學も醫學も
あらずもがなの神學も
熱心に勉強して、底の底まで研究した。
さうしてこヽにかうしてゐる。氣の毒な、馬鹿な己だな。
その癖なんにもしなかった昔より、ちっともえらくはなってゐない。
マギステルでござるの、ドクトルでござるのと學位倒れで、
もう彼此十年が間、
弔り上げたり、引き卸したり、竪横十文字に、
學生どもの鼻柱を撮まんで引き廻してゐる。
そして己達に何も知れるものでないと、己は見てゐるのだ。
それを思へば、殆ど此胸が焦げさうだ。

ファウスト博士とメフィストフェレス
1979.11.14 ドイツ連邦共和国発行

ミュンヒハウゼン
Kerl Friedrich Hieronymus von Münchhousen(1720-1797) ドイツの軍人。若い頃からロシア軍とともにトルコ軍と戦ったりして見聞を広めたが、1760年領地に戻り、ハノーファーなどの社交場で途方もない身の上話の語り手として有名になった。彼をモデルにした一人称の主人公による冒険奇譚が『法螺吹き男爵の冒険』。民間に流布していた断片的逸話類を収集しミュンヒハウゼンの名と結びつけたものが最初英語で出版されたが、ドイツの詩人G.A.ビュルガー(1747-1794)がさらに話を加えて1786年に刊行、古典的名作となった。
1977.1.13 ドイツ連邦共和国発行
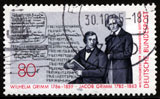 |
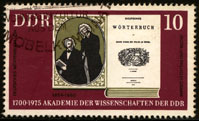 |
| 1985.1.10 ドイツ連邦共和国発行 |
1975.7.2 ドイツ民主共和国発行 |
グリム兄弟 Jacob Grimm 1785-1863 Wilhelm Grimm 1786-1859
ともにドイツの言語学者。ヘッセンのハーナウに生まれ、ともにカッセルの図書館司書、ゲッティンゲン大学教授を務めた。ハイデルベルクのロマン派と密接な関係を持ち、アルニムやブレンターノの収集した民謡集に刺激を受け、ドイツ各地で民衆の口からメルヘンを収集。『グリム童話』(1812-15)、『ドイツ伝説集』(16-18)を兄弟で出版した。1838年には『ドイツ語辞典』(1961年に完成。全16巻)の作業に着手。また兄のヤーコプは言語学の分野で才能を示し、ヨーロッパ諸語間における音韻法則、いわゆる「グリムの法則」を発見した。

ハイネ Heinrich Heine 1797-1856
ドイツの詩人。貧しいユダヤ商人の子として生まれ、ハンブルクの叔父のもとで銀行業務の見習いをしたのち、ボン、ゲッティンゲン、ベルリンの各大学で法律、文学、哲学をまなびながら本格的文学活動に入った。叔父の娘たちへの悲恋などをうたった詩集『歌の本』(1827)、風刺的な紀行文集『旅の絵』(1826-31)などを発表、文名を高めた。1831年パリに移住、新聞、雑誌への寄稿などによりドイツ、フランス相互の文化交流に努めたが、1835年にドイツ連邦議会により著作発表を全面禁止された。以後も『アッタ・トロル』(1743執筆)、『ドイツ・冬物語』(1744)など反動ドイツを批判諷刺する詩作品を発表、1848年以後脊椎病で寝たまま創作を続けた。
1997.11.6 ドイツ発行
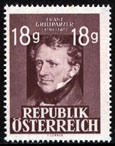
グリルパルツァー Franz Grillparzer 1791-1872
オーストリアの劇作家。19歳のとき弁護士の父を失い苦学し、長らく官吏を務めた。ゲーテやシラーの古典主義を理想とし、バロック劇の伝統、ウィーンの民衆劇、当時のロマン主義の影響も受けている。『祖先の女』(1817)、『サッフォー』(1818)が出世作。代表作は古代ギリシアに取材した三部作『金羊皮』(1821)で、卓越した心理分析によって複雑な人間の葛藤をみごとに描写。そのほか『海の波、恋の波』(1831)や歴史劇『オトカル王の幸福と最期』、短編小説『ウィーンの辻音楽師』(1847)などがある。
1947年 オーストリア発行
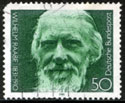
ラーベ Wilhelm Raabe 1831-1910
ドイツの小説家。ベルリン大学在学中に書いた処女長編『雀横町年代記』(1857)で成功を収め、以後作家としてたつ。長編『森から来た人々』(63)のなかの言葉「星を仰げ! 横町に目を注げ!」が象徴するように現実に根ざした理想主義を志向。作風は写実的で、辛辣なアイロニーと暖かいユーモアにあふれる。
1981.8.13 ドイツ連邦共和国発行
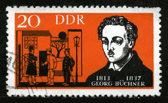
ビューヒナー Georg Büchner 1813-1937
ドイツの劇作家、医者。貧しい医師の長男として生まれる。ストラスブール大学で医学、自然科学を
学び、ギーセン大学で歴史、哲学を修める。七月革命の影響を受けて革命思想に目覚め、ヘッセン大公の悪政を暴いたパンフレット『ヘッセンの急使』(1834)で官憲に追われた。のちチューリヒ大学で学位を取得、専任講師となったがチフスのため23歳で夭折。作品にはフランス革命を素材にした4幕の戯曲『ダントンの死』、心理小説『レンツ』、喜劇『レオンスとレーナ』、未完の戯曲『ヴォイツェク』(のちにベルクによってオペラ化)がある。
1963.4.9 ドイツ民主共和国発行
【リルケ生誕125年】

イメージした本の表紙
リルケ Rainer Maria Rilke 1875-1926
ドイツの詩人。プラハに生まれる。
新ロマン派風の詩で出発したが、ロシア旅行を契機に『時祷詩集』『形象詩集』で独自の詩境を開拓。1902年からパリでロダンに師事。言葉による彫刻ともいうべき事物詩に挑み、『新詩集』にその成果を示すとともに、この都会の生活の直視を通じて人間実存の不安に迫り小説『マルテの手記』を生んだ。以後アフリカ・スペイン、イタリア、フランスなどを遍歴したのち、21年からスイスのミュゾットの館に定住。10年がかりの大作『ドゥイノの悲歌』は20世紀詩の頂点といわれる。
2000. 9. 9 ドイツ発行

トーマス・マン Thomas Mann 1875-1955
ドイツの小説家、評論家。リューベックの穀物商の家に生まれる。『ブッデンブローク家の人々』で
文名を確立する。ナチスに対しては評論や講演で抵抗を示し、1933年亡命。スイスからアメリカに移住し、戦後スイスに定住。作品には『トニオ・クレーゲル』『ベニスに死す』などがあり、ほかに多くの文学、哲学、政治評論がある。1929年ノーベル文学賞受賞。
1975.3.18 ドイツ民主共和国発行

ブレヒト Bertolt brecht 1898-1956
ドイツの劇作家、詩人。富裕な製紙工場主の家に生まれたが、第1次大戦末期に召集され、反戦思想に目ざめた。ミュンヘン大学では医学を専攻したが、学業を放棄して演劇活動に入り、『夜打つ太鼓』(1922)、『バール』(1923)の成功によって演出家ラインハルトの「ドイツ座」に招かれる。作曲家 ヴァイルの音楽による『三文オペラ』は世界各国で上演された。1930年共産党に入党、社会を変革する目的の教訓劇を試みている。1933年以降15年にわたって各地を亡命。かたわら『肝っ玉おっ母とその子どもたち』(1939)、『ガリレオ・ガリレイの生涯』(1943)、『ブンティラ旦那と下男マッティ』(1948)などを書いた。1947年東ベルリンに帰国。亡命期の経験を通じて、叙事演劇、異化効果などの理論を提唱。20世紀演劇に新時代を画した。また、古い詩型や庶民の歌謡に新生命を吹き込むなど、詩の分野での成果も大きい。
1998.12.5 ドイツ発行

『エーミールと探偵たち』の表紙
ケストナー Erich Kästner 1899-1974
ドイツの詩人、小説家。職人の家に生まれ、第1次世界大戦に参加。セント、ライプツィヒ、ロストク、ベルリンの大学で文学、歴史、哲学を学びつつ詩作や評論に活躍、『新ライプツィヒ新聞』編集に参加。1927年、ユーモアと皮肉をもって現代を諷刺した抒情詩集『腰の上の心臓』で認められた。少年小説の分野でも第一人者で『エーミールと探偵たち』(1929)、『点子ちゃんとアントン』(1931)、『飛ぶ教室』(1933)などがある。ワイマール時代の大都会の生活の病弊をえぐった小説『ファービアン』(1931)と詩集がナチスの弾圧で焼かれ、国内での出版活動も禁止されたが、第2次世界大戦後、再び諷刺詩や少年小説に活躍。西ドイツペンクラブ会長を長期間務めた。
1999.2.18 ドイツ発行
《戻る》
◆ 中世編 へ
◆ 近世以降 へ
◆ 英国編 へ
|