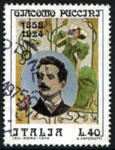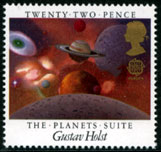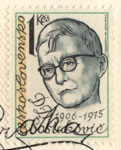Composer

1941.8.25 ボヘミア・モラヴィア地域発行
ドヴォルジャーク Antonin Dvorak 1841-1904
チェコの作曲家。宿屋兼肉屋の長男として生まれ、父の反対を押し切ってプラハに出、オルガン学校を苦学して卒業。1862年にプラハ国民劇場の仮劇場のヴィオラ奏者となり、1866年に指揮者に就任したスメタナの薫陶を受ける。1878年ブラームスの紹介で管弦楽曲《スラブ舞曲》第1集をベルリンで出版、一躍名声を高めた。1891年プラハ音楽院教授となり、のちの院長時代をふくめ、スーク、ノヴァークら多くの音楽家を育成した。1892年ニューヨーク国民音楽院の院長に招かれて滞米、その間に《交響曲第9番(新世界から)》《弦楽四重奏曲第12番(アメリカ)》などの名作を発表。帰国後オーストリアの終身上院議員になり、死に際しては国葬が行われた。スメタナを継ぐチェコ国民楽派の作曲家で、その音楽にはドイツ・ロマン派の諸様式とチェコの民俗音楽の語法の高度な融合がみられる。ほかに《弦楽セレナード》、オラトリオ《スターバト・マーテル》、《ピアノ三重奏曲・ドゥムキー》、オペラ《ルサルカ》などがある。
Music: 交響曲第9番「新世界より」より第4楽章 「ユーモレスク」

1983.5.3 ノルウェー発行
グリーグ Edvard Grieg 1843-1907
ノルウェーの作曲家。ライプチヒ音楽院に学び、1862年郷里でピアニスト、作曲家としてデビュー。1864年作曲家ノールロークと知り合い、自国の音楽的伝統に根ざした国民主義的音楽への志向を固めた。1966年現在のオスロに居を定め、以後指揮者としても各地で活躍。ノルウェー国民音楽の確立に主導的な役割を果たした。代表作に劇音楽《ペール・ギュント》などがある。
Music: 「ピアノ協奏曲イ短調 第一楽章」
図案背景の楽譜がこの曲です。

肖像とメフィストフェレ
1968.6.10 イタリア発行
ボーイト Arrigo Boito 1842-1918
イタリアの作曲家・台本作者。パドヴァに生まれ、ミラノ音楽院に学ぶ。パリに留学中、ヴィクトル・ユーゴー、ベルリオーズ、ロッシーニそしてヴェルディの知遇を得る。1868年に最初のオペラ《メフィストフェーレ》を完成。スカラ座での初演は大失敗に終わったが、1876年と1881年の大改訂によって、今日ではしばしば公演され、また録音もされるオペラとなっている。これ以降、他のオペラ作曲家のための台本執筆を行うようになり、ポンキエッリの《ラ・ジョコンダ》などを経て、1881年からは、ヴェルディとの一連の共同作業に入り、《シモン・ボッカネグラ》の改訂版の台本を完成させたほか、《オテロ》や《ファルスタッフ》の台本を執筆した。
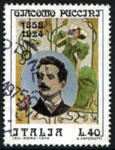
1974.8.16 イタリア発行
プッチーニ Giacomo Puccini 1858-1924
イタリアの作曲家。ルッカで5代続いた音楽家の家系に生まれる。ミラノ音楽院でポンキエリに師事し、学友マスカーニと親交を結んだ。1884年には最初のオペラを発表。第3作《マノン・レスコー》で成功をおさめ、続いて3大傑作として知られる《ラ・ボエーム》《トスカ》《蝶々夫人》を発表、ヴェルディを継ぐオペラ作曲家としての地位を確立した。その後はいずれもニューヨークのメトロポリタン歌劇場で初演された《西部の娘》《修道女アンジェリカ》、唯一の喜歌劇《ジャンニ・スキッキ》などを書き、《トゥーランドット》を未完のまま旅先のブリュッセルで客死した(弟子のアルファーノが補作完成、トスカニーニの指揮でミラノ・スカラ座初演)。ヴェリズモの影響から出発したその作品は、すぐれた台本作家の協力を得て劇的な緊張に満ち、豊かな旋律美と卓越した管弦楽法とが相まって近代オペラの最高峰の一つとなった。
Music: 歌劇「トゥーランドット」より「誰も寝てはならぬ」

1975.11.14 イタリア発行
ブゾーニ Ferruccio Busoni 1866-1924
イタリアの作曲家、ピアノ奏者。フィレンツェに近いエンポリで生まれ、オーストリアのグラーツで少年期を送る。早くから神童として鳴らし、欧米各地でビルトゥオーソとして名声を高める。ヘルシンキ、モスクワ、ボストンで教職に就いたのち、1894年以降はベルリンを拠点にした。以後、演奏と教職のかたわら本格的な作曲活動に入り、《ピアノ協奏曲》などを発表。1907年には主著《音芸術の新美学》を刊行、長短調に代わる新たな音階を提唱し、楽曲形式の変革や多調、微分音を論じた。バッハの作品のピアノ編曲を多く残したほか、ピアノ曲《対位法的幻想曲》、《ソナチネ》6曲、管弦楽曲《悲しき子守歌》、オペラ《嫁選び》《アルレッキーノ》《ファウスト博士》(未完。親友ヤルナッハにより補筆完成され初演)などがある。

1967.8.28 イタリア発行
ジョルダーノ Umberto Giordano 1867-1948
イタリアの作曲家。マスカーニ,レオンカヴァッロとともにヴェリズモ・オペラを代表する。イタリア南部のフォッジアに生まれナポリ音楽院に学ぶ。在学中からオペラに手を染め、《悪の世界》(初演1892年)で注目される。代表作の《アンドレア・シェニエ》は、フランスの詩人シェニエの半生を劇的に描いたもの。《フェドーラ》はテノール歌手
カルーソーの出世作としても知られる。
Music: 歌劇「フェドーラ」より「愛さずにいられぬこの想い」
図案背景の楽譜は《アンドレア・シェニエ》のものだそうですが、Midiを発見できなかったので、カルーゾーの出世作となったロリスのアリアを。

1999.6.16 ドイツ発行
リヒャルト・シュトラウス Richart Strauss 1864-1949
ドイツ後期ロマン派の掉尾を飾る作曲家。ホルン奏者を父にミュンヘンに生まれる。少年時代からピアノ、バイオリン、作曲を学び、10代で早くも成熟した作曲技法を示した。作曲活動の一方でミュンヘン、ワイマール、ベルリンの宮廷楽長を歴任し、1919〜1924年にはウィーン国立歌劇場指揮者を務めた。《ドン・フアン》《ツァラトゥストラはこう語った》《英雄の生涯》などの交響詩で駆使された精緻な作曲技巧は、大管弦楽を用いたオペラ《サロメ》に引き継がれ、《エレクトラ》
《ばらの騎士》などを次々に発表、オペラ作曲家としての地位を不動のものとした。また《家庭交響曲》《アルプス交響曲》で管弦楽曲に新境地を開き、最晩年の《4つの最後の歌》をはじめ、歌曲にも名品を多く残した。
Music: 「7つのヴェールの踊り」
切手の図案は「サロメ」初演時(1905年12月9日 ドレスデン宮廷歌劇場)のポスターだそうです。
ご存じワイルドの原作。曲は図案にもなっている有名な第4場より、何でも望むものを与える、と継父のエロド王に言われてサロメが踊る場面の曲です。
キャサリン・マルフィターノが演じたものを見たことがあるんですが、あれほどエキセントリックな役に観客を引き込んでしまう演技力が、すごいの一言でした。

1985.5.14 イギリス発行
エルガー Sir Edward Wiliam Elgar 1857-1934
イギリスの作曲家。楽器商兼オルガン奏者の父に手ほどきを受け、ほとんど独学でピアノや弦楽器、楽理を習得。父の後を継いで生地の教会のオルガン奏者を務めたのち本格的な作曲活動に入る。1899年に《エニグマ(謎)変奏曲》で作曲家として認められ、1900年に合唱曲《ジェロンティアスの夢》によりヨーロッパ中に名声が広まった。「イギリス音楽のルネサンス」と呼ばれる時期の代表的作曲家の一人。作品はロマン派の様式を受け継ぎ、2つの交響曲、《チェロ交響曲》などの代表作のほか、交響曲《威風堂々》や管弦楽曲《愛の挨拶》が広く親しまれている。《威風堂々》第1番の中間部の旋律はイギリス国王エドワード7世に気に入られ、今日でも「希望と栄光の国」として愛唱され、イギリスの第2の国歌となっている。
Music: 「海の絵」より第2曲「港にて」

1985.5.14 イギリス発行
ディーリアス Frederick Delius 1862-1934
イギリスの作曲家。両親はドイツ人であり、父親のユリウスはヨークシャーの羊毛産業で成功した実業家であった。学業を終えたのち、父親の仕事の見習いをするが肌に合わず、渡米。 トーマス・ウォードに音楽理論を学び、1886〜87年に《フロリダ組曲》を書き下ろし、その後音楽教師ともなる。帰国後、1886〜88年にかけてライプチヒ音楽学校で正式に音楽を学ぶ。1907年に歌劇「村のロメオとジュリエット」が初演され、同年、以後生涯に渡って彼のよき理解者となる指揮者トマス・ビーチャムと会う。1888年にフランスに定住。1921年に全身麻痺に見舞われ、翌年には失明。エリック・フェンビィの筆記により、苦労の末《夏の歌》などを作曲した。絵画的で叙情性に富んだ美しい作品の数々は世界的に愛好されている。
Music: 「春初めてのカッコウを聞いて」
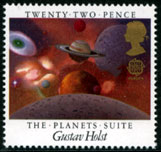
1985.5.14 イギリス発行
ホルスト Gustav Holst 1874-1934
イギリスの作曲家。スウェーデン系移民の家系に生まれ、ロンドンの王立音楽院で音楽を学んだ。王立音楽院ではトロンボーンも学び、卒業後はオーケストラで生計を立てていたこともある。この学生時代にヴォーン・ウィリアムズと知り合い、親交を深めた。1906年からセント・ポール女学校の音楽教師の職にあり、その傍ら作曲活動を行った。最も知られた作品は、管弦楽のために書かれた《惑星》であるが、全般的に合唱のための曲を多く遺している。またイギリス各地の民謡や東洋的な題材を用いた作品でも知られる。
Music: 組曲「惑星」より「木星」

1983.6.9 アメリカ発行
ジョプリン Scott Joplin 1868-1917
米国の作曲家、ピアノ奏者。数多くのラグタイムを作曲したことで知られる。1899年の作品《メープル・リーフ・ラグ》が爆発的なヒットとなり、〈ラグタイム王〉と呼ばれるようになった。1973年のジョージ・ロイ・ヒル監督の映画《スティング》で《エンターテイナー》が主題曲として使われた。
Music: 「エンターテイナー」

1973.2.28 アメリカ発行
ガーシュウィン George Gershwin 1898-1937
アメリカの作曲家、ピアニスト。ロシア系移民の子としてニューヨークに生まれ、10代になって初めてピアノにふれる。商業高校を中退後、音楽出版社のピアノ奏者兼宣伝係となり、仕事の合間に作曲にも手を染めた。1924年ジャズ・バンドのために書かれた《ラプソディー・イン・ブルー》が大反響を呼び、翌1925年には《ピアノ協奏曲ヘ長調》を完成、クラシック音楽界でもその名を高めた。1935年には黒人庶民を主人公にした画期的なオペラ《ポーギーとベス》を発表。その2年後に脳腫瘍のために死去した。
Music: 「サマータイム」
切手の図案になっている「ポーギーとベス」より。スタンダードソングとしてよく知られた曲のようですね。
スコットカタログには“スポーティン・ライフ”(登場人物の名前)とありましたが、具体的にどの場面なのかはちょっと分からないです・・・。

2000.2.17 ドイツ発行
ヴァイル Kurt Julian Weill 1900-1950
ドイツ生まれのユダヤ系作曲家。ベルリンでフンパーティンクに学び、各地の劇場で働いたのち、1921年に《交響曲第1番》を発表。1926年のオペラ《主役》ではジャズの語法を取り入れ、後期ロマン派の美学と訣別。1927年、劇作家
ベルトルト・ブレヒトとの共同作業を開始、《三文オペラ》(1928年)などを発表。辛辣な社会風刺と既存のオペラ批判を展開した。ナチス政権の成立とともに1933年パリに亡命。1935年にはロンドンを経てニューヨークに渡り、1943年米国籍を取得。渡米後はブロードウェーの人気作曲家となり、約10曲のミュージカル、映画音楽を残した。
図案はピアノ演奏をするヴァイルと《三文オペラ》の主役を歌ったメアリー・マーチン。
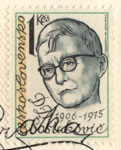
1981.3.10 チェコスロヴァキア発行
ショスタコービッチ Dmitrii Dmitrievich Shostakovich 1906-1975
ロシアの作曲家。卒業作品《交響曲第1番》で世界的な注目を集め、続いてゴーゴリ原作のオペラ《鼻》などで早くもその才能を縦横に発揮。1934年オペラ第2作《ムツェンスク郡のマクベス夫人》の初演が大成功をおさめ、作曲家としての地位を確立。欧米各地でも上演され名声を高めるが、1936年《プラウダ》紙の批判を浴び、上演禁止処分を受ける。以後ソビエト当局による公式批判は生涯に10数回に及び、その応酬の中で創作活動は複雑な軌跡を描いた。1960年代半ばからは心臓疾患に苦しむが、音楽はさらに深みを増し、《交響曲第14番・死者の歌》などを頂点とする傑作群が書き継がれた。
なにゆえチェコスロヴァキアがショスタコービッチの切手なんか発行するのか、ちょっと謎です。モーツァルトはほとんどご当地作曲家扱いですから(「プラハ」って交響曲もありますしね)、何となく分かるんですけど。
Music: 「祝典序曲」
略伝は平凡社マイペディア、世界大百科事典より。(ディーリアスとボーイトのみウィキペディアを参照)
《戻る》 ■ バロック・古典派 へ ■ 19世紀ロマン派 へ