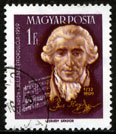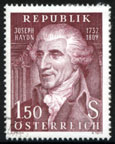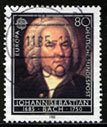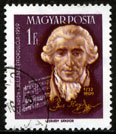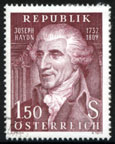Composer
《バロック》

肖像と「オルフェオ」の登場人物
1967.5.15 イタリア発行
モンテヴェルディ Claudio Monteverdi 1567-1643
イタリアの作曲家。ルネサンスからバロックへの音楽様式の転換をなしとげ、初期バロック・オペラを確立した。1582年には早くも15歳で《3声モテット集》を出版。1590年からマントヴァ公にヴィオラ奏者として仕え、1601年に楽長となる。マントヴァでは《マドリガーレ集》、教会音楽《聖母マリアの夕べの祈り》などを出版する一方、1607年にはオペラ《オルフェオ》を完成。言葉と音楽とが高度に融合した劇的表現でその後のオペラの真の出発点となった。1613年からヴェネツィアのサン・マルコ大聖堂の楽長となり、楽団の指導に力を尽くすとともに教会音楽を書き、また各地の宮廷のために多くのオペラやバレエ曲を作曲。1637年からヴェネツィア初の市民のための公開オペラ劇場が相次いで誕生、これらの劇場のために書かれた4つのオペラのうちの2つ、ともに70代半ばの作ながら創意みなぎる《ウリッセの帰郷》と《ポッペアの戴冠》が今日に残されている。
Music: 「オルフェオ」よりリトルネッロ

サインとパイプオルガン
1987.5.5 ドイツ連邦共和国発行
ブクステフーデ Dietrich Buxtehude 1637?-1707
デンマーク出身のオルガン奏者、作曲家。1668年リューベックの聖マリア教会のオルガン奏者に就任。終生この地位にあってドイツ各地に名声を広めた。北ドイツ・オルガン楽派最大の巨匠とされ、そのオルガン音楽はJ.S.バッハにも大きな影響を与えた。
Music: 「Herzlich tut mich Verlangen」

1975年 イタリア発行
ヴィヴァルディ Antonio Lucio Vivaldi 1678-1741
イタリアの後期バロックを代表する作曲家。生地ヴェネツィアで司祭となり、1703年同地の女子音楽学校〈ピエタ慈善院〉の音楽教師に就任。以後1740年まで主にこの職にあってバイオリンや作曲、合奏の指導に当たる一方、カンタータ、コンチェルト、ミサ曲などを多く書いた。その間ヴェネツィア、フィレンツェなどでオペラを上演、1738年にはアムステルダムの王立劇場100年祭のために大規模な音楽を手がけるなど、その名声は広くヨーロッパ各地に届いた。1740年にはピエタの職を辞してヴェネツィアを後にし、ウィーンで没した。オペラ、宗教音楽、世俗カンタータ、ソナタなど多くの作品があるが、中心となるのは500曲以上のコンチェルトで、ソロ・コンチェルト形式の完成者として知られる。バイオリン協奏曲集《和声と創意の試み》の最初の4曲は、《四季》として有名。
Music: 「四季」より「春」
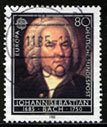
1985.8.7 ドイツ連邦共和国発行
バッハ Johann Sebastian Bach 1685-1750
アイゼナハに生まれる。16世紀以来多くの音楽家を輩出した一族の出身。1708年ワイマール宮廷楽師兼オルガン奏者となり、各地を旅し、多くのオルガン曲やカンタータを書く。1717年からのケーテン宮廷楽長時代には器楽曲の傑作を数多く生みだした。対位法をきわめ、フランス、イタリアの様式も包括しながら完成された音楽を作った。バロック最大の音楽家といわれる。
Music: 「G線上のアリア」
「主よ人の望みの喜びを」

1985.8.7 ドイツ連邦共和国発行
ヘンデル Georg Friedrich Händel 1685-1759
中部ドイツのハレに生まれ、ハレ大聖堂で見習オルガン奏者を務めたのち1703年にハンブルクに赴き、オペラ劇場のバイオリン奏者などを務める一方オペラ作曲家としてもデビュー。1710年ハノーファーの宮廷楽長となるが同年ロンドンにわたり、イタリア語によるオペラ《リナルド》で成功、英国での地歩を固めた。1742年初演のオラトリオ《メサイア》が成功後は英語によるオラトリオを多数発表した。

「水上の音楽」
1985.5.14 イギリス発行
Music: 「水上の音楽」よりアリア
【ヨーロッパ切手(音楽年)】

1981.5.5 ドイツ民主共和国発行
テレマン Georg Philipp Telemann 1681-1767
バッハの同時代人で、生前は彼をはるかにしのぐ名声を保った。生地マグデブルクなどで初期の教育を受け、ライプチヒ大学在学中の1704年、新教会のオルガン奏者兼音楽監督に就任。その後はアイゼナハ、フランクフルトなどの宮廷楽長を歴任し、1721年からはハンブルクに定住。ヨーロッパ全土に知られる作曲家として多方面に活躍し、オペラ40曲以上、室内楽曲350曲以上など、各分野に膨大な数の作品を残している。19世紀以降急速に忘れ去られたが、20世紀に入って再評価が進んでいる。
Music: 「組曲 イ長調」よりアルマンド

1987.11.13 オーストリア発行
グルック Christoph Willibald Gluck 1714-1787
ドイツに生まれ、ボヘミアで育つ。1741年オペラ第1作を発表し、1745年にロンドンに渡ってヘンデルと親交を結ぶ。その後イタリア・オペラの一座の指揮者としてヨーロッパ各地を巡演し、1752年以後ウィーンを活動の拠点に定めた。1762年に《オルフェオとエウリディーチェ》を発表。過剰な音楽的装飾と歌手の技巧誇示を排し、ドラマ性に重きをおいたオペラの創造を提唱して後世に多大の影響を与えた。
Music: 「オルフェオとエウリディーチェ」より「エウリディーチェを失って」
《古典派》
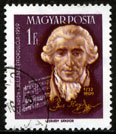 |
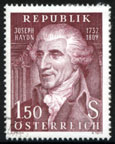 |
| 1959.9.20 ハンガリー発行 |
1959.5.30 オーストリア発行 |
ハイドン Franz Joseph Haydn 1732-1809
〈古典派〉様式の確立に大きく貢献したオーストリアの作曲家。7歳でシュテファン聖堂児童合唱団員となったが、声変りのため16歳でやめ、その後約10年は安定した職を得られず放浪生活を送ったといわれる。1761年アイゼンシュタットに住むハンガリーの侯爵エステルハージに副楽長として仕え、1766年前任者の死により楽長に昇格、以後約30年間この地位にあって多くの作品を書いた。その業績はベートーヴェンに継承され、またモーツァルトとも交流があった。
Music: 「弦楽四重奏曲《皇帝》 第2楽章」

1981.3.10 チェコスロヴァキア発行
モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
オーストリアの作曲家。幼時から天才ぶりを示し、父レオポルトに連れられてパリ、ロンドンなどを訪問、クラヴィーア演奏のかたわら音楽的見聞を広めた。1769年からザルツブルク大司教に仕えるが、同年から1773年にかけてイタリアに3度旅行する。1781年にウィーンに出てフリーの音楽家となり、作曲家ウェーバーのいとこコンスタンツェと結婚、フリーメーソンに加入する。創作活動は生涯最高の高まりをみせ、オペラ《フィガロの結婚》
《ドン・ジョヴァンニ》《コシ・ファン・トゥッテ》
《魔笛》、《交響曲第40番》、《ディベルティメント変ホ長調》などの代表作が次々と誕生するが、生活はしだいに窮乏し、《レクイエム》を未完のまま35歳で死去。ハイドンと並んで古典主義の確立者といわれる。
Music:
「交響曲第40番 第1楽章 ト短調」

1970.1.20 ドイツ民主共和国発行
ベートーベン Ludwig van Beethoven 1770-1827
ドイツの作曲家。ボンの宮廷楽団歌手の子に生まれ、父からピアノを学ぶ。宮廷楽団でビオラ奏者として活動したのち、1792年にウィーンへ出て、モーツァルトに会い、ハイドンなどの指導を受ける。1798年頃から難聴に苦しむが、この苦境を克服して《交響曲第3番・英雄》を完成、音楽的にも密度の高い独自の作風を確立。続く約10年間に唯一のオペラ
《フィデリオ》、《交響曲第5番・運命》、《ピアノ・ソナタ第21番ワルトシュタイン》その他の傑作を書き、ソナタ形式を完成。1815年以後は高度な対位法、変奏曲の手法を中心とした瞑想的作品を書くようになり,ピアノ曲《荘厳ミサ曲》《第九交響曲》などが生まれた。古典派音楽を完成し、ロマン派音楽への橋渡しの役割を果たした。
原語発音とずれたカタカナ表記の名前が定着しちゃってる場合、悩むことがしばしば。ウェーバーをヴェーバー、ワーグナーをヴァーグナーなら、まあ分かるだろうと思います。ドボルザークをドヴォジャークとは書きませんけど、このくらいならまだ分かるかもしれない。どうしようもないのがこの人、ベートーベン。オランダ系なんで、“ファン・ベートホーフェン”と読むのが正しいんですけど(旅行中にTVつけてたら、子ども向け番組で確かにこう言ってました)、さすがにこう書いたんじゃ誰だか分かってもらえないですよね・・・
Music: 「月光ソナタ 第1楽章」
略伝は平凡社マイペディア98、世界大百科事典、ウィキペディアより
《戻る》 ■ 19世紀ロマン派 へ ■ 20世紀 へ