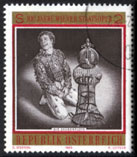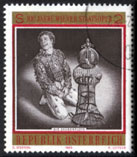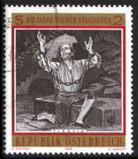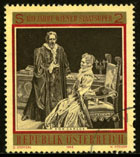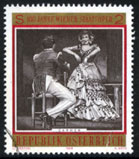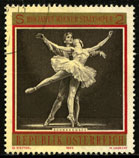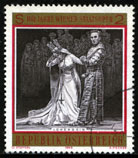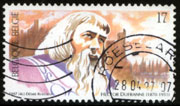Stage

1969.5.23 オーストリア発行
「ドン・ジョヴァンニ」 Don Giovanni モーツァルト作曲
騎士長の娘ドンナ・アンナのところに忍び込んだドン・ジョヴァンニは、かけつけた騎士長を決闘の末殺してしまう。新たに発見したターゲットは、実は以前に捨てたドンナ・エルヴィーラ。後を押しつけられた従者のレポレッロは、主人の女性遍歴を皮肉交じりに紹介する。続いて婚礼の祝いの真っ最中の村娘ツェルリーナに目をつけたドン・ジョヴァンニ、宴会のさなかに言葉巧みに連れ出すが、ツェルリーナが騒ぎ出した。レポレッロを犯人にでっちあげるも、仮面をつけて招待されていたドンナ・エルヴィーラや、父を殺した犯人を捜すドンナ・アンナたちに追いつめられてしまう。
次のターゲットを求めるドン・ジョヴァンニは、レポレッロと服を交換。エルヴィーラとともにいるところを見つかったレポレッロは、自分の正体を明かして這々の体で逃げ出す。墓場で落ち合った二人が話していると、突然石像が「その笑いも今夜限りだ」と話しかけてきた。その石像はドン・ジョヴァンニが殺した騎士長のものであったが、ドン・ジョヴァンニは晩餐に招待する。本当に晩餐にやってきた石像は、過去を悔い、生活を改めるように言うが、ドン・ジョヴァンニは拒絶。すると轟音が響き渡り、ドン・ジョヴァンニは石像に導かれて地獄へ落ちていく。
以下のこのシリーズはすべてウィーン国立歌劇場100年の記念切手。場面が“第一幕「酒の歌」”となっていてはいささか信憑性に疑問ありですが(普通に考えたらこれ第2幕の晩餐の場面でしょ?)、さる本によると図案のドン・ジョヴァンニはエーベルハルト・ヴェヒターだそうです。この役での映像は残ってないんでしょうが、オペレッタの映像で見たことがあります。
「ルクセンブルク伯爵」の題名役が格好良かった〜♪
あまり興味の持てないお話でしたが、初演の地・プラハの等族劇場で見た実演が結構面白く、同じ劇場での公演の映像がお気に入りになり、アムステルダムの映像に至って題名役に一目惚れ。ドン・ジョヴァンニのキャラ次第、ということのようです(笑)。なので、この
手持ちの映像2つに限っては大好きなのですが、他のも積極的に見てみたいとはあまり思えなかったり・・・。
Music: “カタログの歌” “メヌエット”
 |
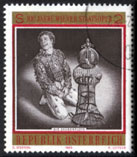 |
| 1967.9.26 ハンガリー発行 |
1969.5.23 オーストリア発行 |
「魔笛」 Die Zauberflöte モーツァルト作曲
大蛇に襲われて失神した王子タミーノは、夜の女王の3人の侍女に救われる。入れ違いにやってきた鳥さしパパゲーノは自分が王子を助けた、とウソをつくが、すぐにばれてしまう。夜の女王はザラストロに捕らわれている娘パミーナを救出したら結婚させるといい、タミーノは救出に向かう。タミーノには魔法の笛が、お供をすることになったパパゲーノには魔法の鈴が与えられた。2人がザラストロの館に行くと、実は彼は徳の高い僧で、パミーナが母親に感化されないように保護されていることを知る。
ザラストロはタミーノとパパゲーノを試練にかけることにする。タミーノの裏切りに怒った夜の女王はパミーナにザラストロを殺せ、というがパミーナはできないでいる。
パミーナは、沈黙の試練だとは知らずにタミーノが自分に話しかけないのは嫌われたからだと思い、自殺を考える。しかし、3人の童子に救われ、タミーノと一緒に火と水の試練を受けて突破する。
一方のパパゲーノは試練を守れるはずもなかったが、なんとか救われて、パパゲーナと結ばれた。
舞台は一応エジプト、だそうです。途中で善者と悪者が逆転したりとかなり矛盾の多いストーリーなのですが、フリーメーソンの思想が反映されているのだとか。夜の女王のアリア、歌詞の内容はかなりのものですが、コロラトゥーラがきれいなので、結構好きな曲だったりします。(映画「アマデウス」の中で、モーツァルトにヒステリックにわめきちらす義理の母がいつのまにか舞台でアリアを歌う夜の女王になる、という笑えるシーンがありましたね〜。)
デセイのDVDで初めて直前の台詞も聞きましたが、現代にも通じるような、ずいぶんリアルな台詞なんでびっくりしました。“鈴の音”は昔音楽の時間にリコーダーで吹いた懐かしの曲です。
気に入るまでに少々時間を要しましたが、
ガーディナー指揮コンセルトヘボウ公演の映像を見てから好きな演目になりました。ジェラルド・フィンリーのパパゲーノが、グロッケンシュピールを自分で弾いちゃってます(もちろん“鈴の音”も)。
ちなみに、右の切手の図案のパパゲーノは、ヴァルター・ベリーだそうです。
Music: “おれは鳥さし”
“「夜の女王」のアリア”
“何てきれいな鈴の音”
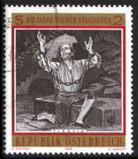
1969.5.23 オーストリア発行
「フィデリオ」 Fidelio ベートーベン作曲
夫のフロレスタンが政治犯として刑務所に収容されているレオノーレは、男装してフィデリオと名乗り看守長ロッコに仕えている。刑務所長のドン・ピツァロは政敵フロレスタンを不当に監禁していたため、司法大臣のドン・フェルナンドが臨時視察に来ることを知ってフロレスタンを殺そうとする。しかし、ドン・ピツァロがフロレスタンを短剣で刺そうとした瞬間、レオノーレがその前に立ちふさがる。そこへ司法大臣が現れて、ドン・ピツァロは逮捕され、フロレスタンは晴れて自由の身となった。
フロレスタン役はアントン・デルモータだそうです。
Music: “序曲”
“神よ、ここは何という暗さだ”

1967.9.26 ハンガリー発行
「魔弾の射手」 Der Frieschütz ヴェーバー作曲
舞台はボヘミア。猟師マックスは射撃が絶不調。森林保護官のクーノーには、明日の射撃会で見事な成績を収めねば、娘のアガーテとは結婚できないと宣言されてしまう。猟師仲間のカスパールは百発百中の魔弾を明日の射撃大会に使うようそそのかした。夜、先に狼谷に来ていたカスパールに対して、悪魔は最後の一発は自分の思い通りにすると言う。マックスとカスパールは嵐の中で魔弾を作った。翌日、射撃会ではマックスが魔弾を命中させている。領主は最後にあの鳩を撃てと命じ、最後の魔弾をマックスが撃ったところ、飛び出してきたアガーテが倒れてしまう。しかし、死んだのはカスパールだった。マックスはことの次第を正直に答え、領主に永久追放を宣告されてしまう。しかし、隠者が登場し、1年の試練の後にマックスの行いが正しければアガーテと結婚させてやろうと提案し、領主もこれを認めた。
Music: “狩人の合唱”
余談ですが、以前、「鉄腕ダッシュ」でヨーロッパ1万円でどこまで行けるか、みたいな企画をやってたことがありました。最後スキーだったかスノボだったかでアルプスを越えた山口くん。無事イタリア到着の場面で、BGMがなんとこの曲。イタリアちゃうやろ、と思わずつっこみたくなった私でした。(街中のシーンとかはまっとうにヴェルディだったんですけどね〜。)
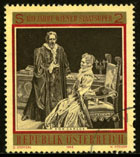
1969.5.23 オーストリア発行
「ドン・カルロ」 Don Carlo ヴェルディ作曲
王子カルロは政治的思惑で継母となった元婚約者のエリザベッタへの恋情を断ち切れないでいる。友人のボーザ侯ロドリーゴは恋の悩みを忘れるために、迫害を受けているフランドル地方の人民を共に救おうと諭した。エボリ公女は、カルロが愛しているのがエリザベッタだと知って激怒、報復を誓う。火刑場で、フランドル人を連れたカルロは異端者たちを救うようにと父王フィリッポ2世に訴え、ついに剣を抜く。ロドリーゴが間に入り、カルロは拘禁される。
王子の処遇に悩む国王は、宗教裁判長に「死刑とすることで問題ない」と言われる。またエボリ公女の出した証拠をもとに、王妃に対して不貞を責めた。牢獄にいるカルロの元にやってきたロドリーゴは自らが悪者になり、カルロの無実が明らかになるようにしてきたといい、フランドル地方の未来をカルロに託すと銃に撃たれてしまう。死んだロドリーゴの整えていた手筈により、エリザベッタとカルロは修道院で落ち合った。カルロはフランドル脱出を決意し、2人は天上での再会を約束する。そこへ国王と宗教裁判長がやってきて、2人を逮捕しようとする。しかし、修道僧の姿を借りた先王カルロの霊が、カルロを墓の中に連れて行く。
原作はシラーの戯曲。実在のフィリッポ(=フェリペ)2世については
こちらを参照されたし。
Music: “アリア”
 |
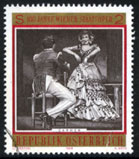 |
| 1967.9.26 ハンガリー発行 |
1969.5.23 オーストリア発行 |
「カルメン」 Carmen ビゼー作曲
セビリャの煙草工場でジプシーの女工カルメンは喧嘩騒ぎを起こし牢に送られることになった。しかし護送を命じられた伍長ドン・ホセは、婚約者ミカエラのいる身ながら、誘惑に負けて彼女を逃がしてしまう。代わりに牢に入っていたドン・ホセが出てくると、カルメンは歌い踊って歓迎するが、やがて帰営ラッパが聞こえてきた。帰営を許さないカルメンと別れてドン・ホセが隊に戻ろうとしたところへ隊長がカルメンを訪ねてやってきた。嫉妬に燃えるドン・ホセは隊長に剣を抜いてしまい、脱走兵となってジプシーの密輸団に身を投じる。しかし、カルメンの心は闘牛士エスカミーリョに移っていった。ミカエラから母親が病気であることを知らされたドン・ホセは、未練を残しながら山を下りた。闘牛場にエスカミーリョはカルメンとともに登場する。それを物陰で見ていたドン・ホセは一人になったカルメンによりをもどそうと迫るが拒絶され、逆上してカルメンを刺し殺してしまう。
素敵な曲が多いのは認めますが、一体誰に感情移入しろっちゅうんじゃい、というストーリーのおかげで、苦手なオペラでもあります。フランチェスコ・ロージ監督のオペラ映画のみ辛うじて許容範囲。といいながら、一度舞台で見たこともありまして、結構楽しんでしまったのですが、この演目に開眼したかというと微妙です。そのあたりのことは
こちら。
右の切手の図案、カルメンはジーン・マデイラ、ホセはルドルフ・ショックだそうです。
Music: “前奏曲”
“ハバネラ”
“花の歌”
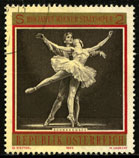
1969.5.23 オーストリア発行
「白鳥の湖」 Льбединое Озеро チャイコフスキー作曲
明日の舞踏会で結婚相手を見つけなければならない王子ジークフリート。白鳥狩りに出かけた彼は、
白鳥たちが次々に娘の姿に変身して踊り始めるのを見た。中でも一際美しいオデットは、ロットバルトという魔法遣いのために白鳥の姿にさせられていて、夜だけしか人間の姿に戻れず、魔法を解くには、愛の力が必要なのだという。彼女に惹かれたジークフリートは永遠の愛を誓う。だが、それを知ったロットバルトは娘のオディールをオデットになりすませて舞踏会に送り込み、ジークフリートに愛を誓わせてしまった。傷心のオデットのもとに、真相に気付いたジークフリートが駆けつけて誤解は解かれたのだが・・・
ここから先が2パターンあるのだそうで、誓いを破ってしまった以上どうにもならず2人は身投げ、その愛の力でロットバルトが倒れ、2人は天上で永遠に結ばれる、というのが原作の結末。しかし、これではあんまり一般うけしそうもない、ということでか、2人がロットバルトを倒し、魔法が解けてオデットをはじめ全ての白鳥が人間の姿に戻ってめでたしめでたし、というエンディングの方がポピュラーのようです。
Music: “情景”
“白鳥の踊り”
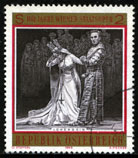
1969.5.23 オーストリア発行
「ローエングリン」 Lohengrin ヴァーグナー作曲
ブラバント公女エルザは元婚約者のテルラムント伯から弟ゴットフリートを殺した廉で訴えられた。国王はテルラムントとエルザのために決闘をする騎士のうち、勝った方が潔白だとする判決を行うことに決める。このとき河の上流から白鳥にひかれた小舟に乗った騎士が現れ、エルザに素性を聞かないこと、勝ったら結婚することを約束させて決闘に挑み、彼女の嫌疑を晴らした。
だが、魔術に長けたテルラムント夫人オルトルートは、エルザの心に騎士に対する疑惑を植え付けていった。結婚式が終わり二人だけになると、エルザはこらえきれなくなり、ついに名前と素性を聞いてしまう。謎の騎士は聖杯王パルジファルの息子でローエングリンと名乗る。聖杯を守る騎士たちは素性を明かすと、その守る力が消えてしまうのだ。迎えにやってきた白鳥の首飾りを見たオルトルートはこの白鳥こそ自分が魔法をかけたゴットフリートだという。それを聞いたローエングリンが祈ると白鳥はゴットフリートの姿に戻り、ローエングリンはこれこそブラバント公と言い残して去ってゆく。
ローエングリン役はヴィントガッセン、エルザ役はグリュンマーだそうです。
Music: “第1幕への前奏曲”
“第3幕への前奏曲”
“婚礼の合唱”
【《ニュルンベルクのマイスタージンガー》 初演100年】

自筆譜とサイン
1968.6.21 ドイツ連邦共和国発行
「ニュルンベルクのマイスタージンガー」 Die Meistersinger von Nürnberg ヴァーグナー作曲
教会の礼拝で互いに一目惚れしたエーファと騎士ヴァルター。明日、マイスターたちによる歌合戦があり、その優勝者にエーファと結婚する権利が与えられることを聞いたヴァルターは、マイスターになる試験を受けるが、彼の歌は歌作りの規則からは大きく外れていた。書記ベックメッサーは失格を宣告するが、靴屋のザックスは、ヴァルターに素質があることを見抜いた。その夜、エーファは、家を抜け出してヴァルターと駆け落ちの相談を始める。エーファに愛の歌を捧げにやって来たベックメッサーは、乳母をエーファと思い込んで歌い出す。しかし、偶然二人の相談を聞きつけたザックスが、ベックメッサーの歌を邪魔して騒ぎを起こし、そのどさくさにヴァルターを自分の家に引き入れ、エーファを家に帰した。エーファをひそかに愛していたが、二人のために一肌脱ごうと考えるザックス。歌合戦ではベックメッサーが最初に歌うが、練習不足のため大失敗。ヴァルターの歌は素晴らしく、全員が喝采する。一旦はマイスターの称号を拒否するヴァルターだが、ザックスに説得され、晴れて優勝者となりエーファと結ばれる。
初演は1868年6月21日、バイエルン宮廷歌劇場。指揮はハンス・フォン・ビューロー(ってアノ人ですか・・・)。実在のザックスについては
こちらを参照されたし。第3幕の「目覚めよ、朝は近づいた」は実際のザックスの詩に基づくものだそうです。
それにしても騎士がマイスターになれるの? ってあたりがとっても消化不良なこのストーリー(マイスターって職人さんでしょ?)。誰か納得のいく説明をしてくれないかなあと常々思ってます、はい。
Music: 楽劇《ニュルンベルクのマイスタージンガー》前奏曲

1967.9.26 ハンガリー発行
「イーゴリ公」 Knyaz' Igor' ボロディン作曲
ノヴゴロド公イーゴリの遊牧民ポロヴェツ討伐を語ったロシアの中世叙事詩が原作。
ポロヴェツ軍との戦いに赴いたイーゴリ公だが、出陣の朝の凶兆が適中、息子ウラディーミルとともに囚われの身となってしまう。悲報は夫の帰りを待つヤロスラーブナのもとにも届いた。
イーゴリ公の人柄に惚れ込んだ敵の指揮官コンテャク汗は、陣営をあげての祝宴で歓待する。そのころウラディーミルは汗の娘コンチャコーヴナと恋仲になっていた。
キリスト教徒のポロヴェツ人オヴルールの導きで逃げようとするイーゴリとウラディーミルだが、コンチャコーヴナが引きとめようとするので、ウラディーミルは捕まってしまう。イーゴリの逃亡を知った汗は明日また戦えば良いと黙認し、快くウラディーミルを婿に迎えて祝福する。
ちょっと待て、まだポロヴェツとは戦う予定なら、敵の婿になってしまった息子と戦わなきゃいけないだろ、それで大円団なのか? と突っ込みたくならないでもないストーリーですが・・・
Music: “ダッタン人の踊り”

1969.5.23 オーストリア発行
「ばらの騎士」 Der Rosenkavalier リヒャルト・シュトラウス作曲
元帥夫人マリー・テレーズは伯爵オクタヴィアンと朝を迎えていた。そこへ彼女の従兄のオックス男爵が現れ、新興貴族ファーニナルの娘ゾフィーと結婚するので、婚約のしるしとして花嫁に銀のばらを送る「薔薇の騎士」を紹介してほしいと頼む。元帥夫人はオクタヴィアンを推薦した。
ファーニナルの屋敷でゾフィーに銀のばらを渡すオクタヴィアンだが、互いに一目ぼれする2人。そこへ現れたオックス男爵の下品な振る舞いにゾフィーはうんざりし、オクタヴィアンにオックスと結婚しないで済む方法を相談する。ゾフィーとの仲を咎められたオクタヴィアンはオックスと決闘になり、ケガをさせてしまう。
オックスを懲らしめるべく、オクタヴィアンは小間使いマリアンデルに変装して逢い引きの約束をし、一騒動を起こす。そこへ元帥夫人が現れて騒ぎを収めた。退散するオックス。オクタヴィアンとゾフィーの間に芽生えた愛を感じ取った元帥夫人は身を引く決心をし、静かに部屋を出ていく。
元帥夫人はアンネリーゼ・ローテンベルガー(ソプラノ)、オクタヴィアンはクリスタ・ルートヴィヒ(メゾソプラノ)だとか。ちなみにオクタヴィアンはズボン役といいまして、女が男装して歌う役ですので念のため。
Music: “ワルツ

1967.9.26 ハンガリー発行
「青ひげ公の城」 A Kékszakallú Herceg Vára バルトーク作曲
親兄弟の反対を振り切って青ひげ公の妻となったユーディトは、陰気な城を明るくしてみせるという。城にある7つの扉の中に入ってみたいと彼女はせがみ、最初は「必要ない」と言っていた青ひげ公も第1の扉の鍵を渡した。第1の部屋は拷問室。同じようにして開けた第2の部屋は武器庫。第3の部屋は
宝物庫。第4は花園。第5の扉が開くと、青ひげ公の広大な領地が見渡せた。だが、どの部屋にも血が流れているのだった。残りの2つの扉は開けないでおこうという青ひげ公。だが不審を募らせたユーディトは第6の扉を開ける。そこは涙の池だった。そして第7の扉が開くと、3人の女性が立っていた。
青ひげ公はユーディトを美しく装わせ、彼女は4人目の女として、他の女性と並び動かなくなってしまうのだった。

1997.2.10 ベルギー発行
マリー・サス Marie Sasse 1834-1907
ベルギー(ヘント)出身のソプラノ歌手。父の死後、カフェで歌い家計を支えた。1852年ヴェネツィアで「リゴレット」のジルダを歌ってオペラデビュー。1865年、マイアベーアの「アフリカの女」(ヴァスコ・ダ・ガマをめぐる2人の女性の葛藤劇)の女王セリカを創唱。1867年にはヴェルディの「ドン・カルロス」のエリザベートを創唱した。
このページを参考にさせていただきました。
図案は「アフリカの女」の方ですね。
王立モネ劇場のオペラシリーズの1枚。

1997.2.10 ベルギー発行
Ernest van Dijck 1861-1923
ベルギーの歌手(ヘルデンテノール)。その時代の最も有名なヴァーグナー歌手の一人。 1887年にはバイロイトに招かれてパルジファルを歌い、1912年にはローエングリンを歌った。1899年にはウィーンで、1902年にはメトロポリタン歌劇場で歌っている。 後にアントワープ音楽院(1906-1923)やブリュッセル音楽院(1909-1923)で教師を務めた。
こんなページを見つけたので、原文と自動翻訳をにらめっこ、辞書も引かずに適当訳。
マスネの「ウェルテル」タイトルロールを創唱したテノールさんだそうです。お名前はエルネスト・ファン・ディックと読むんでしょうか。
どう見ても切手の図案は「ウェルテル」には見えないんですが、ワーグナーかしら? カタログには載っておらず、いろいろ検索してもみましたが、目下のところ不明です。
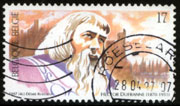
1997.2.10 ベルギー発行
エクトール・デュフランヌ Hector Dufranne 1870-1951
ベルギー(モンス)出身のバス・バリトン歌手。1896年モネ劇場で「ファウスト」のヴァランタンを歌ってデビュー。1900年からパリのオペラ・コミックに出演。1902年ドビュッシーの「ペレアスとメリザンド」のゴローを創唱する。1910年から1922年まではシカゴで活躍し、プロコフィエフの「3つのオレンジへの恋」のレアンドルを創唱するなどしている。1939年に第2次世界大戦の勃発と時を同じくして引退。パリに住み、死ぬまで声楽を教えた。「サロメ」のヨカナーンをはじめ、幅広いレパートリーを誇った。
このシリーズの中では一番有名な方のようで、CDも残っているみたいです。
英語版ウィキペディアや
このページを参考にさせていただきました。図案は「ペレアスとメリザンド」のゴローですね。

マントヴァ公(「リゴレット」)に扮したカルーソー
1973.12.15 イタリア発行
カルーソー Enrico Caruso 1873-1921
イタリアのテノール歌手。1894年に生地ナポリでデビュー。1898年ミラノで《フェドーラ》(
ジョルダーノ作曲)のロリスを創唱して絶賛される。生まれながらの美声とベルカント唱法とによって一世を風靡、特に1903年以来メトロポリタン歌劇場で黄金時代を築いた。声は劇的な表現も可能なリリック・テノールで、純粋にドラマティック・テノールのための役柄は舞台では歌っていない。残された録音は復刻されたものも多く、イタリア・オペラ理想のテノールとしていまなお聞かれている。また戯画の名手としても知られ、当時の音楽家を描いた似顔絵等を集めた本が出版されている。
Music: 「リゴレット」より“女心の歌”

1987.8.27 アイルランド発行
ウェックスフォード・オペラ・フェスティバル
1951年に始まった、アイルランド南東部の町ウェックスフォードで10月から11月にかけて行われる音楽祭。アイルランドの伝統的な祭り4枚組の中の1枚です。
で、これまた例によって演目不明・・・
参考文献:『オペラガイド126選』(山田治生他編著/成美堂出版)
『音楽・切手の366日』(平林敏彦著/薬事日報社)
カルーソー略伝は平凡社マイペディア98、世界大百科事典より
|
《戻る》 ◆ オペラDVDコレクション へ