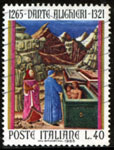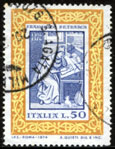|
Literature |
 |
【アーサー王伝説】
 |
 |
| アーサー王と魔術師マーリン |
湖の乙女 |
 |
 |
| ランスロットと王妃グウィネヴィア |
ガラハッド卿 |
イギリスの王アーサーにまつわる物語。モデルはサクソン人の侵入を撃退したケルト系ブリトン人の英雄と考えられる。11世紀頃から吟遊詩人の詩や文献にアーサーにまつわる伝説がみられるようになり、1139年に完成したジェフリー・オヴ・モンマスの『ブリタニア列王史』に初めてまとまった形で描かれた。12世紀フランスの作家クレチアン・ド・トロワをはじめ、仏・独・英語などで膨大な文学作品が産み出されているが、トマス・マロリーによる作品をカクストンが『アーサー王の死』と題して1485年に出版したものが現在一般に知られている。
王中心の一代記から、宮廷風恋愛や聖杯の主題が取り入れられて王の騎士たちである「円卓の騎士」などのエピソードが中心となり、アーサーの王妃グウィネヴィアに恋するランスロット、トリスタンとイゾルデの物語、ペルスヴァルの聖杯伝説などを含む。
1985.9.3 イギリス発行
《中世ドイツの吟遊詩人》
大ハイデルベルク歌謡写本、別名マネッセ歌謡写本所載のミニアチュア

ハインリヒ・フォン・ルッゲ 1150頃-1200頃
1175から1178の間に文献に登場、1190年のフリードリヒ1世の死を悲しむ歌がある。

ヴォルフラム・フォン・エッシェンバハ Wolfram von Eschenbach 1170頃-1220頃
中世高地ドイツ語時代の詩人。ハルトマン・フォン・アウエ、ゴットフリート・フォン・シュトラスブルクとともにホーエンシュタウフェン王朝時代の三大宮廷叙事詩人といわれる。広い文学的な教養を身につけていたことが知られているが、生涯については他の詩人たちと同様ほとんど不詳。13世紀初頭にテューリンゲン方伯ヘルマン、ヴェルトハイム伯らのもとで詩作。9編のミンネザングも残っているが、クレチアン・ド・トロワの『ペルスヴァルまたは聖杯物語』などにならい、アーサー王伝説と聖杯(グラール)伝説とを結び合わせた叙事詩『パルツィファル』(1200-10頃)が名高い。無邪気な自然児が騎士の理想像に成長する苦難の道程をうたったこの2万5000行の叙事詩はドイツ文学における教養小説の源泉とされている。そのほかフランスの武勲詩『アリスカンの戦い』を素材としてサラセン人と戦うキリスト教徒の騎士の姿を描いた叙事詩『ヴィレハルム』(1212-18)、『ティトゥレル』と呼ばれている断片の恋物語がある。

ヴァルター・フォン・メッツ

ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデ Walther von der Vogelweide 1170頃-1230頃
中世高地ドイツ語時代で最も名高いミンネゼンガー。騎士階級の出身。出生地は不明だが、オーストリア地方で成長したとされる。ウィーンのバーベンベルク家の宮廷で教養を身につけ、ラインマル・フォン・ハーゲナウを師としてミンネザングを修業。のち師と対立し、オーストリア大公フリードリヒ1世の死後、1198年に封土を求めてヨーロッパ各地の宮廷への遍歴の旅に出、フィリップ2世、オットー4世らのドイツ王(皇帝)たち、テューリンゲン方伯ヘルマン、マイセン辺境伯ディートリヒなどのもとを訪れる。最後に皇帝フリードリヒ2世に仕え、1220年頃ビュルツブルク近辺に待望の小さな封土を与えられた。従来の伝統的なミンネザングの枠をこえて、身分の低い娘への愛、いわゆる「低きミンネ」を賛美する一方、多くのすぐれた政治的格言詩、宗教詩を書き、当時の政治、道徳、ローマ・カトリックの腐敗を嘆き批判した。特に皇帝と教皇との争いに関しては、痛烈にローマ教皇を攻撃した。
1970.2.5 ドイツ連邦共和国発行
【社会福祉】

ハインリヒ・フォン・シュトレットリンゲン

マインロー・フォン・ゼーフェリンゲン Meinloh von Sevelingen
初期のいわゆる「ドーナウ地方の詩人」の一人。1160-1170年ごろに詩作。トルバドゥールの影響がみられる。

ブルクハルト・フォン・ホーエンフェルス Burkhart von Hohenfels
彼の城、ホーエンフェルス城の廃墟はボーデン湖畔ジップリンゲンにある。皇帝フリードリヒ2世、ドイツ王ハインリヒ7世らに仕えたミニステリアーレで、1212-1242年の記録に名が出てくる。

アルブレヒト・フォン・ヨハンスドルフ Albrecht von Johansdorf
1165年頃の生まれ。バイエルン出身のミニステリアーレ。パッサウの大司教に仕え、おそらく1189/90年の皇帝フリードリヒ1世の十字軍に参加。
1970.2.5 ドイツ連邦共和国ベルリン地区発行
【社会福祉】
参考文献:『ドイツ中世恋愛抒情詩選集 ミンネザング』(ヴェルナー・ホフマン・岸谷敞子・石井道子・柳井尚子訳著/大学書林)

ハーメルンの笛吹男
あるネズミ取りの笛吹男が、この町の鼠を笛の音により川に誘い込んで一掃したのに、住民が約束した報酬を払わないため、復讐として町の130人のこどもたちを同じ方法で町の外に連れ去ってしまったという伝説。1284年に実際起こったこどもたちの失踪事件を核に持つ。
1978.5.22 ドイツ連邦共和国発行

Rattenfänger von Hamelnであれば「ハーメルンの笛吹男」なんですが、これはRattenfänger von“Korneuburg” “コルノイブルク”の笛吹男。
ウイーンの近くの地名らしいんですが、似たような話があったんでしょうか。
1998.1.23 オーストリア発行
【神話と伝説シリーズ】
1965.10.21 イタリア発行
ダンテ Dante Alighieri 1265-1321
イタリアの詩人。フィレンツェに生まれる。9歳のときに運命の女性ベアトリーチェに出会う。1295年以降積極的に市政に参画。1300年に市の統領の一人に選ばれるが、政敵に追放され、公金横領罪・反逆罪等の汚名を負わされる。以後、死ぬまで亡命と放浪の生活を余儀なくされる。晩年はラベンナ公の庇護を受け、同地を最後の安住の地とした。彼の名を不朽のものとした《神曲》は、追放後に起稿され、死の直前に完成した。

1972.11.23 イタリア発行
【ダンテ神曲出版500年】
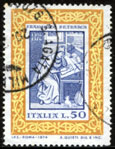 |
 |
1974.7.19 イタリア発行
【死去600年】 |
2004年 イタリア発行
【生誕700年】 |
ペトラルカ Francesco Petrarca 1304-1374
イタリアの詩人。早くから古典文学を愛読し、父の希望した法学の勉強を放棄。1327年、『カンツォニオーレ』(1350)の中心的主題となる女性ラウラに出会い、恋愛詩を書き始めた。その後、詩作と執筆のための静かな生活を求めてアヴィニョン、パルマ、ミラノ、ヴェネツィアなどを転々とし、1341年叙事詩『アフリカ』により桂冠詩人の称号を受けた。

ボッカチオ Giovanni Boccaccio 1313-1375
イタリアの小説家・詩人。若くして商業見習いのためにナポリにやられたが、父の意に反して文学の世界に没入。1327〜39年にはナポリで宮廷生活を経験。1340年見習い先のバルディ商会が倒産したため、故郷チェスタルドに帰って『アメートの妖精談』『愛の姿』『フィアンメッタ』などを著した。最大の傑作は、ペストの難を郊外の別荘にのがれた男女が10日にわたって1日1話を順番に物語る形式で描かれた『デカメロン』(1349-51)である。
1975.12.22 イタリア発行

「カンタベリー物語」の挿し絵
チョーサー Geoffrey Chaucer 1340?-1400
イギリスの詩人。酒商の家に生まれ、10代から小姓として宮廷に仕えた。1369年にパトロンであった
ランカスター公ジョンの夫人ブランシュの死を悼んで『公爵夫人の書』を創作。国王の使いとしてイタリアを訪問、またロンドン港の税関監査官も務め、『誉の宮』『鳥の議会』『善女物語』などイタリア文学に影響された作品を書いた。1386年に失脚するが、のち再び官吏となり、テムズ川岸工事監督などを務める。代表作『カンタベリー物語』はカンタベリー大聖堂に詣でる巡礼たちによって語られる物語集。題材の豊かさ、ユーモアに満ちた人間洞察、中世英語の完成などで「英詩の父」と呼ばれる。
1976.9.29 イギリス発行
【イギリスの印刷500年】

ローラント王 『狂乱のオルランド』の挿絵より
アリオスト Ludovico Ariosto 1474-1533
イタリアの詩人。エミリアのレッジオで要塞司令官の息子として生まれる。幼少から詩を好むが父の命令により5年間を法律の勉強に費やす。父の死後、エステ家の枢機卿イッポーリト1世に仕え、将校・外交官として活躍したのち、イッポーリトの兄フェラーラ公アルフォンソ1世に仕える。1517年以降ガルファニャーナの総督となったが、晩年に結婚して余生をフェララで送った。イタリア・ルネサンス文学の傑作『狂乱のオルランド』(1507頃〜32)を著して、後世のヨーロッパ文学に大きな影響を与えた。
1974.9.9 イタリア発行

ティル・オイレンシュピーゲル
1510-1511年に出版されたドイツの民衆本。ティルという農民の子が、放浪者・道化師あるいはもぐりの職人となって各地を渡り歩き、愉快ないたずらと頓知で国王・教皇から司祭や親方までさまざまな身分の者たちをあざむきからかう滑稽話で、各国語に翻訳された。
ブラウンシュヴァイクの徴税書記であったヘルマン・ボーデが先行する伝承をもとにして創作したものとみられている。
切手の図案に登場する話は、左上から時計回りに (阿部謹也訳 岩波文庫より)
・第4話 オイレンシュピーゲルが若者たちを舌先三寸でまるめこんで、はいていた二〇〇足以上の靴をぬがせ、大人も子どももそのために髪をひっぱりあう大乱闘をひきおこしたこと。
・第29話 オイレンシュピーゲルがエルフルトで驢馬に旧約詩篇の読み方を教えたこと。
・第87話 オイレンシュピーゲルがブレーメンの市場で女が自分の壺をすべて粉々に割るようにしむけたこと。
・第26話 オイレンシュピーゲルがリューネブルクの国で農夫から畑の土を少し買って荷車に積み、土のなかにもぐりこんだこと。
日本では『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』で知られる作品。実際読んでみるとあんまり“愉快”でもないような気がしますが。スカトロ話がやたらと多いし・・・
切手の図案でティルの頭はネコ耳みたいな帽子をかぶっていますが、これは阿呆帽というのだそうで、中世の挿絵などではこれをかぶらせて“阿呆”だということをあらわすのだとか。
1977.1.13 ドイツ連邦共和国発行
参考文献:『ブリタニカ国際大百科事典』
《戻る》
◆ 近世以降 へ
◆ 英国編 へ
◆ ドイツ編 へ