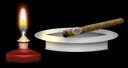
Hard-boiled

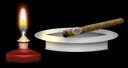 |
Hard-boiled |
 |
主人公がストイックでない小説をハードボイルドとは呼ばない(笑)。
| ロバート・B・パーカー Robert B. Parker | |||||
|
主人公スペンサー(ファーストネームはご本人が言わないので不明)。ボストン在住。元ボクサーで、しばしばトレーニングのシーンが出てきたりするのですが、ばりばりの“体育会系”というわけでもなく、詩を愛好してたり、おいしい料理をつくっていたり。(恋人の顔をプリントしたTシャツを着てジョギングしてたりも・・・) 『初秋』を読んだのがきっかけで、追いかけるようになったシリーズです。 寡黙なものと相場が決まっているハードボイルドの探偵としては異色な饒舌さなのだそうですが、相棒の黒人ホークとの“掛け合い漫才”や恋人スーザンとのディスカッションが毎回の楽しみ。アメリカ社会の実態が描かれているのも興味深いところです。 ファンの多いシリーズらしく、『スペンサーの料理』『スペンサーを見る事典』『スペンサーのボストン』といった本も出版されています。 | |||||
離婚した夫が連れ去った息子を取り戻して欲しいという依頼を受け、スペンサーはその少年ポールを見つけ出した。だが、彼は両親の駆け引きの材料に使われ、何事にも関心を示そうとしなかった。ポールを保護することになったスペンサーは、彼の自立のためにボクシングや大工仕事を教え始める・・・ | |||||
| シリーズ作品リスト 訳者:菊池 光 ハヤカワ・ミステリ文庫 | |||||
|
『ゴッドウルフの行方』 The Godwulf Manuscript 1973 |
『誘拐』 God save the Child 1974 |
『失投』 Mortal Stakes 1975 |
『約束の地』 Promised Land 1976 | ||
|
『ユダの山羊』 The Judas Goat 1978 |
『レイチェル・ウォレスを探せ』 Looking for Rachel Wallace 1980 |
『初秋』 Early Autumn 1981 |
『残酷な土地』 A Savage Place 1981 | ||
|
『儀式』 Ceremony 1982 |
『拡がる輪』 The Widening Gyre 1983 |
『告別』 Valediction 1984 |
『キャッツキルの鷲』 A Catskill Eagle 1985 | ||
|
『海馬を馴らす』 Taming a Sea-Horse 1986 |
『蒼ざめた王たち』 Pale Kings and Princes 1987 |
『真紅の歓び』 Crimson Joy 1988 |
『プレイメイツ』 Playmates 1989 | ||
|
『スターダスト』 Stardust 1990 |
『晩秋』 Pastime 1991 |
『ダブル・デュースの対決』 Double Deuce 1992 |
『ペイパー・ドール』 Paper Doll 1993 | ||
|
『歩く影』 Walking Shadow 1994 |
『虚空』 Thin Air 1995 |
『チャンス』 Chance 1996 |
『悪党』 Small Vices 1997 | ||
|
『突然の災禍』 Sudden Mischief 1998 |
『沈黙』 Hush Money 1999 |
『ハガーマガーを守れ』 Hugger Mugger 2000 |
『ポットショットの銃弾』 Potshot 2001 | ||
| 原 尞 Hara Ryo | |||||||||
|
洒脱な文章、キレのいい会話、印象的な登場人物、緻密に組み立てられたストーリー、リアリティのある事件、地道な調査と、そして鮮やかなどんでん返し。ハードボイルドはバイオレンスアクションに非ず、と思っている私に、そうそう、ハードボイルドってのはこうでなくちゃ! と思わせたこのシリーズ。 とにかく主人公がかっこいい。冷たくはないのだけれど、感傷に流されることもなく、捜査に自分の主義主張を押し出しもしない。渋い中年である私立探偵・沢崎。愛想なしで金銭には無頓着。総じて不器用な男なのですが、セリフがいいのです。たとえば、高圧的な物言いをされる場面ではこんなふうに。 「弁護士を雇えるような身分ではないので、彼のいまの忠告を正しく理解できたかどうか自信がないのですが――要するに彼は、ぐずぐず言わずに知っていることを喋ったほうがてっとり早く金になるぞ、と言ってくれているのですか」 (『そして夜は甦る』より) 脇役もなかなかの存在感です。アル中の元パートナー渡辺が起こした事件以来の腐れ縁、新宿署の この、渡辺の起こした事件には、『さらば長き眠り』である決着がつきます。というわけできれいに片ついてしまったし、これで完結ってこともあるのかな、なぞと思ってみもしましたが、文庫版には「死の淵より」という掌編が収録されており、「第二期」に向けた構想はおありの模様。でもけりがついてしまった以上、錦織警部や橋爪との関係がこのままということは考えられず、どうなってしまうのか・・・少し気になるところです。 過去の事件や人間関係がストーリーに絡んでくることが多いので、読むときはシリーズの順番に読んだ方が良いです。とはいえ、『天使たちの探偵』の収録作品は『私が殺した少女』をまたいでるので、どちらを先にするかはちょっと悩むところかも(私は『天使たち』を先に読んで、正解だったと思ってますが)。 ちなみに、文庫のみですが、あとがきがわりにショートストーリーがつくという趣向もこのシリーズの特徴。『そして夜は甦る』収録の「マーロウという男」では表題どおりマーロウ論、『私が殺した少女』収録の「ある男の身許調査」では著者の経歴、『天使たちの探偵』収録の「探偵志願の男」では沢崎が私立探偵になった事情、という内容です。エッセイ集『ミステリオーソ』にも「番号が間違っている」という掌編あり。 | |||||||||
事務所を訪ねてきた男は、佐伯というルポ・ライターが来たかどうかを知りたがり、大金の入った封筒を預けていった。ほどなく佐伯の妻の実家に呼ばれた沢崎は、連絡を絶っている佐伯を探し出すことを頼まれるのだが・・・
拾った宝くじが当たったように不運な日は一本の電話から始まった。面会場所に指定された
依頼人宅へ向かった沢崎は、誘拐事件に巻き込まれていたのだった・・・ ハメット、チャンドラー、ロス・マクドナルドの個性は、一般に考えられているように彼らの創造した探偵たちの個性によっているのではなくて、彼らの依頼人や彼らが関わる事件の“個性”によっているのではないかということだ。乱暴な限定の仕方だが、ハメットはプロの犯罪者を相手にし、チャンドラーは富豪や特権階級の犯罪を相手にし、ロス・マクドナルドは最終的には一般家庭の犯罪を相手にした。〈ポイズンヴィル〉で調査をするリュウ・アーチャーは考えられないし、崩壊しかけた家庭の玄関のベルを鳴らすサム・スペードも考えられない。作者に可能なのは、彼の探偵にふさわしい依頼人と事件を与えることだけで、探偵の個性はむしろ読者によってつくられるのかもしれない・・・・・・
というくだりが『ミステリオーソ』にあるのを読みながら、やっぱり沢崎の相手は、よんどころない事情から事件を起こした人間より、もう少し確信犯的な人間の方がふさわしいんじゃないか、などと思ってしまったのでした。相手に向かって吐くセリフは「私は勝負に負けた人間が嫌いではないですがね。自分の敗北に気付かない人間や敗北を認めようとしない人間は、性に合わないのです」(『そして夜は甦る』より)というたぐいのほうが似合ってるんじゃないかと。
事務所を訪れた10歳の少年は、「ある女の人を守ってほしい」と言い、1万円札5枚を残して雨の中に消えた。やむなく調査を始めた沢崎は、銀行強盗事件に巻き込まれることになる・・・「少年の見た男」。娘のひき逃げ事件を目撃していないかと沢崎に尋ねた男は、次の日も事務所を訪ねてきた。昔の女に宛てた手紙を買い取れと脅迫されており、受け渡し現場に同行してもらいたいのだという・・・「子供を失った男」。事務所を訪ねてきた母親は、息子から「人殺しの罪を着せられるかもしれない」という電話を受けていた。調査の手がかりをつかむべく少年補導員を訪ねた沢崎だったが、その男は市議会員選挙の立候補者で、選挙活動の真っ最中だった・・・「選ばれる男」。その他「二四〇号室の男」「イニシャル“M”の男」「歩道橋の男」の全6編を収録した短編集。 | |||||||||
| シリーズ作品リスト ハヤカワ文庫JA | |||||||||
| 『そして夜は甦る』 1988 |
『私が殺した少女』 1989 |
『さらば長き眠り』 1995 |
『天使たちの探偵』 〈短編集〉 1990 | ||||||
| 『愚か者死すべし』 2004 | |||||||||
| レイモンド・チャンドラー Raymond Chandler | ||||||||
スターンウッド将軍の邸宅を訪ねたマーロウ。将軍は、娘が非合法の賭博で作った借金を、ガイガーという男に要求されているのだという。ガイガーの経営する書店を張り込み、自宅を突き止めたマーロウは、その家の中から銃声が轟くのを聞いた・・・
化粧品会社の社長に妻の居所探しを依頼されたマーロウ。メキシコで結婚するという電報が最後の音信だったが、彼女の愛人はその事実を否定する。彼女が最後に滞在していた湖畔の別荘を訪ねたマーロウは、別荘の管理人が指さす水中に死体があるのを見た・・・ | ||||||||
| シリーズ作品リスト 訳者:清水 俊二 ハヤカワ・ミステリ文庫 | ||||||||
|
『大いなる眠り』 The Big Sleep 訳:双葉十三郎 〈創元推理文庫〉 1939 |
『さらば愛しき女よ』 Farewell, My Lovely 1940 |
『高い窓』 The High Window 1942 |
『湖中の女』 The Lady in the Lake 1943 | |||||
|
『かわいい女』 The Little Sister 〈創元推理文庫〉 1949 |
『長いお別れ』 The Long Goodbye 1953 |
『プレイバック』 Playback 1958 | ||||||
| 大沢 在昌 Osawa Arimasa | ||||||||
|
主人公鮫島警部。国Ⅰに受かったキャリアでありながら、公安内部の暗闘に巻き込まれ、その鍵を握る手紙を預かったまま新宿署に転任してきたという設定。はみだし刑事ゆえに署の中でも孤立している、単独遊軍捜査官なのですね。 主人公への思い入れは分かりますが、三人称で書かれてる分、地の文に出るのがちょっと(苦笑;キャリアって設定も諸刃の剣になりそうではあるし)。 「あんたはやっぱりバカマッポだね。正義漢ぶって、怪我しても、殴られても、俺がやんなきゃ誰もやんないって、法律背中にしょって、つっこんでくんだ。死んだら本望だろ。格好いいって思ってんだろ」 と言わしめるきわどさのあるキャラクターではあります、確かに。 恋人であるロックシンガーの晶、防犯課長の“マンジュウ”(死人の意)こと桃井、弾道検査の専門家・鑑識の藪、など存在感のある脇役がいる分、それほど気になるわけでもないんですが。 そろそろ桃井も定年退官の歳が近づいておりますが、そうなったらこのシリーズ、どういう方向に進んでくんでしょうね? | ||||||||
歌舞伎町周辺で警官が連続して射殺される事件が起きた。署内に捜査本部が設置されるのをよそに、鮫島は改造銃作りの天才・木津を追うのだが・・・
歌舞伎町ではコロンビア人の街娼が殺され、近くのホテルでボヤ騒ぎが起きた。鮫島は藪の紹介で消防庁調査課の吾妻に協力を要請される。再び起きた街娼殺人事件の現場に、甲屋という植物防疫官が現れた。殺された女性は南米から恐るべき稲の害虫の蛹を持ち込んでおり、羽化するまでにはあと数日しかないというのだ・・・ | ||||||||
| シリーズ作品リスト 光文社文庫 | ||||||||
| 『新宿鮫』 1990 |
『毒猿』 1991 |
『屍蘭』 1993 |
『無間人形』 1993 |
『炎蛹』 1995 |
||||
| 『氷舞』 1997 |
『灰夜』 2001 |
『風化水脈』 2000 |
『狼花』 2006 |
|||||