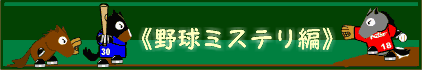
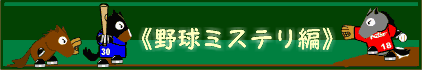
| �X�g���C�N�E�X���[�ŎE������@�@Strike Three You're Dead |
| ���`���[�h�E���[�[���@�@Richard Rosen |
| �i��@�~ ��@�@�n���J���E�~�X�e������ |
|
�A�����J�T���ƃN���u�ŗD�G�������ҏ�܍�B �W��29���A�y�i���g���[�X�̍Œ��ɁA�v�����B�f���X�E�W���G�[���Y�̃����[�t�s�b�`���[�A���f�B�E�t�@�[�X�����b�J�[���[���ő��E�̂Ŕ��������̂ł����A���̎�������������̂��A�`�[�����C�g�̃Z���^�[�A�n�[���F�C�E�u���X�o�[�O�B �����A�Ȃ�ƒT����������̑僊�[�K�[�Ȃ̂ł��B ����Ȃ��ɂ����x���Ă��E�E�E�@�Ǝv���܂������A�j�b�N�l�[�����g�����h�A�싅����߂����w����̐�U�e�[�}�A��k�푈�j�̌������ĊJ���悤�ƍl���Ă��郆�_���l�I��A�Ɛݒ�ɔ�����͂���܂���ł����i�j�B �u���肪����_���ē����Ă���̂́A�Ŏ҂̒��q�������Ƃ����B�v�Ƃ����o�������n�߁A���͂����܂��ł����A�L�^�}�j�A�̂��Z�����A���l�~�b�L�[�Ƃ̉�b�����������o���Ă��܂��B �i�l�I�ɂ́A�~�b�L�[�ɘA��čs���ꂽ�o�b�e�B���O�Z���^�[�ŁA�q�ǂ����u����������ł��Č����Ă�B�˂��A�����Ƃ�����̂ق������܂���v�ƌ�����V�[������ԍD���G�j �o�b�g���炢�������畁�ʂ̃~�X�e���ł�����Ƃ��ēo�ꂵ�܂����ǁA�g�s�b�`���[�̓�����{�[���h����ѓ���̂����ɂȂ��Ă��肷�邠����A�싅�~�X�e���Ȃ�ł͂ł��ˁB �쒆�̃t�����Z�X�ɔ�ׂ���A�^���ēv�l�ȂA����܂肻�̂܂�܂����Ŗʔ��������A�Ƃ��v���Ă݂���i�j�B ����ɂ��Ă��A�����̓��{�v���싅������ɂ��A�t���[�E�G�[�W�F���g���ă~�X�e���̑�ނɂȂ�Ȃ��A�Ƃ����̂ɉʂĂ��Ȃ����A���e�B���E�E�E�i�܁j�B ���Ȃ݂Ɏ�l���A���ތ�ɗ��j�w�҂ł͂Ȃ��Ė��Ƌ��̎����T��ɂȂ��Ă���A�Q��قǑ��҂�����܂��B |
![]()
| �����@�@Mortal Stakes |
| ���o�[�g�E�a�E�p�[�J�[�@�@Robert B. Parker |
| �e�r�@�� ��@�@�n���J���E�~�X�e������ |
|
���b�h�\�b�N�X�̃G�[�X�A�}�[�e�B�E���u�ɔ��S�������̋^��������Ƃ����B���c�̋ɔ�̈˗��ŃX�y���T�[�͒������J�n���邪�E�E�E�B �X�y���T�[�E�V���[�Y��R��ځB�I�[�\�h�b�N�X�ȃn�[�h�{�C���h�Ƃ��Ďn�܂������̃V���[�Y���A�g�X�y���T�[�E�V���[�Y�h�ɂȂ��Ă����]���_�̍�i�B �u���̓_�����ȂB�������B���͂��̓_�����Ȃv�ƃ��X�g�ŃX�y���T�[���g������Ă���̂ł����A�����́g�K�́A�M�O�h�ɂǂ�������邩�A�Ƃ��������傽��e�[�}�ɂȂ��Ă��銴���ŁA�ǂ��炩�Ƃ����Ƃ��܂�싅�̘b�͏o�Ă��Ȃ��ł��B �{�X�g���ݏZ�̃X�y���T�[�ł�����A��͂背�b�h�\�b�N�X�̃t�@���B�i���������V�J�S�ݏZ�̂u�E�h�̓J�u�X�̃t�@���ł����B�j�C�炷���Ɂg�I�[���X�^�[�h��g���b�h�E�\�b�N�X���D�������N�h�̃����o�[�̖��O���������ʂ�����ȂǁA�f�B�e�[���ɂ��Ȃ�싅���o�ꂷ��V���[�Y�Ȃ̂ł����A�Ǘ��l�A�僊�[�O�ɂ͂��炫���m�����Ȃ����̂ŁA�w�V���x�Ɂg�V���[���X�E�W���[�h�ɂ܂��L���ȉȔ��u�R���ƌ����Ă�A�W���[�v���o�Ă����̂��������Ċ�ȊO�A����͓ǂݔ����Ă܂��i��j�B�t�F���E�F�C�E�p�[�N�A�R�`�|�D�^�P�b�g�ȂǂƂ����P�ꂪ����Ȃ蓪�ɓ����Ă���Ƃ����̂��A�Ȃɂ��M�����Ȃ��悤�ȁi�j�B �]�k�Ȃ���A�u�g�[�L���[�E�W���C�A���c�v�]�X�Ƃ����Ȕ������������߁A�����ł͂ǂ������Ă������낤�ƕ��D�����N�����Ē��ׂĂ݂���E�E�E�BYokohama Giants�ƂȂ��Ă����̂ɂ͑唚�ł����B �i1975�N�ɂ́u���R�n�}�v�Ƃ����c�͓��{�ɂ͖��������͂��ł����B�j |
![]()
| ��̉h���@�@The Spoiler |
| �h���j�b�N�E�X�^���Y�x���[�@�@Domenic Stansberry |
| �����@�Ђ�� ��@�n���J�����Ƀ~�X�e���A�X�E�v���X |
|
�A�����J�T���ƃN���u�ܐV�l�܌���B �t���[�����X�̐V���L�ҁA�t�����N�E���t�g���͒n���}�C�i�[���[�O���c�z���I�[�N�E���b�h�E�B���O�X����ޒ��A�`�[���̓�ێ胉���f�B�[�E�O�[�`�F�A���C�Y���E����鎖���ɑ�������B������ǂ������t�g���͂₪�āA�E�l�ƕp��������Ύ��������ԁA���c�I�[�i�[�ƒn���c���̗��s�������ނ̂����E�E�E �����ł͕����Ă���A������Ƃ܂��ȃs�b�`���[�͍��g����A��ɂ������グ�Ă��炦�Ȃ��A�Ƃ����`�[��������̂��߁A�Ԉ���Ă��u�����͊��҂��ēǂ܂Ȃ��������������i��j�B�u�Ս��ȏɂ����Ė��Ɗ�]���ׂ��Ă������܂�`�������̂��v�Ƃ̍�҂̃R�����g�����邻���ł����B�S�ʂɃ��A���ȕ��A���܂�~���͂Ȃ��̂ł����A���ĕs�������ɂɊւ�����ߋ�������l�����A�s����\���L�����f�ڂ��悤�Ɩz������㔼���͂Ȃ��Ȃ��ǂ܂�����̂�����܂��B ���t�g������w�Ŗ싅������Ă����Ƃ����ݒ�̂��߂�����̂ł��傤���A�싅�̏�ʂ̕`�ʂ͂��Ȃ蒚�J�ł��B |
![]()
| �����@�@Dead in Center Field |
| �|�[���E�G���O���}���@�@ Paul Engleman |
| ��с@�f ��@�}�K�Ѓ~�X�e���[ |
|
1984�N�x�V�F�C�}�X�܃y�[�p�[�o�b�N�����܍�B
1961�N�āB��̏����̈˗����āA�����҂ɉ�ɏo�����������T��}�[�N�E�����Y���[�̓o�b�g�œ����Ԃ��ꂽ���̂�����B���̗����A�j���[���[�N�E�W�F���c�̃I�[�i�[����˗����������B�`�[���̃z�[�������o�b�^�[�A�}�[�r���E�����X�̓x�[�u�E���[�X�̎��N�ԃz�[�������L�^60�{��j�낤�Ƃ��Ă���̂����A���c���Ƀ����X������ȏ㎎���ɏo���ȂƂ��������͂����̂��Ƃ����E�E�E �o���[�E�{���Y��73�{�̐V�L�^��������͍̂��N�̘b�ł����A���N���O�̃}�O���C�A�ƃ\�[�T������ȃz�[�������������L���ɐV�����Ƃ���ł͂�����̂́A���̑O�ɋL�^���X�V�����l�̂��Ƃ͒m��Ȃ��āB���ׂĂ݂���1961�N�Ƀ��W���[�E�}���X�i�g�W�F���c�h���Ă������烁�b�c�̑I�肩�Ǝv�����烄���L�[�X�̑I��ł����j�̑ł���61�{�ƕ�����܂����B���Ŏ҂Q�l�Ƃ����ݒ�́A�����̃����L�[�X�ł̓}���X�ƃ~�b�L�[�E�}���g�����u�l�l�L���m���v�ƌĂ�Ă������Ƃ̔��f�ł��傤���A�u�[�C���O���������������ƁA�R�~�b�V���i�[�̓��ʌ����ɂ���ĐV�L�^�Ƃ͔F�߂��Ȃ��������ƂȂǁA�A�E�g���C���͂��Ȃ蓖���̏ɑ����Ă���悤�ł��B�i�����̂��Ƃ�`�����u�U�P���v�Ƃ����f�������̂��Ƃ��j���N���[�X�̑��̋L�^���������j�����{���Y�����������Ƃ������b�ł�����A40�N���������ł����[�X���q�͌��݂̂悤�ł��B�������Ƀe�B�h�E�F����������قǃC��������Ă�l�Ԃ͂������Ȃ��Ǝv���܂����ǁi�j�B ���������Γ��{�̋L�^�͂܂��܂����݂ł����ˁB�L�^��j�肻���ȑI�肪�o�Ă����Ƃ��A��x�Ƃ��ΐ푊��̃`�[���̊ē�����Ă�Ȃ�Ă������ȁ[�A�Ɩ��ȂƂ����S�����Ǘ��l�ł��i�j�B ��l���}�[�N�E�����Y���[�͂��ă}�C�i�[���[�O�̓�ێ�ŁA���ڂɎ������̂��߂Ɏ������A�����T��ɂȂ����Ƃ����ݒ�B��l�́u����v�Ō���鏬���ł�����A���܂�i�����������ł͂Ȃ��ł��i�j�B �Ō�܂œW�J�͂�߂܂���ł������A��������ꂽ���A�I���������ƂȂ�������Ȃ��Ƃ������A�]�C���Ȃ��Ƃ������B�G�s���[�O�̈���~�����悤�ȋC�������ł����B �f�B�b�N�E�t�����V�X��ǂ�ł��āA����̉���Ȗ�肪�g�t�B�[���f�B���O�h���Ė�������������邾�낤�ȁ`�ȂǂƎv�������Ƃ������ł����i�j�A���̏����ł̓I�[�i�[�̖����Ɏg���Ă܂����B����܂�t�B�[���f�B���O�̂����I�[�i�[�ł����������ł����ǁE�E�E ����ň����Ă���̂̓s���i�b�v�K�[�����H�����ł����A���̎����w�i�v�Ǖ��x�͍Ăі싅�E�����䂾�����ł��B |
![]()
| �_��ꂽ�僊�[�K�[�@�@Follow the Sharks |
| �E�B���A���E�f�E�^�v���[�@�@William G. Tapply |
| ���c�@�O�� ��@�T���P�C���� |
|
�R�C���̃N���C�A���g�̈�l�A�T���E�t�@���[�i�̑��d�E�i���s���s���ɂȂ����B�d�E�i�̕��͂��ă��b�h�\�b�N�X�̍��������肾�����G�f�B�E�h�i�K�������A�R�N�O�ɃT���̖��Ɨ������đ��q�Ƃ͕ʋ����Ă����B�قǂȂ��R�C���̂��ƂɗU���Ƃ���d�b���������Ă����B�Ȃ����Ɛl�͐g����̔z�B�W�ɃR�C�����w�����Ă����̂����E�E�E �ٌ�m�u���C�f�B�E�R�C���V���[�Y�R��ځi�O����������j�B���Ƃ��ƃX�|�[�c�G���Ɋ�e���Ă����o���̂����҂Ƃ������ƂŁA�G�f�B�E�h�i�K�����߂���f�B�e�[���ɂ͖ڂ�������Ƃ��낪����܂����B��w�R�N�����h���t�g�Ŏw���ł��āA���c�͂P�N��ł��̊Ԃ̎��Ɨ��͋��c�����A�Ȃ�Č_���ׂ��ł��ˁ`�A�A�����J�ł́B �i��l�����܂��C�̂��̂Ƃ��R�̂��̂Ƃ�������Ȃ���w�݊w���̖싅�I��ƌ�������̂��A���Y�Ƃ̕������R�̂悤�ɔF�߂Ă���A�Ƃ����̂ɂ��ڂ�������܂������ǁG�j�B �ƍ߂������~�X�e���[�ł�����A�ꂢ��������Ό��A�Ƃ͂����܂���B���������̏����̏ꍇ�A�㖡�������Ƃ������A�ނ���s�����ɋ߂����̂ŁE�E�E�B�Ɛl�ɐl�����߂��Ⴍ����ɂ��ꂽ��Q�҂��Ō�ɎE����Ă��܂��̂ɑ��āA��l���ɂ͍߈������y�����鎖�����^������B����Ȏ�l���������~�ς���悤�ȂƂ��Ă����悤�ȃ��X�g�ɂ����Ȃ�A�Ō�̔�Q�ғ�l���炢������W�J�ɂ��ł����ł���`�A�Ƃ����C�����Ă��܂��̂ł���B �Ɛl�̓��@���o�Ă��Ȃ��̂������s�ǁB�[�I�Ɍ������Ȃ낤���ǁA�E����̗���𗘗p���ċ��������߂�A�Ƃ������͂ނ��낱�̔Ɛl�A�͂�����E���𗠐��Ă邶��Ȃ��ł����B�����܂ł̂��Ƃ����Ȃ�A�����������@�������Ȃ����ƍl���������Ȃ낤�Ƃ������́B�Ƒ�����Q�ɑ������o��l�������āA�F�l�Ǝv���Ă����Ɛl�ɉ��炩�̔����������Ă�����ׂ����낤���E�E�E ���ƁA�����ȂƂ���ł�����B��̓��m�l�������o�ꂷ���ł����A��l���A��x����Ē����������ŁA�{�����m��Ȃ��̂ɓ��{�l���Ɣ��f���Ă��ł���B�`���C�j�[�Y�ł��R���A���ł��Ȃ��W���p�j�[�Y�Ȃ͉̂��������ȂH�@�Ɠ��m�l�Ƃ��Ă͂߂��Ⴍ����C�ɂȂ�����ł����ǁB |
![]()
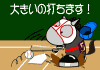
![]()
| �p�[�t�F�N�g�E�u���[�@�@Perfect Blue |
| �{���@�݂䂫�@�@Miyabe Miyuki |
| �n���������� |
|
�Ă̍b�q�����o�ꂪ���҂���Ă��鎄�����c�w�����Z�싅���̃G�[�X�A�������F���E�Q����A�K�\�����������ďĂ���Ă��܂��A�Ƃ����������N�����B����ɏo���킵�����F�̒�i��A�@���T�㎖�����������̉���q�A�����Ę@���Ƃ̈���Ō��x�@���̃}�T�͎����̐^�������n�߂�̂����E�E�E �T�㌢�}�T�̈�l�̂Ō���鏬���B�g�Љ�h�h�ȃe�[�}�����グ���Ă��镪�A��肫��Ȃ��悤�͋C�����͎c��܂������A�M�v���y���őS�̂̃g�[�������邭�i�i��̃L�����N�^�[�������ł��j�A�nj㊴�͈�������܂���ł����B �l�I�ɂ��u�E�E���j�E�E�Ȃ��Ȃ��@���͂����邱�Ƃ͔F�߂邪�v�u�z���g�B�L���J�[�v�݂����Ȃ�炾���v�Ȃ�ĉ�b���������肷��̂�������Ɗ������i�j�B�D�_����ւ̉Ȕ��Ƃ����̂����X���G�ł�����܂����B �w�Ύԁx�Ɂg��̖싅��h���o�Ă���ȂǁA�{������̏����ł͎��X�싅���f�B�e�[���Ɏg���Ă��āA���ꂪ�Ȃ��Ȃ��ǂ�ł��Ċy�����ł��B�i�������������ɏE���Ă݂܂����B�j ����ҋy�ё��̍�i |
![]()
| �݂������@�@Baseball Rhapsody |
| �V���@�^�@�@Tendou Shin |
| �n���������� |
|
���{�V���[�Y��ڑO�ɁA�u�����q�[���[�Y�v�̖����ēj���g�قƂ�ǁh���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����^���[�̓W�]�䂩��A���Ԃ��Ă����x���[�X�ƁA�����Ă����}�X�N�ƁA�g���[�h�}�[�N�̌ՂЂ��������c���ď����Ă��܂����̂��B����R�[�`���Ԃ̗��݂ŁA�V���L�Җ�c�L�͂R�l�̎��L�҂ƂƂ��ɑ{���ɂ̂肾�����A�V���[�Y��O��̏I�������A���x�͑㗝�ē|�R���A���Ă����O�O�������ۂ�Ǝc���ďh�ɂ�������Ă��܂��E�E�E ���{�̃v���싅������ł�����Ȗʔ����������ǂ߂�̂��I�I�@�Ɠǂ݂Ȃ�����삵�������B�i����A�r���Ƃ��m���̏�����ǂゾ�������̂ŁG�j�u��Z���̔z�������܂�������Ă���v�Ƃ̎��o����́g�{�X�h��c�L��A�T����̐V���L�҂��Ȃ��Ȃ������Ă���܂����A�����̕`�ʂ� �u��������Ə��荇���Đ^�փ|�g���Ɨ��Ƃ��A���͐����悭�Ԃ��肠���ĐK�݂��������t�F���X�ۂ܂œ]�������B�S���͓˂����߂ΏR�Ƃ��A�������Ď悤�Ƃ��ē����z���ꂽ�B �@�ŐȂ̂���������Ԃ�ɗ�炸�S������̂������B�ǂ̑Ŏ҂��т��т��o�b�g��U������A����̐��Ԃ̍s�����B��݂̓o�b�g�ƕߎ�̃~�b�g�̊Ԃ̑傫�Ȃ����Ԃɂ�����������z���Ă���悩�����v �Ƃ������q�ŁA�A�i�E���T�[�̐⋩���łȂ��̂��������i�j�B ��z�V�O�ȃX�g�[���[�ł͂���܂����A�ł����o�b�^�[���T�[�h�ɑ���悤�Ȓ������͂Ȃ��A���Ȃǂ��^�l�𖾂������͒ʂ��Ă��āA���S���ēǂ߂܂��B�X�|�[�c�ɐ�����j�����������A�݂����Ȃ��̂������Ƃ������܂�Ă��邠����������ł��ˁB ���I�Ƃ����Ό��I�A���I�łȂ��Ƃ�������قnj��I�łȂ�������Ȃ��V���[�Y�̌����A���\�D���ł��i�j�B ����ҋy�ё��̍�i |
![]()
| �X�^�W�A���@���̎������@�@A Rainbow Over the Stadium |
| ��@�ĊC�@�@Aoi Natsumi |
| �n���������� |
|
�p���_�C�X�E���[�O�̖��N�ʼn��ʋ��c�E���C���C���{�[�Y�B�����p�[�e�B�ɏo�Ȃ���悤�Ȑ����Ń��C���{�[�Y����̊ϋq�ȂɌ���A���������W���̖싅���s�ł��鋅�c�I�[�i�[�E���X�����q�́A�X�^�W�A���Ō���������s�v�c�Ȏ�����N�₩�ɉ����������B�A��Z�ҏW�B ��L���w�݂������x���D���Ȑl�ɂ��E�߂��܂��A�Ƃ����R�s�[�ɂ��Ď�Ɏ�����̂ł����A�ŔɋU��i�V�I�@�ł����B���[���A��������A��D���i�j�B�ŏ�����I�[�i�[���X�����q�̖싅���s�Ԃ肪�킹�Ă���܂����A��b���ƂɈقȂ����A�ϐ풆�̎��������������̑g�ݗ��ĕ����Ȃ�Ƃ����܂��ł��B �t�F�[����z�[���X�`�[���Ƃ������A�߂����Ɍ����Ȃ��悤�ȃV�[��������i�t�F�[���Ȃ�ă��[���A���߂Ēm��܂������A�����ő��ɂ��z���Ȃ���ȁE�E�E�j�B ����`�[���̑I����t�����`���C�Y�ɂ��Ȃ悤�Ȗ����ɂȂ��Ă܂����A���C���{�[�Y�̑I��͂��ׂĐF�̓����������B�O�l�I��܂Łg�u���E���h�Ƃ����Â�悤�Ȃ̂�������Ə��܂��B �ȑO�J�[�v�ɂ��������I�肢�܂����ˁB�B�ꋅ��Ō����z�[��������ł����I��i�NjL�F�ēɂ��Ȃ����Ⴂ�܂����G�j�B ����ɂ��Ă��A���������ւ��������Č��Ȃ��Ă��悭�i�ՌÒ��̕ی��I�G�j�A��������������邱�Ƃ��Ȃ��āA�ʼn��ʂȂ���D���`�[���ɂ͏����z���A�l�^�C�g�����N�����K���l�����ă`�[���Ȃ�āA����Ӗ����z�I�ȋ��c����Ȃ����ƁB�n���ɂ��������ɋ���ɉ����ɋ삯����̂ɁA�Ǝv���Ă��܂����Ǘ��l�ł����i�j�B |
![]()
| ���� |
| ����@�\��@�@Higashino Keigo |
| �u�k���� |
|
�V�˓���E�{�c���u��i���ďt�̑I�����Z�싅���ɏo�ꂵ���J�z���Z�싅���B����܂��Ȃ��A�ߎ�k�����������ƂƂ��Ɏh�E�̂Ŕ��������B�قǂȂ����Đ{�c���h�E���̂Ŕ������ꂽ���A�Ȃ�ƉE�r���ؒf����A���̂̂��̒n�ʂɁu�}�L���E�v�Ƃ�����̕������c����Ă����E�E�E�B �ׂ����Ƃ���ɒ���ꂽ�����������Ă��邵�A�o��l���������Ɛ������l�Ԃ����������邵�A�~�X�e���[�Ƃ��đ�Ϗo���̂悢��i�ł���͔̂F�߂�̂ł����E�E�E�ЂƂ��ɓnj㊴�����������i��j�B�Ƃ����̂��A����Ύ���ł���s�b�`���[�{�c���u�Ɋ���ړ��ł��Ȃ������̂ł��B���̐��i�̋��܋���Ȃ���A���̏������藧���Ȃ��̂͂킩���ł����A���������Ɍ��������邱�Ƃ��͂����肵�����Ă镪�A��������������悤�Ȋ����ŗ]�v�ɐh���B�i���͂ނ���k���ߎ�ɓ���Ă��܂��܂�����B����ȗ��R�ŎE�����Ȃ�Ă���܂肾���āE�E�E�j �ʂɐ��i�̂����o��l���łȂ���Γǂނ̃C���A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�ނ��둽�����܂��Ă邭�炢�̕����D�݂������肷��̂ł����E�E�E�B |
![]()
| ���F�̎c�� |
| ��{�@����@�@Sakamoto Kouichi |
| �u�k���� |
|
�]�ː에����܍�B
���s�X�|�[�c�̋L�Ғ��R�́A�Ă̍b�q�����W���̊��Ƃ��āA�u�M���w���A�K�u�쐼�A���w���̎O�Z�̌��ˁv���咣����B�K�u�쐼�̊ē���Ǝ��w���̊ē^�c�́A���ĐM���w���Ńo�b�e���[��g�ݍb�q���ŗD�������̂����A�s�K�Ȏ��̂���݂��ɔw�������Ă����B���R�͂��Č�����ő�������l�ւ̎�ނ��n�߂邪�A����Ȓ��A�싅�q���̃n���f�t���E����鎖�����N����E�E�E�B �Ƃ����ᔻ�̂���A�Z�~�v���������싅�Z�����N�̂悤�ɒn����\�ɂȂ鍂�Z�싅�̌���A�����ɂ����Ă��Ă��āA�Ƃɂ����X�g���[�g��{�Ő^���������I�@�Ƃ������̂��鏬���ł��B���ꂾ���ɂ����������ł���˂��A�o�����̈�s�ځA ���a�Z�\�l�N�@���@���E�E�E�B �i�P�s�{�ɂȂ����̂����a63�N�X�������炵�傤���Ȃ���ł����ǁG�j �l�I�ɁA���w���̋{�{����̍��オ�C�ɂȂ�܂��B160�L���߂��X�g���[�g�𓊂��āA�������R���g���[�����Q�ŁA���܂��ɓ��������ƂȂ�v���̋��c���ق��Ƃ��܂����ˁB����ς����̔�ь����l�������J��L�������ł��傤���B�v���ɍs����Ɠ��傠����_�����Ⴂ�����ȋC�����邵�E�E�E�B �Ƃ������A�{�{�ȊO�̑I��ɂ܂��������݊���������ł���ˁB�w�p�[�t�F�N�g�E�u���[�x�̌�œǂ肷��ƁA����ē͈�́A�I�肽���̏������ǂ�������肾�����̂�H�@�Ƃ����̂��傢�ɋC�ɂȂ��ł����ǁB |
![]()
| �l���l�̖ڌ��� |
| �L�n�@���`�@�@Arima Yorichika |
| �������� |
|
�s���������Ă����Z�l�^�[�X�̂S�ԑŎҁE�V�C���́A�_�u���w�b�_�[�̑���ɓ�ŐȘA���Œ��ł� �������B�����E���ԂɃq�b�g���������O�ŐȁA�O�ۂ�ڑO�ɂ��ē]�|�A�f�Î��ɉ^�э��܂ꂽ�Ƃ��ɂ͂��łɐ▽���Ă����B��t�͋��S�ǂ̔���Ɣ���B�������X�^���h�ł����ڌ����Ă������R������ �^�O������A�⑰��������Ĉ�̂��i�@��U����B�S�������Ď@��́A�̓��̃R�����G�X�e���[�[���������Ă��邱�Ƃ���L�@�Ӎ܂̐ێ�̉\����F�߂����A����I�Ȍ��ߎ�͌��������Ȃ������E�E�E�B ���a33�N�ɎG���f�ڂ̍�i�B�V�C�����푈�ɍs���Ă����Ƃ����ݒ�ł������肷�邠����A��������40�N�ȏ�O�̍�i�ł��B�ł�10�N���傢�������Ȃ��w�݂������x�Ɣ�ׂĂ��A���炭�Â��悤�Ȋ����ł��ˁB����Ȓ��Ɂu�_����̓���}���邽�߂̐��x�v�Ȃ�Ă����i�{�[�i�X�E�v���[���[�Ƃ����āA�ŏ��̂Q�N�͐�ɂQ�R�֗��Ƃ��Ȃ��Ƃ������́j���o�Ă��邠���肪���U���܂����B�����������ȑ{���ł��Ȃ��̂ɁA�����̌Y������͎g����ȑ{���͎g����A�ɓ��܂łƂ͂����o���ɂ͍s����ŁA�����̌�������Ă���ȂɌ�����������ł��傤���ˁ`�B�V�C�̎��ɑ���^��Ă̂ɍ���������킯�łȂ��A�����ȊO�̉����ł��Ȃ������킯�ł����B �Ƃ����킯�ŁA���{�T���ƃN���u�܂���܂�����i�ł��銄�ɂ́A���܂�~�X�e���Ƃ��Ă̏o���̗ǂ��͊����܂���ł����B���A�V�C�̎��ɂ���ă��M�����[�̃`�����X��݂͂����Ȃ���A�u�V�C�E���v�Ƃ����쎟�����������ŃX�����v�ɗ�������ł��܂�����㎵�Y���i�N��̋L�q���Ȃ���ł����A�����ŁA�u�i�N���ρv�Łu��R�ɏオ���ĎO�N�v�̂����肩��l����26�A7���炢���ȁB�V�C�̔N����o�Ă��Ȃ���ł����A37�A8���ĂƂ��ł��傤�B�j���������čďo������܂ł̃h���}�Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ��ǂ݉���������܂����B�W�X�Ƃ������̂��Ɠ��ŁA���ꂪ�܂���ۓI�ł����ˁB �������Z����ɖ싅�ɔM���������ĕ��Z�����A�v���싅�̃e�X�g�������Ƃ�����A�m���v���`�[����10���N���s�b�`���[������Ă����Ƃ����o���̍�҂������i���ҋ߉e���s�b�`���[�p�ł���I�j�A�싅�Ɋւ���L�q�͐��m���Ǝv���̂ł����A�ꃖ���C�ɂȂ�Ƃ��낪�B�����̏I�ՂɁA�V���ɍڂ�������L���ƐV�C�̑Ō����тƂ̊�Ȉ�v�A�ĂȘb���łĂ����ł����E�E�E�B���́[�A���̑I��ɂ͐V���ȊO�̃X�����v�v��������������ł��傤���H�@����s�b�`���[�̑����Ƃ����H ���Ȃ݂ɁA�w���w�Ɨ��j�ƃ~�X�e���[�x�i�R���^�։ؖ[�j�Ƃ����{�ɂ��A�{�����ɏo�Ă���g�o�h�Ƃ����̂̓p���`�I���Ƃ����_��̂��Ƃ������ł��B�l�̂ɑ��镛��p���傫���Ƃ��Ō��݂͐����E�̔��E�g�p���ׂċւ����Ă���Ƃ̂��Ƃł����B�R�����G�X�e���[�[�Ƃ����Ǝv���o���̂���̃T�����Ȃ̂ł����ǁA��������Ƃ��Ƃ͎E���܂Ƃ��ĊJ�����ꂽ���̂ȂƂ��B ���̍�҂ɂ͖싅�q�����������w�����y�i���g�x�Ƃ�����i�����邻���ł��B��́u�����������v���N�����̂͂��̍�i�̔��\����10�N����ŁA�t�Ƀl�[�~���O�̃q���g�ɂȂ����̂������Ȃ̂ŔO�̂��߁B |
![]()