|
|
|
|
| Baseball | ||
| 《女性選手編》 | 《野球ミステリ編》 | 《その他》 | |
|---|---|---|---|
|
ポール・R・ロスワイラー 『赤毛のサウスポー』 バーバラ・グレゴリッチ 『彼女はスーパー・ルーキー』 梅田 香子 『勝利投手』 仁川 高丸 『こまんたれぶー』 |
リチャード・ローゼン 『ストライク・スリーで殺される』 ロバート・B・パーカー 『失投』 ドメニック・スタンズベリー 『九回裏の栄光』 ポール・エングルマン 『死球』 ウィリアム・G・タプリー 『狙われた大リーガー』 |
宮部 みゆき 『パーフェクト・ブルー』 天藤 真 『鈍い球音』 青井 夏海 『スタジアム 虹の事件簿』 東野 圭吾 『魔球』 坂本 光一 『白色の残像』 有馬 頼義 『四万人の目撃者』 戸松 淳矩 『名探偵は九回裏に謎を解く』 準備中 |
原 尞 『さらば長き眠り』 マイクル・シャーラ 『最後の一球』 バウトン&アジノフ 『ストライク・ゾーン』 有栖川有栖 ほか 『新本格猛虎会の冒険』 ローレンス・ブロック 『泥棒は野球カードを集める』 カーター・ディクスン 『墓場貸します』 |
|
|
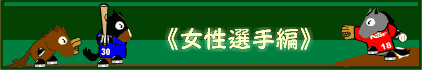
| 赤毛のサウスポー The Sensuous Southpaw | ||
| ポール・R・ロスワイラー Paul R. Rothweiler | ||
| 稲葉 明雄 訳 集英社文庫 | ||
| レッド・ウォーカー | ピッチャー(左投左打) | ポートランド・ビーバーズ |
|
元大リーグピッチャーの父から英才教育を受けてきた主人公が、父の旧友が監督を務める球団に入団。コミッショナーの猛反対、相手チームの試合放棄、チームメイトの反発等々に遭いながらも、ナックルとスクリュー・ボールを駆使してリリーフ・ピッチャーとして大活躍。ナショナル・リーグのお荷物だったチームも快進撃を始めるが・・・ 元々スポーツライターだった人の書いた小説だそうで、試合の描写などはなるほど上手いです。とにかく面白い小説であることは間違いないと思うのですが、出場停止処分を引き起こしてしまう事件が事件だったり、と全体のトーンが多分に少年マンガ的なあたり(なにせ題名からして“官能的なサウスポー”であるくらいですから)、好みが分かれるかもしれません。(“PLAYBOY BOOKS”って、『プレイボーイ』に連載されてた小説か何かなんでしょうか?) 日本人女性選手の登場する続編があるらしいですが、管理人未読です。 | ||
![]()
| 彼女はスーパー・ルーキー She's on first | ||
| バーバラ・グレゴリッチ Barbara Gregorich | ||
| 浜野 サトル 訳 ハヤカワ文庫 | ||
| リンダ・サンシャイン | ショートストップ(右投右打) | シカゴ・イーグルス |
|
リトルリーグに始まって大学まで野球を続けた主人公が、シカゴ・イーグルスにスカウトされ、2A、3Aを経て大リーグに昇格。万年4位だったイーグルスの快進撃の立役者となるが・・・ チームメイト、マスコミその他にさんざん苦労させられるのもお約束のようです(笑)。 個人的にここに挙げた小説の中では一押しだと思う小説。 人生ドラマ仕立てではありますが、テンポのよい文章にユーモアが効いていて、辛気くささがないのがお気に入り。 2Aの監督に「サン“ビーム”」と呼ばれた次には3Aの監督に「“ムーン”シャイン」と呼ばれるといった具合に、なかなか笑わせてくれますし、野球に関しても結構詳しいです。 ニール・ヴァンターリンの辛辣にしてウイットのきいたコラムも一読の価値あり。 「同チームの中堅手でありスラッガーであるウォリー・シチパノゾースキーは丸くて白く見えるボールが来ればだぼはぜのようにくいつく。ホーム・プレートめがけて飛んでくるボールはどれにしても白くて丸く見えるのだから、ゾースキーはやみくもにバットを振りまわし、あげくは空気を打ってしまうのである。」 「この暴れ馬は二十世紀への出走をかたくなに拒んでいる。自分の馬はたくさんの部品を持っているが、肝心の思考をつかさどる部分の大きさが蠅たたき程度でしかないということに、モウァリンスキー氏も遅まきながら気づきはじめたらしい」 といった具合です(こんな記事読ませてくれる新聞あったら、絶対とるのに;笑)。 | ||
![]()
| 勝利投手 | ||
| 梅田 香子 Umeda Youko | ||
| 河出文庫 | ||
| 国政 克美 | ピッチャー(左投左打) | 中日ドラゴンズ |
|
昭和61年度の文藝賞佳作。 ドラゴンズの選手が主人公でありながら、全編ほぼこれ広島弁、お好み焼きも出てくるのに(いくら主人公及びバッテリーを組むキャッチャーがともに広島出身とはいえ)、名古屋弁もみそ煮込みも出てこないのが少々不思議な小説。 (そりゃまあ「オレの体にはドラゴンズ・ブルーの青い血が流れている」とのたもうたとかいう人にカープのユニフォームは着せられないでしょうけれども・・・って思ってたらそうでもないみたい。2001.12.20追記) 岡山出身の星野監督が名古屋弁を操れるのかどうかは寡聞にして知りませんが、野次の一つくらいが「タワケ!」であってもいいような気はするのですけど。 導入部など、どう真相を小出しにしていくのかな、というミステリー的な面白さがありますし、なかなか読ませるストーリーなのですが、なんとなくきれいにまとめすぎ、という感じはあります。 上記二作の主人公とくらべて、チーム内での人間関係には全く苦労させられている様子がないのはやっぱり父上様(=広岡監督。一応名前は変えてありますが)のご威光があるせいかしら、などと勘ぐりたくなってしまったり(苦笑)。 実在の人物を登場させている実名小説であるだけに(完全に架空の野球関係者はキャッチャー及川だけ? ・・・カープの元監督を連想しなくもないんだけど、恋愛小説の主役をはれるようなキャラかい? ってとこでぴんとこない(笑)。)、あまり性格悪くは書けなかったということなのでしょうけど。 | ||
![]()
| こまんたれぶー Comment Allez-Vous? |
| 仁川 高丸 Nigawa Takamaru |
| 角川書店 |
|
「元気な女の子というと、どうしていつも「野球をやってる女の子」になるのかふしぎです。」と斎藤美奈子さんが書いてらしたけど(『読者は踊る』/文春文庫)、そのでんで行くと、このお話の主人公は多分とっても珍しい。何せ、「好きでもなんでもない野球を二年間もしていた」女の子なのだ。 佐倉嬢。小学5年生。「成就寺ジャングルズ」の敗戦処理投手で、打率とデッドボール投球数と乱闘キン蹴りの裏三冠王。そして、話は「突然、引退の日が来た。」から始まる。朝起きたら初潮を迎えていたから。 なんなの、その生理がくると引退って。それにその敗戦処理投手って??? そもそもはチームの人数が規定に満たなくなったということで、女の子を入団させることになったそうなのだけれど、町内会長一家がその事情を説明に来る場面が何とも笑える。これは窮余の一策なのだから、野球の純粋さを保つために初潮を迎えたら退団してもらいたいとか、レギュラー出場は避けたいから敗戦処理投手に(花形ポジションのピッチャーをやれるんだから文句ないだろと言わんばかり)とか、参加してもらいに来てるにしては言い草が実に手前勝手なのだ。そりゃあ「要するに、野球がしたいのはあなた達で、子供達はつきあわされてるだけなんですね」とママもツッコむというものですよ。 「子供会会長のハゲの長男は帽子の庇に「甲子園」と書いているタイプで、だから投手志望でありながら決してチームでは投げなかった。リーグは軟球だし、身体が出来上がる前の小学生時代にピッチングを覚えてはいけない、という父親つまりハゲの教えを忠実に守っていたのだった。」と続くに到って思いっきり笑いこけてしまった。 この「あたし」の一人称語りがなんとも小気味良い。何しろ「母子家庭」とからかう男子どもにやりかえすくだりが「本当なら、九州にある県を全部言えるようになってから口をきけと言いたかったけれど、いじめはいけないのだ」なのだ。 読んでるうちに、『ぼくは勉強ができない』の時田秀美くんがむしろ優等生に思えてくるから怖い(笑)。もっとも考えてみれば、あちらは、どういう事情があってか教科書には載らなかったとはいえ、二三行削れば河合塾の模試には使える文章だったんですよね。こちらはどう細工しても無理だろうからなあ。 というわけで、彼女の一人称語りのみで話が進む、第二章の「敗戦投手(エース)」まではとにかくめっぽう面白い。全編この調子で進めば、多少人は選ぶだろうけど面白いよ、と勧められる本だっただろうと思うのだけれど、いかんせん、ここから先が、今までとは比較にならんほど強力に人を選ぶ展開なんである。 そりゃあまあ、「もうあたしは、このまま一生ずっと女の子なのだ。昨日までなら、まだ胸もペチャンコだし、ふとしたきっかけで、男の子にも女の子にも変身できるような気がしていたのに。」 「もうこの先ずっと女だと決まってしまったあたしは男のユニフォームを着てはいけないのだ。もしユニフォームを着続けたらあたしはオナベになるのだ。」という、何というか、苛立ちが、この本のテーマなのだろうから、ペニスマン、ホモ、オナベにオカマ、とエキセントリックな人間の登場のオンパレードになるのもそう不自然ではないんだろうけど、拒絶反応を起こす人もけっこういるんじゃないかと。正直言って、私自身が読みながら何回か「うっ」と思いましたし。 それにしても、嬢というとんでもない本名と、ママが風呂敷に凝っているという設定が、最後でああいう風に効いてくるとは思わなかったです。 |
![]()
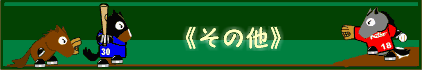
| さらば長き眠り |
| 原 尞 Hara Ryo |
| ハヤカワ文庫JA |
|
400日ぶりに事務所に戻った沢崎を待っていたのは一人の浮浪者だった。事務所を訪ねてきた魚住と名乗る男に、事務所の人が戻ってきたら連絡してくれるよう頼まれたのだという。しかしなかなか連絡のとれないまま、沢崎は魚住について調べ始める。彼は11年前甲子園に出場した高校野球の選手だった。準々決勝の試合で八百長の嫌疑をかけられ、無罪が認められたものの、それが発表される前に姉が自殺。どうやら姉の自殺について疑問を抱いているらしかった・・・ 私立探偵沢崎シリーズ長編第3作目。錦織警部の風貌が「旧ライオンズの豊田泰光に見違えるほどよく似て」(『そして夜は甦る』より)いるという設定、そしてこれもチャンドラーに倣ったのかもしれませんが、地の文にしばしば登場する野球を使った比喩。ついつい野球の絡むストーリーの登場を期待しながらシリーズを読み進んでいたため、元高校野球選手の登場する作品なのを喜んだ私(笑)。 私立探偵である沢崎は、依頼人の依頼を受けてから調査にかかります。が、この作品では何と、全体の1/5を読み終えないと「依頼人」に会えません。しかも「調査を、して……ください」と言ってもらうまでにさらにその倍近くかかるという・・・。「ようやく探偵に復帰した思いだった」という独白にになるのももっともかと(笑)。地道な調査からだんだん意外な事実が浮かび上がってくる、という展開は今までどおりですが。 チャンドラーの『さらば愛しき女よ』『長いお別れ』『大いなる眠り』を足して3で割ったような題名である本作、エッセイ集『ミステリオーソ』によると、『長いお別れ』のような主人公(探偵)と登場人物との間の“友情物語”を書こうと試みた作品なのだそうです。実は、『長いお別れ』は、個人的にきちんと話をのみこめなかった作品でした。具体的にこの謎を追っている、という点がはっきりしないような気がしたこともありますが、テリー・レノックスってマーロウがそこまで思い入れるような魅力ある人物か? というあたりでひっかかってしまったのですね。 一方、初めて見た時の印象を 野手たちの三つのエラーで満塁のピンチに立たされているのに、次の打者を凡打に討ち取って零点に押さえることだけに集中しているマウンドのピッチャーのようだった と描写される魚住彰。本来外野手でありながら、急遽マウンドに引っ張り上げられた甲子園で三試合連続の完投勝利をあげる度胸の良さ、そして自分を憐れむような余計な性格を持ち合わせない潔さ、沢崎が思い入れるのももっとも、と思わせる、なかなかに魅力的な人物なのです。 明かされる真相は『私が殺した少女』に似てあまり後味のいいものではないのですが、印象は断然この作品の方が良かったのは、やはり慶彦少年と魚住彰の差というものでしょう。「おれからの餞別だ」というラストシーンが最高に決まっている、というのもありますが(笑)。 さて、沢崎シリーズの第一期完結、ということでなのか、今までの事件で関わってきた人間たちがかなりの人数登場してたりします(本筋には関係ないところで出てきた人もいましたっけ)。そして沢崎と錦織警部や清和会の橋爪とのつきあいのきっかけとなった、元パートナー渡辺の起こした事件にもある決着が。 あ、もっとも片付いてない謎もありました。『私が殺した少女』にも出てきた「この世で一つだけ暗記している女の電話番号」って・・・? そして相良はちゃんと5万円返してもらえたんでしょうか(笑;それにしてもヤクザのベンツをタクシー代わりに使うって・・・)。 全くの余談です、著者紹介のところでこの作品が「畢生の大作」と書かれているのが気になってしょうがないのは私だけでしょうか? 「渾身の大作」ならともかく、何か絶筆みたいで縁起でもないと思っちゃうんですけど・・・ |
![]()
| 最後の一球 For Love of the Game |
| マイクル・シャーラ Michael Shaara |
| 朝倉 久志 訳 ハヤカワ文庫 |
|
ビリー・チャペル、37歳。独身だがこの4年間は出版社に務める美女キャロルと交際中。大リーグで17年間チームのエースとして投げ続け、野球殿堂入りが確実視されているが、最近は最下位に低迷するチーム状況もあり、疲れの出てくる試合の中盤で打ち込まれるケースが増えてきていた。シーズン最終登板になるヤンキース戦をむかえる朝、彼は思いもよらぬ話を聞かされる・・・ 恋愛小説という面もあるためか、とにかく甘い! ひとえに大甘の甘口、という印象です。それでもなんとか“美しい物語”が成り立っているあたり、さすがアメリカ人と言うべきか。これが同年輩でも日本プロ野球の選手だったりしたら(それにしても37歳とは思えない主人公ですが)、全然違うストーリーにしないと収拾つかなくなるでしょうね。ニール・ダイヤモンドをバックにしょって投げるのが様になる選手を思いつけないですし(笑)。 それにしても、登板前にショックのダブルパンチをくらってからこの快投って・・・その辺が大投手たる所以なんでしょうか? 仮にも恋人という立場にありながら、よりによって今日これから投げるっていう日の朝にそんな話を持ち出さんでもよかろうに、という気がして仕方がないんですけど。 というわけで、リアリティには少々問題ありという感じですが、昨今のFA大全盛の状況をみれば、こういう古き良き時代の話(71年か72年頃を想定しているらしい)が受けたのも分かる気がします。 パーカーだって『儀式』で「ウォール・ストリート・ジャーナルを 読んでいるみたいだ」とスペンサーに言わせてますし・・・ しかし、オーバースローとサイドスローを織り交ぜたピッチングスタイル、というのはなかなか誘惑的ですね。見たことないので一度見てみたい(笑)。 |
![]()
| ストライク・ゾーン Strike Zone |
| ジム・バウトン&エリオット・アジノフ Jim Bouton & Eliot Asinof |
| 村上 広基 訳 文藝春秋 |
|
シカゴ・カブスのピッチャー、サム・ウォード。複数のチームを転々とし、シーズン終盤にメジャーに上がってきたばかりのナックルボール・ピッチャーである。そんなサムに、これに勝てばシカゴ・カブスの優勝が決まるという最終戦での先発が言い渡された。他のピッチャーが故障や不調のため、いきなり声がかかったのだ。 ブラッシュボールを使えというピッチング・コーチに「おれにとって度胸はなにかときかれたら、試合後に打者と駐車場で待ち合わせて、こちらの喉元にボールを投げさせることです」と言い返してしまうサムといい、ホームチーム贔屓の判定をしないためになかなか大リーグに上がれなかったアーニーといい、要領よく振る舞えずに家族に負担をかけてしまうあたりのよく似ていること。それぞれの事情がよく書き込まれていて、不器用な男二人の物語としてもなかなか読み応えがありました。 大リーグには疎いのでよく分からないんですが、まえがきを読むところでは、著者のバウトンは元選手のようです。登場する選手も実在の選手らしく、どうやら実名小説のようなのですが、最初あんまりピンときませんでした。だってサミー・ソーサが8番バッターなんですもん・・・(笑)。 余談ですが、「ディノサウルス」って普通に「恐竜」の訳でいいんじゃないでしょうか。そんな恐竜いたっけ、と少々悩んでしまいましたよ(笑)。 |
![]()
| 新本格猛虎会の冒険 |
| 有栖川有栖 ほか |
| 東京創元社 |
|
初版が出たのが2003年3月28日。とはいえまめに新刊をチェックする習慣のない私のこと、この本の存在を知った時にはすっかり阪神フィーバー真っ最中。名古屋を裏切った監督(と言って悪けりゃ“人を二階に上げて梯子に火かけた”ですか?)に広島を裏切った4番打者を擁するチームが首位を独走の状況では、興味はあっても読む気になれるわけもなく。おまけにトドメの一打を喰らったのが贔屓のピッチャーとあっては、縁もゆかりも全くないことは無いけれど、日本シリーズでは力一杯ホークスがんばれにもなるというもので。ともあれ、これでちょっぴり溜飲を下げたので(直後のドタバタで大分冷めたけど)、やっとシーズンオフの間に読んでみよかという気になったのでありました(笑)。 阪神タイガースなミステリアンソロジーということで、覚悟(笑)はして読み始めたのだけれど、逢坂剛の序文でさっそくつっかえました。あのね、「広島の金本のように、迷わず阪神に来てくれる根性のある選手」って、考えなしに喋るわ結論は引き延ばしまくるわ、優柔不断が服着て歩いてるような言動で、カープファンを果てしなくイライラさせまくったことを知らんのかい(実際にFA宣言に到った時、私の周囲で虚心にショックを受けてたの、ベイスターズファンの方お一人でした)。これが阪神ファンの贔屓目だと明らかに分かる文脈で出てくるなら苦笑ですませるのだけど、事情を知らずに読んだら信じちゃいそうだなあ、と思ったらついマジになってしまいましたよ。気を取り直して本編行こ。 「五人の王と昇天する男達の謎」(北村薫) シェーのポーズはどの選手を意味するか? というダイイングメッセージの話。個人的には本筋の謎より「五人の王」の真相がめちゃ受けました。確かに一度聞いたら忘れられない(笑)。メッセージが意味する選手というのも、推理というよりはむしろなぞなぞの答えみたいな感じで、それはそれで楽しかったですが。ところで大下二塁手って、あの「鬼軍曹」ですよね? 「一九八五年の言霊」(小森健太朗) 読み始めてすぐにオチが分かってしまった、というか、最後これでオトすとは思わなかったです。50周年の話は「日本プロ野球50年」の切手絡みで似たような話を聞きましたっけ。 「黄昏の阪神タイガース」(E・D・ホック) 何か、誘拐事件の捜査が日本っぽくないんですよね。それに、第二のベーブ・ルースを真面目に目指す奴なんか絶対いてへん(笑)! それよりホックがなんでこんな企画に参加したかの方がよっぽどミステリーだ・・・ 「虎に捧げる密室」(白峰良介) 動機は分からなくもないなあと思ってしまうところがなんとも(苦笑)。ちょっと苦しいなあ、と思うのが目撃者を警官にしていること。かりにもプロなんだから気付きませんか? 「阪神タイガース共犯事件」(いしいひさいち) アリバイ・トリックをこういう風にギャグにするとは・・・(笑)。 「甲子園騒動」(黒崎緑) 個人的にはこれが一押し。ボケ・ホームズ&ツッコミ・ワトソンの推理漫才、初めてお目にかかりましたが、最初っから最後まで笑いっぱなしでした。事件自体も『スタジアム 虹の事件簿』風の趣があって、なかなかきちんとしています。ただ、阪神ファンじゃない私でも、掛布、真弓、田尾、フィルダー、みんな覚えてるんですよね~(さすがにカークランドは知らないけど、木枯らし紋次郎のヒントになった選手というのを聞いたことはあるし)。一人くらい、ファンしか覚えてないよ! な選手が出てきたら、もっと笑えたんじゃないかと・・・(広島だったら「代走・今井」とか;笑)。 「猛虎館の惨劇」(有栖川有栖) ご近所名物虎屋敷で起きた首なし殺人のお話。TとHだからなんとか建物になってるんで、曲線の入るCとDとかYとGじゃ建物にするのは相当苦しいよなあ、といらんこと考えてしまった私。犯人が首を切らなければならなかった理由は意外にも納得できるものでしたが、最後のオチがちょっと余計な気も。 既読本のリストを見てもらえばお分かりでしょうが、私、新本格と付くミステリはまず読まない人間なので、その点でも覚悟のいる本だったのですが、存外楽しく読めました。執筆者一同がどの程度今年の優勝を信じていたかは謎ですが、どこだったか書評サイトで、うちのチームも「新本格○○会の冒険」を出したら優勝できるかも、というコメントを拝見しまして、それもいいかも、とちょっぴり思ってしまったり(笑)。しかし、あっという間に話が古くなるのが野球ネタの宿命とはいえ、まだ1年経ってないというのに、新庄は日本に帰ってくるわ、名前を口に出せない方が本当に監督になっちゃうわ、気象衛星の性能が落ちて天気予報はよく外れるようになるわ(これは野球じゃないか)、えらい時間の流れを感じてしまいました。 それにしても、デトロイトの虎チームが正しくはタイガーズだったとは知らなんだ。 |
![]()
| 泥棒は野球カードを集める The Burglar Who Traded Ted Williams |
| ローレンス・ブロック Lawrence Block |
| 田口 俊樹 訳 ハヤカワ・ポケットミステリ |
|
泥棒稼業の隠れ蓑のつもりで始めた古本屋だったが、いまではすっかり本屋の主人としてまっとうな暮らしを送っているバーニイ。しかし、店の新しい大家に家賃の値上げを通告され、その値上がり分を捻出するためにやむなく泥棒稼業を復活させることになった。首尾良くとある高級アパートメントに忍び込んだまではよかったが、浴室で素っ裸の男の死体を発見。そのうえ、全く身に覚えのない高価な野球カード・コレクションを盗んだ疑いまでかけられてしまった・・・ ユーモア・ミステリー、泥棒バーニイ・シリーズ第6作目。「ゴルディロックスと3匹のくま」(昔に読んだ記憶がありますね。確か女の子の名前が“きんきらこ”という訳でした)、キンジー・ミルホーンシリーズ、ココシリーズをパロディにしたバーニイとキャロリンのやりとりがなかなか笑わせてくれます。丸めたサンドイッチの包み紙に飛びつくスピードは大リーグのショート顔負け、というシャム猫ならぬマンクスのラッフルズがシリーズ初登場。野球カードがメインの話ですから、ベーブ・ルース、テッド・ウィリアムズら往年の名選手らのエピソードも結構楽しめます。 個人的にはチャルマーズのカードの話が面白かったです。 1950年にチャルマーズ・マスタード社が販売促進キャンペーンの為に作ったテッド・ウィリアムズ一人で40枚(!)のセット。出し惜しみして番号の高いカードは終わり近くまで出さなかったため、毎回同じカードしかもらえないのに子供が飽き、マスタードを買わされるのに親がうんざりした結果、40枚揃ったセットは大変珍しくなってしまったにもかかわらず、白黒写真で印刷もお粗末なため、収集家には人気が無く、目の玉が飛び出すような値段もつかないというカードなのだとか。あんまりせこいことすると・・・って証明ですね(笑)。 |
![]()
| 墓場貸します A Graveyard To Let |
| カーター・ディクスン Carter Dickson |
| 斎藤 数衛 訳 ハヤカワ・ミステリ文庫 |
|
ニューヨーク有数の資産家マニングは、みんなの前から姿を消してみせる、とメリヴェール卿ら一同に対して挑戦した。マニング財団からの使い込みが発覚し、愛人とともに姿をくらますのだという。 「クリケットのファンが野球を間延びしてると言うとはね」 「クリケットはそもそも間延びするようにできているのよ。でも、野球はちがうわ。それなのにいつも間延びしてしまうの。ピッチャーなんかボールを投げるまえに何世代も人が生き死にするぐらいねばるし、ほかのみんなも何をするにもねばる、ねばる」 (中略) 「ショートストップのことだ。内野でセカンドとサードのあいだにあるポジションだけれど、だったらセカンドとサードっていうのはなんなのなんて、お願いだから訊かないでくれよな。まだ小さかった頃、二ューヨーク・ジャイアンツの本拠地、ポロ・グラウンドでのジャイアンツ戦で彼を見たのを覚えてる。ずんぐりして、脚なんかガニ股みたいに見えたけど、全盛期には俊足で鳴らし、盗塁がうまかったんだ」 「塁を盗むなんて。あなたたちアメリカ人って、そんな野球の塁ぐらいのことでも正々堂々とできないのよね」 なんて会話が楽しめたのに味をしめて読み出したカー(ディクスン)作品。この作品では正直ストーリーそっちのけで 「野球をするメリヴェール卿!」を楽しませてもらいました(笑)。 マニングの息子ボブに誘われて草野球の練習に顔を出したメリヴェール卿が元マイナーリーガーのピッチャーから柵越えを連発するシーンがあるんです。昔大リーグの選手と一緒に練習をしたことがあって、契約を提示されたこともあったのだとか。守備はひどく、ベースの上では金縛り同然だったらしいですが・・・(笑)。 この柵越えが事件の解決に一役かってるあたりがうまいです。 |
![]()