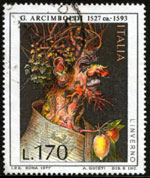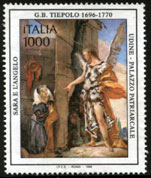Art Gallery
《荘厳の聖母(オニサンティの聖母)》
1305〜10年頃 板 テンペラ 325×204cm フィレンツェ・ウフィツィ美術館所蔵
1966.10.20 イタリア発行
ジョット Giotto di Bondone 1266-1337
イタリアの画家、建築家。フィレンツェの近郊に生まれ、主としてアッシジ、フィレンツェ、ローマ等で活躍。羊飼いをしていた彼をチマブエが見つけて弟子にしたとバザーリが伝えているが、初期の経歴は不明。純造形的にも、図像学的にも、イタリア絵画をビザンツ文化の伝統から解放した最初の人として、イタリア絵画史上極めて重要である。従来の図式的で生硬な人物に初めて人間的な息吹きを与え、また平面的な背景の描写に現実的な空間感覚を導入し、次代のルネサンス絵画の開花を促した。作風にはローマ派の絵画やイタリア・ゴシック彫刻の影響が見える。最も確実視される作品はパドヴァのスクロベニ礼拝堂内の『キリストと聖母の生涯』連作フレスコ画。アッシジの聖フランチェスコ聖堂の《聖フランチェスコ伝》連作が彼の作として知られているが、賛否論争が絶えない。1334年から建築家としてサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂の鐘塔に着手したが、業半ばで死去した。
1995.11.2 アメリカ発行
《施しをする聖ステファヌス》
フラ・アンジェリコ Fra Angelico 1387/40-1455
イタリアの画家。本名グイド・ディ・ピエトロGuido di Pietro。フィレンツェ北郊フィエゾレのドミニコ会修道院に入り修道士となり、1449年には同院の修道院長となる。14世紀絵画の宗教的伝統と1420年代フィレンツェの新絵画運動とを結合した新宗教画様式を確立。1438年サン・マルコ修道院再建のおり、その装飾にあたった。ゴシック趣味を残しながら、明るい色彩と明快な画面構成をもち、宗教的感情にあふれる宗教画を描いたほか、J.ポロックの〈ドリップ・ペインティング〉を思わせる異様な作品もある。
1955.11.26 イタリア発行
リッピ Fra Filippo Lippi 1406-1469
イタリアの画家。早くから孤児となり、伯母に育てられ、1421年サンタ・マリア・デル・カルミネ修道会に入会。初期の作品には同修道会のフレスコ画の作者マサッチオの影響が見られ、1440年代の始めごろからはフラ・アンジェリコの影響を受けるようになる。崇高な中に人間的な感情を盛り込んだ画風で、多くの〈聖母子像〉やプラト聖堂壁画などの作品がある。奔放な性格から詐欺事件を起こしたり、特認を得て修道女ルクレツィアと結婚しフィリピーノをもうけるなど逸話が多い。
1984.10.30 アメリカ発行
《プリマヴェーラ(春)》 (部分)
1482年頃 テンペラ 203×314cm フィレンツェ・ウフィツィ美術館所蔵
ボッティチェリ Sandro Botticelli 1445-1510
初期イタリア・ルネサンスの代表的画家。本名Alessandro di Mariano dei Filipepi。フィレンツェ生れ。フィリッポ・リッピに師事したといわれる。早くからメディチ家を中心とする人文主義者たちに迎えられ、1470年代にはメディチ家の人々や自分も画中に配した『三王礼拝図』や新プラトン派の影響の見られる『春』などを描いた。1481年から翌年にかけてバチカン宮殿の装飾のためにローマに滞在。その後は写実にとらわれない美しい線描と優麗な色彩を特徴とする詩的で装飾的な画風に到達、『ヴィーナスの誕生』や『聖告』などを描いた。ダンテの『神曲』に描いたさし絵は線描家としての面目をよく表している。晩年はサヴォナローラに帰依し、神秘主義的な傾向を強め、1501年の『神秘の降誕』を最後に絵筆を絶った。
1995.10.24 モナコ発行
ペルジーノ Perugino 1450?-1523
イタリアの初期ウンブリア派の代表的画家。本名Pietro di Cristoforo Vannucci。初めピエロ・デラ・フランチェスカに学び、のちフィレンツェでベロッキオに師事、相弟子にレオナルド・ダ・ヴィンチがいた。1481年にボティチェリらとともにシスティーナ礼拝堂の装飾を制作した。その後バチカン宮殿やイザベッラ・デステのための作品を制作し、晩年は故郷ペルージャに引退した。フィレンツェ派のモニュメンタルな様式とウンブリア派の親しみやすい様式とを融合した画風で、明快な画面構成と洗練された色彩美、背景に用いられた風景描写の美しさに定評がある。
1986.10.24 アメリカ発行
《システィーナの聖母》
ドレスデン国立絵画館所蔵
1983.11.10 イタリア発行
《ガラテイアの勝利》
1511年 ファルネジーナ邸
1970.4.6 イタリア発行
ラファエロ Raffaello Santi 1483-1520
盛期ルネサンスの古典的芸術を完成した三大芸術家の一人。画家であった父に学び、 1500年頃ペルジーノの工房に入ったとされる。1504年にフィレンツェに行き、ミケランジェロ、ダ・ビンチなどの影響を受けながら『テンピ家の聖母』などを描き名声を得た。1508年にローマに移り、法王ユリウス2世のためにバチカン宮殿の〈書名の間〉に『アテネの学堂』『パルナッソス』などの傑作を描いた。壁画の他には多くの聖母像があり、肖像画にも傑作を残している。
《羊飼いの礼拝》
ジョルジョーネ Giorgione 1477?-1510
ヴェネツィアにおける盛期ルネサンス様式の創始者。生涯については不明の点が多く、確証ある真作も少ない。主として個人の収集家のために油絵を制作。従来の鋭く堅い描線やアクセントの強い彩色を排し、柔らかい肉付けと調和的な色調を創出したのが最大の功績。美しく、繊細に描写した自然風景を裸体や着衣の人物像の背後に置き、詩的で夢幻的な情趣をかもし出した。代表作『眠れるビーナス』、『テンペスタ(嵐)』など。
1971.11.10 アメリカ発行
《フローラ》
1515年頃 79×63cm フィレンツェ・ウフィツィ美術館所蔵
ティツィアーノ Tiziano Vecellio 1490?-1576
イタリア盛期ルネサンスのヴェネツィア派を代表する画家。9歳の時ヴェネツィアに出てモザイク師の門に入り、のちジョバンニ・ベリーニに学び、ジョルジョーネの影響を受けた。1515年頃から『聖愛と俗愛』、『フローラ』などで次第に独自の画風を形成、『聖母被昇天』、『バッカスとアリアドネ』、『ペーザロ家の聖母』などで盛期ルネサンスの愛と自然への豊かな詩情を表現。ほかに『ダナエ』、『ウルビノのビーナス』や『カール5世の騎馬像』などがある。華麗な色彩を用いて風俗画・風景画的要素の多い歴史画、宗教画、神話画を描き、肖像画にも傑作を残した。初期の抒情的表現は、中期以後、力強い動感と劇的な迫力に富む表現に到達し、ヴェネツィア派の画風の頂点を極めるとともに、ルーベンス、ベラスケスなどにも影響を与えた。
1976.9.15 イタリア発行
《冬》
1563年 66.6×50.5cm ウィーン美術史美術館
アルチンボルト Giuseppe Arcimboldo 1527/30-1593
イタリアの画家。ミラノ生れ。1562年プラハに移り、1587年までハプスブルク家のルドルフ2世の宮廷画家として仕え、伯爵に叙せられた。マニエリスムの画家の中でもきわめて特異な地位を占める。代表作『四季』の連作や『水』にみられるように、主題ごとに花,果実,動物等を寄木細工のように集めて人物像(頭部または全身)にまとめあげた作品が多く、20世紀に入りその怪奇性、幻想性からシュルレアリスムの先駆として評価された。
1977.9.5 イタリア発行
《サラと天使》
1966.10.20 イタリア発行
ティエポロ Giovanni Battista Tiepolo 1696-1770
ルネサンスから続いたヴェネツィア画派の最後を飾る大家。作品は、神話、宗教、伝説に題材を求めた装飾性豊かな大作が多く、遠近法の効果を強調した空間構成、華麗な色彩、躍動感を特色とする。1750年にグライフェンクラウ司教に招かれ、ヴュルツブルクに滞在、司教館の皇帝室と階段室にドイツ皇帝フリードリヒ1世の生涯そのほかのフレスコ及び祭壇画を制作した。1761年カルロス3世に招かれてスペインに赴きマドリッドの王宮にフレスコ連作を描く。当地で不遇の晩年を過ごすが、その作品は2世代後のゴヤに大きな影響を与えた。
《花嫁を運ぶアポロ》
ヴュルツブルク宮殿 皇帝の広間の天井画
1996.3.7 ドイツ発行
【ティエポロ生誕300年】
解説は平凡社マイペディア、世界大百科事典及びブリタニカ国際大百科事典より
◆ その1 へ
◆ その2 へ
◆ その3 へ
◆ 造形編 へ
>>Stamp Album