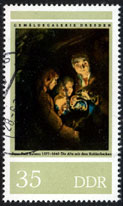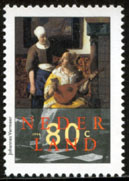Art Gallery

天使ガブリエル
ファン・アイク Jan Van Eyck 1385?-1441
初期フランドル絵画の創始者。ホラント伯に仕えて一時ハーグにいたが、1425年
ブルゴーニュ公フィリップの宮廷画家となり、1429年末までリールに居住、1431年以降ブルッヘに定住した。
その間フィリップの外交使節として1427年スペイン、1428年ポルトガルに旅行。
兄フーベルトのあとを継承して1432年に大作
『ヘントの祭壇画』を完成した。
『アルノルフィニ夫妻の結婚』などの作品がある。
1968.11.1 アメリカ発行

メムリンク Hans Memlinc 1440?-1494
フランドルの画家。ケルンで修業したのち、ブリュッセルでR.ウェイデンに師事したと思われる。
1465年以降ブルッヘに定住し、敬虔な情感をたたえた静穏な作風で多くの祭壇画を制作した。また
表情豊かに人物の特徴をとらえた肖像画は特にブルッヘ在住のイタリア人に好まれた。
1966.11.1 アメリカ発行

《自画像》
ホルバイン Hans Holbein der Ältere 1470-1524
ドイツ・アウグスブルクの画家。皮革商から画家になった。ドイツにおける後期ゴシックからルネサンスへの転換期の重要な画家で、明確な形象と穏やかな色調を特徴とする肖像画、祭壇画を残した。息子のアンブロジウス、父と同名のハンスも画家として活躍。
1974.7.16 ドイツ連邦共和国発行
【ホルバイン死去740年】

《裸の自画像》
1505年頃 薄緑の紙 筆 インク 白のハイライト 29×15cm ヴァイマール国立美術館所蔵
1971.5.18 ドイツ民主共和国発行
デューラー Albrecht Durer 1471-1528
ドイツの画家、版画家。ドイツ・ルネサンスの完成者。父は同名の金細工師で、初め父の助手を勤めた。1494-95年にかけて第1回のイタリア旅行を行い、ニュルンベルクに帰郷して工房を構え、1520-21年にかけてはフランドルに旅行、ネーデルラント美術に親しむ。
ゴシック的な深い宗教感情と、イタリア・ルネサンスの古典的な造形理念とを調和させ、透徹した自然観察を基に独自の画風を創造した。
切手下部中央はイニシャルのAとDを組み合わせたモノグラムで、このように絵にサインを入れるのは
デューラーが始めたと言われる。

《若い兎》
1502年 紙 水彩 21.5×22.6cm ウィーン・アルベルティーナ美術館所蔵
1969.9.26 オーストリア発行
 |
 |
|
《3人の農夫》
1971.5.18 ドイツ民主共和国発行 |
《パグパイプ奏者》
1971.5.21 西ベルリン発行 |
【デューラー生誕500年】

《子を抱く若い母親》
クラーナハ Lucas Cranach der Ältere 1472-1553
ドイツ・ルネサンスの代表的画家、版画家。クローナハの生まれ。父から画技を修得。初めウィーンの宮廷に出入りし、のち1505年ヴィッテンベルクでザクセン選帝侯の宮廷画家となり、初期の宗教的な作品から歴史・神話画に転じた。市参事会員や市長としても活躍、
ルターとも親交があり、彼の肖像画やルター派の宣伝版画の制作を手がけた。また1508/09年頃に初めて女性裸体画を描き、独特の官能性をたたえた女性像で知られるようになった。
1972.7.4 ドイツ民主共和国発行
【クラーナハ生誕500年】

《画家と商人》
1565年頃 ペン素描 25×21.6cm ウィーン・アルベルティーナ美術館所蔵
ブリューゲル Pieter Bruegel de Oude 1525/30-1569
ネーデルラントの画家で、北方ルネサンスの代表的画家。1551年アントウェルペンで画家組合に登録し、翌年からフランス、イタリアに遊学した。帰国後出版者H. コックのもとで銅版画の下絵画家として働く。1559年頃ころから油彩画を手がけ、『ネーデルラントの諺』、『謝肉祭と四旬節の喧嘩』、『子供の遊戯』などで群衆構図に関心をもつ。1561年の『反逆天使の転落』『悪女フリート』などでH. ボッシュ風の怪奇的・幻想的モティーフを駆使。1563年ブリュッセルへ移住。1565年に『季節画シリーズ』を制作し、絵画史上注目すべき季節的情趣のあふれた自然と農民の野良仕事を描く。次いで宗教画『ベツレヘムの幼児虐殺』『ベツレヘムの人口調査』などで厳冬のフランドルの農村をその舞台に選ぶ。晩年は『農民の婚宴』『農民の踊り』など農民の生活を精力的に描き、同時に『怠け者の天国』『盲人の寓話』のような、人間の実存を直視した寓意画の世界を樹立した。同名の長男、次男ヤンも画家として活躍した。
1969.9.26 オーストリア発行

《自画像》
1977.5.15 ドイツ連邦共和国発行
【ルーベンス生誕400年】
ルーベンス Peter Paul Rubens 1577-1640
フランドルのバロックを代表する画家。ドイツのウェストファーレン地方ジーゲンに法律家の子として生まれる。1600年にイタリアに留学、ヴェネツィア、ローマに滞在し、ティントレットやダ・ヴィンチ、ティツィアーノらの作品を研究。1600年マントヴァ公の宮廷画家となって活躍したが、1608年に母の死去のためアントウェルペンに帰国。この頃から豊麗な色彩、力強い動感、劇的な画面構成など独自の様式が開花した。大規模な工房を経営し、作品の中には弟子や助手の手の入っているものも多い。
 |
 |
|
《レルマ公騎馬像》
スペイン発行 |
《三人の騎士》
1967.6.7 ドイツ民主共和国発行 |
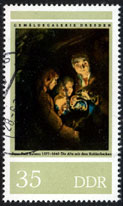 |
 |
| 《火鉢を持つ老女》 |
《噴水のそばのバテシバ》 |
1977.6.28 ドイツ民主共和国発行
【ドレスデン国立絵画館所蔵のルーベンス】

《灰色のコートを着た男》
ドレスデン国立絵画館所蔵
ハルス Frans Hals 1580?-1666
オランダの画家。幼時期に家族とともにハールレムに移住し、生涯同地で活躍。イタリア風にそまっていたオランダ絵画を真に国民的な画風に戻し、一般市民の風俗、肖像を描いた。細部の描写を省略したすばやく大胆な筆触で対象を生き生きと写しとる画風は、19世紀後半のフランス絵画に影響を与えた。またオランダ独自の〈集団肖像画〉を確立した。
1980.9.23 ドイツ民主共和国発行

《自画像》
1639年頃 エッチング ウィーン・アルベルティーナ美術館所蔵
1969.9.26 オーストリア発行
レンブラント Rembrandt Harmenz.van Rijn 1606-1669
オランダの画家、版画家。製粉業者の子に生まれ、1620年ライデン大学に入学するが、画家に転向。生地ライデンやアムステルダムで修業し、1632年頃からもっぱらアムステルダムで活動した。初期にはおもに宗教画を描いたが、1630年頃から写実的手法により肖像画を描いて名声を博し、このころが社会的にも経済的にも最も成功した時期となった。その後平板な写実にあき足らず、人間精神の表出に向かったが、1642年の集団肖像画・通称『夜警』(アムステルダム国立美術館蔵)の不評、同年の愛妻サスキアの死などにより次第に貧窮に陥った。しかし、強い明暗対立、まろやかな色彩を特徴とするその芸術はますます円熟味を加え、後世「魂の画家」といわれるように、自己の内面を吐露した宗教画、肖像画、風景画、神話画等に多数の傑作を残した。そりわけ青年期から晩年に到るまで描かれた自画像は深い精神性を示している。1656年破産宣告を受け、さらに第2の妻と息子にも先立たれ、不遇のうちに死去した。

《手紙を書き取らせる男》
1982.2.26 フランス発行
【切手の日】
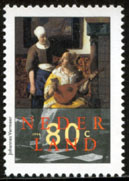
《恋文》
1669-70年頃 画布 油彩 44×38cm アムステルダム国立美術館所蔵
フェルメール Johannes Vermeer 1632-1675
オランダの画家。デルフト生れ。1653年生地の画家組合に登録、終生同地で活躍。現存作品約35点という極端な寡作のためもあって死後まもなくまったく忘却されたが、1860年代に再発見されて以後は着実に評価が高まり、今日ではレンブラントと並ぶ17世紀オランダ絵画の最高峰とあまねく認められている。日常の行為に没頭する単身もしくは少数の人物(とくに女性)をあらわした『牛乳を注ぐ女』『真珠のネックレス』等の一連の傑作によって、独自の絵画世界を確立。入念な構成、黄と青を主調とする調和的な色彩などに卓抜した手腕を示した。写真を思わせる精密な遠近法や珠のような微妙な光の表現などから、カメラ・オブスクラの利用も推測されている。
 |
 |
|
《手紙を書く婦人と召使》
1670年 画布 油彩 71.1×60.5cm
アイルランド国立絵画館所蔵 |
《青衣の女》
1663-64年頃 画布 油彩 46.6×39.1cm
アムステルダム国立美術館所蔵 |
1996.2.27 オランダ発行

《聖母子》
ムリーリョ Bartolomé Esteban Perez Murillo 1617-1682
スペインの画家。1645年から1646年にかけて最初の大作をセビリアのフランシスコ修道院に描く。1648年頃から3年間マドリッドに滞在、ベラスケスの援助を受ける。1660年にセビリア絵画アカデミー創立、その院長に就任。ティツィアーノ、ルーベンスなどの影響を受けたのち、柔らかく甘美な色彩と金色の靄のような輝きを帯びた光を特徴とする画風をうち立て、スペイン・バロックの代表的画家の一人となった。〈無原罪の御宿り〉の聖母を好んで描く一方で、路傍の貧児を写実的に描き、風俗画家、肖像画家としても才能を発揮した。
1967.10.18 イギリス発行
【クリスマス】
解説は平凡社マイペディア、世界大百科事典及びブリタニカ国際大百科事典より
◆ イタリア編 へ
◆ その2 へ
◆ その3 へ
◆ 造形編 へ
>>Stamp Album