| ■ 古代生物編 |
【第29回万国地質学会議記念】

アンモナイトと地図と地層図
1992.8.24発行
1992.8.24発行
【アンモナイト】 中生代に栄えた頭足類(イカ・タコの仲間)の一種。
エジプトの太陽神アモンの角になぞらえられたことからこの名がつけられた。
日本では菊石とも呼ばれる。 4億〜3億5000万年前のデボン紀に出現し、恐竜などとともに白亜紀末に絶滅。 渦巻状に巻いたものが一般的だが、ほどけた巻や複雑な巻きに進化したものもあり、 大きさも数センチ〜2メートルほどまでとさまざまである。 オウムガイとは異なり、貝の中のへやを仕切っている壁の向きが外の方にふくれている。 短期間に広く分布するような生活型をもち、生存期間が短く、局地的な環境条件に左右されにくい 、という条件を備えているため、地質年代を示す示準化石として重要視されている。 |

1958.4.15 中華人民共和国発行
蒿里山三葉虫
【三葉虫】 古生代、特にカンブリア紀からオルドビス紀に栄えた節足動物。 大きさは2〜10センチくらいで、頭、胸、尾の3つの部分に分かれており、 また体長方向にも三つに区分することができる。。 体全体がたくさんの節になっているので、ダンゴムシのように体を丸めることができた。 比較的浅い海の海底を這って生活していたらしい。 |

1982.12.1 南アフリカ発行
ブラディサウルス
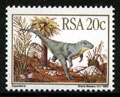
1982.12.1 南アフリカ発行
ユーパルケリア
恐竜の先祖である槽歯類(テコドント)の仲間。体長60〜90cm。肉食。三畳紀初期に生息。 中空の軽いほっそりした骨をもち、眼窩と鼻孔の間には前眼窩孔と呼ばれる隙間があった。 この隙間には体内の余分な塩分を濃縮し排泄する塩分泌腺があり、そのため海辺で餌をとることが できたと考えられている。 |

1982.12.1 南アフリカ発行
リストロサウルス
体長1mほどの草食爬虫類。ほ乳類の先祖の仲間。 三畳紀(約2億4000万年前)に生息。 |

1982.12.1 南アフリカ発行
トリナクソドン
ペルム紀後期〜三畳紀初期にかけて生息。 |
【切手の日(先史時代の動物)】

1992.10.3 スウェーデン発行
トラコサウルス
【切手の日(先史時代の動物)】

1992.10.3 スウェーデン発行
コエロドンタ・アンティクィタス マンモス
【マンモス】 更新世(164万年〜1万年前)に生息。体長6m、体高4.3m、牙の長さ5m。 シベリアからは毛や肉がそのまま残った氷漬けマンモスが発見されている。 |

1958.4.15 中華人民共和国発行
腫骨鹿
戻る ■ イギリス編 へ ■ アメリカ編 へ ■ オーストラリア編 へ