ジュラシックパーク(確か1)を見て、「何でヴェロキラプトル(最後の大立ち回りの主役を
張った恐竜)がアメリカにいるの?」と首をひねった程度には(笑)恐竜に凝ったことがあります。 (ヴェロキラプトルはモンゴルで発見された恐竜。アメリカにも同種のデイノニクスという恐竜が いますし、“恐ろしい爪”という名前のついたこちらの方が、映像的にも迫力があると思うのですが) そんなこともあって、恐竜の切手というと飛びつきたくなるのですが、 やっぱり人気があるだけあって高いんですよね〜(苦笑)。 解説を書く際に参考にした文献の主なものは以下のとおりです。 『よみがえる恐竜たち 切手ミュージアム1』(長谷川善和・白木靖美/未来文化社) 『恐竜のすべて』(ジャン=ギィ・ミシャール/小畠郁生・監修/創元社「知の再発見」双書) 『化石は語る 恐竜の時代』(小畠郁生/思索社) 『恐竜の足跡』(小畠郁生/新潮選書) 『恐竜発掘』(ドン・レッセム/加藤珪・訳/二見書房) |
| ■ 日本編 |
【国立科学博物館100年】

フタバスズキリュウの骨格復元図・星座と博物館
1977.11.2発行
1977.11.2発行
| フタバスズキリュウ | 首長竜 | |
| 白亜紀後期 | 発見地:日本 | 全長7m |
|
昭和43年、福島県いわき市で、当時高校生だった鈴木直さんが発見。
川によって浸食された首の部分を除いて、ほぼ一頭分の骨が発掘された。 化石の周りからたくさんのサメの歯が発見されており、サメの群れと闘って死んだのではないかと 考えられている。 復元骨格はいわき市の「石炭・化石館」に展示されており、国立科学博物館にもレプリカがある。 | ||
【ふるさと切手・福井県】

イグアノドン・ドロマエオサウルス
1999.2.22発行
1999.2.22発行
| イグアノドン | 鳥盤目 鳥脚亜目 | |
| 白亜紀前期 | 発見地:ヨーロッパ・北アフリカ他 | 全長5〜9m 体重5t |
|
世界で最初に発見された恐竜化石。
名前は「イグアナの歯」という意味で、発見された歯の化石がイグアナの歯に似ていたところから、
発見者のマンテル博士が名付けた。 角状にとがった親指が特徴だが、当初はサイのような角と誤って復元されていた。 ベルギーのベルニサール炭坑からは完全な骨格が20体も発見されており、足跡化石は日本や スピッツベルゲンなど、世界中で発見されている。 勝山市の手取層群から発見されたものには、「フクイリュウ」という和名がつけられている。 | ||
| ドロマエオサウルス | 竜盤目 獣脚亜目 | |
| 白亜紀後期 | 発見地:アジアなど | 全長4〜5m |
|
名前は「走るトカゲ」という意味。 足指に鎌のような大きな鉤爪を持ち、二足歩行で、 集団で狩りをして生活していたと考えられている。 勝山市の手取層群から発見されたものには、「キタダニリュウ」という和名がつけられている。 | ||
| ■ 外国編 |
【切手の日(先史時代の動物)】

1992.10.3 スウェーデン発行
| プラテオサウルス | 竜盤目 原竜脚亜目 | |
| 三畳紀後期 | 発見地:ヨーロッパ・南アメリカ | 全長6m |
|
カミナリ竜の祖先にあたる恐竜。雑食性だった。 前足は後ろ足の半分ほどあり、二足歩行ばかりではなく四足歩行もできたらしいと考えられている。 名前は「平らなトカゲ」の意味らしい(歯がへら状だから?)。 ドイツのトロシンゲンからはフォン・ヒューネによって大量の化石が発見されており、移動中に倒れた ものか、突然起こった土砂崩れの犠牲になったものと考えられている。 | ||

1958.4.15 中華人民共和国発行
| ルーフェンゴサウルス | 竜盤目 原竜脚亜目 | |
| 三畳紀〜ジュラ紀前期 | 発見地:中国雲南省 | 全長6m |
|
中国名「許氏禄豊竜」。カミナリ竜の祖先にあたる恐竜。 1938年、楊鐘健教授によって、雲南省の禄豊盆地で発掘された。 通常は後ろ足だけで歩いていたが、前足の長さが後ろ足の約3分の2もあることから、 四足歩行もできたらしいと考えられている。 主に植物を好んだ雑食性と考えられるが、魚を餌にしたという説もある。 ※ 世界最初の恐竜切手 | ||
 |
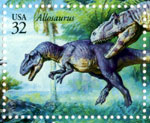 |
| 1993年 オーストラリア発行 | 1997.5.1 アメリカ発行 |
| アントロデムス | 竜盤目 獣脚亜目 | |
| ジュラ紀後期 | 発見地:北米・アフリカ・オーストラリア | 全長10.7m 体重2t |
|
いわゆるアロサウルス。しかし学名上はアントロデムスが正しいとのこと。 鋭い爪、大きな顎、ナイフのように鋭い歯が武器で、 噛みついた歯のあとがあるカミナリ竜の骨の化石も発見されている。 | ||
 |
 |
 |
| 1997.5.1 アメリカ発行 | 1991.8.20 イギリス発行 | チェコ発行 |
| ステゴサウルス | 鳥盤目 剣竜亜目 | |
| ジュラ紀後期 | 発見地:北アメリカ | 全長4〜9m 体重2t |
|
名前は「屋根のある爬虫類」という意味。 背中に互い違いに並んだ三角形の骨板が特徴。 敵に襲われたときに弱い腹部を守るために広げられたとも、これをガチャガチャ鳴らして敵を 脅かしたり仲間に危険を知らせたとも考えられている。 尾には二対のスパイクがあり、防御用の武器として用いられた。 脳がとても小さかったため、背中にその働きを補う神経のかたまりがあった。 | ||
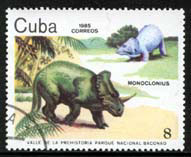
1985年 キューバ発行
| モノクロニウス | 鳥盤目 角竜亜目 | |
| 白亜紀後期 | 発見地:北アメリカ | 全長5m |
|
名前は“1本の幹を持ったもの”という意味。 初めて発見された角竜で、白人とインディアンの戦いの さなか、間一髪で掘り出されたというエピソードがある。 | ||
■ イギリス編 へ ■ アメリカ編 へ ■ オーストラリア編 へ ■ その他古生物編 へ