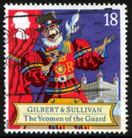Operetta

1970.9.11 オーストリア発行
「こうもり」 Die Fledermaus ヨハン・シュトラウス2世作曲
8日間の禁固刑を言い渡されてしまったアイゼンシュタインは、妻のロザリンデと夕食をとるために一時帰宅。そこへ友人ファルケ博士がやってきて、オルロフスキー邸で舞踏会が開かれるから、その後で刑務所に出頭すればいい、と誘う。すっかりその気になり、妻には内緒で出かけるアイゼンシュタイン。ロザリンデ一人が残る家にはかつての恋人アルフレートが入り込む。ところがそこへ刑務所長フランクが現れ、すっかりくつろいでいたアルフレートをアイゼンシュタインと思い込んで連行していく。
オルロフスキー邸での舞踏会。小間使いアデーレは女優オルガ、アイゼンシュタインはフランスの侯爵ルナール、刑務所長フランクはシュヴァリエ・シャグランというふれこみで紹介される。そこへ仮面をかぶりハンガリーの伯爵夫人に変装したロザリンデも現れる。妻と気付かず彼女を口説いたアイゼンシュタインは、口説きの小道具の懐中時計を取り上げられてしまう。やがて午前6時の鐘が鳴り、アイゼンシュタインとフランクは2人して会を後にする。
刑務所へ出頭したアイゼンシュタインは所長のフランクと驚きの再会。フランクは彼ならすでに収監したと取り合わない。刑務所を訪れたロザリンデは昨日の経緯を弁護士に話すが、その弁護士は変装したアイゼンシュタインで、正体を現して妻をなじる。昨夜の懐中時計を取り出してやりこめるロザリンデ。そこにファルケ博士とオルロフスキーが現れる。実はかつて恥をかかされたファルケが仕組んだ仕返しだったのだ。最後はすべてはシャンパンのせい、と大円団。
大好きなオペレッタです。生の舞台も4回も見ていて、これは目下私の最多記録。といっても全部同じ公演ですが(爆)。2回目にはオチなんかほとんど分かってるんですけど、それでもとにかく楽しかったです。その一世一代の大バカの記録は
こちら。
Music: “序曲” “ぶどう酒の情熱の炎に”

1970.7.3 オーストリア発行
「乞食学生」 Der Bettelstudent カール・ミレッカー作曲
舞台は18世紀初頭、ザクセン選帝侯アウグスト支配下のポーランド。伯爵家の娘ラウラに言い寄って扇子で叩かれてしまったクラクフ司令官オレンドルフは、仕返しのために収監中の貧乏学生のシモンを貴族に仕立てて彼女と結婚させようとする。ラウラを本当に愛してしまったシモンは、手紙で真実を知らせようとするが、彼女の手に渡らぬまま結婚式は始まり、そこへ囚人たちをつれた看守がやってきてすべてを暴露してしまう。シモンの秘書に扮しているヤンは、実は対立王スタニスワフの士官。シモンに王の総司令官の身代わりになって時間稼ぎをしてほしいと頼み、大金と引き替えにオレンドルフにシモンを引き渡す。シモンは死刑を宣告されるが、先ほどの大金を軍資金に、本物の総司令官の指揮する反乱軍が蜂起に成功、オレンドルフは逮捕される。シモンはその功により伯爵の位を授けられることになり、めでたくラウラと結ばれる。
メルビッシュ公演のDVDが国内盤日本語字幕付きで出ています。見たことはないですが、ちょっと興味あり。
Music: “ワルツ”

1970.9.11 オーストリア発行
「小鳥売り」 Der Vogelhändler カール・ツェラー作曲
舞台は18世紀初めのプファルツ。選帝侯が狩猟区に狩りにやってくるとの知らせに、猟区の監督官ヴェプスは、農民たちの密猟のために獲物がいなくなってしまったのをとりなすからと袖の下を要求する。ところが選帝侯は急用のため狩猟を中止。それでは都合が悪いヴェプスは甥のスタニスラウスを偽の選帝侯に仕立て上げる。それを知らない侯妃マリーは、夫の浮気の現場を押さえようと、農家の娘になりすましてやってくる。村の郵便配達の娘クリステルはチロルの小鳥売りアーダムと恋仲だが、彼にに定職が見つからないので結婚できない。クリステルは彼に動物園の職を頼もうと、偽の選帝侯のいるあずまやに入っていく。恋人が他の男と一緒にいたことを知って怒るアーダム。失望した彼は侯妃とも知らずマリーに関心を示す。クリステルからあずまやの中にいたのが偽の選帝侯スタニスラウスであることを知らされた侯妃マリーは、その罰をアーダムに委ね、アーダムはスタニスラウスはクリステルと結婚すればいいと突き放してしまう。しかし最後には二人は仲直りし、めでたく結ばれる。
これも
メルビッシュ公演のDVDが国内盤日本語字幕付きで出ています。クリステル役のグフレラーが可愛くてしかも上手いです。郵趣家のはしくれとしては「私は郵便配達のクリステル」なんて曲があるのも外せない。お帽子の飾りがポストホルンの形だったり、乗ってる自転車が黄色だったりするあたりも芸も細かいです。しかし料金後払いの時代に封筒に切手が貼ってあっちゃまずいでしょ〜(笑)。18世紀ってったらまだ切手発明されてないし。
Music: “僕のおじいちゃんが20歳の時”

1970.7.3 オーストリア発行
「ワルツの夢」 Ein Waltzertraum オスカー・シュトラウス作曲
舞台は架空の小国フラウゼントゥルム侯国。侯の一人娘ヘレネはウィーンでニキ中尉と恋仲になり、身分違いながら結婚することになった。しかしニキは因習にとらわれた田舎の宮廷に浮かぬ顔。そこへ昔の連隊の仲間モンチ中尉が訪ねてくる。庭から聞こえてくるウィンナ・ワルツに、一緒に宮殿を抜け出す二人。音楽を奏でているのはウィーン娘の楽団で、ニキは指揮をしていたフランツィと惹かれ合う。夫の心を取り戻したいヘレネはフランツィの助けを借りて、宮殿の中をウィーン風に変える。フランツィは二人の幸せを喜びながら、楽団を率いて次の目的地に向かう。
シュトラウスの綴りはStraus。末尾のsがワルツ王より一つ少ないです。当然親戚関係はありません。オペレッタの作曲を勧めたのはシュトラウス2世だそうですが。しかしまあ、なんとも露骨なウィーン万歳のお話ですなあ(笑)。あらすじを読んだ限りでは、同じ作者なら「チョコレートの兵隊」のが今に通じる内容で面白そうな気がします。

1970.9.11 オーストリア発行
「四分の三拍子の二つの心」 Zwei Herzen im Dreivieteltakt ロベルト・シュトルツ作曲
ニッキとヴィッキのマーラー兄弟はオペレッタの台本作家。二人の台本に曲をつけているトーニは、主題歌になるワルツがなかなか思い浮かばない。そこへ寄宿学校にいる兄弟の妹へディが帰ってくる。かねてからトーニの曲に興味を持っていたへディは、トーニの家を訪ね、トーニは素晴らしいワルツのメロディが生まれてくるのを感じる。興奮したトーニはマーラー兄弟の家を訪ね、完成したワルツを演奏しようとするが、どういうわけか思い出すことができない。劇場では新作オペレッタの最後のリハーサルが行われているが、トーニはワルツのメロディーを未だに思い出せないでいる。そこへへディがそのワルツを口ずさみながら入ってくる。二人は幸せに手を取り合う。
1930年に封切られたオペレッタ映画が基になって、舞台版が作られたそうです。作曲のシュトルツ、検索するとむしろ指揮者としての方がよく引っかかってきました。

1970.7.3 オーストリア発行
「メリー・ウィドウ」 Die Lustige Witwe レハール作曲
ポンテヴェドロ公国のパリ公使館では、君主の誕生日祝賀会が開かれている。莫大な遺産を持つ未亡人ハンナは求婚者に囲まれていて、彼女の財産が国外流出するのを恐れる公使ツェータは書記官ダニロにハンナとの結婚を命じる。ハンナとダニロはかつては恋人同士だったのだが、ダニロのおじの反対に遭ったため、ハンナは金持ちの老人と結婚してしまったのだ。お互い未練はあるのに、素直になれない二人。公使夫人があずまやでの逢引きを見つかりそうになったため、ハンナが身代わりになる。ショックを受けるダニロ。
妻の浮気を知った公使は、離婚してハンナと結婚しようとするが、ハンナは再婚すると自分はすべての遺産を失うと明かす。それを聞いてやっとハンナに愛を告げるダニロ。ハンナは続いて、自分が遺産を失うのは、それが新しい夫のものになるからと言うのだった。
「こうもり」ほどではないにしてもいくつかDVDが出ていますが、ドイツ語・劇場上演で日本語字幕付きというと、
チューリヒ公演のものだけみたいですね。これ、大のお気に入りディスクで、大いにオススメです(笑)。
Music: “ワルツ”

肖像と《ジュディッタ》の楽譜
レハール Lehár Ferenc 1870-1948
オーストリアの作曲家、指揮者。現ハンガリー領コマーロムでドイツ人軍楽隊長の父とハンガリー人の母の間に生まれる。12歳でプラハ音楽院に入学しバイオリンと作曲を学ぶ。軍楽隊指揮者を経て、1902年からウィーンで指揮者として活動を始める。ワルツ《金と銀》が出世作となり、1905年にオペレッタ《メリー・ウィドウ》で空前の成功を収める。1909年の《ルクセンブルク伯爵》のほかはなかなか成功を得られなかったが、名テノール歌手リヒャルト・タウバーを得て1926年にベルリンで初演した《パガニーニ》で新境地を開き、《ほほえみの国》(1929年)などの名作を残した。最後の作品《ジュディッタ》(1934年)は初めてウィーン国立歌劇場で初演された。
1970.4.30 ハンガリー発行

リンケ Paul Lincke 1866-1946
ベルリン生まれのオペレッタ作曲家。市役所の職員の息子として生まれ、早くからバイオリンを習う。18歳の頃からベルリンの舞踏会用ホールなどで指揮者を務める。1893年アポロ劇場と契約を結び、指揮の傍ら自作を相次いで発表。1897年にベルリンで上演した《地上のヴィーナス》が出世作となり、多くのオペレッタを作曲した。ウィーンのオペレッタと異なり、ワルツが少なく大衆的な歌謡が多く取り入れられていたこともあり、当時のベルリン市民に人気を博した。代表作は気球での月旅行を題材にした《月の女神ルーナ》。また、作曲活動だけでなく、音楽出版業を幅広く営み、自作のオペレッタも出版している。
1996.8.14 ドイツ発行

アッシャー Leo Ascher 1880-1942
ウィーン生まれ。オペレッタの作曲を中心に活動し、オペレッタ《復讐の神》で有名となった。そのほか50以上にわたる舞台音楽や映画音楽も作曲している。晩年にはニューヨークに移り、そこで死去した。
1980.8.18 オーストリア発行
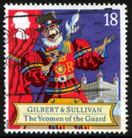
1992.7.21 イギリス発行
「ロンドン塔の衛兵」 The Yoman of the Guard サリヴァン作曲
ロンドン塔の衛兵メリル軍曹の娘フィービは、ロンドン塔に幽閉されているフェアファックス大佐に心を寄せている。大佐は魔法使いとされ、無実の罪で死刑を宣告されているのだ。そこへ彼女の兄レイナードがやはり衛兵として着任。彼の顔がここでは知られていないのを利用して、親子3人は大佐をレイナードに変装させて脱獄させる。一方大佐は自分が遺産目当てで陥れられたのを知っており、死ぬ前に歌手のエルシーと結婚して、彼女に遺産を残そうとする。死刑囚の脱獄の知らせを聞いて、エルシーは死ぬべき夫が自由の身になったことに当惑し、レイナードに変装している大佐の胸に失神して倒れ込んでしまう。本物のレイナードが、国王が大佐の恩赦に署名していたのに、それが握りつぶされていたことが発覚したことを知らせにくる。大佐は改めてエルシーと結婚、失恋したフィービは看守長と、そして軍曹は脱獄の秘密を握るカラザース夫人と結ばれ、3組の結婚式が行われる。

1992.7.21 イギリス発行
「ゴンドラの船頭」 The Gondoliers サリヴァン作曲
ゴンドラ漕ぎのマルコとジュゼッペはそれぞれ結婚式を挙げるところ。そこへプラザ=トロ公が現れ、幼くして宗教裁判長に誘拐され、ゴンドラ漕ぎに育てられた王子を探しに来る。プラザ=トロ公は娘のカシルダを王妃にしたいのだ。探し当てた宗教裁判長は、ゴンドラ漕ぎには王子と同い年の子どもがいて、育てているうちにどちらがどちらか分からなくなってしまった、王子の乳母であったイネスならこの問題を解決できると言う。マルコとジュゼッペは、宗教裁判長にどちらかが王様だと告げられ、新妻を残して王国へ出発する。しかし捜し出された王子の乳母は、実は二人のうちのどちらでもなく、従者ルイスが王子であると明かす。ルイスと恋仲だったカシルダは大喜び。娘を王妃にすることができた公夫妻も満足で、王様になれなかった二人のゴンドラ漕ぎも、愛する妻と結ばれることができ、全員が幸せになってめでたく幕。
Music: “ガヴォット”
参考文献:『オペレッタ名曲百科』(永竹由幸/音楽の友社)
『ウィーン・オペレッタ探訪』(渡辺忠雄/オール出版)
『魅惑のウィンナ・オペレッタ』(寺崎裕則/音楽の友社)
『音楽・切手の366日』(平林敏彦著/薬事日報社)
|
《戻る》