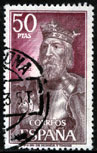Western
Medieval History

アルフォンソ3世 848-910
アストゥリアス王(在位866-910)。オルドニョ1世の子。ムワッラド(改宗イスラム教徒)やモサラベ(イスラム支配下のキリスト教徒)の反乱に揺れるアル・アンダルス(イスラム支配下のイベリア半島)の動揺をついて大規模なレコンキスタ運動を展開し、ドゥエロ川沿岸を占領、支配し、ブルゴスの町を創建、さらにその支配を東方に拡大した。10世紀初頭にはレコンキスタ理念に基づいて西ゴート王の継承者に位置付けられた。
1961.11.27 スペイン発行
【オビエド市1200年】
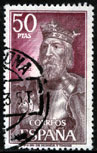
フェルナン・ゴンザレス 910-970
初代カスティーリャ伯(在位932-970)。932年、イスラム軍に対抗するべくレオン王ラミーロ2世によって全カスティーリャの伯に任命された。ラミーロ2世の没後、レコンキスタを主導し、レオン王家や王位継承問題への介入などを通じて、伯権力の自立性を強め、レオン王の宗主権を承認しつつもカスティーリャ伯領を事実上分離させた。
1972.1.22 スペイン発行

エル・シッド El Cid 1040?-99
本名ロドリゴ・ディアス・デ・ビハール。シッドの通称はアラビア語のsid(君主)に由来する。スペインの国民的英雄。傑出した野戦指揮官で、生涯にわたって輝かしい勝利を収めたところから、中世騎士物語に由来する「勝利者」Campeadorとも呼ばれる。ブルゴス近郊ビハールに下級貴族の子として生まれる。カスティーリャ王サンチョ2世に仕えて軍人としてすぐれた指揮能力を示し、ことに王が末弟アルフォンソからレオンの王位を奪い取った際の戦闘でめざましい働きを示した。サンチョ2世が暗殺され、アルフォンソが王位を継いでからも10年近くこの王に仕えるが、のちに疎まれて追放された。このためイスラム教徒のサラゴーサ王に仕えて政治顧問となり、数々の功績をあげた。1083年にアルフォンソ6世との間に一度は和解が成立するもすぐに破れたが、1086年サグラハスの戦いに敗れた王に再び呼び戻され、バレンシアのイスラム教王国にアルフォンソの宗主権を確立すべく尽力。1089年に三たび宮廷を追われると、バレンシア征服に着手し、1094年にはこれに成功、ムラービト軍の北上を阻止して王にも等しい地位にのぼった。その武勲はのち多くの吟遊詩人にうたわれ、12世紀初頭には中世スペイン最大の叙事詩『わがシッドの歌』が成立した。
1962.7.30 スペイン発行

サンチョ6世と認可状 12世紀の細密画
サンチョ6世 ?-1194
ナヴァラ王(在位1150-94)。ガルシア5世の子。「賢王」と呼ばれた。彼の治世の初めにアラゴンとカスティーリャはナヴァラ分割の条約を結んだが、巧みな外交政策でこの難関を乗り切り、カスティーリャ王アルフォンソ7世の娘と結婚した。しかし彼はアルフォンソ8世の未成年の時期にカスティーリャの問題に介入した。また、移住農民に特権を与える特許状を制定し、ユダヤ人や移住民を保護した。娘のベレンゲラは
イングランド王リチャード1世の王妃。
1981.8.5 スペイン発行
【ビトリア市800年】

ハイメ1世 1208-1276
アラゴン王(在位1213-76)。征服王とも呼ばれる。アルビジョワ十字軍に苦慮した父ペドロ2世により、3歳でシモン・ド・モンフォールの人質となるが、この懐柔策は失敗に終わり、彼が5歳の時にペドロ2世はミュレの戦いで戦死。数ヶ月後には母を失い、教皇によってアラゴンのテンプル騎士団に預けられた。親政を開始すると、政治・行政・財政機構の再建に取り組む一方で、1229年にはマヨルカ、1238年にはバレンシアの再征服に成功する。国王都市バルセローナの自治権強化につとめ、アレクサンドリアやチュニスなどにカタルーニャ承認の居留地を開設した。1244年にはカスティーリャ王フェルナンド3世とアルミスラ条約を結び、カスティーリャ王国との西部国境を確定させた。フランスに対しては
ルイ9世とコルベイユ条約を結んで南フランスへの要求を正式に放棄する一方、王太子ペドロをシチリア王女コンスタンツェと結婚させて、シチリア領有を狙うルイ9世の弟シャルル・ダンジューを牽制した。また身分制議会の「カタルーニャ議会」を、バルセロナの市会「百人議会」を誕生させ、海事法を整備して『海事法令集』にまとめさせた。自伝的年代記『事実の書』を残している。
1977.2.10 スペイン発行

彩色写本“Constitutiones Jacobill” 14世紀 ブリュッセル アルバート王立図書館所蔵
【ハイメ2世】 1243-1311 マヨルカ王(在位1276-1311)。ハイメ1世の子でペドロ3世の弟。ハイメ1世の死後マヨルカを相続。ペドロ3世のシチリア王位を認めないローマ教皇マルティヌス4世がアラゴン十字軍を起こした際、兄への協力を拒み、逆にフランス軍と結んでカタルーニャに侵攻したが敗退。1285年にはペドロの息子のアルフォンソにマヨルカを制圧された。
1987.9.16 スペイン発行
【ハイメ2世治世下におけるマヨルカの郵便事業】

ハイメ3世 1315-1349
マヨルカ王(在位1324-1349)。
1984.6.29 スペイン発行
【バレアレス諸島自治権】

サンショ1世 1154-1211
ポルトガル王(在位1185-1211)。初代ポルトガル王アフォンソ1世の子。ベイラ東部のコヴィリャンやグアルダの植民を推進して対レオン王国の辺境拠点とした上で、十字軍の艦隊の支援のもとに、一時アルガルヴェの重要な拠点シルヴェスを攻略して「ポルトガル・アルガルヴェ王」を名乗った。これに対して南のイスラム太守諸国はムワッヒド軍の下に結集して反撃を試み、1190年エヴォラを残してテージョ川まで迫った。こうして再びテージョ河が両陣営の国境となり、サンショはテージョ以北の各地に植民地特許状を公布して植民地活動に専念した。
1955.3.17 ポルトガル発行

アフォンソ2世 1186-1223
ポルトガル王(在位1211-1223)。サンショ1世の子。キリスト教国同盟軍に加わり、1212年のラス・ナバス・デ・トローサの戦いでムワッヒド軍を大破した。1211年コインブラで最初のコルテス(身分制議会)を開催。1216年以降、聖俗貴族に相続領地の安堵を申請させる所領確認制(コンフィルマサン)を始め、さらに1220年、役人を派遣して検地(インキリサン)をおこなわせた。ブラガ大司教と教皇庁は国王を破門して検地に抵抗した。
1955.3.17 ポルトガル発行

アフォンソ3世 1210-1279
ポルトガル王(在位1248-1279)。アフォンソ2世の子。教皇によって廃位されたサンショ2世の没後、聖職者たちの支持で即位。1249年、アルガルヴェ西部のファロ、シルヴェスを落としてレコンキスタを完了させた。首都をコインブラからリスボンに移し、各都市の支持を得てレイリアにコルテスを召集し、1254年のこのとき初めて自治体を代表する平民がコルテスに出席した。アルガルヴェを征服したことでカスティーリャとの対立を招いたが、やがて和解が成立、カスティーリャ王アルフォンソ10世の庶出の娘ベアトリスと結婚した。まもなく検地を再開して多くの貴族を屈服させ、また強力な宗教裁判所を設けて教会からも多くの土地を没収した。聖職者たちはこれに抗議して逃散、アフォンソは破門されて廃位の脅迫を受けたが、晩年まで屈しなかった。
1955.3.17 ポルトガル発行

ディニス 1261-1325
ポルトガル王(在位1279-1325)。アフォンソ3世の子。「農夫王」の称がある。1284年以降、国王査察使を派遣して王領地の検地を徹底して行わせ、北部全域にわたって土地台帳を作成した。また、貴族の裁判権の乱用を取り締まり、封建的諸特権の証明を義務づけて領主権の拡大を抑制。さらにローマ法を導入、1290年にはその専門家の育成を兼ねた学校(後のコインブラ大学)をリスボンに創設。1288年にはサンティアゴ騎士団をカスティーリャから切り離して独立させ、1297年にはカスティーリャとアスカニーゼス条約を結んで両国の国境を画定した。また1312年にテンプル騎士団が廃止されると、長年の教会勢力との闘争にいったんピリオドを打ち、1319年にローマ教皇から「キリスト騎士団」新設の認可を得てテンプル騎士団の財産を移転し、王権の支配下に置いた。
彼の治世に王権の強化は一つの頂点に達したが、経済面でも中世の最盛期を迎えた。農業の振興のために植民や干拓を奨励、多くの入植地に定期市の開設を許可する特許状を発布して地域間交易を刺激し、北欧と取り引きする商人にも免税特権を与えて保護した。またレイリアでマツの防砂植林を推進して造船業の発展を図った。1317年には地中海に横行するイスラム海賊を掃討するためにジェノヴァからエマヌエレ・ペサーニョを世襲提督として招聘し、海軍を創設した。文芸の保護者でもあり、自らも詩人であった。
ポルトガル発行

アフォンソ4世 1291-1357
ポルトガル王(在位1291-1357)。ディニス王の子。カスティーリャ王と争ったが、1340年イスラム教徒との戦いではカスティーリャ王アルフォンソ11世に協力し、アンダルシアのサラド河畔で、レコンキスタにおけるキリスト教徒の優位を決定的にする大勝利を得た。1355年には王子ペドロの愛人でカスティーリャ貴族の娘イネス・デ・カストロを政治的に有害と判断して処刑した。
1955.3.17 ポルトガル発行

フェルナンド 1345-1383
ポルトガル王(在位1367-1383)。ペドロ1世の子。1375年にペストで激減した農民がより待遇のよい土地を求めて移動するのを防ぐためセズマリア法を公布したが、見るべき効果を上げることはできず、飢えに苦しむ農民は都市に流入して社会不安のもとになった。1369年にはアラゴン、グラナダと組んでカスティーリャの王位継承問題に介入。さらに1372-73年には王位継承権をイングランド国王エドワード3世の王子ジョン・オブ・ゴーントに譲って再びカスティーリャと交戦した。カスティーリャがフランスと同盟を結んだため、この戦いは英仏間の百年戦争と連動することになった。カスティーリャ王エンリケ2世によってリスボンが焼き討ちされ、海軍はほぼ全滅した。2度の敗戦にもかかわらず、リスボンの城壁を強化増築し、1381年3度目の戦争を始めたが、貴族も民衆も戦意に乏しく、援軍のイングランド軍も各地を略奪するに及んで1382年に和約が結ばれ、唯一の娘ベアトリスをカスティーリャ国王ファン1世と結婚させることを余儀なくされた。うち続く戦争で国土は荒廃し、戦費を補うために行われた悪貨の鋳造と平価の切り下げ、それに伴う物価の高騰で困窮する都市下層民や職人層は、この間にリスボンをはじめ各地でたびたび反乱を起こしている。
1955.3.17 ポルトガル発行
参考文献:
『ブリタニカ国際大百科事典』
『スペイン・ポルトガル史 新版世界各国史16』(立石博高・編/山川出版社)
『ポルトガル史』(金七紀男/彩流社)
『ナバラ王国の歴史』(レイチェル・バード著・狩野美智子訳/彩流社)
|
《目次》
■ カロリング朝以前へ
■ ノルマン・コンクエスト へ
■ 12〜13世紀 へ
■ 百年戦争前後 へ
■ 中・東欧 へ
■ 思想・文化 へ
■ 美術工芸など へ