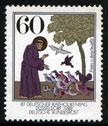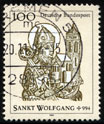Western
Medieval History
 |
 |
1979.8.9 西ドイツ発行
【死去800年】 |
1998.4.16 ドイツ発行
【生誕900年】 |
ビンゲンのヒルデガルド Hildegard von Bingen 1098-1176
アルゼー近郊のベルマースハイムで貴族の家に生まれ、8歳のときディジホーデンベルク修道院のシュポンハイム伯夫人ユッタのもとに預けられる。15歳頃誓いを立てて修道女となり、ユッタが死ぬとその後任に任命された。
幼時から幻視体験に恵まれ、『スキウィアス』(「道を知れ」の意 1141〜50)をはじめとする三冊の作品にまとめられた。医学・薬学に関する作品やアルファベット改良の試みもあり、作曲も残している。また教皇や皇帝など多数の人々との間の厖大な書簡が残されている。
1147年頃ビンゲン近郊のルーペルツブルクに移り住み、そこで生涯を終えた。
彼女の神学的著作はドイツ神秘主義の源流の一つとされる。
右側の切手、消印がど真ん中に押されちゃって図案が見にくいですが、これは彼女の著作『スキウィアス』の挿絵に描かれた彼女の幻視「天地創造と贖罪」だそうです。
| 【第87回ドイツカトリック集会】 |
|
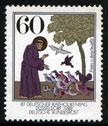 |
 |
1982.8.12 西ドイツ発行 |
13世紀のフレスコ画
1976.10.2 イタリア発行 |
アッシジのフランチェスコ Francesco d'Assisi 1181/82-1226
本名ジョバンニ・フランチェスコ・ベルナルドーネ。フランチェスコ修道会の創設者。
イタリア・ウンブリア地方アッシジの富裕な織物商の子に生まれる。1202年アッシジとペルージアとの戦争に従軍して捕虜になり、ほどなく回心。1207年に清貧の生活に入った。
サン・ダミアーノ聖堂を再建し、キリストの言葉を聞いて説教を開始。
乾いた山道でのどの渇いた旅人に会い、彼が祈りを捧げると水が湧き出したり、野の鳥を集めて説教をすると、鳥たちは一羽として飛び立たず、彼の説教に耳を傾けた(図案はこの場面。アッシジの聖フランチェスコ修道院上堂にあるジョット作の『聖フランチェスコ伝』第15図より)、などのエピソードがある。1217年にはエジプトに渡ってスルタンに説教し、感服させて聖地巡礼を許されたという。1224年夏アラベルナ山にて聖痕を受け、盲いて生涯を終えた。1228年に教皇グレゴリウス9世によって聖人に列せられた。
ちなみに1980年には環境保護(エコロジー)の守護聖人に指定されているのだそうです。

Ordo fratrum minorum : 「小さき兄弟たちの修道会」
アッシジのフランチェスコによって始められたフランチェスコ派托鉢修道会の正式名称。
町の人々に説教を始めた彼のもとにはまもなく11人の同志が集まり、「小さき兄弟たち」と自称。フランチェスコは福音書の訓戒からなる短い会則を与え、1209年に教皇インノケンティウス3世から認可の口約を得た。彼らの説教活動はイタリア各地に及び、1219年には管区長が置かれるようになる。翌年、総会の要望でフランチェスコは第二会則を草案。これは修正されたうえで
1223年に教皇ホノリウス3世によって認可され、ここに「小さき兄弟たち」は正式の修道会となった。
1212年には修道院に住む女子の修道会部局(「クララ会」)が、21年にはおよび職業活動をしている信者の平信徒団体が「第三会」として加わっている。
1995.2.16 クロアチア発行
【Visovac修道院550年】

ロート・アン・デア・ロートの聖ヴェレーナ教会にある像
ノルベルトゥス Norbertus 1080/5-1134
プレモントレ会創立者。故郷クサンテンの聖堂の参事会員となったが、皇帝ハインリヒ5世の宮廷に世俗生活をおくった。1115年回心、司祭となり各地で改革を説いた。1120年フランスのラン近郊プレモントレに修道会を創立、アウグスティヌスの戒律をとり、シトー会になった組織を確立。1126年マクデブルク大司教。1582年列聖。
1984.5.8 ドイツ連邦共和国発行

リューベックに残る聖エリーザベトの物語の絵(部分)
テューリンゲンのエリーザベト 1207-1231
ハンガリー王アンドラーシュ2世の娘。1221年テューリンゲン方伯ルートヴィヒと結婚、1男2女を得る。1225年よりマールブルクの聴罪師コンラートの指導下に生来の従順、清貧、隣人愛の生活を深め、1226年の飢饉には、十字軍従軍の夫の留守中であったが、全収入を貧者の糧に施した。1227年に夫が死ぬとその親類からの迫害が強まり、死にいたる3年はみずから設けたフランシスコ施療院で祈祷と慈善の生活を送った。その美しい人格はドイツ国民の敬愛を集め、聖堂模型を持つか、寡婦のベールをかぶりパンと飲器をもって貧者を伴った姿で多くの美術品に表現されている。1235年列聖。
1981.11.12 ドイツ連邦共和国発行

アルベルトゥス・マグヌス Albertus Magnus 1193?-1280
中世スコラ哲学の巨峰の一人。ドイツでの教授活動の後、1245年頃パリで教え、1248年ケルンにドミニコ会の総合学院(ストゥディウム・ゲネラーレ)を設立。1254-57年ドイツ管区長。56年サンタムールのギョームと対決。1260年レーゲンスブルク司教。1263年よりドイツ、ボヘミアで十字軍唱導。哲学ではアラビア経由のアリストテレスの全作品を注解し、その自然学によって新世界を開き、弟子トマス・アクィナスによる体系化を促した。(ギリシャ哲学とキリスト教神学の結合)反面偽ディオニュシオスの全作品の注解にみられる新プラトン主義的傾向は、弟子シュトラスブルクのウルリッヒらを通して14世紀ドイツ神秘主義の源流となった。
1980.5.8 ドイツ連邦共和国発行

授業風景
トマス・アクィナス Thomas Aduinas 1225-1274
イタリアのドミニコ会士、神学者、聖人。天使的博士と綽名された。アルベルトゥス・マグヌスに学び、1252年パリ大学教授となった。そこで托鉢修道会を攻撃する教区付司祭教授たちに反駁した。3年後イタリアに帰り、活躍。69年再びパリ大学教授、アリストテレス説をめぐる論争に参加。中庸的立場でこれを擁護し、その原理を批判的に摂取してカトリックの信仰を定型的に説明し、あわせて自律的哲学を樹立した。可能態としての本質領域に対して、現実態としての存在領域の優位、豊かさを洞察し、存在の類比によって神の秘義を不完全ながら探求すると同時に、人間本性の深い理解を求めた。72年パリを去り、ナポリにおいて新設の大学充実に専念した。『神学大全』などの主著のほか、アリストテレスその他の注解、討論、詩などが多い。
1974.2.15 ドイツ連邦共和国発行

ネポムクのヤン 1340?-1393
プラハ大司教の総代理。南ボヘミアのネポムクの生れ。プラハ大司教と争っていたボヘミア王ヴァーツラフ4世によって逮捕され、拷問を受けて落命。遺体は
カレル橋の上からブルタヴァ川に投げ捨てられたが、後に川岸で発見された。1729年に列聖されたが、これは民間に根強く残るフス信仰に対抗するための、カトリック側からの対抗宗教改革の一環でもあった。水に関わる守護聖人として知られ、しばしば橋に彼の像が立てられている。十字架や棕櫚の枝を手にし、頭上に5つの星が輝く人物として描かれることが多い。
旅先で見かけた彼の像の写真を、こちらにまとめてみました。
1993年 スロヴァキア発行
 |
 |
1965年 チェコスロヴァキア発行
【死去550年】 |
1952.7.5 チェコスロヴァキア発行
【ベトレーム礼拝堂説教師就任550年】 |
ヤン・フス Jan Hus 1371?-1415
ボヘミアの神学者、宗教改革家。出身地はチェコ南西部のフシネツという村だと推定されるが、確証はない。プラハ大学で哲学や神学を学び、1398年同大学教授、1401年同大学の哲学部長となり、同大学のチェコ化に尽力し、1409年同大学総長となった。その間1402年にプラハのベトレーム礼拝堂の専属説教師となり、教会のヒエラルヒーに反対し、多くの点でウィクリフと一致しつつ、聖書的道徳主義と急進的・神学的な教会改革を求めた。彼の教会批判は、身分制とドイツ人の支配に反抗する社会的・チェコ民族主義的思想と結合した。1410年に破門され、コンスタンツ公会議に皇帝ジギスムントの与えた通行許可証をもっておもむいた。しかし期待した公開の神学的論争は実現されず、異端者として起訴され、聖餐論・ウィクリフ信奉・教皇制批判の罪で有罪判決を受け、火刑に処せられた。このために彼は殉教者とされ、1419〜36年にフス戦争が起きる原因となった。一方でチェコ語の改革、国民文学の確立にも尽力した。

チェコスロヴァキア発行
【ベトレーム礼拝堂600年】

トマス・ア・ケンピス Thomas a Kempis 1380?-1471
本名Thomas Hemerken。ドイツの神秘思想家。デーフェンデルの「共同生活兄弟団」に学び、1399年兄ヨハネスが院長を務めるアウグスティヌス参事会修道院に入り、『聖書』の研究に専念。各国語に訳されて広く読まれた『キリストのまねび』は彼の作とされる。
1971.5.3 ドイツ連邦共和国発行

ニコラウス・クザーヌス Nicolaus Cusanus 1401-1464
ドイツの哲学者、宗教家。モーゼル河畔クーエスのブドウ園主の子として生まれる。ドイツ、イタリア各地に諸学を学び、1430年司祭となった。1431〜37年のバーゼル公会議では公会議秘書を務めた。のちに教皇派に転じ、1437年教皇使節としてコンスタンティノープルにおもむき、つかの間の東西教会合同を達成。1448年枢機卿、1450年ブリクセン司教。教皇の委託でドイツ各地を歴訪し、規律と秩序を教会にもたらそうとしたが、永続的効果を生まなかった。1433-34年に大改革書『教会調和論』をあらわし、「死の病」が帝国をおびやかしているとして、教会と帝国の並行した改革と全般的な和合を論じた。教会統一に尽力した神秘主義者である反面、数学や経験的知識を重視し、個体を小宇宙であるとみて重視し、ライプニッツの先駆となった。
1958.12.3 ドイツ連邦共和国発行
【クザーヌス・ホスピス500年】
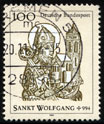
ヴォルフガング Wolfgang 924-994
ベネディクト会士。レーゲンスブルク司教。ハインリヒ2世の教師。「大施与者」と呼ばれる。
1994.10.13 ドイツ連邦共和国発行

1350年頃の細密画
ヘートヴィヒ 1174?-1243
中世ドイツの女子修道者。メラニア伯の家に生まれ、シュレジェン公ハインリヒ1世と結婚。夫とともに領内のキリスト教化に尽くし、大修道院を創設した。1267年列聖。
1993.10.14 ドイツ連邦共和国発行

コンポステーラの聖ヨハネ
キリストの使徒聖ヤコブは42年頃イェルサレムで殉教した。弟子たちは師の遺骸を小船にのせ、1週間後にその船はスペイン北西部ガリシア地方の岸に漂着したという。9世紀初頭、ペラギウスなる隠修者がその墓を奇跡的に「発見」し、その知らせを機に、アストゥリアス王アルフォンソ2世(在位790-842)がサンティアゴ教会を建立した。以来、聖ヤコブはレコンキスタの精神的な指導者として登場するようになる。997年に大聖堂はイスラムの猛将アル・マンスールに徹底的に破壊された。現在の大聖堂は1116年に着工され、1122年ごろ完成したといわれる。
聖遺物崇拝の拡大を背景に、聖ヤコブを祀ったサンティアゴ教会と、それを中心に成立した都市サンティアゴ・デ・コンポステーラは、やがてローマ、イェルサレムと並ぶ中世ヨーロッパの三大聖地の一つへと成長し、ヨーロッパ全域から多数の巡礼者を集めた。サンティアゴ巡礼の拡大を背景に、ブルゴス、レオン、サンティアゴ・デ・コンポステーラなどの巡礼路都市の発展も著しく、この時期のカスティーリャ経済の主軸となった。サンティアゴ巡礼路都市では巡礼者向けの商業・手工業が発達し、週市や年市が開催されたばかりか、多数のフランス人が定着した。しかし教会・修道院の支配下に置かれた都市が多く、そのため12〜13世紀のサアグンやサンティアゴ・デ・コンポステーラで自治権を求める激しいコミューン運動が発生した。
巡礼者は大きなツバ広の帽子とたっぷりとした裾長の外套、そして肩からは毛布とずた袋を下げ、身長よりも少し長い杖を持ち、ホタテ貝のカラを帽子や外套にべたべたとくっつけていた。ホタテ貝はサンティアゴが伝道したガリシアの海岸でたくさんとれる貝類で、そこからサンティアゴの象徴となった。
1982.3.31 スペイン発行
【コンポステーラ聖年】

『狩猟の書』の挿絵
ガストン(3世)・フォワ=ベアルン 1331-91
通称フェビュス。12歳で母親の後見のもとに父の遺領を継承。クレシーの戦い(1346)の翌年、フィリップ6 世に対し、自領は神にのみ属すると宣言、以後は中立的な立場を保持して領土の保全と拡大に努めた。近隣のアルマニャック伯とは古くから敵対関係にあったが、1362年と1373年の二度にわたって戦い、勝利を収めた。1381年にはアルマニャック家と縁戚関係にあったラングドック総代官ベリー公ジャンと戦ってこれを破り、南フランスにおける覇権を確立した。
北方十字軍に参加したり(1357-58)、ジャクリーの乱の際にモーで叛徒に包囲され孤立していた貴婦人たちを救出するなど、同時代人の間では騎士としての名声が高かった。また、音楽や文学にも造詣が深く、『祈祷の書』と『狩猟の書』をフランス語で著している。狩猟の分野では最も名声を博し、フロワサールも『年代記』のなかでフェビュスが猟犬を使った狩猟をとくに好んだことに言及している。
『狩猟の書』 : 1387年に口述筆記が始まり、1389年に成立という説が有力。猟犬を用いた狩猟のみが主題となっており、経験主義的で実際の狩猟に役立つ情報が簡潔に述べられている。ブルゴーニュ公フィリップ(豪胆公)に献呈された。多数の写本が作成され、現存する写本の数は44冊にのぼるといわれる。
1991.7.13 フランス発行
 |
 |
| 「恋のトレチセ」 |
1514年の印刷の様子 |
織物商カクストン(1422?-1491)が1470〜72年にかけてケルンで印刷術を学び、1474年にフランドルで、自ら訳した『チェスの手引き』などを出版したのが英国の活版印刷のはじまり。1476年頃イギリスにもどり、ウエストミンスターに印刷所を設けて、百科事典『世界の鏡』、
チョーサーの『カンタベリー物語』など約100種類の
書物を出版した。
1976.9.29 イギリス発行
【イギリスの印刷500年】
| 【マインツ大学450年】 |
【テュービンゲン大学500年】 |
 |
 |
大学の印章
最初に設立された大学は、ボローニャ、パリ、オックスフォード。1400年の時点では53を数えるまでに増加した。教会の管理下にあったため、聖職者教育の場となった。また、優秀な官僚を養成するための機関をしても機能した。
1977.5.17 1977.8.16 ドイツ連邦共和国発行
参考文献:
『ブリタニカ国際大百科事典』
『西洋中世の女たち』(エーディト・エンネン/阿部謹也,泉眞樹子・訳/人文書院)
『中世を生きぬく女たち』(レジーヌ・ペルヌー/福本秀子・訳/白水社)
『中世異端史』 (グルントマン/今野國雄・訳/創文社)
『スペイン・ポルトガル史』(立石博高・編/山川出版社)
参考論文:
「中世後期の戦士的領主階級と狩猟術の書」(頼 順子)[pdf]
|
《目次》
■ カロリング朝以前へ
■ ノルマン・コンクエスト へ
■ 10〜13世紀 へ 
■ 百年戦争前後 へ
■ イベリア半島 へ
■ 中・東欧 へ  ■ 文学 へ
■ 美術工芸など へ
■ 文学 へ
■ 美術工芸など へ