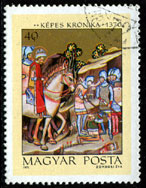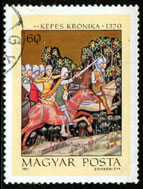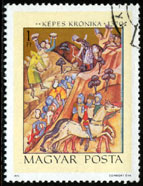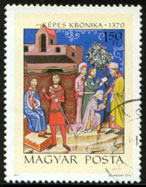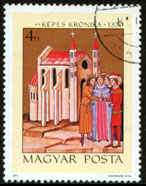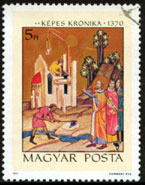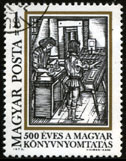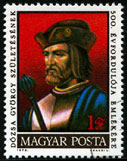Western
Medieval History
 |
 |
| ゲーザ公がこの地を選ぶ |
イシュトヴァーン王 |
【ゲーザ】 ?〜997 マジャール族がカルパチア盆地に定住した時の最高首長アールパードの曾孫。970年に大首長となると、氏族・部族組織をつぶしていく形で父祖の拡大政策を継承し、封建制国家の形成を目指した。部族長の独立をつぶし、彼らの城塞にゲーザ自身の守備隊を駐屯させ、これによってハンガリーに王城県制の基礎を据え、晩期にはティサ河西方地域を彼の権威下に統一。また、近隣の封建制諸国家との間に緊密な結びつきを確立するべく、975年にローマ教会にて一家で洗礼を受けた。ドイツ・ヴェネツィアと和協し、ハンガリーにキリスト教聖職者・騎士を移住させたが、異教にも寛大であった。
1972.8.20 ハンガリー発行
【セーケシュフェヘールヴァール1000年】

イシュトヴァーン1世 ?-1038
初代ハンガリー王(在位977-1038)。ゲーザの子。神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世の妹ギゼラと結婚。もとの名はヴァイクであったが、受洗してイシュトヴァーン(ラテン語のステファヌス)と名のる。ハンガリーに滞在していたプラハ大司教アダルベルトから教育を受ける。ゲーザが死ぬと、反対者たちを鎮圧して後継者の地位を固め、王冠を承認されてハンガリーを西方キリスト教社会の一員とした。伝承ではちょうど1000年のクリスマスの日に、神聖ローマ皇帝
オットー3世の同意を得て、ローマ教皇
シルヴェステル2世から贈られた王冠をもって戴冠式をあげたといわれる。さらに黒マジャールを討って全マジャール氏族・部族を支配下に置き、長期にわたる統治で、国家の統一と繁栄の時代をもたらした。キリスト教教会機構を確立し、城県制度を導入して各県にイシュパーンと呼ばれる地方長官をおき、法令を発布して、その制度は以後数世紀にわたってハンガリーの社会・宗教・政治体制全般の基礎となった。遊牧民の伝統に根ざした民族信仰を持つマジャール人にキリスト教を布教するため、抵抗するものは残虐に罰せられている。治世末期には一人残っていた息子のイムレを失い、王位継承問題に悩まされた。1083年、ラースロー1世の時代に息子イムレとともに聖者の列に加えられた。
1961.11.25 ヴァチカン発行
 |
 |
|
教皇シルヴェステル2世とAstrik大司教
1938.1.1 ハンガリー発行
【没後900年】
|
イシュトヴァーンの王冠
1939.6.1 ハンガリー発行
|
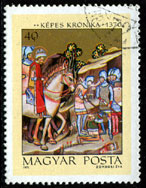 |
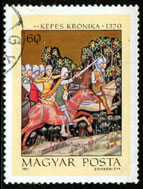 |
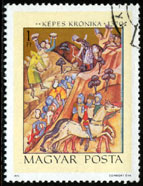 |
| コパーニュの斬首 |
ペーテル王を追うアバ・シャームエル |
バサラプ、カーロイ1世に勝利 |
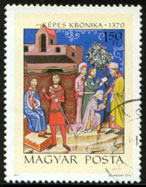 |
 |
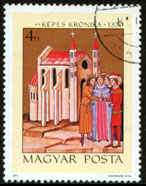 |
| シャラモン王とゲーザ公の争い |
イシュトヴァーン王と王妃ギゼラ
によるオーブダ教会の設立 |
カールマーン王と
王弟アールモシュの和解 |
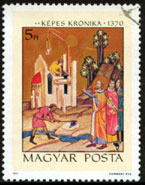
ラースロー1世によって建てられたOradea教会
1971.12.10 ハンガリー発行
ケペシュ・クロニカ(「彩飾年代記」)
初期の歴史書の集大成ともいえる14世紀最大の歴史書。僧カールティ・マールクによって著され、1933年までウィーンの宮廷文庫にあったため「ウィーンの彩飾年代記」とも称される。スコラ学、特に聖トマス・アクィナスのスコラ学の教化を受けており、13世紀の年代記作者たちが主に社会的紛争に興味を持っていたのに対し、14世紀の歴史家たちは国王と封建社会の結びつき、すなわち国内での既成秩序と、国外での外国征服をもっぱら賞賛した。挿絵はラヨシュ1世の宮廷画家メッジェシ・ミクローシュによって描かれた。
上左: ゲーザの強権によって服従させられていた部族長たちは、遊牧民族の古来の慣習に従えば相続権を持つ、ゲーザの大伯父の直系でアールパード家中最年長男性のコパーニュの王位継承を支持。これに対してイシュトヴァーン1世は
ドイツ騎士団を差し向け、コパーニュは戦死。遺体は四つ裂きにされ、三つはハンガリー西部の三城の城門に釘付けにされ、残る一つはトランシルヴァニア首長に送りつけられたとか。馬に乗っている人物に後光があるので、これがイシュトヴァーン1世ですね。
上中: 息子イムレを失ったイシュトヴァーン1世は妹とヴェネツィア公との間の子ペーテル・オルセオロを王位継承者に指名。しかし即位したペーテルは側近をドイツ人・イタリア人で固めたためにハンガリー人の反感をかい、イシュトヴァーン1世の義弟アバ・シャームエルによって追放された。
上右: アンジュー家出身の王カーロイ・ロベルトは、もともとハンガリーの一部であったワラキア平原の旧クマニアを支配下に取り戻そうと試みたが、封建的群雄割拠時代に独立したワラキア侯バサラプの抵抗のため失敗すると、ルーマニア人国家の自立を黙認した。
スコットでは"Basarad"の勝利となっていて、ちょっと違うかなとも思うんですが、該当しそうな名前がこのワラキア侯しか見あたらなかったので・・・
下左: アンドラーシュ1世は弟のベーラに王位継承権を譲ったが、後に息子のシャラモンに王位を継がせようとしたため、武力衝突が生じ、ベーラが即位、シャラモンは義兄にあたる皇帝ハインリヒ4世のもとに庇護を求めた。王の急死によりシャラモンは帰国し即位したが、今度はベーラ王の子ゲーザとラースローとの間に抗争が生じ、戦いに敗れたシャラモンは再び皇帝の下に逃亡した。
そのほかについては現在のところ詳細不明・・・

2003.9.30 中華人民共和国発行
【図書芸術】

ペーチ大学の教師と生徒のレリーフ
1367年ラヨシュ1世によってペーチに大学が創設された。しかしこれはまもなく廃止され、教会の幹部はパリやイタリアのみならず、新設のウィーンやプラハ、クラクフの大学にも留学した。13世紀に創設されたヴェスプレームの「総合学院(ストウディウム・ゲネラーレ)」やジギスムントが創設したオーブダの大学も廃止の運命をたどった。
1967.10.9 ハンガリー発行
【ハンガリー高等教育600年】

マーチャーシュ 1443-1490
ハンガリー王(在位1458-1490)、ボヘミア王(1469-1478)。マティアス・コルヴィヌス(大鴉の意)ともいう。対トルコ戦の英雄フニャディ・ヤーノシュの子。父の死後、フニャディ派の抹殺を図る勢力によって兄が処刑され、彼自身はラディスラウス5世の人質としてプラハに幽閉された。釈放後、中小貴族の力により1458年国王に選出される。以後専門の宮廷官吏スタッフを組織し、裁判制度を改革、傭兵軍を保持して中央集権化政策を進め、議会を出し抜いて絶対主義導入を図ったが、特権喪失を恐れる支持層の中小貴族と妥協せざるをえなくなる。対外的にはトルコやポーランドなどの近接国とのたびたびの戦争に勝利を収めた。1468-85年にかけてのチェコ及びオーストリア遠征によって中欧帝国の建設を図り、1485年には半年にわたる包囲の末ウィーンを占拠した。またイタリアから人文主義者を宮廷に招くなどして学芸や文化を保護、奨励。自身もコルヴィナ文庫に500冊以上の豪華本の蔵書を誇った。ブダの宮廷は華麗な建物や国際的な人文主義者サークルを抱える、アルプス以北のルネサンスと人文主義文化の最高の中心地であった。
ハンガリーとジョイント発行の切手。じゃきっと王妃様がベルギーの出身なんだな〜と思ったのですが、調べてみたら、向かって左に描かれている王妃様はナポリのアラゴン家の王女ベアトリーチェ(フェランテ1世の娘、二度目の妃)なんですね。一体ベルギーとはどんな関わりが・・・?
1993.5.15 ベルギー発行
【歴史シリーズ】
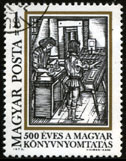
植字 コメニウスの『世界図絵』より
1472年、ヘス・アンドラーシュによってハンガリー最初の印刷所がブダに設立された。マーチャーシュ王は新発明の印刷機をすぐさま政治的宣伝の道具にしようとし、反フリードリヒ3世のポスターが次々と刷られた。この印刷所の設立も国王に仕える一役人の示唆によるもので、最初の印刷物は王を「第二のアッティラ」と賛美するトゥローツィのハンガリー年代記であった。印刷術がすばやく導入されたことは、読書人層がかなり大きかったことを物語っている。
1973.6.5 ハンガリー発行
【ハンガリー印刷500年】
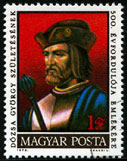
ドージャ・ジェルジュ Dózsa György ?-1514
南ハンガリーの辺境城塞守備兵。ナーンドルフェヘールヴァール(ベオグラード)守備隊士官として戦功をあげ、貴族の称号を得る。1514年、大司教バコーツ・タマーシュにより対トルコ十字軍司令官に指名される。十字軍に参加した農民の悲惨さを知り、また支配階級が対トルコ戦準備に横槍を入れたことから、自軍を領主に向けることを決意。民衆の圧制者に対する宣戦を布告、全国に燃え上がった大農民戦争を指導した。大平原(アルフェルド)地方に勝ち進んだが、テメシュヴァールで貴族の連合軍に敗れて捕らわれ、残酷に焼き殺された。
1972.6.25 ハンガリー発行
【大モラヴィア国1100年】
 |
 |
| 9世紀の指輪とモラヴィア入植地の地図 |
9世紀の銀の円盤 |
アヴァール帝国の崩壊後の820年代、支配下に置かれていたスラヴ人の一部が本格的な自立の動きを見せはじめた。中でも有力だったのはモラヴァ川流域に拠点を築いていたモイミール(在位830頃-846)とその一族で、彼は833年頃にさらに東のニトラにいたプリピナという首長を追放し、国家の形を整えはじめた。彼はザルツブルク大司教座による布教を容認し、おそらく自身も洗礼を受けていたと思われる。モイミールが東フランク王によって廃位された後、跡を継いだ甥のロスチスラフ(在位846-870)はパッサウ司教の監督下に置かれていたモラヴィアの宗教的な自立をめざし、ローマ教皇ニコラウス1世にスラヴ語でキリスト教を布教する使節の派遣を要請したが、東フランクとの友好を維持しなければならなかった教皇はこれを拒絶。ロスチスラフは2年後、同様の要請をビザンツ皇帝ミカエル3世に行い、今度は成果を得ることができたが、870年に東フランクに捕らえられて幽閉されてしまう。跡を継いだ甥のスヴァトプルク(在位871-894)はただちに東フランクの軍隊を追い出して独立を回復、さらに国家の領域を、南はドラヴァ川、東はティサ川、北はオーデル川にまで広げ、モラヴィアの全盛期を築いた。しかし、彼の死後息子たちが相争い、さらにマジャール人の侵入を受け、901年には東フランクとの同盟を成立させるも、902年から906年頃にかけて壊滅的な打撃を受け、モラヴィア国は崩壊した。
1963.3.25 チェコスロヴァキア発行

コンスタンティノス(キュリロス)とメトディオス 826/7-869 815-885
ギリシアのテッサロニキ出身の兄弟。メトディオスの方が年長だが、コンスタンティノスの名を先に並べるのが習慣になっている。863年頃モラヴィア王の要請を受けたビザンツ皇帝と総主教フォティオスによって、モラヴィアに派遣された。メトディオスは帝国官僚として多くの業績をあげており、コンスタンティノスは高名な学者として広く注目を集めていた。また彼らの出身地テッサロニキ周辺にはスラヴ人が多く住んでいたため、スラヴ語にも堪能だったことがこの任務に選ばれた理由の一つでもあったという。コンスタンティノスは命令を受けるとグラゴール文字(キリル文字の原形)というスラヴ語の表記のための新たな文字を考案。モラヴィアに到着した二人は著述や翻訳を進めるかたわら、現地の人々の中から優れた弟子を養成し、新たな教会組織の基礎固めに努めた。867年一通りの任務を終えて帰国の途についたが、ヴェネツィアでビザンツ帝国の政変を知りローマへ向かう。コンスタンティノスはこの地で病死したが(直前に修道士となってキュリロスの名を得る)、メトディオスは教皇ハドリアヌス2世からシルミウム大司教に任命され、再びモラヴィア方面に赴いた。しかし東フランク側によって捕らえられ、各地を転々とする獄中生活をおくる。873年に解放されるとスラヴ語で典礼を行う教会の発展に尽くしたが、885年に彼が死去すると、スラヴ語の典礼は禁止され、従わない聖職者たちはモラヴィアから追放された。こうしてヨーロッパ中央部に「スラヴ語で典礼を行う教会」をつくる試みは失敗に終わった。しかし追放された聖職者の一部はブルガリアに保護を求め、その後のブルガリアでは古代スラヴ語によるキリスト教文化が見事に開花した。
1935.6.22 チェコスロヴァキア発行
【伝道者キュリロスとメトディオスのモラヴィア到着1000年】

ミエシコ2世 Mieszko II Lambert 990-1034
ポーランド王(在位1025-34)。初代ポーランド王ボレスワフ1世の子。兄弟が神聖ローマ皇帝やキエフと手を結んだため、1031年にはチェコに亡命。翌年には帰国したが、父が得た新領土と王号を放棄した。彼の急死後、その子カジミエシ1世が追放され、ピアスト国家が一時消滅する状況に陥った。
1987.12.4 ポーランド発行

リーグニッツの戦い
1241年4月9日シロンスク(シュレジェン)公ヘンリク2世敬虔公の率いるドイツ・ポーランドの連合軍がバトゥ率いるモンゴル軍とシュレジェン南西のリーグニッツ(現ポーランドのレグニツァ)で戦い、ヘンリクは戦死。モンゴル軍も多大の損害を受け南東方へ撤退した。ワールシュタットWahlstattの戦いともいう。
ボレスワフ3世以後細分化が侵攻したポーランドの統一を目指す動きはこれでいったん頓挫した。
1992.4.16 ドイツ連邦共和国発行
【リーグニッツの戦い750年】
参考文献:
『ハンガリー史1・2』(パムレーニ・エルヴィン著・田代文雄/鹿島正裕 共訳/恒文社)
『ドナウ・ヨーロッパ史 新版世界各国史19』(南塚信吾編/山川出版社)
『ポーランド・ウクライナ・バルト史 新版世界各国史20』(伊東孝之・井内敏夫・中井和夫編/山川出版社)
『物語 チェコの歴史 森と高原と古城の国』(薩摩秀登/中公新書)
|
《目次》
■ カロリング朝以前へ
■ ノルマン・コンクエスト へ
■ 10〜13世紀 へ 
■ 百年戦争前後 へ
■ イベリア半島 へ
■ 思想・文化 へ  ■ 文学 へ
■ 美術工芸など へ
■ 文学 へ
■ 美術工芸など へ